 |
■CALENDAR■
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
| | | | | |
<<前月
2025年11月
次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■POWERED BY■
■OTHER■
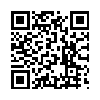
携帯からもご覧いただけます
|
2012,01,30, Monday
本日ご案内するのは、近隣市「芝山町」「芝山仁王尊」「観音教寺」で2月3日(金)に開催されます「節分会」「追儺式」です。
「芝山仁王尊」「観音教寺」(2011年4月25日のブログ参照)は、「天台宗」の寺院で正式名称を「天應山観音教寺福聚院」です。
天應元年(781年)勅命により「征東大使」「中納言 藤原継縄」公がこの「布令」の下に当地に「寺院」を建立し、「御本尊」として奉持して来た「十一面観世音菩薩」を奉安し、創建されました。
「芝山仁王尊」「観音教寺」は、昔から「火事・泥棒除け」の「お仁王様」の通称で親しまれ、「火消し衆」や「商家」の篤い「信仰」を得て「江戸の商家で火事泥棒除けのお仁王様のお札を祀らないお店(たな)はない」とまで言われていたそうです。
「節分」は、各「季節」の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことですが、「節分」とは「季節を分ける」こてをも意味しています。
江戸時代以降は特に「立春」(毎年2月4日ごろ)の「前日」を指します。
「季節」の「変わり目」には「邪気(鬼)」が生じると考えられており、それを追い払うための「悪霊払い行事」が執り行われています。
「節分の行事」は「宮中」での「年中行事」であり、「延喜式」では、彩色した「土」で作成した「牛」と「童子」の「人形」を「大内裏」の「各門」に飾っていたそうです。
「追儺」とは「大晦日」(12月30日(旧暦))の「宮中」の「年中行事」であり、「平安時代」の「初期頃」から行われている「鬼払いの儀式」です。
「鬼やらい」(「鬼遣らい」、「鬼儺」などとも表記)、「儺(な)やらい」とも呼ばれています。
「追儺」はもとは「中国」の「行事」であり、「宮廷」の「年中行事」となり、現在の「節分」の元となった「行事」です。
「芝山仁王尊」「観音教寺」「節分会」「追儺式」には、毎年数多くの「参加者」があり、「法要」の後、「周辺地域」の「名士」たちが「年男」・「年女」として「特設会場」に上がり、「豆まき」や「景品」の「福まき」をします。
「芝山仁王尊」「観音教寺」「節分会」では、「大般若」転読・「除災招福」「護摩」・「星祭」を厳修。
「大般若経」の「風」に当たるだけで「除災招福」の「功徳」を得られると古来よりいわれています。
「法要」終了後、「三重塔」前「特設舞台」にて「鬼やらい」の「寸劇」と「福撒き」が行われます。
また「昼食」に用意される「特別料理」も大好評なのだそうです。
「芝山」の「古刹」で行われる「節分会」「追儺式」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「芝山仁王尊」「観音教寺」「節分会」「追儺式」詳細
開催日時 2月3日(金) 13時〜 (「福まめまき」は14時半頃)
開催会場 芝山仁王尊 山武郡芝山町芝山298
問合わせ 0479-77-0004
備考
「芝山仁王尊」「観音教寺」「節分会」「追儺式」では、「法要」は13時から「大護摩道場」で行われ、続いて「鬼やらい」が14時頃から「三重塔」前で行われます。
「法要」内容は「除災招福護摩」、「第密星祭供養」、「大般若転読」で、「鬼やらい」では「鬼の寸劇」と「豆撒き」となっています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=910 |
| 地域情報::成田 | 07:40 AM |
|
|
2012,01,28, Saturday
本日二つ目にご紹介するのは、近隣市「成田市」「坂田ヶ池」にある「片歯の梅」です。
「片歯の梅」は、「坂田ヶ池総合公園」にあります。
「坂田ヶ池総合公園」は、豊かな自然に恵まれた「坂田ヶ池」の周囲を囲む約17ha(ヘクタール)の広大な「公園」で、「房総のむら」に隣接しています。
「水」と「緑」豊かな「公園」で、「大人」から「子供」まで楽しめる憩いの場所です。
そんな「坂田ヶ池」また「印旛沼」にまつわる「昔話」が今も語り継がれています。
「昔話」は、「片歯の梅」という「悲しいお話」です。
以下が語り継がれている「片歯の梅」です。
その昔、「坂田ヶ池」に住む「雄の大蛇」が、毎年「梅雨時」になると「土手」を越えて「長沼」の「雌の大蛇」に逢いに行きました。
その度、「田」や「家」を守る「土手」が崩れてしまったそうです。
村人たちは、「土手」が崩れないようにするには、人柱を立てた方が良いということを耳にしました。
そこへ、「子供」を背負った「女の人」が通りかかったので、この「親子」をふびんと思いながらも埋めてしまいました。
それ以来、「土手」は崩れることがなくなり「村々」は助かったそうです。
ところが、いつの間にか、埋めた「場所」の「土手」に、「梅ノ木」が育ちました。
しかしその「梅」は、「実」が半分しかないことから「片歯の梅」と呼ぶようになりました。
その「梅ノ木」は、埋められた時に「子供」が、半分かじったままの「梅」から生えたものだと伝えられています。
今でも「片歯の梅」の「木跡」として残されています。
「悲劇の地」に咲く「梅ノ木」跡は今もひっそりと「成田の地」に佇んでいます。
備考
「坂田ヶ池総合公園」に隣接している「房総のむら」は、「房総」の「伝統的な生活様式」や「技術」を「来館者」が直接体験するとともに、県内各地から出土した「考古遺物」や、「武家」・「商家」・「農家」などの「展示」を通して「歴史」を学んでいただくことを「目的」とする「博物館」です。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=907 |
| 地域情報::成田 | 09:12 AM |
|
|
2012,01,28, Saturday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「宗吾霊堂」で来週の2月3日(金)に開催されます「節分会追儺式」です。
「宗吾霊堂」(2010年12月23日のブログ参照)は、「成田市」にある「真言宗豊山派」の「寺院」「東勝寺」のことで「山号」は「鳴鐘山」。
「義民・佐倉惣五郎」の「霊」が祀られていることから「宗吾霊堂」と広くよばれています。
「宗吾霊堂」の「由緒」ですが、「開創年代」等については不詳ですが、「桓武天皇」の「勅命」により、「坂上田村麻呂」が創建したといわれています。
たびたび「火災」があり、「寺地」を転々とし、1662年(寛文2年)「澄祐」により再興され「下方字鐘打」に移りました。
1910年(明治43年)「火災」により焼失し、1921年(大正10年)「現在地」に再建されました。
「宗吾霊堂」では、「吉例」に則り、「立春」の前日に「節分会追儺式」を修行し、「年男」はもちろん、「女性」のみ(特別)の「豆まき」も執り行われます。
「本堂行道縁」からは、「福豆」、「紅白餅」、「小銭」、「お菓子」などがまかれるそうです。
また「宗吾霊堂」「追儺式」では、「向島鳶職組合」による「江戸時代」より引き継がれている「伝統行事」「梯子(はしご)乗り」の「実演」(妙技)が「呼び物」になっているようです。
(11時と16時に披露されるそうです。)
「宗吾霊堂」には、「厄落とし」のため「何十年」も続けて参加される方も数多く見られるそうです。
「宗吾霊堂」「節分会追儺式」にて、「袴」を着て、「御本堂」の「行道縁」から「豆」をまく気分を味わってみてはいかがでしょうか?
「宗吾霊堂」「節分会追儺式」詳細
開催日時 2月3日(金) 11時・14時・16時〜
(年男) 第一回 11時〜 第二回 16時〜
(特別年女) 14時〜
開催会場 宗吾霊堂 御本堂前 成田市宗吾1-558
修行料 年男 30000円
(裃着用、御護摩札、御供物、福守、福豆、福枡、祝膳、御土産)
特別年女 15000円
(裃着用、御護摩札、御供物、福守、福豆、福枡)
豆まき体験のみ
時間 午前11時のみ
修行料 10000円 (福守、福豆、福枡)
問合わせ 0476-27-3131
備考
「宗吾霊堂」「節分会追儺式」1月20日に「参加希望者」は「締切」になっています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=906 |
| 地域情報::成田 | 09:11 AM |
|
|
2012,01,18, Wednesday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「下総地区」の「しもふさ七福神巡り」です。
「成田市」「下総地区」には、「乗願寺」(布袋尊)、「昌福寺」(寿老人)、「楽満寺」(恵比寿)、「常福寺」(大黒天)、「成田ゆめ牧場」(福禄寿)、「眞城院」(弁財天)、「龍正院」(毘沙門天)の「七福神」が祀られており、これらの「七福神」を拝することにより、「七つの幸福」が授かるといわれています。
「しもふさ七福神」は、昭和61年(1986年)に「村おこし事業」の一環として誕生しました。
「しもふさ七福神巡り」は、拝することで「幸福」が授かるといわれ、約175kmの道のりとなります。
「しもふさ七福神」とは以下の「寺院」となります。
「乗願寺」(布袋尊)は、「赤城の子守唄」で有名な「板割浅太郎」ゆかりの「寺」で知られています。
「乗願寺」は、延慶3年(1310年)に「中聖知得上人」の開基され、「御本尊」は「阿弥陀如来座像」で「時宗」の「寺」です。
弘治年間(1555年〜1558年)には当時の「助崎城主」の「命」によって「成田市幡谷」より現在地に移されました。
「乗願寺」「山門」は「助崎城」の「大手門」を使用、「本堂」には「閻魔大王」・「安産」、「子育地蔵尊」・「板割の浅太郎」の「位碑」などが安置されています。
「乗願寺」「境内」には、「夜泣き」「地蔵尊」が祀られ、「幼児」の「夜泣き」が直ると言われています。
また「布袋尊」を祀っており「しもふさ七福神巡り」のひとつとなっています。
「昌福寺」(寿老人)は、永正11年(1514年)に「太蓮社良翁上人」が開山したといわれる「浄土宗」の「寺院」です。
「昌福寺」の「御由緒」ですが、火災により「書物」が焼失しているため不明だそうです。
元文5年(1740年)に「十間四面総欅造り」で「天井」に「極彩色」の「百花の絵」、「内陣欄間」に「龍」などの「彫刻」を施した現「本堂」が再建されたそうです。
その後、「山門」、「鐘楼堂」、「僧坊」等の「伽藍」が整備されましたが、現在は「本堂」のみ残っています。
また「しもふさ七福神」の一神の「寿老人」が祀られていることで知られています。
「楽満寺」(恵比寿)は、建暦2年(1212年)に「国一禅師」により開基となりました。
「楽満寺」の「御本尊」は「如意輪観世音」です。
「楽満寺」の「行事」として3月26日から16日間、「札打ち」と称する数十か町村の「観音巡拝」と、春秋に「利根川」沿岸の「常総層」の村々を「観音様」のご分身を背負って回る「背負い観音」は特異な「行事」として知られています。
「楽満寺」「本堂」にはたくさんの「女人観音拝み絵馬」があり、静かな「境内」に「しもふさ七福神」の一神「恵比寿様」がお祀りしてあります。
「楽満寺」「縁日」は毎月19日で「庶民救済」、「福財」、「商売繁盛」、「安産」、「子育て」で広く信仰を集めています。
「常福寺」(大黒天)は、「名木のお不動様」として知られている「真言宗」の「寺院」で、延応元年(1239年)に「湛導和尚」の開基と伝えられています。
「常福寺」の「御本尊」は「不動明王」です。
「常福寺」は、一時火災に遭い衰微しましたが、寛永2年(1625年)に「宥ばん和尚」(「成田山」中興の祖)によって中興され、「不動明王」をお祀りしてから賑わったと言われています。
そのようにして「常福寺」は、「青銅の不動尊」を安置したそうです。
「常福寺」「境内」には、「仁王門」、「本堂」、「鐘楼」、「念仏堂」が整備され、「しもふさ七福神」のひとつ「大黒天」も祭られています。
「常福寺」は、「裏山」の「緑」とあいまって静寂を保っています。
「成田ゆめ牧場」(福禄寿)は、「千葉県」北部の中央、「利根川」の南岸に広がる緑豊かな「田園」と「丘陵地帯」にあります。
「牧場」の「面積」は、「東京ドーム」の何倍もする約9万坪の「牧草地」を、そのまま生かした「自然」を楽しめる「施設」です。
「成田ゆめ牧場」(2010年8月24日のブログ参照)開設は、昭和62年(1987年)7月21日で、「秋葉牧場」の「100周年」を記念して「秋葉博行」場長の「ゆめ」を託し開場したそうです。
「成田ゆめ牧場」場内は、「牧場」・「オートキャンプ場」に分かれて、「牧場」では、「軽スポーツ」、「農業体験」、「食料」の「自家製品作り」、「釣り堀」、「遊園」、「小動物コーナー」などがあります。
「成田ゆめ牧場」内には「しもふさ七福神」のひとつ「福禄寿」が祀られています。
「眞城院」(弁財天)は、「天台宗」の「寺院」で「御本尊」は「阿弥陀如来」です。
「しもふさ七福神」のひとつ「弁財天」が祀られています。
「眞城院」は、元禄年間に「高岡藩」の「井上」氏により「堂宇」が一新されました。
翌年「境外」「池中」に「弁財堂」が建てられて「藩内」の「五穀豊穣」の「祈願所」となりました。
「眞城院」では、毎年2月3日の「節分」には「弁財天」前で「諸願成就」を祈願しています。
「龍正院」「滑河観音」(毘沙門天)は、「坂東33ヶ所観音霊場」()の「第28番札所」の「天台宗」の「寺院」で、「御本尊」は「十一面観世音菩薩」です。
「龍正院」「滑河観音」は、平安時代初期の承和5年(838年)に「慈覚大師」の開基と伝えられています。
「延命」・「安産」・「子育て」の「守り本尊」として知られ、「境内」には、「しもふさ七福神」のひとつ「毘沙門天」が祀られています。
「龍正院」「滑河観音」には「仁王門」、「本堂」並びに「宝きょう印塔」、「夫婦松」など貴重な「遺品」が残されていて、「境内」はとても美しい所なのだそうです。
また「龍正院」「滑河観音」では毎年8月9日に「四万八千日」(2011年8月7日のブログ参照)が行われていることで知られています。
「しもふさ七福神めぐり」行程の一例ですが、「滑河駅」からのルートとして、「滑河駅」〜0.7km〜「眞城院」〜5.2km〜「成田ゆめ牧場」〜0.6km〜「常福寺」〜1.8km〜「楽満寺」〜4.0km〜「乗願寺」〜3.9km〜「龍正院」〜0.8km〜「昌福寺」までの約17kmの「道のり」となっています。
また毎月「7の日」は、「しもふさ七福神」の「御縁日」で、「しもふさ七福神めぐり」の「御朱印」は、毎日承っており、「御朱印」の「受付時間」は8時30分〜16時00分となっています。
「成田市」「下総地区」の「七福神めぐり」にお出かけしてみてはいかがでしょうか?
「しもふさ七福神巡り」詳細
「乗願寺」
所在地 成田市名古屋234
問合わせ 乗願寺 0476-96-2580
「昌福寺」
所在地 成田市西大須賀1872
問合わせ 昌福寺 0476-96-0067
「楽満寺」
所在地 成田市中里309
問合わせ 楽満寺 0476-96-1944
「常福寺」
所在地 成田市名木953
問合わせ 常福寺 0476-96-3380
「成田ゆめ牧場」
所在地 成田市名木730
問合わせ 成田ゆめ牧場 0476-96-1009
「眞城院」
所在地 成田市高岡163
問合わせ 眞城院 0476-96-0176
「龍正院」「滑河観音」
所在地 成田市滑河1196
問合わせ 龍正院 0476-96-0217
問合わせ 成田市東商工会下総支所 0476-96-2839
備考
「しもふさ七福神」「福禄寿」が祀られている「成田ゆめ牧場」では、「金魚草」「ストック」「ポピー」などの「花摘み」(2011年1月19日のブログ参照)ができます。
また「園内」では「旬」を迎える「いちご狩り」も楽しめるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=890 |
| 地域情報::成田 | 10:01 AM |
|
|
2012,01,16, Monday
本日ご案内するのは、近隣市「印西市」の「いんざい七福神めぐり」です。
「いんざい七福神めぐり」は、室町時代に「商人」に「福」を授ける「神々」として「信仰」が強まったそうです。
「いんざい七福神」とは、「観音寺」(弁財天)、「泉蔵寺」(毘沙門天)、「最勝院」(布袋尊)、「長楽寺」(大黒天)、「厳島神社」(弁才天)、「上町観音堂」(寿老人)、「三宝院」(恵比寿)、「宝泉院」(福禄寿)のことをさし、すべて巡ることが「いんざい七福神めぐり」です。
ちなみに「七福神」の「御利益」は、「弁財天」は「福徳・芸能・愛嬌」、「毘沙門天」は「威光・七難即滅」、「布袋尊」は「大漁・福徳円満」、「大黒天」は「豊穣・有福蓄財」、「弁才天」は「学術・知恵・福徳」、「寿老人」は「無病長寿」、「恵比寿」は「防災・商売繁盛」、「福禄寿」は「招福安泰」だそうです。
「いんざい七福神めぐり」の8つの「寺社」は次の通りです。
「観音寺」(弁財天)は、天長6年(829年)〜承和4年(837年)の間に、「円仁上人」(のちの「慈覚大師」)が「手賀沼」湖畔の高台に開山された「古刹」です。
「観音寺」の「御本尊」は、「阿弥陀如来」の「半跏(はんか)踏み下げ座像」で、「勢至菩薩(せいしぼさつ)」と「観世音菩薩」を「脇侍」としています。
「観音寺」「境内」には、「観音堂」、「弁天堂」、「仁王門」、「仁王尊」、「閻魔堂」などがあります。
昔から、「厄除仁王尊」のある「寺」として知られています。
「泉倉寺」(毘沙門天)は、「三葉畑」が点在する「小倉群落」にあり道端の「光堂」と刻まれた「石碑」を見ながら坂を上るところにあります。
「泉倉寺」「御本尊」は「阿弥陀如来」で、「青磁色」の「重層銅板葺き」の「阿弥陀堂」形式の「本堂」は、美しく映えています。
「泉倉寺」「本堂」脇の「客殿」には、「木造延命地蔵菩薩坐像」が安置されているそうです。
「最勝院」(布袋尊)は、「天台宗延暦寺派」に属し「泉倉寺」の「末寺」です。
「最勝院」「御本尊」は、「阿弥陀如来」です。
「最勝院」の由緒は不明で、「いんざい七福神めぐり」の「布袋尊」を祀る「札所」としても知られています。
「最勝院」「境内」は約191坪の広さがあります。
「七福神めぐり」(布袋尊)の「御朱印」は、「最勝院」「本堂」に設置されています。
「長楽寺」(大黒天)は、「慈覚大師」(円仁)により承和11年(844年)頃、創立された「天台宗」の「古刹」です。
「長楽寺」「境内」にあった「国宝観音」は、昭和25年(1950年)2月12日に焼失したそうです。
昭和60年(1985年)〜平成元年(1989年)にわたり、「長楽寺」「本堂」の修理、「観音堂」の新築をしています。
「長楽寺」「本堂」にあった「梵鐘」は、応安2年(1369年)に「森内家吉」氏から、寄附されたもので、昭和47年(1972年)9月29日に「千葉県指定文化財」に指定されています。
なお「長楽寺」には、「商売繁盛」、「除災招福」、「大願成就」の「御利益」がある「福寿開運の神様」・「大黒天」を祀っています。
「厳島神社」(弁才天)は、延宝7年7月の創立で、「御祭神」は「市杵嶋姫命(イチキシマヒメノミコト)」・「水波能賣命(ミヅハノメノミコト)」を祀っています。
「厳島神社」の「敷地」526坪の「境内」には「本殿」(銅板葺流造)、「拝殿」(瓦葺切妻造)が建ち並びます。
「六軒新田」の開発が行われていた延宝年間(1675年頃)に「大森」の「宮島」氏によって「安芸の宮島」から勧請されたと伝えられています。
「厳島神社」の「境内」に、「いんざい七福神」のひとつ「弁才天」が祀られています。
「上町観音堂」(寿老人)は、「御堂」東南にある「三宝院」に属しています。
本来「三宝院」はこの場所にあり、移転後もこの「御堂」のみ残ったと伝えられています。
「御本尊」は他の寺院から移されたものとも地域の有力者から寄進されたものともいわれていますが、不詳なのだそうです。
「御堂」には1年に1日だけ御開帳される「銅造十一面観音立像」(千葉県の重要文化財)が安置されています。
「いんざい七福神」の「寿老人」を祀る「寺」としても知られています。
「三宝院」(恵比寿)は、「天台宗」の「古刹」で寛正6年(1645年)の建立で、基となったのが「慈眼庵」だそうです。
「慈眼庵」はその後、寺院化して「三宝院」と改め、現在地には寛文年中(1661年〜1663年)に置かれたと伝えられています。
やがて「稲荷神社」の「別当寺」として、「稲荷山神宮寺三宝院」と称するようになりました。
「三宝院」「境内」には、「海の守護」と「商売繁盛」、「庶民救済」の「神様」「恵比寿」を祀っています。
「宝泉院」(福禄寿)は、天長6年(829年)〜承和4年(837年)にかけて、「慈覚大師」により「仁明天皇」の「勅願所」として建立されたといわれています。
かつては「七堂伽藍」の「大寺」で、「下寺」に「八ヶ寺」を擁したといわれており、「宝泉院」「境内」には、「臼井城主」・「原式部少輔胤成」の「祈願所」があったといわれています。
現在では「宝泉院」と「地蔵寺」を残すだけだそうです。
また「宝泉院」には、人々に限りない「幸運」と「長寿の源」を授けてくれる「神様」「福禄寿」を祀っています。
「印西市」の「各郷」に点在している「七福神」を巡って「福」を授かりに訪れてみてはいかがでしょうか?
「いんざい七福神めぐり」詳細
所在地
「観音寺」
所在地 印西市浦部1978
問合わせ 観音寺 0476-42-2804
「泉倉寺」
所在地 印西市和泉971
問合わせ 泉倉寺 0476-42-3322
「最勝院」
所在地 印西市発作地先
問合わせ 泉倉寺 0476-42-3322
「長楽寺」
所在地 印西市大森2034-1
問合わせ 長楽寺 0476-42-2302
「厳島神社」
所在地 印西市大森4336
問合わせ 小林鳥見神社 0476-42-2358
「上町観音堂」
所在地 印西市木下1446
「三宝院」
所在地 印西市竹袋141
問合わせ 三宝院 0476-42-2582
「宝泉院」
所在地 印西市別所1005
問合わせ 宝泉院 0476-42-7387
問合わせ 印西市観光協会 0476-42-5111
備考
「いんざい七福神めぐり」で少しユニークなのは、「水」を司(つかさど)る「弁才天」(「弁財天」)を祀る「社寺」が、「厳島神社」と「観音寺」の2ヶ所になっていることです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=888 |
| 地域情報::成田 | 07:20 AM |
|
|
2012,01,02, Monday
本日二つ目にご案内するのは、近隣市「栄町」「印西市」「匝瑳市」にある「今年の干支」「龍」にゆかりのある「龍角寺」、「龍腹寺」、「龍尾寺」の「龍寺めぐり」です。
2012年は「辰年」です。
「今年の干支」「龍」は、「中国神話の生物」で古来神秘的な存在として位置づけられてきました。
「龍」は「神獣・霊獣」であり、「麒麟(きりん)」、「鳳凰(ほうおう)」、「霊亀(れいき)」とともに、「四霊」のひとつとして扱われています。
「日本の龍」は、様々な文化とともに「中国」から伝来し、元々「日本」にあった「蛇神信仰」と融合したとされています。
「龍」は「水の神」として各地で「民間信仰」の対象となっていて、「灌漑(かんがい)技術」が未熟だった時代には、「旱魃(かんばつ)」が続くと、「竜神」に「食べ物」や「生け贄(いけにえ)」を捧げたり、「高僧」が祈りを捧げるといった「雨乞い(あまごい)」が行われていたようです。
「匝瑳市の伝説」「大寺の龍尾寺」(2011年5月10日のブログ参照)でアップしましたが、「印旛沼」に伝わる「龍神様」に「雨乞い」をしたところ、「沼」の中から「龍神様」が現れ天に舞い上がると、突然雨が降り続いたのですが、「雷光(らいこう)」と「雷鳴(らいめい)」がとどろき、「天空」で舞い上がった「龍」が三つに裂けたそうです。
三つに裂けた「龍」ですが、「頭」は「安食(あじき)」に、「腹」は「本埜(もとの)」に、「尾」は「大寺(おおでら)」に落ちていたのが見つかったそうです。
人々を旱魃(かんばつ)から救った「龍」を見つけ、村人たちは手厚く葬ったそうです。
そして「頭部」は、「石の唐櫃(からびつ)」に納めて「龍角寺(りゅうかくじ)」の堂前に埋め、「腹部」は、「本埜」の「地蔵堂」に納め、「尾部」は、「大寺」の「寺」に納めたそうで、その後「龍角寺」、「龍腹寺」、「龍尾寺」とそれぞれ「寺」の名前となったそうです。
「龍角寺」は、「印旛郡栄町」にある「天台宗」の寺院で、山号は「天竺山」、「御本尊」は「薬師如来」で、「天竺山寂光院」と号します。
発掘調査の結果、7世紀にさかのぼる「伽藍跡」が検出されており、創建年代の古さという点では、「関東地方」でも屈指の「古寺」です。
また「龍角寺」には、「御本尊」でもある「銅造薬師如来坐像」(頭部のみ「奈良時代」の作)があり、「国指定重要文化財」に指定されています。
「龍腹寺」は、「印西市」(旧「本埜村」)にある「天台宗」の寺院で、「山号」は「玄林山」、「御本尊」は「薬師如来」で、1681年(天和元年)の「縁起」によれば、917年(延喜17年)の創建とされますが、807年(大同2年)の創建とも、天平年間(729年〜748年)「龍角寺」を開いた「釈命」の創建ともされています。
当初「勝光院延命寺」と称していましたが、上記の「印旛沼の龍神伝説」の「龍」の「胴」がこの地に落ち、それを祀ったことから「龍腹寺」と号したといわれています。
「龍尾寺」(2011年5月10日のブログ参照)は、「匝瑳市大寺」にある「真言宗智山派」の寺院で、山号は「天竺山」、「御本尊」は「釈迦如来」で、正式名は「天竺山尊蓮院龍尾寺」です。
「匝瑳市」で最も古い歴史を持つ寺院で、境内にある「薬師堂」の前に立っている「石灯籠」は、古くからの「龍神信仰」を伝えています。
「印旛沼」に伝わる村人を救った「勇壮な龍の伝説」にゆかりのある「栄町」「印西市」「匝瑳市大寺」の「古寺」「龍角寺」、「龍腹寺」、「龍尾寺」。
「新年の初詣」に「龍神伝説」ゆかりの「龍寺めぐり」にお出かけしてみてはいかがでしょうか?
「龍寺めぐり」詳細
「龍角寺」
所在地 印旛郡栄町龍角寺239
問合わせ 0476-95-4224
「龍腹寺」
所在地 印西市龍腹寺626
問合わせ 印西市教育委員会生涯学習課 0476-42-5111
「龍尾寺」
所在地 匝瑳市大寺1856
問合わせ 0479-74-1379
備考
「印西市」にある「龍腹寺」には、「印西大師二十一番札所」でもある「仁王門・地蔵堂」が一般参拝可能で、南北朝期の制作と推定される「梵鐘」があり、「千葉県重要文化財」に指定されています。
また「龍角寺」の焼失した「塔」の「礎石」は、「穴」に溜まる「水」の「水位」が変わらぬことから「不増・不滅の石」と呼ばれています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=864 |
| 地域情報::成田 | 07:58 AM |
|
|
2012,01,01, Sunday
本日三つ目にご紹介するのは、近隣市「成田市」「成田山書道美術館」で本日1月1日(祝・日)〜3月4日(日)の期間開催されます「つどうみほとけ〜成田山新勝寺の仏教絵画」です。
「つどうみほとけ〜成田山新勝寺の仏教絵画〜」の開かれている「成田山書道美術館」は、「成田山新勝寺」の裏手に広がる緑豊かな「成田山公園」の一角にあります。
「四季折々の景観」を楽しみながら、「成田山書道美術館」の扉を開けるとそこには「書の世界」が待っているそうです。
「成田山書道美術館」入り口正面、「企画展示ホール」の正面には高さ13.3m、幅5.3mもの「原拓 紀泰山銘」が「来館者」を出迎えます。
この「拓本」は、「中国」の「名山・泰山」にある「碑」のものです。
広い館内には、江戸時代後期以降の「書道の名作」が多数展示、収蔵され、「研究所」としての機能も兼ね備えているそうです。
「成田山書道美術館」で行われる「つどうみほとけ〜成田山新勝寺の仏教絵画〜」では、「成田山新勝寺」で所蔵する「不動明王二童子図」や「両界曼陀羅図」などのほか、「釈迦堂」に貼り込まれていた「狩野一信」「風神雷神図」を初公開するそうです。
また、1階では「成田山書道美術館」所蔵の「江戸の書」を、「特別展示室」では、「九重年支蒐集」の「豆雛」を展示するそうです。
「成田山新勝寺」には「不動明王図」をはじめとしてさまざまな「仏教絵画」が所蔵されています。
「尊像」は、古くから「新勝寺」に参詣する者を温かく見守ってきました。
「不動明王」が「制多迦(せいたか)・矜羯羅(こんがら)両童子」を伴い、「曼陀羅図」では、「大日如来」を中央に配して多くの「尊像」が周囲を取り巻いているように、それらの多くは、単体ではなく、複数の「尊像」が集合する形で描かれています。
それぞれに異なる「尊影」を巧みに書き分ける「画工」の手腕は、それを見る人びとの「心」に「みほとけのおしえ」を染みわたらせるようです。
「初詣客」で賑わう「成田山新勝寺」の「仏教絵画展」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「つどうみほとけ〜成田山新勝寺の仏教絵画」詳細
開催期間 1月1日(祝・日)〜3月4日(日)
開催会場 成田山書道美術館 成田市成田640
開館時間 9時〜16時 (最終入館〜15時30分)
休館日 月曜日 (祝日の場合は翌日)
入館料 大人500円 大高生300円
問合わせ 0476-24-0774
備考
「つどうみほとけ〜成田山新勝寺の仏教絵画」の開催される「成田山書道美術館」は1月中は無休で営業するそうです。
また正月三が日は「開・閉館」ともに30分延長するそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=862 |
| 地域情報::成田 | 09:32 AM |
|
|
2011,12,30, Friday
本日三つ目にご案内するのは、近隣市「成田市」「宗吾霊堂」で大晦日夜半から1月1日(祝・日)から行われます「新年大護摩修行」です。
「新年大護摩修行」の行われる「宗吾霊堂」(2010年12月23日のブログ参照)は、「真言宗豊山派」で、「義民」「木内宗吾様」(「佐倉宗吾」・「木内惣五郎」)のお墓があることでも知られています。
また「義民」「木内宗吾伝」を「立体パノラマ」で知ることが出来る「宗吾御一代記館」も「宗吾霊堂」内にあります。
「宗吾霊堂」は、新年の「初詣」スポットとして人気で、多くの人々が訪れています。
また「宗吾霊堂」新春恒例の「新年大護摩修行」では、新たな第一歩を踏み出す新年にあたり、皆様の「家内安全」・「商売繁盛」・「厄除招福」・「所願成就」を祈念し「大護摩」を修行しているそうです。
「新年大護摩修行」は、元旦0時・1時・2時・6時・10時(以降1時間おきに16時まで)に催行されます。
1月2日から3日は、6時半・10時(以降1時間おきに16時まで)催行。
1月4日から9日は、10時以降1時間おきに16時まで催行。
1月10日からは10時〜15時まで随時修行されるそうです。
なお1月中の土・日曜日は、11時・14時に「大護摩」を修行されるそうです。
「新年大護摩修行」の行われる「初詣期間中」は、「宗吾霊堂」境内周囲の「駐車場」が大変に混雑しますので、「公共交通機関」の利用をお願いしているそうです。
また1月中は「有料駐車場」となります。
(大型1500円、小型700円)
「成田の名刹」「宗吾霊堂」で行われる「新年大護摩修行」。
この機会にご祈祷しに「宗吾霊堂」「東勝寺」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「新年大護摩修行」詳細
開催日時 1月1日(祝・日) 0時00分〜
開催会場 宗吾霊堂 成田市宗吾1558
問合わせ 0476-27-3131
備考
「宗吾霊堂」では、「大晦日」の日に「除夜の鐘つき」を体験できるそうです。
また当日は、地元若衆「宗和会」によって、温かい「汁物」や「甘酒」が振る舞われるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=856 |
| 地域情報::成田 | 10:20 AM |
|
|
2011,12,30, Friday
本日二つ目にご紹介するのは、近隣市「芝山町」「航空科学博物館」でお正月の三が日に行われます「お正月行事」です。
「航空科学博物館」(6月7日のブログ参照)は、「成田国際空港」に隣接した「山武郡芝山町」にある「日本最初」の「航空専門」の「博物館」です。
1989年(平成元年)8月1日に開館した「航空科学博物館」には、管内施設に本格的な「飛行機」の展示物の数々を見ることができたり、マニア垂涎の「航空機器」展示、「屋外展示場」に「各種航空機」を10機以上を展示、また「エアロコマンダー680」、「R-22」、「セスナ175」などの「プロペラの回る飛行機」や「ヘリコプター」に搭乗できる「有料体験装置」があります。
また「大型旅客機」の「シュミレーション」「DC-8シミュレーター」や、「パイロット」気分で「コックピット」に乗り込んだりする「747-400大型可動模型」などがあります。
(12月10日のブログ参照)
また「航空科学博物館」「展望台(展望室)」では「ガイド」の説明を参考に「成田国際空港」の離着陸する「航空機」を見ることができます。
年始にかけ「航空科学博物館」では、3つの「お正月行事」として「1番機と初日の出をみよう」、「航空アート展」「ヴィンテージポスター」、「飛行機工作教室」を行うそうです。
「1番機と初日の出をみよう」の内容ですが、「元旦」の朝5時に開館し、「成田国際空港」に新年に飛来する「1番機」と「初日の出」を5階「展望展示室」から見ることができる毎年恒例の企画なのだそうです。
「航空アート展」「ヴィンテージポスター」は、「ボーイング747」と前後の時代を象徴する「ジェット旅客機」をテーマにした「ヴィンテージポスター」を展示するというものです。
「飛行機工作教室」の内容ですが、新しい年のはじまりに良く飛ぶ「紙飛行機」を作って飛ばしてみようという企画です。
上手に飛ばすコツなども説明するそうです。
「芝山町」の「大人の社会見学スポット」「航空科学博物館」の「お正月行事」に参加してみませんか?
「航空科学博物館の正月行事」詳細
「1番機と初日の出をみよう」
開催日時 1月1日(祝・日) 5時〜17時
「航空アート展」「ヴィンテージポスター」
開催期間 1月1日(祝・日)〜3月25日(日)
「飛行機工作教室」
開催期間 1月2日(月)〜4日(水)
開催時間 13時〜14時半
参加料金 無料 (入場料別途)
定員 40名
申込方法 当日10時から受付
「航空科学博物館」詳細
所在地 山武郡芝山町岩山111-3
開館時間 10時〜17時(最終入館16時半) 1月1日は5時〜開館
休館日 月曜(祝日の場合は翌日) 12月29日〜1月いっぱい無休
入場料金 大人500円 中高生300円 4才以上200円
問合わせ 0479-78-0557
備考
「航空科学博物館」は年末12月29日から31日まで休館日となっていますのでご注意下さい。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=855 |
| 地域情報::成田 | 10:17 AM |
|
|
2011,12,30, Friday
本日ご紹介するのは、近隣市「成田市」「成田国際空港旅客ターミナルビル」で年始の1月1日(祝・日)に行われます「新春航空安全祈願祭」です。
「航空安全祈願祭」は、「成田国際空港旅客ターミナルビル」において「航空機」及び「空港」をご利用になる「お客様」の「安全」と「国際交流」の「推進」、ならびに日本の「お正月の風習」を皆様に味わっていただき、「地域」と「空港」の共存共栄を目的として、毎年「元旦」に執り行われている「行事」です。
「新春航空安全祈願祭」式典の内容ですが、「成田山新勝寺」「大導師」「職衆」による「安全法楽」、「成田国際空港」への「乗入れ社」への「護摩札」授与及び「鏡開き」が行われるそうです。
「式典」終了後には、「お客様」への「屠蘇(とそ)」の「振る舞い」を行います。
「屠蘇」に使用した「枡(ます)」は「お土産」にお持ち帰りいただけるそうです。
また「お正月の風習」に触れていただけるよう、「筝」・「尺八」の「演奏」(イベントスペース「SKYRIUM(スカイリウム)にて」)及び「獅子舞の披露」(「屠蘇振る舞い所」にて、一ヶ所につき約15分ほど)も行われます。
「筝・尺八 演奏」は「第2旅客ターミナルビル」「3階国際線出発ロビー」イベントスペース「SKYRIUM(スカイリウム)」にて、「清野さおり」さん、「清野樹盟」さんによる「演奏」が披露され、「獅子舞」は「第1旅客ターミナルビル」「4階国際線出発ロビー」「南ウイング」「北ウイング」(2ヶ所)にて、「三里塚天神囃子」によります「獅子舞」が披露されるようです。
世界の玄関口「成田国際空港」の新春恒例の催し「新春航空安全祈願祭」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「新春航空安全祈願祭」詳細
開催日時 1月1日(祝・日) 8時〜8時20分
開催会場 成田国際空港旅客ターミナルビル 成田市三里塚御料1-1
問合わせ (社)成田市観光協会 0476-22-2102
備考
「鏡開き」後の「屠蘇」「振る舞い」ですが、一ヶ所の「樽酒」は72リットル入っているそうです。
ちなみに「樽酒」は、「成田」の「銘酒」「長命泉」(1月19日のブログ参照) です。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=854 |
| 地域情報::成田 | 10:14 AM |
|
PAGE TOP ↑
|
 |



