 |
■CALENDAR■
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
<<前月
2026年02月
次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■POWERED BY■
■OTHER■
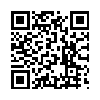
携帯からもご覧いただけます
|
2016,03,06, Sunday
本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「佐原の町並み」、「小野川」、「与倉屋大土蔵」「特設会場」で3月12日(土)に開催されます「第4回さわら雛舟」「第4回小江戸さわら春祭り」です。
「佐原の町並み」は、「香取市」「佐原」の「市街地」にある「歴史的」な「建造物」が残る「風情」のある「町並み」です。
「佐原」は、江戸時代に「利根川東遷事業」により「舟運」が盛んになると、「小野川」(2012年9月7日のブログ参照)には、「物資」を「陸」に上げるための「だし」と呼ばれる「河岸施設」が多くが作られました。
明治以降もしばらくは「繁栄」は続き、「自動車交通」が発達し始める昭和30年(1955年)頃までにかけて、「成田」から「鹿島」にかけての「広範囲」な「商圏」を持つ「まち」となっていました。
上記のように「利根川水運」で栄えた「商家町」の「歴史的景観」を「今」に残す「佐原の町並み」が、「佐原」の「市街地」を「南北」に流れる「小野川」沿い、「佐原の市街地」を「東西」に走る「香取街道」、及び「下新町通り」などに見ることができます。
「佐原の町並み」ですが、「佐原」が最も栄えていた江戸時代末期から昭和時代前期に建てられた「木造町家建築」、「蔵造り」の「店舗建築」、「洋風建築」などから構成されています。
「佐原の人々」は、「江戸の文化」を取り入れ、更にそれを「独自の文化」に昇華していて、「江戸優り(エドマサリ)」といわれるほど栄えていたそうで、「当時」の「面影」・「歴史景観」を今に残し、またそれを活かした「まちづくり」に取り組んでいることが認められ、「佐原の町並み」は、平成8年(1996年)12月、「関東」で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」(重伝建)に選定されています。
「佐原の重伝建」は昔からの「家業」を引き継いで今も「営業」を続けている「商家」が多いことから、「生きている町並み」としても評価されています。
「重要伝統的建造物群保存地区」には、「佐原の偉人」「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)が過ごし、寛政5年(1793年)建築された「伊能忠敬旧宅」(国指定史跡)(2012年2月24日のブログ参照)のほか、「千葉県」の「県指定有形文化財」も8軒(13棟)が「小野川」沿いや「香取街道」沿いに軒を連ねています。
「重要伝統的建造物群保存地区」「千葉県指定有形文化財」ですが、大正3年(1914年)建築の「三菱館」(2012年1月27日のブログ参照)、「土蔵」が明治元年(1868年)「店舗」が明治28年(1895年)建築の「福新呉服店」(2012年4月29日のブログ参照)、「店舗」が安政2年(1855年)「土蔵」が明治25年(1892年)以降に建築の「中村屋商店」(2012年5月21日のブログ参照)、明治13年(1880年)建築の「正文堂書店」(2013年6月22日のブログ参照)、「店舗」が天保3年(1832年)「土蔵」が明治元年(1868年)建築の「いかだ焼き本舗正上」(2011年12月28日のブログ参照)、「店舗」が明治25年(1892年)「土蔵」が明治23年(1890年)建築の「小堀屋本店」(2012年8月31日の
ブログ参照)、、明治25年(1892年)建築の「中村屋乾物店」、「店舗」が明治33年(1900年)「土蔵」が寛政10年(1798年)に建築の「旧油惣商店」が指定されています。
「樋橋(トヨハシ)」(2012年2月13日のブログ参照)は、「香取市」「佐原」に架かる「橋」で、「通称」「ジャージャー橋」とも呼ばれています。
「樋橋」ですが、もともと江戸時代に「小野川」「上流」でせき止めた「農業用水」を「佐原」の「関戸方面」(現「佐原駅方面」)の「田」に送るために「小野川」に架けられた、大きな「樋(トヨ)」だったそうで、その「樋」を「人」が渡るようになり、昭和時代に「コンクリート橋」に、1992年(平成4年)に現在の「橋」になったそうで、「橋」を造る際に、かつての「ジャージャー橋」の「イメージ」を再現するため、「水」が落ちるように造られたそうです。
なお「樋橋」ですが、1996年(平成8年)に、「環境省」の「日本の音風景100選」に選定されています。
「小野川」は、「香取市」を流れる「一級河川」で「利根川水系」「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)の「支流」です。
「利根川」の「支流」である「小野川」は、江戸期より「水運の集散地」として「佐原のまち」を発展させました。
「小野川」は「農業用水」としても古くから利用され、「香取市」「牧野地先」に「堰」を造り、「樋橋」をかいして「市内」「関戸方面」や「本宿耕地方面」に「水」を引いていましたが、1951年(昭和26年)に「国鉄」(当時)「佐原駅」「北側」に「小野川」から「掘り込み式」の「佐原港」が完成しましたが、「船」の需要がなくなっていたため、1970年(昭和45年)に埋め立てられています。
2004年(平成16年)には、「佐原」の「市街地」の「洪水」を解消するため「香取市」「牧野地先」から「本宿耕地地先」「利根川」まで流す「小野川放水路」が完成しています。
「与倉屋大土蔵」は、「香取市」「佐原」にある「土蔵」で、明治22年「建造」の「日本最大級」の「大土蔵」です。
「与倉屋」ですが、江戸末期より「醤油」の「醸造業」を戦前まで営み栄えた「佐原の商家」で、現在は「倉庫業」を営んでいるそうです。
「与倉屋大土蔵」ですが、「店」の「向かい」の「蔵」で、戦後まで「年貢米」の「貯蔵庫」として使われており、より広く「作業場」を確保するため、「柱」を「最小限」に減らす「小屋組み」という「手法」となっています。
「何層」にも張り巡らされた美しい「梁」と、500畳分の「空間」の「広さ」はまさに圧巻で、現在では、「蔵」の持つ独特な「雰囲気」を活かして「イベント」や、「コンサート」などに利用されています。
「与倉屋大土蔵」は、普段「蔵内」を見ることはできないそうで、「道路」沿いから「外観」を見ることができるそうです。
また「倉庫」の中には「佐原の大祭」で以前使用されていた「山車」が保管されているそうです。
「さわら雛めぐり」(2015年2月6日・2014年1月26日・2013年2月16日・2012年2月2日・2011年2月10日のブログ参照)ですが、今年(2016年)で「11回目」の開催となる「催し」で、「佐原の町並み」、「佐原の商家」などを「会場」にして行われている「佐原まちぐるみ博物館」(2011年12月26日のブログ参照)の「季節」毎に開催している「イベント」のひとつで、「佐原まちぐるみ博物館」は、「佐原の商家」の「おかみさんたち」により結成された「佐原おかみさん会」(2011年2月5日のブログ参照)によって運営されています。
「第11回さわら雛めぐり〜お雛さまの舟遊び〜」(201年1月28日のブログ参照)ですが、2月7日(土)から3月29日(日)までの「期間」開催され、「佐原」の古い「商家」に伝わる、どこか「憂い」を帯びた「お雛様」を「店先・店内」に飾り、「情緒」ある「佐原の町並み」をめぐりながら、それぞれ違った「お雛様」に会いに、「まちあるき」(まちめぐり)する「北総の小江戸」「佐原のまち」ならではの「新春恒例」の「催し」です。
「さわら雛舟」は、2013年(平成25年)から行われている「催し」で「佐原まちぐるみ博物館」を運営している「佐原おかみさん会」と「観光推進協議会」が共催、開催されている「イベント」です。
「さわら雛舟」は、「佐原」の「早春イベント」「さわら雛めぐり」の「メインイベント」として開催され、「舟」を「雛壇(ヒナダン)」に見立てて「行列」をつくり、荘厳な「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)の「雅楽」が奏でられる中、仮装した「お雛様」が「舟」に乗り、「小野川」を下る「水上飾り雛流し」(水上雛まつりパレード)という「内容」で行われています。
今年(2016年)で4回目を迎える「さわら雛舟」ですが、3月12日(土)に開催され、「雛舟」は1日3回運航されます。
「第4回さわら雛舟」の「会場」(コース)ですが、「小野川」で、「伊能忠敬旧宅」前より運航され、「平安装束」を着た「お雛さま」、「お内裏さま」、「五人囃子」、「官女」、「稚児」が「舟」に乗り、「香取神宮」の「雅楽」が奏される中、「小野川」を「舟」で進みます。
なお「第4回さわら雛舟」の「運航時間」ですが、11時00分〜、13時30分〜、15時00分〜となっており、「小雨決行」、「ゆるキャラ」も登場するそうです。
「小江戸さわら春祭り」も、2013年(平成25年)から行われている「イベント」で、「さわら雛めぐり」「期間中」「さわら雛舟」と同日開催されています。
今年(2016年)で4回目を迎える「小江戸さわら春祭り」ですが、「与倉屋大土蔵」を「特設会場」にして行われている「イベント」で、3月12日(土)に開催されます。
「第4回小江戸さわら春祭り」の「内容」ですが、「佐原囃子」(2012年2月23日のブログ参照)の「演奏」や「手踊り」の「披露」、「ブラスバンド」の「演奏」が行われるほか、約8mの「迫力」ある「山車(ダシ)」の「展示」、「北総地域」の「物産市」の開催、「佐原」、「香取」の「北総の幸」が振る舞われます。
ちなみに「佐原囃子」は、「香取市」「佐原」の「一大行事」で「夏」(八坂神社祇園祭)(2015年7月7日・2014年7月8日・2013年7月10日・2012年7月9日・2011年7月11日のブログ参照)と「秋」(諏訪神社秋祭り)(2015年10月9日・2014年10月8日・2013年10月10日・2012年10月10日・2011年10月3日のブログ参照)に年2回開催されている「佐原の大祭」(2011年7月13日のブログ参照)などで演奏されている「祭囃子」で、「神田囃子」、「京都祇園囃子」と並ぶ「日本三大囃子」のひとつに数えられている「お囃子」で、もともとは「佐原」周辺の「神楽」の「囃子方」が「山車」に乗り込み、「神楽囃子」を演奏したものに、「江戸」の「様々」な「文化」を取り入れようとした「佐原」の「町衆達」が、文化文政期に活躍した「義太夫奏者
(ギダユウソウシャ)」・「豊竹式太夫」を「客人」として迎え入れ、「構想」12年から13年かけて作り上げられたのが、今日(コンニチ)の「佐原囃子」なのだそうです。
「第4回小江戸さわら春祭り」では、「特設ステージ」が設けられ、「佐原囃子」の「披露」、「篠笛奏者」の「片野聡」さんの「演奏」ほか、多彩な「イベント」が行われ、上記のように「小江戸さわら春祭り」「会場内」には、「佐原の大祭」で実際に曳き廻されている約8mの迫力ある「山車」を特別展示するほか、「水郷地域」・「北総地域」の「物産販売」(千葉県物産展)など、「食」の「魅力」を広くPRするそうです。
「第4回小江戸さわら春祭り」の「ステージスケジュール」は、下記の通りです。
会場 与倉屋大土蔵特設会場
10時45分〜 下座演奏 (恵寿美会)
11時05分〜 篠笛演奏 (片野 聡)
11時25分〜 手踊り (花柳 もよ)
12時00分〜 篠笛演奏 (片野 聡)
12時40分〜 手踊り (花柳 もよ)
13時10分〜 下座演奏 (佐原中学校)
13時30分〜 篠笛演奏 (片野 聡)
13時50分〜 手踊り (花柳 もよ)
14時20分〜 下座演奏 (佐原中学校)
14時35分〜 篠笛演奏 (片野 聡)
「第4回さわら雛舟」、「第4回小江戸さわら春祭り」が行われる「香取市」では、3月5日(土)から3月12日(土)の「期間」、「JR東日本」の「イベント」「駅からハイキング」が開催されます。
「駅からハイキング」ですが、「事前予約不要」の「無料」の「ハイキングイベント」となっています。
「風情」ある「北総の小江戸」「佐原の町並み」、「小野川」、「与倉屋大土蔵」で開催される豪華絢爛(ゴウカケンラン)な「平安雛装束」が「川面」に映える「水郷佐原」ならではの「催し」「第4回さわら雛舟」、「伝統芸能」が披露される「イベント」「第4回小江戸さわら春祭り」。
この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「第4回さわら雛舟」詳細
開催日時 3月12日(土) 11時〜
開催会場 佐原の町並み 香取市佐原イ
小野川
「第4回小江戸さわら春祭り」詳細
開催日時 3月12日(土)(日) 10時〜16時半
開催会場 与倉屋大土蔵特設会場 香取市佐原イ1730
問合わせ 水郷佐原観光協会 0478-52-6675
備考
「第4回さわら雛舟」、「第4回小江戸さわら春祭り」の開催される「会場」周辺(小野川両岸)では、「交通規制」(歩行者天国)が行われるそうです。
「交通規制区間」は、「本宿側」は、「佐原小学校」「田宿町側」角地から「共栄橋」、「新宿側」は、「与倉屋」角地から「共栄橋」の「区間」となっています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2868 |
| 地域情報::香取 | 10:25 AM |
|
|
2016,03,05, Saturday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山新勝寺」で3月6日(日)に開催されます「第26回全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」です。
「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照)は、「成田市」にある「真言宗智山派」の「寺」であり、「真言宗智山派」の「大本山」のひとつです。
「成田山新勝寺」は、1000年以上の「歴史」をもつ「全国有数」の「霊場」で、「成田」を「代表」する「観光地」でもあり、「正月3が日」には約300万人、「年間」約1000万人以上の「参拝客」が訪れています。
「成田山新勝寺」の「御本尊」は「不動明王」で、「成田山新勝寺」は上記のように「関東地方」「有数」の「参詣人」を集める「著名寺院」で、「家内安全」、「交通安全」などを祈る「護摩祈祷」のために訪れる方が多い「不動明王信仰」の「寺院」のひとつであり、「成田のお不動さま」の「愛称」で親しまれています。
「成田山新勝寺」の「御本尊」である「不動明王」ですが、「真言宗」の「開祖」「弘法大師」「空海」が自ら「一刀三礼」(ひと彫りごとに三度礼拝する)の「祈り」をこめて「敬刻開眼」された「御尊像」なのだそうです。
「成田山新勝寺」では、この「霊験」あらたかな「御本尊」「不動明王」の「御加護」で、千年以上もの間、「御護摩」の「火」を絶やすことなく、「皆様」の「祈り」が「一体」となり「清浄」な「願い」となって現れるそうです。
「成田山新勝寺」は、「開山1080年」を間近に控えた現在も「成田山のお不動さま」として数多くの「人びと」の「信仰」を集めています。
「成田山」の「開山の祖」「寛朝大僧正(カンチョウダイソウジョウ)」は、延喜16年(918年)に生まれ、天慶3年(940年)「平将門の乱」を鎮めるため「朱雀天皇」の「勅命」により「関東」に下り、「この地」に「成田山新勝寺」が開山されました。
「寛朝大僧正」は、「皇室」との「血縁」もある大変に「格」の高い「僧侶」で、後に「真言宗」初めての「大僧正」に任じられ、「成田山」の他にも「京都」に「遍照寺」を開山しているそうです。
「成田山新勝寺」は、上記のように平安時代中期に起きた「平将門の乱」の際、939年(天慶2年)「朱雀天皇」の「密勅」により「寛朝大僧正」を「東国」に遣わしたことに「起源」を持ちます。
「寛朝大僧正」は、「京」の「高雄山」(神護寺)「護摩堂」の「空海」作の「不動明王像」を奉じて「東国」へ下り、翌940年(天慶3年)、「海路」にて「上総国」「尾垂浜」に上陸、「平将門」を調伏するため、「下総国」「公津ヶ原」で「不動護摩」の「儀式」を行ったそうです。
「成田山新勝寺」では、この天慶3年を「開山の年」としています。
「平将門の乱」「平定後」の永禄年間(1566年)(永禄9年)に「成田村一七軒党代表」の「名主」が「不動明王像」を背負って「遷座」され「伽藍」を建立された「場所」が、現在の「成田市」「並木町」にある「不動塚」周辺と伝えられており、「成田山発祥の地」といわれています。
「成田山新勝寺」の「寺名」ですが、「また新たに勝つ」という「語句」に因み「新勝寺」と名づけられ、「東国鎮護」の「寺院」となったそうです。
「成田山新勝寺」では、平成20年(2008年)に「開基1070年祭記念大開帳」が行われ、これにあわせて、平成19年(2007年)には「総欅造り」の「総門」が「落慶」され、「新勝寺」の「表玄関」として「荘厳」な「たたずまい」を見せています。
この「総門」は、開かれた「庶民のお寺」「成田山」と「門前町」とをつなぐ「担い手」として、「大開帳」を記念し創建されたもので、「総門」前にある「門前広場」は「参拝客」の「憩いの場」となっています。
「成田山新勝寺」ですが、「総門」をくぐって、「境内」に入ると大きな赤い「提灯」のある「仁王門」があり、「境内」には、数多くの「建造物」が立ち並んでいます。
「仁王門」から「東海道五十三次」にならった53段の「石段」を上がると、「成田山」の「シンボル」である「大本堂」が現れ、「成田山新勝寺」「大本堂」では、「世界平和」と「人々の幸せ」を願って「開山」以来「毎日」欠かさずに「御護摩祈祷」が厳修されています。
「成田山新勝寺」の「伽藍」ですが、「JR」および「京成電鉄」の「成田駅」から「成田山新勝寺」への「参道」が伸び、「参道」を10分ほど歩き、「急」な「石段」を上った先の「台地上」に「境内」が広がっています。
「石段」の「途中」に「仁王門」、「石段」を上った先に「正面」に「大本堂」、その手前「右手」に「三重塔」、「鐘楼」、「一切経堂」などが建っています。
この他、「大本堂」の「左手」に「釈迦堂」、「大本堂」の「背後」の「一段」高くなった「地」には「額堂」、「光明堂」、「開山堂」、「成田山平和大塔」(2012年5月7日のブログ参照)などが建っており、「成田山新勝寺」「境内」の「東側」は「広大」な「成田山公園」(2011年11月8日・2010年11月12日のブログ参照)があります。
「成田山新勝寺」にある「釈迦堂」、「光明堂」、「表参道」にある「薬師堂」(2013年5月22日のブログ参照)ですが、「歴代」の「成田山」の「大本堂」です。
これほどの「数」の「御堂」が現存している「寺院」は大変珍しく、それぞれの「建物」には「建立時」の「建築様式」を「今」に伝えており、江戸中期から末期の「建物」である「仁王門」、「三重塔」、「釈迦堂」、「額堂」、「光明堂」の「5棟」が「国」の「重要文化財」に指定されています。
「全国氷彫刻展」は、「NPO法人日本氷彫刻会」が主催している「イベント」です。
「NPO法人日本氷彫刻会」「総本部」の「活動」として、大きなものですが、例年2月に「北海道」「旭川」で開催される「氷彫刻世界大会」、例年7月に「東京」で開催される「全国氷彫刻展夏季大会」なのだそうです。
「NPO法人日本氷彫刻会」は、「全国」に「北海道」、「関東」、「東日本」、「西日本」、「東海」、「四国」、「九州」の7つの「地方本部」と、「地方本部」に属していない「宮城県支部」があり、それぞれ「各地」の「イベント」で、「氷彫刻」の「大会」や、「作品展示」を行って活動しています。
例として「北海道地方支部」ですが、「北海道」「旭川」で開催される「氷彫刻世界大会」の他、「札幌支部」の「会員」は、「さっぽろ雪まつり」の「すすきの氷の祭典」に出品、「大氷像」の「制作」にかかわり、「釧路支部」の「会員」ですが、「帯広氷まつり」で「作品制作」など、「総本部」の「行事」の他に「各地」で活躍しています。
「氷彫刻」は「過去」において、地域的には「北国」の、そして特殊な「技術」を持つ、特定の人たちのものという「社会的認識」があったそうですが、「日本氷彫刻会」は、昭和35年(1960年)に、その前身「全国氷彫刻研究会」という「名前」で発足して以来、「南」は「沖縄」から「北」は「北海道」まで、それぞれの「地域」に「活動」の「拠点」を置き、たとえば「南国地域」での「氷彫刻」の「素晴らしさ」をPRしたり、「北国地域」の「冬まつり」などにおける「イベント」で、「一般の方」に対して、「氷彫刻技術」の「指導」・「助言」・「支援」を行うなどの「活動」を続けてきたそうです。
「全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」(2015年3月4日・2014年3月1日・2013年3月8日・2012年3月7日・2011年2月27日のブログ参照)ですが、「成田山新勝寺」「境内」で行われている「氷彫刻」の「大会」で、迫力溢れる「制作」の「過程」を「ライブ」で楽しめ、「氷彫刻」の「職人」の「皆さん」の「芸術品」を愛(メ)でる「イベント」となっています。
「全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」は、例年「成田山公園」を「会場」に行われる「人気」の「催し」「成田の梅まつり」(2016年2月2月18日・2015年2月17日・2014年2月16日・2013年2月11日・2012年2月9日・2011年2月10日のブログ参照)の「期間中」の「日曜日」に開催され、多くの「観光客」、「鑑賞客」、「地元」の「皆さん」で賑わいます。
「第26回全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」ですが、3月6日(日)に「成田山新勝寺」「大本堂」前「広場」周辺を「会場」に執り行われます。
「第26回全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」では、1基270kgの四角い「氷柱」を、「氷彫刻」の「職人たち」の「熟練の技」により、約20基それぞれに、「彫刻」が施された「様々」な「氷彫刻」の「形」に作り上げていく様子を、間近で鑑賞することができ、「氷の塊」が「芸術品」となる様子を楽しむことができます。
「第26回全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」では、「冬」ならではの「氷の芸術品」が、「壮大」な「成田山新勝寺」「大本堂」を「バック」に、雄々しく立ち並ぶ様は、圧巻だそうです。
「第26回全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」の「スケジュール」は、下記の通りです。
10時15分 開会式
(大本堂正面階段踊り場/雨天時・大本堂第一講堂)
10時30分 競技開始
12時30分 競技終了・審査
13時00分 特別大護摩参詣「成功成就」
14時15分 表彰式
「真言宗智山派」の「大本山」「成田山新勝寺」で開催される「氷彫刻」の「展示・観賞会」「第26回全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」。
この機会に「成田市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「第26回全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」詳細
開催日時 3月6日(日) 10時15分〜
開催会場 成田山新勝寺 成田市成田1
問合わせ 成田山新勝寺 0476-22-2111
備考
「第26回全国氷彫刻展成田山新勝寺大会」ですが、「小雨決行」で行われるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2855 |
| 地域情報::成田 | 01:16 PM |
|
|
2016,03,05, Saturday
本日ご紹介するのは、地元「銚子市」「ありがとう外川駅」で3月9日(水)に開催されます「ありがとうを叫ぼう」です。
「銚子電気鉄道株式会社」(2012年2月11日のブログ参照)は、「銚子市」(2010年9月20日のブログ参照)に「鉄道路線」を有する「鉄道会社」で、「銚子電鉄」あるいは、「銚電」と「略称」されています。
「銚子電鉄」は、「全長」6.4kmの「銚子駅」(2011年5月7日のブログ参照)から「外川駅(トカワエキ)」(2011年7月7日のブログ参照)までの「10駅」を約20分で結ぶ「地元客」、「観光客」の「皆さん」に「人気」のある「ローカル鉄道」です。
「銚子電気鉄道株式会社」の「路線」の「延長」(距離)ですが、「芝山鉄道」(千葉県・2.2km)、「紀州鉄道」(和歌山県・2.7km)、「岡山電気軌道」(岡山県・4.7km)、「水間鉄道」(大阪府・5.5km)、「流鉄」(千葉県・5.7km)に次いで、「全国」で「6番目」に短い「鉄道」なのだそうです。
「銚子電気鉄道株式会社」ですが、1913年(大正2年)に、現在の「銚子電気鉄道」にあたる「銚子」から「犬吠」間の「鉄道路線」を開業したものの、「利用不振」から1917年(大正6年)に「路線」を廃止して解散した「銚子遊覧鉄道」の「関係者」が、再び「路線」を復活させるために「銚子電鉄」を設立したそうです。
その後、「銚子電鉄」は、1922年(大正12年)7月5日に「銚子」から「外川」間を開業、1948年(昭和23年)8月20日に「銚子電気鉄道」に「社名変更」しており、「銚子電鉄」は、2012年(平成24年)に「開業」90周年を迎えています。
当ブログでは、「銚子電気鉄道株式会社」「各駅」の「見どころ」や、「おすすめスポット」を、「銚子電鉄」「各駅見処紹介」と題し、「東日本旅客鉄道」(JR東日本)・「銚子電気鉄道」(銚子電鉄)の「共同使用駅」「銚子駅」(JR東日本・管理)から、「仲ノ町駅(ナカノチョウエキ)」(2011年5月11日のブログ参照)、「観音駅」(2011年5月14日のブログ参照)、「本銚子駅(モトチョウシエキ)」(2011年5月16日のブログ参照)、「笠上黒生駅(カサガミクロハエエキ)」(2011年5月20日のブログ参照)、「西海鹿島駅(ニシアシカジマエキ)」(2011年5月26日のブログ参照)、「海鹿島駅(アシカジマエキ)」(2011年5月28日のブログ参照)、「君ヶ浜駅(キミガハマエキ)」(2011年5月31日のブログ参照)
、「犬吠駅(イヌボウエキ)」(2011年6月21日のブログ参照)、「外川駅」の「順」に、「銚子電気鉄道株式会社」の「各10駅」を紹介し、「銚子電鉄」「各駅」の「特徴」、「歴史」、「周辺見処紹介」をアップしています。
ちなみに「銚子電鉄」の「起点」は、上述のように「銚子駅」で、「終点」は「外川駅」、「駅数」10駅(起終点駅含む)、「複線区間」なしの「全線単線」、「最高速度」40km/hの「鉄道」です。
「外川駅」は、「銚子」の「漁業」(2012年1月24日のブログ参照)「発祥」の「地」である「外川漁港」(2013年1月4日のブログ参照)を有し、「漁村」でもある「銚子市」「東南部」「外川町2丁目」(「外川町」の「北部」)にある「銚子電気鉄道株式会社」の「駅」(終点)です。
「外川駅」ですが、「単式ホーム」1面1線と、「機回し線」(留置線)1線を有する「地上駅」で、修復を繰り返しながらも「銚子電鉄」「開業時」より建つ「平屋」の「木造駅舎」を有しています。
「外川駅」「駅舎内」の「待合室」には、「木製」の「ベンチ」が並び、「夜」は「白熱電球」が点灯しています。
「外川駅」は、「駅員配置駅」でもあり、「硬券入場券」・「乗車券」、「各種鉄道グッズ」の「展示」および「発売」をしています。
「外川駅」周辺には、「外川集落」の「案内」などが提示され、「駅舎内」「ベンチ」には「地元住民」「手作り」の「座布団」が置かれています。
「外川駅」が位置する「外川町」は、上述のように「銚子市」「東南部」の「まち」で、「外川」(2010年12月13日のブログ参照)ですが、江戸時代初期に「崎山治郎右衛門」によって、「外川漁港」とともに同時に開かれた「まち」で、緩い「斜面」に「碁盤(ゴバン)の目状」に整った「区割り」がされています。
また「坂のまち」として知られている「外川」は、「まち」の「特色」をなす「大小」8つの「坂道」に、「通り名」を記した「プレート」が埋め込まれており、「坂」の多い「外川のまちあるき・坂あるき」が楽しめるようになっています。
「坂道」8つの「通り名」は、下記の通りです。
王路
阿波通り
長屋通り
新浦通り
一条通り
一心通り
本浦通り
条坊通り
「外川のまちあるき・坂あるき」の「発着点」である「銚子電鉄」の「外川駅」は、2007年(平成19年)4月に、「日経新聞」から発表された「訪ねる価値のある駅ベスト10」で「見事」10位に輝いています。
ちなみに「外川漁港」は、「銚子市」「外川町」にある「第2種漁港」で、「銚子市」の「南部」に位置し、「外川漁港」「背後」には「台地」があり、「外川漁港」周辺「集落」は「斜面」と、「低地」にあり、「水郷筑波国定公園」(2012年8月3日のブログ参照)の「区域内」にあります。
「外川漁港」周辺ですが、「東側」は「犬吠埼」(2012年4月16日のブログ参照)、「南側」は「屏風ヶ浦(ビョウブガウラ)」(2012年5月20日のブログ参照)から「九十九里浜」(2012年5月11日のブログ参照)に続いています。
「外川漁港」の「沿革」ですが、1658年(万治元年)「紀州」「有田郡」「広村」出身の「崎山治郎右衛門」氏によって、「本浦」築港。
その後、「外川漁港」は、1661年(寛文元年)に「新浦」の竣工、その後「外川漁港」は、1952年(昭和27年)2月29日に、「第2種漁港」に指定されています。
「外川漁港」で「水揚げ」される主(オモ)な「魚種」ですが、「金目鯛(キンメダイ)」(2011年2月14日・2010年11月17日のブログ参照)、「アカムツ」、「クロムツ」となっています。
「銚子電気鉄道株式会社」は、昨年(2015年)「駅名」の「ネーミングライツ」(命名権)の「販売」を行う「事業」「駅名愛称ネーミングライツ事業」を実施し、「県内外」から「遊技業者」、「土木工事会社」、「IT企業」など6社が応募し、2015年(平成27年)12月から7駅に「愛称」が付けられました。
昨年12月時点の「駅名愛称ネーミングライツ事業」で決まった「駅」の「愛称」は、下記の通りです。
仲ノ町駅 カクタ パールショップともえ
観音駅 藤工務所 藤工務所
笠上黒生駅 メソケアプラス 髪毛黒生
西海鹿島駅 根本商店 三ツ星お米マイスター根本商店
海鹿島駅 藤工務所 藤工務所 文芸の里
君ヶ浜駅 MIST solution ミストソリューション
犬吠駅 沖縄ツーリスト One Two Smile OTS 犬吠埼温泉
「銚子電気鉄道株式会社」「駅名愛称ネーミングライツ事業」の「契約」は1年更新となっており、「初年度」は830万円の「増収」となったそうです。
ちなみに「銚子電気鉄道株式会社」「駅名愛称ネーミングライツ事業」の「命名権」ですが、「銚子駅」を除く、「仲ノ町駅」から「外川駅」までの9駅を80万円〜200万円で募集しており、「本銚子駅」と、「外川駅」の2駅は、引き続き「スポンサー」を探しており(2015年12月時点)、「命名権販売」(ネーミングライツ)の「収入」は安全な「運行確保」のための「車両維持費」などに充てられるそうです。
「銚子電気鉄道株式会社」「駅名愛称ネーミングライツ事業」ですが、上記のように「笠上黒生駅」の「愛称」が、「ヘアケア商品」を扱う「都内」の「企業」より「髪毛(カミノケ)黒生」になるなどユーモアあふれる「命名」もあり、「銚子電鉄」「名物」の「ぬれ煎餅(センベイ)」(2011年9月9日のブログ参照)の「生地」を納入する「地元」「銚子市」の「老舗米穀販売店」「根本商店」は、「西海鹿島駅」の「愛称」「三ツ星お米マイスター根本商店」の「命名権」を取得、「君ヶ浜駅」の「愛称」「ミストソリューション」は、「地名」「君ヶ浜」の素とされている「霧の浜」から転じたとされることより命名され、「犬吠埼灯台」(2011年1月1日のブログ参照)に近い「犬吠駅」の「命名権」を購入した「沖縄ツーリスト」(那覇市)は、「知名度」が低い「一帯」の「温泉」をPRしようと「One Two Smile OTS 犬吠埼温泉」としたそうです。
また「銚子電気鉄道株式会社」では、新しい「駅名看板」を設置し、「銚子電鉄」「車内」での「新・駅名」の「車内放送」を開始しています。
なお今年(2016年)に入り「銚子市」に「しょうゆ製造工場」がある「ヒゲタ醤油」(東京都・中央区)(2011年9月10日・2010年12月20日のブログ参照)が、「銚子電気鉄道株式会社」が販売する「駅名愛称ネーミングライツ事業」「命名権」(ネーミングライツ)を購入し、「本銚子駅」の「愛称」を「ヒゲタ400年玄蕃(ゲンバ)の里」と命名したそうです。
また「同社」が募集していた「駅名愛称ネーミングライツ事業」で、「銚子電鉄」「終点」「外川駅」の「命名権」(ネーミングライツ)を「松戸市」の「早稲田ハウス(株)」(代表取締役・金光容徳氏)が取得、2016年(平成28年)2月11日(祝・木)から「銚子電鉄」「外川駅」の「愛称」を「ありがとう外川駅」としました。
「銚子電気鉄道株式会社」では、「ありがとう外川駅」誕生を祝って、2月11日(祝・木)9時00分より「銚子電鉄」「外川駅」を「会場」に、「ありがとう外川駅」「誕生式」(2016年2月10日のブログ参照)を行いました。
この度(タビ)「銚子電気鉄道株式会社」では、「銚子電鉄」「ありがとう外川駅」を「会場」に「ありがとうを叫ぼう」を開催するそうです。
「ありがとうを叫ぼう」は、3月9日(水)の「ありがとう記念日」の16時30分から17時30分まで開催され、「参加費」「無料」で行われます。
ちなみに「ありがとう記念日」とは、「サン(3)キュー(9)」の「語呂合わせ」で、日頃言えない「ありがとう」を伝える「日」で、「全米感涙協会」が制定された「記念日」、「ありがとう」を伝えたい「人」が生きていることに感謝する「日」でもあるそうです。
「ありがとうを叫ぼう」では、「卒業式を前にお世話になった先生や友達にありがとうを伝えたい人」、「日頃なかなか感謝の気持ちを伝えられない家族」、「子供に生まれてきてくれてありがとうを伝えたいお父さん、お母さん」等、「ありがとう」を伝えたい「方」を募集しています。
「ありがとうを叫ぼう」「式次第」は、下記の通りです。
第1部 「ありがとうポスト」お披露目式
第2部 全米感涙協会認定式
認定1 感涙駅第1号「ありがとう外川駅」 (銚子電鉄×早稲田ハウス)
認定2 感涙ポスト第1号「ありがとうポスト」 (銚子電鉄×銚子郵便局)
第3部 「ありがとう」イベント
1 感涙映画の上映
2 ギフトブック「ありがとう」(あさ出版)の朗読
3 「銚子電鉄ありがとう外川駅でありがとうを叫ぼう」イベント
「ありがとうを叫ぼう」の「イベント内容」は、下記の通りです。
・ありがとう外川駅のホームで思いを伝えたい人が日頃の「ありがとう」を伝えたい相手に感謝を伝えてありがとうと叫ぶ!
・「ありがとう記念日」感涙駅第1号認定記念「一日乗車券弧廻手形」販売 (限定100枚 700円)
※3月9日(水)9時00分〜 「ありがとう記念日」感涙駅第1号認定記念一日乗車券弧廻手形をありがとう外川駅窓口で販売するそうです。
3月9日(水) 9時00分〜 ありがとう外川駅窓口で「ありがとう葉書」を無料配布 (限定39枚)
「ありがとうを叫ぼう」を参加される「方」の「イベント当日」の「流れ」ですが、下記の通りです。
1 ありがとうを伝えたい方と一緒に16時30分までにありがとう外川駅に集合。
2 ありがとう外川駅のホームで感謝の気持ちを伝えて「ありがとう」を叫ぶ。
3 参加者には、オリジナル「ありがとうポスト貯金箱」プレゼント
「銚子観光」の「シンボル」のひとつ「銚子電鉄」「ありがとう外川駅」で開催される「ありがとうイベント」「ありがとうを叫ぼう」。
この機会に「銚子市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「ありがとうを叫ぼう」詳細
開催日時 3月9日(水) 16時半〜17時半
開催会場 銚子電鉄ありがとう外川駅 銚子市外川町2-10636
問合わせ 銚子電気鉄道株式会社 0479-22-0316
備考
「ありがとうを叫ぼう」参加の際の「駐車場」ですが、「銚子信用金庫」「外川支店」となっていますが、「銚子電鉄」では、「駐車場」「台数」に限りがあるので、なるべく「公共交通機関」の「利用」を呼びかけています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2871 |
| 地域情報::銚子 | 10:16 AM |
|
|
2016,03,04, Friday
本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」で募集している「城山公園さくら開花予想クイズ」です。
「香取市」は、2006年(平成18年)3月27日に「佐原市」・「山田町」・「香取郡」「小見川町」・「栗源町(クリモトマチ)」の「1市3町」が合併(新設合併)し、誕生した「市」です。
「香取市」は、「千葉県」の「北東部」に位置し、「北部」は「茨城県」に接し、「首都」「東京」から70km圏、「世界の空の玄関口」(WORLD SKY GATE)「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)から15km圏に位置しています。
「香取市」「北部」には、「水郷」の「風情」が漂う「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)が「東西」に流れ、その「流域」には「水田地帯」が広がり、「香取市」「南部」は「山林」と「畑」を「中心」とした「平坦地」で、「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の「一角」を占めています。
「香取市」には、「日本」の「原風景」を感じさせる「田園」・「里山」や、「水郷筑波国定公園」(2012年8月3日のブログ参照)に位置する「利根川」周辺の「自然景観」をはじめ、「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)のひとつである「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)、「舟運」で栄えた「佐原のまち」には「日本」で初めて「実測日本地図」「大日本沿海輿地全図」を作成した「佐原の偉人」「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)の「旧宅」(国指定史跡)(2012年2月24日のブログ参照)、江戸時代から昭和初期に建てられた「商家」や「土蔵」が、現在も、その「姿」を「今」に残し、「関東地方」で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている「佐原の町並み」など「見どころ」が多い「市」であり、「香取市」は「水」と「緑」に囲まれ、「自然」・「歴史」・「文化」に彩られた「まち」として知られ
ています。
「香取市」「小見川地区」は、「香取市」「東部」に位置する「水辺」と「自然」に恵まれた「地域」です。
「香取市」「小見川地区」「中心部」は「低地」で、「西部」と「東部」に「丘陵」が見られ、「小見川地区」は、「水の郷百選」に選ばれており、「水と緑の文化」をはぐくむ「まち」として知られています。
「香取市」「小見川地区」にも「佐原地区」と同じように、「利根川」の「舟運」で栄えた「老舗」が今も残り、「先祖」から続く「家業」を引き継いで「商売」を続けている「店舗」もあり、「風情」のある「佇まい」は、今も「小見川地区」「市街」のところどころに残っています。
「水郷の小江戸」(北総の小江戸)「佐原」の「東」、「銚子」へ向かう途中に位置する「小見川」は、江戸時代から「利根川舟運」の「中継港」、「街道の要衝」、「宿場町」、さらに「小見川藩の陣屋町」として発展してきました。
「小見川」は、現在の「国道356号線」である「佐原銚子街道」と「地方道28号線」である「旭街道」が合流し、江戸時代初期には、すでに「小見川宿」として発展しており、「周辺舟運」を背景に「小見川」は「町場化」していったそうです。
さらに「小見川」は、「銚子」から「江戸」「間」を結ぶ「内川廻り」の「中継港」しての「機能」に加え、「周辺農村」及び「干潟地方」から「八日市場方面」に渡る「広域米」や「諸産物」を集め、「江戸方面」へ積み出す「利根川水運」の「集散地」として発展していきました。
当時の「小見川」では、2と7の「日」には「六斎市」が開かれ、他に「須賀神社」、「妙剣神社」の「祭礼市」も開かれるほど賑わっていたそうです。
江戸期の「小見川」は、「本町」・「新町」を初め、「8町」に分かれる「規模」であり、「醸造業」も盛んで発達しており、「小見川」の「醸造業」ですが、「醤油」5軒、「酒蔵」4軒、「濁酒」5軒の「記録」があり、現在も「小見川」には、1軒の「酒蔵」と、1軒の「醤油醸造業」が存続しています。
「小見川城山公園」(2011年2月26日のブログ参照)は、「香取市」「小見川」で、「桜」や「躑躅(ツツジ)」の「名所」として知られている「公園」です。
「小見川城山公園」ですが、「城山」の名前の通り、平安時代にかけ、「豪族」「栗飯原氏」の「城」が築かれたと伝えられる「小見川城址」があり、今でも「本丸跡」に「土塁」、「空堀」、「土橋」、「曲輪」といった「城」の一部が残っているほか、古代の「城山古墳群」と呼ばれる「古墳群」もあります。
ちなみに「小見川城址」ですが、1199年(建久10年)に「栗飯原朝秀」氏が、築城したと伝えられています。
「栗飯原氏」は、中世の「下総国」「香取郡」「小見川郷」(香取市小見川)「一帯」を領した「千葉氏」の「古族」です。
「栗飯原」は、「アイハラ」、「アイバラ」と読み、平安時代末期、「平常長」「四男」・「栗飯原常基」を「祖」とし、戦国末期までの約五百年、「小見川周辺」を領していたそうです。
「小見川城山公園」は、「茨城県」と「千葉県」を繋(ツナ)ぐ「利根川」を跨(マタ)いだ「小見川大橋」から「国道356号線」「小見川大橋入口交差点」から「千葉県道・茨城県道44号線」「成田小見川鹿島港線」「成田方面」へ0.7kmのところに位置しています。
「小見川城山公園」は、「下総台地」(北総台地)上に位置するため、「小見川市街地」や「鹿嶋・神栖方面」を望むことができます。
「小見川城山公園」内には、「遊具」が整備された「アスレチック広場」や「チビッコ広場」、「わんぱく広場」のほか、「茶会」や「華道」などの「集まり」もできる「数寄屋造り」の「清風荘」などあり、「清風荘」ですが、「有料」で借りることができる「施設」となっており、「子ども」から「大人」まで利用できる「公園」となっています。
「小見川城山公園」には、70種あまり、約6000本の「様々」な「樹木」が植えられ、「四季」を通じて、いろいろな「花木」が楽しめる「公園」となっています。
「小見川城山公園」ですが、「四季」の中でも「春」には、1000本の「染井吉野(ソメイヨシノ)」と4000本の「躑躅(ツツジ)」が「小見川城山公園」の「山一帯」に咲き乱れ、「北総随一」の「花見の名所」であり、「桜の名所」として知られています。
ほかにも「小見川城山公園」では、「夏」の「紫陽花(アジサイ)」や「百日紅(サルスベリ)」、「秋」の「アベリア」や「金木犀(キンモクセイ)」などが咲き、「行楽」に訪れる「花見客」、「家族連れ」の「目」を楽しませています。
「小見川城山公園」で、「桜」、「躑躅」が咲き誇る3月下旬から5月初旬にかけて「水郷おみがわ桜つつじまつり」(2015年3月31日・2014年3月30日・2013年3月30日・2012年3月24日のブログ参照)が開催されており、「千葉県さくらの名所20選」にも選定されています。
「水郷おみがわ桜つつじまつり」は、1931年(昭和6年)に「小見川」に「鉄道」が開通されたことを「きっかけ」に始まったとされている「イベント」です。
「水郷おみがわ桜つつじまつり」の「はじまり」ですが、1945年(昭和20年)代後半に「小見川」の「観光協会」の「皆さん」が「城山」(小見川城山公園)に「ボンボリ」を灯し、今のかたちの「桜まつり」の「原形」ができ、現在まで「桜つつじまつり」が開催され続けられています。
当時の「小見川城山公園」は、「個人所有」の「別荘」であったそうで、その後、「城山」は「町」(旧・小見川町)に寄付され、「城山公園」として整備され、以前より「盛大」な「桜まつり」として現在に引き継がれています。
「桜」は「香取市」の「木」として、また「小見川」の「春のシンボル」として、80年以上にわたり、多くの「人々」から愛され続けている「桜まつり」として「水郷おみがわ桜つつじまつり」は行われています。
「小見川城山公園」のある「香取市」の「水郷小見川観光協会」は、毎年「春」に実施している「水郷小見川さくらつつじまつり」「開催」に先駆け、「小見川城山公園」の「桜」の「開花日」を当てる「クイズ」「城山公園さくら開花予想クイズ」(2015年2月26日・2014年2月25日・2013年2月24日・2012年2月22日・2011年2月26日のブログ参照)を実施しています。
そして本年(2016年・平成28年)も「城山公園さくら開花予想クイズ」が行われます。
上記のように「小見川城山公園」は、「千葉県内有数」の「さくらの名所」として知られ、「小見川城山公園」「園内」には1000本ほどの「桜」が植えられており、「城山公園さくら開花予想クイズ」の「クイズ」の「対象樹」ですが、「小見川城山公園」「園内」の「城山公園観光案内所」「脇」にある「大桜」(ソメイヨシノ)の「桜の花」となっており、「大桜」の「桜の花」が5輪開いた「状態」を「開花」としています。
「城山公園さくら開花予想クイズ」は、上記のように「城山公園観光案内所」「脇」「大桜」5輪の「開花」を当てる「クイズイベント」で、「城山公園さくら開花予想クイズ」では、「正解者」の中から抽選で、「豪華商品」をプレゼントするそうです。
「城山公園さくら開花予想クイズ」「豪華商品」ですが、「正解者」の中から抽選で、1名に「液晶テレビ」、3名に毎年8月1日に行われる「小見川の夏の風物詩」「水郷おみがわ花火大会」(2015年7月31日・2014年7月31日・2013年7月31日・2012年7月29日・2011年7月28日・6月15日・2010年7月28日のブログ参照)の「花火大会桟敷席」(6人用)をプレゼントするそうです。
また「城山公園さくら開花予想クイズ」「特別賞」として、「応募者全員」の中から3名の「方」に、「城山公園特製高級箸」(当選者名前入り)が当たるそうです。
「城山公園さくら開花予想クイズ」の「応募方法」ですが、「はがき」に「開花予想日」・「郵便番号」・「住所」・「氏名」・「年齢」・「電話番号」・「このクイズを何でお知りになったか」を記入し、下記まで「ご応募」となっています。
〒287-8501 香取市佐原ロ2127番地
水郷小見川観光協会事務局 (香取市商工観光課観光班) 「城山公園さくら開花予想クイズ」係
となっています。
なお「応募」ですが、1人1枚と限らせていただいており、「締め切り」ですが、3月7日(月)までに「ご応募」下さいとのことです。
(注釈・当日消印有効)
なお、今年(2016年・平成28年)の「水郷おみがわ桜つつじまつり」ですが、4月1日(金)から5月8日(日)まで開催され、「会場」の「小見川城山公園」には、「ソメイヨシノ」などの「桜」1000本と、「つつじ」4000本が「山一帯」に咲き乱れ、「昼夜」問わず多くの「花見客」が訪れるそうです。
「水郷おみがわ桜つつじまつり」ですが、特に「夜」、「城山公園観光案内所」周辺と、「赤橋」周辺は「ボンボリ」で「ライトアップ」され、「幻想的」な「夜桜」が楽しめ、また、「水郷おみがわ桜つつじまつり」「期間中」4月上旬の「土日」には、「野点(ノダテ)」、「お花見コンサート」等の「イベント」が実施されるそうです。
「北総随一」の「さくらの名所」「小見川城山公園」「恒例・クイズイベント」「城山公園さくら開花予想クイズ」。
この機会に「応募」してみてはいかがでしょうか?
「城山公園さくら開花予想クイズ」詳細
上記「ブログ」参照
問合わせ 香取市商工観光課小見川担当 0478-50-1212
備考
「城山公園さくら開花予想クイズ」の昨年(2015年・平成27年)の「開花日」ですが、3月27日で、「応募総数」336人中、「正解者」は41人だったそうです。
なお「城山公園さくら開花予想クイズ」の「過去」(桜の開花日)は、下記の通りとなっています。
2009年(平成21年)3月23日
2010年(平成22年)3月27日
2011年(平成23年)4月2日
2012年(平成24年)4月4日
2013年(平成25年)3月19日
2014年(平成26年)3月27日
2015年(平成27年)3月27日
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2853 |
| 地域情報::香取 | 02:34 AM |
|
|
2016,03,03, Thursday
本日ご紹介するのは、近隣市「芝山町」「航空科学博物館」で3月5日(土)・6日(日)に開催されます「航空ジャンク市」です。
「航空科学博物館」(2011年6月7日のブログ参照)は、「航空」に関する「科学知識」について、その「啓発」を図り、もって「航空思想」の「普及」及び「航空科学技術」の「振興」に寄与し、あわせて「日本」の「航空」の「発展」に資することを「目的」に、「総合的」な「航空思想普及施設」として「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)側に平成元年(1990年)に、「山武郡」「芝山町」「岩山」に開館しました。
「航空科学博物館」ですが、「中央棟」、「西棟」、「東棟」、「展望塔」、「屋外」からなり、「地上2階一部5階」の「建物」が構成されています。
「航空科学博物館」「1階」「中央棟」には、「アンリ・ファルマン複葉機」の「実物大復元模型」(イラスト有り)と、「ピストン・エンジンコーナー」、「ミュージアムショップ」「バイプレーン」があり、「航空科学博物館」「1階」「西棟」には、「ボーイング747大型模型」(操縦体験可能・要「整理券」)と「ボーイング747」の「客室」・「コックピット」・「タイヤ」、「DC-8前脚」、「旅客機の胴体比較」(DC-8とYS-11)、「DC8シミュレーター」(パイロット訓練用シミュレーターを改修したもの)があります。
「航空科学博物館」「2階」「中央棟」には、「下田画伯」の「イラスト」による「飛行機のあゆみ」と、「日本の名機」と「歴史的」な「ソリッドモデル」、「西棟」には、「小型機」・「ヘリコプター」の「コックピット」(「操縦席」に座れます)と「戦前」・「現在」の「パイロット」の「制服比較」、「東棟」には、「NAAコーナー」と、「エコエアポートコーナー」、「成田国際空港」を「インターネット」や「ビデオ」、「模型」等で紹介する「コーナー」があります。
「航空科学博物館」「2階」「東棟」にある「成田国際空港」を紹介する「NAAコーナー」ですが、2014年(平成26年)3月25日に「リニューアルオープン」しています。
「航空科学博物館」「NAAコーナー」ですが、「成田空港ジオラマ」、「音の体験ルーム」、「情報コーナー」、「エコエアポートコーナー」からなり、「様々」な「方向」から「成田国際空港」について学べる「施設」となっており、白く「スタイリッシュ」な「デザイン」に一新された「成田空港ジオラマ」と、「楽しく、分かりやすく」を「コンセプト」に「内容」を一新した「音の体験ルーム」がリニューアルされています。
「航空科学博物館」「3階」は、「展望台」(屋上)となっており、「成田国際空港」を「離着陸」する「ジャンボ」を「間近」に眺め、「迫力」ある「航空機」の「エンジン音」を体験できるようになっています。
「航空科学博物館」「4階」は、「展望レストラン」「バルーン」となっており、「展望レストラン」「バルーン」では、「成田国際空港」の素晴らしい「眺め」を見ながら「食事」ができます。
「航空科学博物館」「5階」では、「ガイドの説明」(土・日・祝日中心)を「参考」に「離着陸」する「ジャンボ」を見ることができるそうです。
「航空科学博物館」「屋外」には、「航空機」と「多目的広場」があり、「小型機」や「ヘリコプター」の「実物」を展示、「YS11試作1号機」(イラスト有り)や「セスナ195」「朝風」(イラスト有り)等があり、「有料搭乗航空機」として「プロペラ」が回る「飛行機」や「ヘリコプター」に搭乗できる「有料体験装置」があるそうです。
「航空科学博物館」の「沿革」ですが、下記の通りとなっています。
1977年(昭和52年) 地元自治体の芝山町より成田空港の開港に関連した博物館建設の要望が運輸大臣に提出される。
1984年(昭和59年) 博物館の建設・運営の事業主体となる財団法人航空科学振興財団が設立。
1988年(昭和63年) 博物館工事に着工。
1989年(平成元年) 8月1日 開館。
1994年(平成6年) 入館者100万人を達成。
1999年(平成11年) 成田空港第1ターミナルビル内にミュージアムショップ「バイプレーン」を開店。
2004年(平成16年) 1月18日 入館者300万人を達成。
2011年(平成23年) 6月23日 成田国際空港株式会社が航空科学博物館敷地(駐車場)内に成田空港闘争の史実や反対派のヘルメットなどを展示した資料館「成田空港空と大地の歴史館」を建設し、開館。
2012年(平成24年) 4月1日 公益財団法人航空科学博物館に移行。
「航空科学博物館」では、「航空」に関する「科学知識」に関する「講習会」、「講演会」、「見学会」、「航空教室」、「セミナー」等を開催しており、「四季折々」「様々」な「催し」、「イベント」を行っています。
また「航空科学博物館」では、「展示即売会」(「航空スケッチ大会」、「紙飛行機工作教室」、「航空機の部品」・「航空グッズ」の「販売」を行う「航空ジャンク市」等)などを催行しています。
「航空ジャンク市」(2013年9月5日のブログ参照)は、毎回「好評」を博している「航空科学博物館」の「恒例イベント」で、「航空ジャンク市」では、普段あまりお目にかかれない「航空部品」や「エアライングッズ」などを販売しており、多くの「航空ファン」、「航空マニア」の「皆さん」が訪れる「人気」の「イベント」です。
「航空ジャンク市」の「開催場所」ですが、「航空科学博物館」1F「多目的ホール」となっており、「料金」は「入館料」のみとなっています。
「航空ジャンク市」の「内容」ですが、「年」2回、3月及び9月に開催される「恒例イベント」で、上記のように、普段あまりお目にかかれない「航空部品」や「エアライングッズ」などを「格安」で展示・販売するといった「内容」となっています。
「航空ジャンク市」には、「旅客機」の「客室シート」をはじめ、「計器」などの「航空部品」、「エアライングッズ」などがラインナップされ、「航空マニア」垂涎(スイゼン)、「航空ファン」興奮の「航空グッズ」が販売され、「航空関連用品」の「蚤の市(ノミノイチ)」といった感じの「イベント」となっています。
過去に行われていた「航空ジャンク市」では、「人気」の高い「機内食用」の「食器」・「カトラリー」をはじめ、「パイロット用」の「シート」、「客室シート」、「計器類」、「アンテナ」、「緊急脱出用」の「ドア」、「機内食用カート」、「操縦捍」、「酸素マスク」などの「航空部品」、「飛行機」の「大型模型」、「エアライングッズ」などが数百円から数十万円の「価格」で販売されていました。
以前行われていた「航空ジャンク市」の「一例」ですが、2014年(平成26年)9月6日、7日に開催された「航空ジャンク市」では、「ボーイング」の「グッズ」、「JAL」や「ANA」といった「航空会社」の「グッズ」販売、その他「機内」で使われた「ポット」などの「食器類」や「航空会社」の「ブランケット」も販売されていました。
また、「飛行機」の「シート」と同じ「生地」を使用して作られた「バッグ」や「クッション」も販売され、「サインボード」、「レーダー」、「計器類」、「翼端」の「ライトカバー」、「小型旅客機」(B737)の「タイヤ」、「パイロットシート」、「エンジンカウル」等の「飛行機」の「様々」な「部品」、「ボーイング」や「エアバス」などの「服」や「バック」、「リフレクター付き」の「パーカー」、「飛行機」の「ダイキャスト」などが販売されていたそうです。
今年(2016年・平成28年)の「航空ジャンク市」ですが、3月5日(土)10時00分から17時00分までと、3月6日(日)10時00分から16時00分までの「2日間」「航空科学博物館」「館内」「1階」を「会場」に開催され、「料金」ですが、「航空科学博物館」「入館料」のみで入館できます。
上記のように「航空ジャンク市」は、「年」2回、3月及び9月に「航空科学博物館」で開催されている「恒例イベント」で、普段あまりお目にかかれない「航空部品」や、「エアライングッズ」、「航空機模型」などを「格安」で販売するそうです。
今回の「航空ジャンク市」の「目玉」ですが、「新入荷」となる「エアラインポスター」・「デザインプレート」となっており、また「人気」の「機内カート」も「再入荷」されたそうです。
今回の「航空ジャンク市」、の「ラインナップ」「一例」ですが、「デザインプレート」(3000円〜)、「格安模型」(500円〜)、「計器類」(3000円〜)、「ボーイングロゴ入りグッズ」(600円〜)等となっており、「航空ファン」・「航空マニア」「垂涎」の「品々」がラインナップされるようです。
「航空専門」の「科学博物館」「航空科学博物館」で開催される「ならでは」の「人気恒例イベント」「航空ジャンク市」。
この機会に「芝山町」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「航空ジャンク市」詳細
開催日時 3月5日(土) 10時〜17時
3月6日(日) 10時〜16時
開催会場 航空科学博物館 山武郡芝山町岩山111-3
開館時間 10時〜17時 (入館〜16時半)
入館料 大人 500円 中高生 300円 4才以上 200円
休館日 月曜日 (月曜が祝日の場合は翌日)
問合わせ 航空科学博物館 0479-78-0557
備考
「航空ジャンク市」が開催される「航空科学博物館」では、3月1日(火)から3月6日(日)までの「期間中」、「航空ジャンク市」の「準備」の為に、「航空科学博物館」「館内」「1階」「多目的ホール」・「ライブラリー」の「利用」(休止)と、3月1日(火)、3月4日(金)から3月6日(日)までの「期間」「DC-8シミュレーター」は利用できません(休止)ので、ご注意下さい。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2852 |
| 地域情報::成田 | 08:31 PM |
|
|
2016,03,02, Wednesday
本日ご紹介するのは、地元「銚子市」「屏風ヶ浦(ビョウブガウラ)」の「国の名勝」、「国の天然記念物」「ダブル指定」です。
「屏風ヶ浦」(2012年5月20日のブログ参照)ですが、「銚子市」(2010年9月20日のブログ参照)「名洗町」を「北端」に、「旭市」「上永井」の「刑部岬(ギョウブミサキ)」(2012年5月26日のブログ参照)が「南端」となる、「海岸線」に連なる「断崖絶壁(ダンガイゼッペキ)」、延々と10kmにわたる「海食崖(海蝕崖)」(海岸の絶壁)のことです。
「屏風ヶ浦」は、「イギリス」と、「フランス」の間にある「ドーバー海峡」(英仏海峡)にある「白い壁(崖)」(ホワイトクリフ)に似ていることから、「東洋のドーバー」とも呼ばれ、「水郷つくば国定公園」(2012年8月3日のブログ参照)に属しています。
「屏風ヶ浦」の迫力ある「風景」は、「ドラマ」・「CM」・「映画」・「プロモーションビデオ」などの「ロケ地」としても好まれています。
「屏風ヶ浦」の「高さ」35m〜60mに及ぶ「岸壁」は、かつては「海底」であった「層」(「砂岩質」の「岩」の部分)の上に「関東ローム層」の「赤土」(「火山灰」が積もった「鉄分」が赤く酸化したもの)が堆積したものだそうです。
「屏風ヶ浦」から崩落した「石」は「潮流」に乗って「九十九里浜」(2012年5月11日のブログ参照)へと流れて行き、「海岸」に打ち上げられる、「九十九里」では「飯岡石」と呼ばれています。
「屏風ヶ浦」は、「砂岩質」の「土壌」が弱いのと、打ち寄せる「波」の「強さ」もあって、有史以来数キロに渡って「岸壁」は削られているそうです。
「銚子市」との「境界」付近には、かつて「通蓮洞(ツウレンドウ)」(2012年6月3日のブログ参照)(風蓮洞)と呼ばれる「海岸侵食」によるものと思われる「洞窟(ドウクツ)」が存在していましたが、現在ではほとんど埋没しています。
「屏風ヶ浦」は、「消波ブロック」の「設置」後、「陸地後退」は緩やかになりましたが、代わりに「九十九里浜」の「侵食」が見られ、「問題」となっているようです。
「屏風ヶ浦」は、「海辺」から「広範囲」にわたって「地層」の様子を観察できる「場所」が少ないことから、非常に「貴重」な「存在」として評価されているそうです。
なお、「屏風ヶ浦」は、「波」による「遭難」の「危険」を伴うため、実際に観察するために、「天候」が良いことや、観察できる「場所」(銚子マリーナ等)は限られています。
「屏風ヶ浦」ですが、「護岸工事」が行われる以前は「年間」50cm〜100cmの「ペース」で侵食され、過去700年間で6kmの「陸地」が侵食されており、かつて平安時代末期に、「源義経(ミナモトノヨシツネ)」「家臣」の「武将」「片岡常春」の居する「佐貫城」がありましたが、現在、その「城址」は「海中」に没してしまったそうです。
「屏風ヶ浦」は「夕陽」の美しい「ビュースポット」としても知られており、特に「秋」から「冬」にかけ、「屏風ヶ浦」の「先端」に沈む「夕陽」は「一見の価値」があります。
また「屏風ヶ浦」では、「年」に何度か「西風」の強い日に、遠く「海上」に「世界遺産」の「富士山」の「姿」を見ることができ、「感動的」な「風景」が現れるそうです。
「銚子市」では、2012年(平成24年)4月に「日本ジオパーク委員会」に「認定申請書」を提出、同年9月24日、「神奈川県」の「箱根」、「秋田県」の「八峰白神」、「秋田県」の「ゆざわ」、「静岡県」の「伊豆半島」と共に、「千葉県」の「銚子市」の5ヵ所を「地域」の「地形」や、「地質」を楽しめる「自然公園」「日本ジオパーク」に認定しました。
「銚子ジオパーク」(2012年9月25日のブログ参照)ですが、「地形」の「特徴」や、「市民」が自主的に「ガイド」を務める「取り組み」が評価されたそうです。
また「銚子ジオパーク」は、「関東」の「地下」にある「地層」が「海岸」で観察できる「屏風ヶ浦」や、「太平洋」に面した「海岸」に1億年以上前からの「地層」が「むきだし」となるなど「海岸沿い」にいくつもの「見どころ」があることなどから、評価されたようです。
「銚子ジオパーク」は、大きくわけて、4つの「ジオサイト」に分かれており、「屏風ヶ浦ジオサイト」、「愛宕山(アタゴヤマ)・千騎ヶ岩(センガイワ)・犬岩(イヌイワ)ジオサイト」、「黒生(クロハエ)・夫婦ヶ鼻(メドガハナ)・宝満(ホウマ)ジオサイト」、「犬吠埼(イヌボウサキ)ジオサイト」となっています。
「屏風ヶ浦ジオサイト」「詳細」は、下記の通りです。
銚子半島の南西側の海岸には、高さ40m〜50mの海食崖が約10kmにわたって続く、「屏風ヶ浦」があります。
屏風ヶ浦は、英国のドーバー海峡のホワイトクリフになぞられて、「東洋のドーバー」と呼ばれる景勝地です。
屏風ヶ浦では、新第三紀鮮新世から第四紀更新世に堆積した犬吠層群に属する名洗層、飯岡層と、香取層、関東ローム層が見られます。
名洗の遊歩道からは、これらの地層が西に向かって緩く傾斜している、雄大な景色を見ることができます。
名洗層と飯岡層は、西に緩く傾斜し、不整合で香取層に覆われます。
名洗層は、主に凝灰質砂岩からなり、ところどころに白いスジのように見える火山灰層を挟みます。
その上位の飯岡層は、青灰色を帯びた泥質凝灰岩が主体であり、名洗層とは時間間隔をおかずにほぼ整合で接しています。
飯岡層は不透水層であるため、その上を覆う透水性の香取層を通過した水が、ところどころで湧水として観察されます。
銚子半島の洪積台地を削る谷地形は、この湧水による谷頭(コクトウ)侵食により形成されたと考えられます。
田村ら(地質学雑誌、116(7)、360-373、2010)は、南関東に分布する250万年前の広域火山灰層の研究を行い、名洗層において、層厚2cmのざくろ石を含むテフラ層を報告しています。
この広域火山灰層は、2009年に改訂された新第三紀と第四紀の境界層付近に位置するとして、注目されています。
火山灰層を横に追って行くと、ところどころで正断層が観察されます。
これは、この地域が引っ張りの場であり、波による侵食に弱いことを示しています。
このため、屏風ヶ浦は、年間1m程度のペースで海岸が失われてきたと言われています。
屏風ヶ浦の台地(下総台地)では、春キャベツが日本一の生産量を誇り、安定した風力を利用して34基(2011年現在)の風力発電施設が設置されるなど、地形的・気候的な特徴を活かした土地利用がなされています。
※以上「銚子ジオパーク」「HP」「屏風ヶ浦ジオサイト」より抜粋、原文まま表記。
昨年(2015年)11月20日に開かれた「国」の「文化審議会」にて、「浮世絵師」・「歌川広重」の「大作」「六十余州名所図会」にも描かれた「屏風ヶ浦」を「国の名勝」及び「国の天然記念物」に指定するよう「文部科学相」に答申したそうです。
(その後、「官報告示」を経て、「国指定名勝」、「国指定天然記念物」に指定される「流れ」)
「屏風ヶ浦」が「名勝」及び「天然記念物」に指定されたことにより、「千葉県内」の「国指定名勝」は4件に、「特別天然記念物」を含めた「天然記念物」は17件となり、「国指定文化財」の「総数」は1件増え、133件となったそうです。
(平成27年11月20日現在) 「屏風ヶ浦」ですが、その「特徴的」な「景観」は江戸時代の「浮世絵師」・「歌川広重」の「六十余州名所図会」や、「文学作品」などに描かれており、「鑑賞上」の「価値」も高いとして、「国の名勝」の「指定」につながり、上記のように「急激」な「風化」と、「侵食」を受けて形成された「地形」が、「地質学上」の「価値」が高いと評価され、「国の天然記念物」の「指定」につながったそうです。
ちなみに「文化審議会」の今回(11月20日)の「答申」では、「屏風ヶ浦」(銚子市)など2件を「名勝」に、戦時中に「首相」を務めた「近衛文麿」が住み、「日米開戦」前の「重要」な「会議」の「舞台」になった「荻外荘(テキガイソウ)」(東京都)など9件を「史跡」に、「伊平屋島」の「念頭平松(ネントウヒラマツ)」(沖縄県)など5件を「天然記念物」に指定するよう、「馳浩文」「文部科学相」に答申されたそうで、近く「答申通り」告示され、「国の史跡」は1759件、「国の名勝」は398件、「国の天然記念物」は1021件になるそうです。
このほか「富士山」などを望む「景勝地」で「信仰の地」としても親しまれた「十国峠」(日金山(ヒガネサン))(静岡県)など3件を「登録記念物」にすることも答申、「登録記念物」は98件になり、また、「登録有形文化財」(建造物)には、「小高記念館」(館山市)など「全国」で124件が新たに登録され、「計」10492件となったそうです。
「屏風ヶ浦」の「国の名勝」および「国の天然記念物」の「指定地」、「面積」、「指定基準」、「文化財の概要」は、下記の通りです。
屏風ヶ浦
指定地
銚子市春日町744番1 他 (屏風ヶ浦の一部)
面積
218376.96平方m
指定基準
名勝の部
八 海浜、十一 展望地点
天然記念物
三 地質鉱物
(二)地層の整合及び不整合
(九)風化及び侵食に関する現象
文化財の概要
屏風ヶ浦は千葉県北東部に位置する下総台地を削る海食崖で、千葉県銚子市犬岩から旭市刑部岬まで、新第三紀鮮新世以降の地層から成る露岩の崖が約10kmにわたって連続する。
一億年以上前の硬い岩石を基盤として約300万年前〜40万年前の海洋性の環境で堆積した犬吠層群と、その上に不整合面で接する内湾的な環境で堆積した香取層や関東ローム層から成る。
切り立った落差約60mの崖は、比較的柔らかい火山灰層などから構成されており、波浪の影響で崖面から剥離・落下した土砂が沿岸流により常に運び去られることにより形成されてきた。
その侵食速度はかつて年間50cm〜100cmと急激であった。
江戸後期以降、その特徴的な地形が形作る景観が名所記や各所図会等の出版物に取り上げられるようになり、歌川広重の「六十余州名所図会」にも描かれた。
そのような絵図等によって、現地を訪れたことのない人々にも屏風ヶ浦の一定の印象が広がったと考えられる。
明治期以降は交通網が発達し、実際に訪れる人々も増加した。
また、海食崖や愛宕山からの景観は絵葉書やパンフレットなどの題材になるとともに、現在までさまざまな文学作品にも描かれてきた。
屏風ヶ浦の地形は、地質学上、また観賞上の価値が高く、重要である。
※千葉県HP 千葉県教育委員会「報道発表案件」より抜粋、原文まま表記
そして、平成28年(2016年)3月1日(火)「官報」に告示され、正式に「屏風ヶ浦」が「国指定文化財」(「名勝」および「天然記念物」)に指定されました。
「屏風ヶ浦」を含む「銚子市内」「全域」は、「貴重」な「地質」や、「地形」を保全しながら活用する「日本ジオパーク」に認定されていることから、「銚子ジオパーク推進協議会」「会長」を務める「越川信一」「市長」は、
「これまで以上にジオパーク活動の中でその価値を伝え、屏風ヶ浦の景観を後世に継承するため魅力を世界中へ発信していきたい」
とコメントしたそうです。
また「銚子市」では、今後、この素晴らしい「景観」をどのように守り、将来に伝えていくか、そして「観光」や「地域振興」につなげていくためどんな活用方法があるかを銚子市全体で考えていきましょうとコメントしています。
「銚子」の「景勝地」「屏風ヶ浦」の「国の名勝」および「国の天然記念物」の「ダブル指定」。
この機会に「銚子市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
備考
今回(昨年11月20日)の「答申」で、新たな「国登録有形文化財」(建造物)に指定されることも「実質的」に決定した「館山市」「館山」の「洋風建築」「小高記念館」ですが、大正11年ごろ、「館山市」に「本店」があった「旧・古川銀行」(現「千葉銀行」に合併)の「鴨川支店」として建てられ、昭和5年ごろに「現在」の「場所」に移築、「県議」、「衆院議員」を歴任した「小高憙郎(トシロウ)」氏の「事務所」などして使われていたそうです。
「小高記念館」ですが、「館山市」や、「安房文化遺産フォーラム」によりますと、「小高憙郎」氏の「没後」、平成18年(2006年)に「地元」の「安房文化遺産フォーラム」が「活動拠点」(事務所)として使用を始めたそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2920 |
| 地域情報::銚子 | 06:08 PM |
|
|
2016,03,02, Wednesday
本日ご案内するのは、となりまち「香取市」「木内大神」で3月3日(木)に開催されます「木内十二座神楽」です。
「木内大神(キウチタイジン)」は、「香取市」「木内」に鎮座する「神社」で、「木内大神」の「社格」は「郷社」です。
「木内大神」ですが、大同年間の「創建」といわれる「神社」で、「木内大神」の「御祭神」ですが、「豊受姫命(トヨウケビメノミコト)」で、「豊受姫命」ですが、「伊勢神宮」「外宮」より勧請されたそうです。
「木内大神」は、古くは「大納言」「四条隆房」が、この地を「領地」とした時から「保護」し、「木内胤朝」(「東胤頼」の「子」)が「社殿」を造営、「神領」を納め、「一族」の「祈願所」としたそうです。
「木内大神」ですが、「千葉氏」や「北条氏」の「崇敬」が厚く、「伏見天皇」の「直筆書」が献ぜられています。
「木内大神」ですが、1589年(天正7年)「栗飯原氏」が「社領」を、1591年(天正9年)「徳川家康」が「朱印地」の「一部」を寄付、1602年(慶長7年)「土井利勝」が「馬具一式」を納めています。
「木内大神」は、1639年(寛永16年)に、この地を領した「内田氏」も崇敬し、1736年(元文元年)「関宿城主」「久世大和守」も「祈願所」と定めています。
その後、「木内大神」は、1787年(天明7年)「正殿」を改造、1902年(大正9年)に「本社」、「拝殿」、「社務所」を改造しています。
「木内十二座神楽」(2012年2月29日のブログ参照)ですが、江戸時代後期、文化年間(1804年〜1818年)には、既に執行されていたといわれ、文政12年(1829年)には「神楽面」11面を修理したとの「記録」が残っているそうです。
「木内十二座神楽」は、明治以前は、「最寄り」の「神職」が相会して奉仕し、明治初期頃から「氏子」の「青年」により、行われるようになりました。
現在「木内十二座神楽」は、「地元」の「有志」で組織された「木内神楽保存会」によって「十二座神楽」が継承され、「氏子」の「安泰」と「五穀豊穣」・「商売繁盛」を祈願し、3月3日の「木内大神」「祭礼」に奉納されています。
「木内十二座神楽」では、「神楽舞人」は「猿田彦命」より、上記のように「氏子」の「安泰」と「五穀豊穣」・「商売繁盛」を願い舞うそうです。
「木内十二座神楽」の「演目」ですが、下記の通りとなっています。
「木内十二座神楽」「演目」
猿田彦の命
三宝荒神
天ノ鈿女命
天児屋根太玉命
天ノ乙女命
手力男命
榊葉
受持の命
八幡
恵比寿
稲荷大明神
種子蒔
素戔鳴命(スサノオノミコト)
「木内十二座神楽」ですが、上記の「12演目」を演じ、「最後」の「演目」が終わるのは、17時00分頃となるそうです。
「木内十二座神楽」ですが、「古事記」や「日本書紀」の「神話」を「題材」に、「舞踏化」した「岩戸神楽」・「神代神楽」の「系譜」にあるといわれ、「舞」の「構成」は、「仮面神」による「一人舞」を「基本」とし、「様々」な「持ち物」を使い、「お囃子」は「横笛」と「太鼓」などが用いられているそうです。
「香取市」「木内」に鎮座する「古社」「木内大神」で奉納されている「伝統芸能」「木内十二座神楽」。
この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「木内十二座神楽」詳細
開催日時 3月3日(木) 12時〜17時頃
開催会場 木内大神 香取市木内1166
問合わせ 香取市商工観光課 0478-50-1212
備考
「木内十二座神楽」ですが、「香取市」の「市指定無形民俗文化財」に指定されています。
「木内十二座神楽」は、4月3日に催行される「須賀神社」の「祭礼」にも奉納されています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2870 |
| 地域情報::香取 | 10:16 AM |
|
|
2016,03,01, Tuesday
本日ご紹介するのは、近隣市「匝瑳市」「ふれあいパーク八日市場」で3月6日(日)に開催されます「石油発動機展示会」です。
「ふれあいパーク八日市場」(2012年6月16日・5月1日・2010年9月11日のブログ参照)は、「東関東自動車道」「成田IC(ナリタインターチェンジ)」から「国道295号線」・「国道296号線」を「匝瑳市」「方面」に向かい、「東総広域農道」「入口」を左折し、「東総広域農道」を約7km(「成田IC」より約30分)、「県道八日市場・山田線」「交差点」にあります。
また「地域高規格道路」「千葉東金道路」(東金有料・東金道)「銚子連絡道」「横芝光IC(ヨコシバヒカリインターチェンジ)」からは、「国道126号線」を「匝瑳市方面」に向かい、「県道八日市場・山田線」へ入り、約4km(「横芝光IC」から約30分)、「東総広域農道」との「交差点」に「ふれあいパーク八日市場」があります。
「ふれあいパーク八日市場」には、1.5ha(ヘクタール)の「敷地」に「普通車」83台、「大型車」3台を収容できる「駐車場」を完備しています。
のどかな「田園風景」が広がる「匝瑳市」にある「ふれあいパーク八日市場」は、「安心・安全・新鮮な農産物、こだわりの匝瑳市産」を「皆様」にお届けするために、平成14年(2002年)3月17日に産声をあげた「都市と農村交流ターミナル」です。
「ふれあいパーク八日市場」では、「匝瑳の大地」をこよなく愛する「生産者」が、手塩をかけた「恵み」の「農産物」等の数々を、「見て・触って・食して」お楽しみいただける「施設」となっています。
「ふれあいパーク八日市場」ですが、2002年(平成14年)3月の開館以来、「施設」の「運用面」(交流・イベント、直売、レストラン運営事業等)については、「八日市場市ふるさと交流協会」(合併後は「八日市場ふるさと交流協会」に名称変更)が行っていましたが、「事業」を継続・拡大していく中で、「協会」が保有する「資産」や「雇用者数」が増加し、「財務運営」や「雇用計画」等について、「協会」は「法人格」を持たない「任意的団体」であったため、その「代表者」が「無限責任」を追わなければならないという「問題」が顕著となり、そこで「行政」としても何らかな「法人格」を有する「組織形態」への移行を検討する必要があると考え、「匝瑳市」と「協会」との双方で「法人化」を目指すことで意見が一致したそうです。
「ふれあいパーク八日市場」の「法人形態」に関しては、「協会」と「匝瑳市」の間で数回の協議を重ね、主に下記の理由から「第3セクター方式」による「有限会社」の設立を進めることで結論に達したそうです。
1 協会単独で有限会社になることは、ふれあいパーク八日市場が公共施設であるため難しいこと
2 NPO法人、株式会社についても検討したが、両法人形態の有する性質上、協会単独での法人化は困難であること。
3 第3セクター方式による有限会社形態をとることにより、公共施設の利用、交流協会の財務運営等について、官民一体となってすすめることが可能であること。
「第3セクター」による「有限会社」の設立に関して「協議」をする「機関」として「ふるさと交流協会第3セクター設立検討委員会」を設立したそうです。
「委員会」の「委員」には、「市」3名、「協会」3名、「農協」2名、「市観光協会」1名の「計」9名で構成し、「法人設立」を目指して検討を重ね、また「専門的」な「アドバイザー」として「千葉県農業会議」及び「会計事務所会計士」に必要な応じて出席を依頼したそうです。
なお、「委員会」においての「検討事項」ですが、「商号」、「資本金」、「社員」その「出資割合」、「役員」と、その「報酬」及び「営業年度」などであったそうです。
以上の「経緯」から、2005年(平成17年)12月1日に、「都市交流事業」・「各種イベント」の「企画運営」、「直売事業」、「レストラン運営」等を「目的」とする「ふれあいパーク八日市場有限会社」が設立されました。
「ふれあいパーク八日市場」の「会社概要」は、下記の通りです。
商号 ふれあいパーク八日市場有限会社
事業内容 都市と農村交流ターミナル
設立 平成13年11月1日
所在地 千葉県匝瑳市飯塚299-2
TEL 0479-70-5080 FAX 0479-70-5081
納入会員 ふるさと交流協会 会員数 128名
「ふれあいパーク八日市場」の「施設概要」ですが、「店舗」「入口」を入りますと、向かって右側に「農特産物コーナー」、左側に「文化コーナー」があります。
「ふれあいパーク八日市場」「農特産品コーナー」の「メイン」で販売しているのが、「匝瑳市産野菜」で、「キャベツ」、「ほうれん草」、「小松菜」、「トマト」などが「定番商品」で、どれをとっても「質」が良いと言われています。
また「ふれあいパーク八日市場」の「人気の秘密」ですが、「野菜」だけではなく、「農特産物」の「加工品」がとても「豊富」で、中でも「棒もち」、「卵焼き」、「卵焼きで巻いた太巻き寿司」等「人気の加工品」を求めに「近隣」から来店される方が多いそうです。
「ふれあいパーク八日市場」「店舗」「左奥」に「匝瑳産の食材」をふんだんに使った「料理」を提供している「レストラン・里の香」があります。
また「匝瑳市」は、「日本有数の植木のまち」(2011年9月30日のブログ参照)として知られており、「ふれあいパーク八日市場」「店舗」(本館)の「外」「西側」には「花・植木見本園」が設置されており、また「ふれあいパーク八日市場」「店舗」(本館)を抜けると、隣接する「飯塚沼農村公園」に行くこともできます。
「ふれあいパーク八日市場」では、「匝瑳産」の「新鮮な農産物」や、懐かしい「ふるさとの味」に出会える「憩いの場」として、「匝瑳市民」はもとより「近隣市町村」からも「大勢」の「来客」のある「人気スポット」となっています。
また「ふれあいパーク八日市場」では、「なにかがあるふれあいパーク」を「キャッチフレーズ」に、「毎週末」や「祝祭日」に、いろいろな「イベント」を行っています。
「石油発動機(セキユハツドウキ)」(オイルエンジン、ケロシンエンジン)は、「灯油」(ケロシン)を「燃料」とする「内燃機関」の「一種」です。
「石油発動機」の「基本構造」ですが、「ガソリンエンジン」とほぼ共通するものでありますが、「主」たる「燃料」を異にすることや、「用途」の「相違」があるため、両者は区別される事が多いそうです。
一方、「グローエンジン」(または「焼玉エンジン」)とは「点火方式」において「別種」のものですが、「用途」・使用された時代の「共通性」や、「名称」の「紛(マギ)らわしさ」などが「原因」で、「往々」にして混同されるそうです。
「石油発動機」は、「焼玉エンジン」よりは取り扱いが「容易」で、「ガソリンエンジン」と比較して「低圧縮」・「低回転」での「使用」が前提で、「構成部品」に高い「工作精度」を要求されないため、「点火用マグネトー」を除けば全般に「製作」が容易で、「地方」の「零細企業」などで広く製造されました。
1930年代から1950年代の「最盛期」には、「日本国内」でも「地方」の「小規模メーカー」に至るまで100近い「メーカー」が存在したと伝えられています。
かつては「石油発動機」は「農業」や、「漁業」に広く用いられましたが、「効率」が良い「小型ディーゼル発動機」の発達、および「小型軽量」で「高性能」、かつ取り扱い「容易」な「小型ガソリン機関」の「性能向上」と「竪型強制空冷」の「汎用機関」が少数製造されているに過ぎないそうです。
一方「現役」を引退したものに関しては、近年、「各地」の「熱心」な「愛好家」の「間」で復元されており、「発動機」を修理する「業者」も存在し、また、当時、製造していた「メーカー」から「模型」が販売されています。
「石油発動機」ですが、「灯油」を「主」たる「燃料」とする「レシプロエンジン」で、「ガソリンエンジン」と同様に「キャブレター」で「燃料」を霧化し、圧縮した「混合気」を「マグネトー」と、「点火プラグ」によって電気着火します。
「軽便」な「用途」を「目的」とすることから、その「全盛期」には一般に「低出力」・「簡易」な「単気筒型」がほとんどであり、「生産性」と、「強度確保」の「面」から「鋳造部品」を多用して製造されていました。
また安定の良い「水平シリンダ型」として、「木製」ないし「形鋼製」の「土台」(台枠)に固定され、「可搬性」を良くしてあるものも多く、「冷却装置」は「シリンダー」の「ウォータージャケット」「上部」に「ホッパー」を持つのみで、「冷却水」の「沸騰蒸発」により冷却を図る「ホッパー水冷式」が大半だそうです。
「原理」は「ガソリン機関」と変わりありませんが、気化しにくい「灯油燃料」でも作動する一方で、「灯油」の「発火点」は「ガソリン」より低く「ノッキング対策」のため「圧縮比」をあまり上げられず、「回転」も高くできないため「効率」が低く、「気化」を促進させる為に「吸気」を予熱する「設計」としたものもあったそうです。
比較的「初期」の「製品」の「吸気弁」は、「気筒内」の「負圧」に伴って自動的に開かれる「自動吸気弁」であることが多く、この点でも「高速回転」には向かないそうです。
「自動吸気弁型」は、「プッシュロッド」は「排気用」の1本のみを備え、第二次世界大戦後になってからは「石油発動機」でも1500〜1800rpm(アールピーエム)の「高速型」が増え、「吸気側」も「カム駆動」となり、「プッシュロッド」も2本となり、その「外観」から、現在では「愛好家内」ではそれぞれを「一本棒」、「二本棒」と呼称されているようです。
「灯油」は「気化性」が悪いため始動には適さず、「発動機」始動時のみ補助的に「ガソリン」を利用するそうで、「キャブレター」の「フロート室」に「ガソリン」を入れてから、「手動」による「弁開放操作」(「デコンプ」と呼ばれる)で「シリンダー圧縮」を機能させないようにしつつ、「ピストン」を「上死点」付近に移動させて始動準備をします。
始動は「フライホイール」の手回し、もしくは「出力軸」の「ロープ牽引」(一種のリコイルスターター)により、「勢い」を付けて「クランクシャフト」に初動の「回転」を与え、この「手動始動自体」は、「低圧縮比」と「ガソリン」の「着火性」の「良さ」から、「予備作業」が済んでいればさほど困難ではありません。
始動後は、しばらく「暖機運転」させ、「回転」が安定してから、「灯油燃料」に切り替え、「機関回転数」は「ガバナー」によってほぼ一定に制御することができたそうです。
かつての「石油発動機」の多くは「燃料タンク」が「灯油用」のみで、「始動用ガソリン」は「別容器」を携行する必要がありましたが、現在製造されている「石油発動機」は、「始動用ガソリン」と、「運転用灯油」の両方が入れられる、「内部」が分割された「燃料タンク」を備えており、「タンク」に「キャップ」が2個ついていることで、他の「エンジン」と容易に区別できます。
また、戦中戦後には「代用燃料化」する為に「木炭ガス発生器」を別に取り付け、「ガスエンジン」とする「改造」も多かったようです。
「石油発動機展示会」ですが、「ふれあいパーク八日市場」で開催される「催し」で、3月6日(日)10時00分から14時00分まで行われるそうです。
また「石油発動機展示会」開催に際し、「ふれあいパーク八日市場」では、「先着」200人に「ゆで卵」をプレゼントするそうです。
「匝瑳」の「都市と農村総合交流ターミナル」「ふれあいパーク八日市場」で開催される「催し」「石油発動機展示会」。
この機会に「匝瑳市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「石油発動機展示会」詳細
開催日時 3月6日(日) 9時〜14時
開催会場 ふれあいパーク八日市場 匝瑳市飯塚299-2
営業時間 9時〜18時
問合わせ ふれあいパーク八日市場 0479-70-5080
備考
「ふれあいパーク八日市場」のある「匝瑳市」では、来月(4月)「JR八日市場駅」「駅前」に「そうさ観光物産センター匝(メグ)りの里」をオープンするそうです。
「そうさ観光物産センター匝(メグ)りの里」ですが、「市内観光情報」の「発信」、「観光案内業務」、「物産販売」を行うそうです。
「そうさ観光物産センター匝(メグ)りの里」の「オープン日程」ですが、下記の通りとなっています。
4月1日(金) オープンセレモニー (13時30分〜) ※観光案内業務開始
4月2日(土) 一般オープン (9時00分〜) ※物販開始
なお「そうさ観光物産センター匝(メグ)りの里」の「施設」の「詳細」ですが、「広報そうさ」4月号でお知らせするそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2856 |
| 地域情報::匝瑳 | 10:53 AM |
|
|
2016,02,28, Sunday
本日ご紹介するのは、近隣市「横芝光町」「坂田城跡梅林」で2月27日(土)〜3月20日(祝・日)の期間開催されます「坂田城跡梅まつり」です。
「横芝光町」は、明治22年(1889年)4月1日の「町村制」の「施行」により、「横芝町」、「古川村」、「栗山村」、「鳥喰上村」、「鳥喰新田」、「両国新田」が合併し、「武射郡」「旭村」が成立、1892年(明治25年)12月28日に「旭村」が「改称」して「横芝村」となり、1897年(明治30年)5月10日「横芝村」が「町制施行」して「横芝町」となり、同年6月1日「JR横芝駅」が開業しています。
1953年(昭和28年)5月18日「国道126号線」が制定され、昭和30年(1955年)2月1日に「横芝町」が「大総村」、「上堺村」と合併した「旧・横芝町」が成立、同じく明治22年(1889年)に「香取郡」「日吉村」、「匝瑳郡」「南条村」、「東陽村」、「白浜村」が誕生し、これら「4村」が昭和29年(1954年)5月に合併し「旧・光町」が誕生、その後「横芝町」と「光町」が平成18年(2006年)3月27日に合併し、「横芝光町」が誕生しました。
「横芝光町」は、「千葉県」「北東部」に位置し、「首都」「東京」から約70km、「県庁所在地」「千葉市」から約40km、「世界の空の玄関口」(WORLD SKY GATE)(2012年12月10日のブログ参照)からは約20kmの「位置」にあります。
「横芝光町」は、2006年(平成18年)3月27日に「山武郡」「横芝町」と、「匝瑳郡」「光町」が合併し、新たに発足しました。
「横芝光町」は、「合併前」の「横芝町」と、「光町」は、「別」の「郡」(「歴史的」にはそもそも「上総国」と、「下総国」という別の「令制国」)に所属していましたが、現在の「横芝光町」は、「山武郡」に属しています。
「横芝光町」の現在の「人口」ですが、「総人口」24730人、「男性」12172人、「女性」12558人、「世帯数」9560世帯となっています。
(2016年2月1日現在)
「横芝光町」の「形状」ですが、「東西」約5km、「南北」約14kmと「南北」に細長く、「面積」は66.91平方km、「北」は「香取郡」「多古町」と「山武郡」「芝山町」、「東」は「匝瑳市」、「西」は「山武市」に接し、「南」は「白砂青松」の続く「九十九里浜」(2012年5月11日のブログ参照)が広がり、「太平洋」に面しています。
「横芝光町」の「地勢」ですが、「中央部」から「南部」にかけては「平坦地」が続き、「北部」は緩やかな「丘陵地帯」を形成しており、かつて「上総」、「下総」の「国境」でもあった「九十九里平野」(2012年7月6日のブログ参照)における「最大」の「河川」「栗山川」(2012年2月18日のブログ参照)が、「横芝光町」「中央部」を「北」から「南」に向けて流れています。
「横芝光町」の「気候」ですが、「黒潮」の「影響」を受け、「年平均気温」は15度、「年間降水量」は1300mm程度で、「夏」涼しく、「冬」暖かい「海洋性気候」となっています。
「温暖」な「気候」と肥沃(ヒヨク)な「大地」に恵まれ、「横芝光町」では、「良質」な「農産物」を生産しています。
「横芝光町」では、「畜産」も盛んで「養豚農家」が数多く、「町営東陽食肉センター」は「千葉県内第2位」の「処理実績」をあげています。
「横芝光町」では、今後「付加価値」の高い「農産物」、「農業体験」・「交流」の「拠点施設」など、新たな「展開」を図っていくそうです。
また「横芝光町」の「工業」ですが、「成田空港圏」の「地の利」を生かして「企業誘致」を進め、さらに「海老川沼」周辺の「土地利用」も検討されているそうです。
また「横芝光町」は、「産業」・「文化」・「スポーツ」の「魅力」を複合した「特色」ある「観光地づくり」を行っており、「活気」ある「商業地づくり」も目指しているそうです。
上記のように「横芝光町」の「産業」は、「農業」・「工業」・「商業」、そして「観光業」と「バランス」がとれた「発展」をしており、活気を生んでいます。
「横芝光町」の「主産業」である「農業」ですが、上記のように「南北」に細長く「平坦地」が多い「横芝光町」の「地形」と「夏」涼しく「冬」暖かい「海洋性気候」といった「農業」に適した「自然環境」を活かし、発展しています。
「横芝光町」の「農業」は、「水田農業」を「中心」に「露地野菜」や「施設園芸」を組み合わせた「複合経営」が盛んで、「農産物」では、「水稲」が「中心」であり、「露地野菜」は「スイートコーン」、「ネギ」がよく知られ、「トマト」、「カボチャ」、「ブロッコリー」などの「栽培」も盛んに営まれています。
また「横芝光町」には「いちご栽培農家」も存在し、12月から5月にはおいしい「いちご」がたくさん収穫されています。
「横芝光町」の「農業」に従事する「若者たち」は「高収益作物」に取り組んでおり、「ハウス内」で「ミニトマト」、「メロン」や「水耕ミツバ栽培」、近年では「シクラメン」など「花き栽培」もするなど、「経営」の「効率化」を考え、「パソコン導入」し「効率化」を実現しているそうです。
「横芝光町」を代表する「農産物」といえば「長ネギ」で、昭和43年(1968年)頃から「麦」の「裏作」として「秋冬ネギ」の「栽培」が盛んになり、昭和47年(1972年)には「国」の「産地指定」を受けています。
「横芝光町」では、昭和40年〜50年代にかけて「宝米地区」や「小田部地区」の「台地畑」が整備されたことも、「ネギ栽培」を後押ししました。
その後も「栽培方法」の「改良」が重ねられ、現在は「春ネギ」、「秋冬ネギ」とともに「国」の「産地指定」を受け、「ひかりねぎ」の「ブランド名」で「市場」で高く評価されています。
また、「横芝光町」では「夏ネギ」の「栽培」にも力を入れ、「周年出荷」を実現しています。
また「横芝光町」では、「特産品」「ひかりねぎ」の「エキス」を贅沢(ゼイタク)に抽出して造られている「ねぎのど飴」も「特産品」として売り出しています。
「ねぎのど飴」には、「ひかりねぎ」の「エキス」のほか、「キンカンエキス」や「ショウガエキス」も加えられ、マイルドで、「のど」にやさしい「飴(アメ)」に仕上げられています。
「坂田城跡梅林」ですが、「坂田城跡梅林組合」の「皆さん」が、「梅酒」や、「梅加工用」に出荷している「梅」の「耕作地」で、「観光梅林」ではないため、知る人ぞ知る隠れた「梅林」だったそうです。
「坂田城跡梅林」は、「梅林」の「樹齢」が約40年で、一本一本が10mに及ぶ「巨木」が1500本(1200本ともいわれる)もあることから、「テレビ放映」や、「各種」「観光雑誌」への「掲載」により、一躍「有名」になると共に、「県下最大級」の「梅林」として「関東近県」にまで知れわたるようになったそうです。
「坂田城跡梅林」は、「JR総武本線」「JR横芝駅」から「北西」に1.8km、「徒歩」で約25分の「ふれあい坂田池公園」に隣接する「坂田城跡」にあります。
「坂田城」ですが、15世紀の中頃、「千葉氏」によって築城された「城」といわれ、「坂田城」は、「本丸」、「一の丸」、「二の丸」、「三の丸」、「四の丸」で構成され、「城域」は、「台地」「全体」にわたっており、400年以上破壊されることなく、当時の「遺構」が現存する「千葉県内」でも「貴重」な「城跡」なのだそうです。
「坂田城」は、戦国時代に周辺を支配していた「井田氏」が築城したと伝えられる、「千葉県内」でも「屈指」の「大規模」な「中世城郭」でした。
中世の「城郭」は、「石垣」や、「水堀」を多用して「主」に「平地」に築かれた近世の「城郭」とは異なり、「土」を切り盛りして造られた「土塁」・「土橋」・「腰曲輪」、そして「空堀」等を組み合わせ、「大地」や、「丘陵」を巧みに利用して築城されています。
現在も「坂田城跡」「台地上」の「山林中」に「土塁」・「空堀」などが残っており、「遊歩道」を歩きながら、「巨大」な「土塁」や、幅広い「空堀」を見ることができるそうです。
「坂田城跡」では、「杉木立」の「本丸跡」を過ぎると、見事に手入れされた「老木の梅林」が少しずつ見えてきて、「坂田城跡梅林」の「中心地」ですが、「本丸」から約1km先の「四の丸」付近に位置しているそうです。
「坂田城跡梅林」を管理している「坂田城跡梅林組合」と、「横芝光町観光協会」は、「坂田城跡梅林」の「魅力」を知っていただくために、毎年2月に「坂田城跡梅まつり」を開催しています。
「坂田城跡梅まつり」では、「期間中」「梅農家」(坂田城跡梅林)による「梅農家売店」「梅のおみせ」が2月13日(土)から3月13日(日)の「期間」に、「手作り」の「梅加工品」や、「漬物」の「直売」のほか、「横芝光町」の「地元農産物」の「販売」も予定しています。
また「坂田城跡梅まつり」では、「期間中」(2月27日〜3月13日)「毎週末」(毎週・土・日曜日)に、「数量限定」で、「芋雑煮」の「無料サービス」も予定しているそうです。
(11時00分頃から、数に限りあり)
また「坂田城跡梅まつり」では、「横芝光町観光協会」による「観光協会売店」も設置され、「毎週」「土曜日・日曜日」に開店するそうです。
「観光協会売店」では、「横芝光町」の「公式マスコットキャラクター」(ゆるキャラ)「よこぴー」(2013年9月1日のブログ参照)の「よこぴーグッズ販売」、「甘酒の無料サービス」、「懐かしの遊びコーナー」、「商工会物産販売」(軽食等)が行われるそうです。
なお「坂田城跡梅まつり」「観光協会売店」ですが、「梅まつり本部」も兼ねており、「坂田城跡梅まつり」「期間中イベント」の「会場」にもなっているそうです。
「坂田城跡梅まつり」「期間中イベント」は、下記の通りです。
2月27日(土) 梅林マルシェ
※地元の新鮮野菜などの販売
3月5日(土) 梅とよこぴーと菜の花の撮影会
3月12日(土) 大声コンテスト (11時00分〜12時00分) 賞品あり!
梅干しの種飛ばし大会 (13時00分〜14時00分) 賞品あり!
3月19日(土) 菜の花摘み取り体験
※体験は無料です。
「坂田城跡梅まつり」「観光協会売店」(梅まつり本部)には、「毎週土曜日」「よこぴー」が遊びに来るそうです。
「梅農家売店」「梅のおみせ」と、「観光協会売店」の「位置関係」ですが、「横芝中学校」付近「坂田城跡梅林」「梅林入口」から「梅農家売店」「梅のおみせ」までは「徒歩」で約20分となっており、「梅農家売店」「梅のおみせ」から「観光協会売店」までは「徒歩」で約15分となっています。
ちなみに「坂田城跡」の「梅加工品」は、「坂田城跡梅林組合」でしか買うことができず、「梅農家」の「皆さん」が「愛情」・「真心」を込めて作った「梅加工品」は、「合成着色料」や、「保存料」は一切使っておらず、「昔」ながらの「味」を楽しめるそうです。
「坂田城跡梅まつり」の「梅の花」を楽しんだ後、「車」で10分程行くと、「横芝光町」の「特産品」が揃う「ひかり直売所」(2012年6月25日のブログ参照)があります。
「ひかり直売所」は、「地元」「横芝光町商工会」が実施した「むらおこし事業」が「きっかけ」に設立された「直売所」です。
「ひかり直売所」の取り扱っている「新鮮野菜」、「特産品」ですが、「長ネギ」、「トマト」、「小松菜」、「米」、「切り餅」、「卵」、「生花」、「ねぎのど飴」、「ねぎ入りソーセージ」、「純米酒」「光鬼米」となっています。
「往時」を偲ばせる「坂田城跡」に開かれている1500本(1200本)の「梅林」が見事な「坂田城跡梅林」で開催される「恒例イベント」「坂田城跡梅まつり」。
この機会に「横芝光町」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「坂田城跡梅まつり」詳細
開催期間 2月27日(土)〜3月20日(祝・日)
開催会場 坂田城跡梅林 山武郡横芝光町坂田登城
問合わせ 横芝光町観光協会 0479-84-1215
備考
「坂田城跡梅まつり」の「会場」「坂田城跡梅林」の「梅」の「開花状況」ですが、「横芝光町産業振興課」「Twitter(ツイッター)」でご確認できます。
「坂田城跡梅まつり」ですが、「荒天」の場合は中止となるそうです。
「坂田城跡梅まつり」の「会場」「坂田城跡梅林 」、「ふれあい坂田池公園」から「ひかり直売所」に向かう「道中」、「横芝光町」の「中央」を流れる「栗山川」を渡ります。
「栗山川」ですが、「鮭(サケ)」の遡上(ソジョウ)する「南限」の「川」とされており、毎年「サケの里親募集」や、「放流式」、「秋」には「鮭」の「捕獲見学会」が行われているそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2849 |
| 地域情報::匝瑳 | 12:49 PM |
|
|
2016,02,27, Saturday
本日ご紹介するのは、地元「銚子市」「銚子電鉄」、「仲ノ町倉庫」、「OTS犬吠埼温泉犬吠駅前広場」で2月27日(土)・28日(日)に開催されます「おつかれさまデハ1001イベント〜昭和の名車ありがとう〜」です。
「銚子電気鉄道株式会社」(2012年2月11日のブログ参照)は、「銚子市」(2010年9月20日のブログ参照)に「鉄道路線」を有する「鉄道会社」で、「銚子電鉄」あるいは、「銚電」と「略称」されています。
「銚子電鉄」は、「全長」6.4kmの「銚子駅」(2011年5月7日のブログ参照)から「外川駅(トカワエキ)」(2011年7月7日のブログ参照)までの「10駅」を約20分で結ぶ「地元客」、「観光客」の「皆さん」に「人気」のある「ローカル鉄道」です。
「銚子電気鉄道株式会社」の「路線」の「延長」(距離)ですが、「芝山鉄道」(千葉県・2.2km)、「紀州鉄道」(和歌山県・2.7km)、「岡山電気軌道」(岡山県・4.7km)、「水間鉄道」(大阪府・5.5km)、「流鉄」(千葉県・5.7km)に次いで、「全国」で「6番目」に短い「鉄道」なのだそうです。
ちなみに「銚子電鉄」の「起点」は、上述のように「銚子駅」で、「終点」は「外川駅」、「駅数」10駅(起終点駅含む)、「複線区間」なしの「全線単線」で、「最高速度」40km/hの「鉄道」です。
「銚子電気鉄道株式会社」ですが、1913年(大正2年)に、現在の「銚子電気鉄道」にあたる「銚子」から「犬吠」間の「鉄道路線」を開業したものの、「利用不振」から1917年(大正6年)に「路線」を廃止して解散した「銚子遊覧鉄道」の「関係者」が、再び「路線」を復活させるために「銚子電鉄」を設立したそうです。
その後、「銚子電鉄」は、1922年(大正12年)7月5日に「銚子」から「外川」間を開業、1948年(昭和23年)8月20日に「銚子電気鉄道」に「社名変更」しており、「銚子電鉄」は、2012年(平成24年)に「開業」90周年を迎えています。
当ブログでは、「銚子電気鉄道株式会社」「各駅」の「見どころ」や、「おすすめスポット」を、「銚子電鉄」「各駅見処紹介」と題し、「東日本旅客鉄道」(JR東日本)・「銚子電気鉄道」(銚子電鉄)の「共同使用駅」「銚子駅」(JR東日本・管理)から、「仲ノ町駅(ナカノチョウエキ)」(2011年5月11日のブログ参照)、「観音駅」(2011年5月14日のブログ参照)、「本銚子駅(モトチョウシエキ)」(2011年5月16日のブログ参照)、「笠上黒生駅(カサガミクロハエエキ)」(2011年5月20日のブログ参照)、「西海鹿島駅(ニシアシカジマエキ)」(2011年5月26日のブログ参照)、「海鹿島駅(アシカジマエキ)」(2011年5月28日のブログ参照)、「君ヶ浜駅(キミガハマエキ)」(2011年5月31日のブログ参照)
、「犬吠駅(イヌボウエキ)」(2011年6月21日のブログ参照)、「外川駅」の「順」に、「銚子電気鉄道株式会社」の「各10駅」を紹介し、「銚子電鉄」「各駅」の「特徴」、「歴史」、「周辺見処紹介」をアップしています。
「銚子電気鉄道株式会社」は、昨年(2015年)「駅名」の「ネーミングライツ」(命名権)の「販売」を行う「事業」「駅名愛称ネーミングライツ事業」を実施し、「県内外」から「遊技業者」や、「土木工事会社」、「IT企業」など「6社」が応募し、2015年(平成27年)12月から「7駅」に「愛称」が付けられました。
昨年12月時点の「駅名愛称ネーミングライツ事業」で決まった「駅」の「愛称」は、下記の通りです。
仲ノ町駅 カクタ パールショップともえ
観音駅 藤工務所 藤工務所
笠上黒生駅 メソケアプラス 髪毛黒生
西海鹿島駅 根本商店 三ツ星お米マイスター根本商店
海鹿島駅 藤工務所 藤工務所 文芸の里
君ヶ浜駅 MIST solution ミストソリューション
犬吠駅 沖縄ツーリスト One Two Smile OTS 犬吠埼温泉
「銚子電気鉄道株式会社」「駅名愛称ネーミングライツ事業」の「契約」は1年更新となっており、「初年度」は830万円の「増収」となったそうです。
ちなみに「銚子電気鉄道株式会社」「駅名愛称ネーミングライツ事業」の「命名権」ですが、「銚子駅」を除く、「仲ノ町駅」から「外川駅」までの「9駅」を80万円〜200万円で「募集」しており、「本銚子駅」と、「外川駅」の「2駅」は、引き続き「スポンサー」を探しており(2015年12月時点)、「命名権販売」(ネーミングライツ)の「収入」は「安全」な「運行確保」のための「車両維持費」などに充てられるそうです。
また「銚子電気鉄道株式会社」では、新しい「駅名看板」を設置し、「銚子電鉄」「車内」での「新・駅名」の「車内放送」を開始しているそうです。
なお今年(2016年)に入り「銚子市」に「しょうゆ製造工場」がある「ヒゲタ醤油」(東京都・中央区)(2011年9月10日・2010年12月20日のブログ参照)が、「銚子電気鉄道株式会社」が販売する「駅名愛称ネーミングライツ事業」「命名権」(ネーミングライツ)を購入し、「本銚子駅」の「愛称」を「ヒゲタ400年玄蕃(ゲンバ)の里」と命名したそうです。
「OTS犬吠埼温泉犬吠駅」は、「銚子電気鉄道株式会社」の「犬吠駅」の「愛称」で、「One Two Smile OTS 犬吠埼温泉」ですが、「銚子電鉄」が募集した「ネーミングライツ」で「One Two Smile OTS 沖縄ツーリスト」が命名されました。
「OTS犬吠埼温泉犬吠駅」の「命名権販売額」ですが、「年」200万円で契約しており、「命名権販売」ですが、「銚子電気鉄道株式会社」の「経営改善策」の「一環」で、「銚子電気鉄道株式会社」は、「協賛企業」6社との「契約」で「初年度」の「収入」は830万円となるそうです。
(2015年12月4日現在)
「デハ1001号」・「デハ1002号」は、「日立電鉄」に譲渡される予定だった「営団地下鉄2000形」のうち、「同社」の「計画見直し」で「譲渡」が中止された「2000形」、「2040号」の「車体」に「同形」「2033」、「2039」の「運転台」を組み合わせて「両運転台化」し、1993年(平成5年)に引退後、「営団1500形電車」(2代)と、「営団地下鉄3000系」の「機器」・「パンタグラフ」・「富士急行モハ5700形」(元・小田急2200形)の「台車」の「取り付け」を行ったものだそうで、「デハ800形」同様、「前面貫通扉」は固定されています。
なお「パンタグラフ」ですが、「増設運転台」側の「外川寄り」にあります。
上記のように入線に際しては、「2039号」の「運転台」を流用して両運転台化され、「モーター」(電動機)と「パンタグラフ」には「営団地下鉄日比谷線用3000形」から、「空気圧縮機」と「電動発動機」、「扇風機」は「営団地下鉄1500N形」から、「台車」は「富士急行5725」の「FS316」を利用したものであり、「営団地下鉄2000形」のものではありませんが、初期の「高性能車」の「集大成的存在」として貴重なものを流用していたそうです。
今回引退する「車両」「デハ1001号」ですが、本来は「9両」が「茨城県」の「日立電鉄」(現・廃止)に入線し、「3000形」の「増備車」になる予定でしたが、実際には「7両」となったため、「日立電鉄側」の「都合」により「キャンセル」となり、「余剰」の「2両」(デハ1001、1002)が「銚子電鉄」にやってきました。
「デハ1001号」は、2007年(平成19年)4月26日から、「ハドソン」の「支援」を受け「ゲーム」「桃太郎電鉄」「シリーズ20周年記念」の「ラッピング車両」となりました。
当所3年間の予定でありましたが、2010年(平成22年)4月8日に「継続実施」が発表され、2012年(平成23年)5月16日まで続きました。
そして「整備」とともに「塗り替え」が行われ、今度は「山吹色」の「銀座線カラー」に塗装変更され、2012年(平成24年)8月11日の「イベント」で初公開されました。
この「銀座線塗装」は「一般向け」に募った「アンケート」で最も多かった「意見」として採用されたもので、また「方向幕」には「イベント用」として「渋谷」「上野」「浅草」が「コマ」に入っているそうです。
「銚子電鉄」では、「新型車輛」「3000形」の「導入」に伴い、「デハ1001」が引退することとなることから「デハ1001」の「引退」を記念して「各種イベント」を開催するそうです。
「おつかれさまデハ1001イベント〜昭和の名車ありがとう〜」「デハ1001・デハ1002最後の共演」と題し開催される「イベント」ですが、2月27日(土)・28日(日)に開催され、「内容」(各種イベント)ですが、「デハ1001おつかれさま運転」、「デハ1001とデハ1002最後の共演」、「記念乗車券・グッズの販売」、「昭和の遊びコーナー」(無料)、「沖縄体感ブース」(無料)、「なりきり制服体験」(無料)、「切符切り体験」(無料)となっています。
「各種イベント」「詳細」は、下記の通りです。
「デハ1001おつかれさま運転」は、2月28日(日)に引退する「デハ1001」の「おつかれさま運転」で、「運行ダイヤ」は、「銚子駅」発「外川」行9時49分→以降 「銚子」〜「外川」間運行→「銚子駅」着15時08分「運転終了」となっており、2月28日(日)「銚子駅」15時08分着後、「運転士」への「花束贈呈」が行われるそうです。
引退する「デハ1001」「前面」に「ヘッドマーク」が装着され、2月27日(土)と、28日(日)では、「デザイン」が異なるそうです。
詳しい「運行ダイヤ」は、「銚子電鉄」「HP」を参照下さい。
「デハ1001とデハ1002最後の共演」ですが、2月27日(土)・28日(日)15時30分から16時30分まで行われ、「入場券」150円が必要となる「イベント」です。
「内容」ですが、「銚子電鉄」「仲ノ町車庫」で「デハ1001」と、「デハ1002」を並べるそうです。
「記念乗車券・グッズの販売」ですが、2月27日(土)・28日(日)10時00分から15時00分まで「OTS犬吠埼温泉犬吠駅前広場」を「会場」に行われます。
「記念乗車券・グッズの販売」の「詳細」は、「銚子電鉄」「HP」を参照下さい。
なお「記念乗車券・グッズの販売」は、「数量限定」のため、なくなり次第「販売終了」となりますので、ご注意下さい。
「昭和の遊びコーナー」(無料)ですが、2月27日(土)・28日(日)10時00分から15時00分まで、「OTS犬吠埼温泉犬吠駅前広場」を「会場」に開催されます。
「内容」ですが、「ベーゴマ」、「めんこ」、「けん玉」、「ゴム跳び」他となっています。
「沖縄体感ブース」(無料)ですが、2月27日(土)・28日(日)10時00分から15時00分まで、「OTS犬吠埼温泉犬吠駅前広場」を「会場」に開催されます。
「内容」ですが、「ゆびハブ」、「カンカラ三線」、「シーサーペーパークラフト」他となっています。
「なりきり制服体験」(無料)ですが、2月27日(土)・28日(日)10時00分から15時00分まで、「OTS犬吠埼温泉犬吠駅前広場」を「会場」に開催されます。
「内容」ですが、「銚子電鉄」の「駅員」の「制服」を着て、「駅員」になりきることができます。
「切符切り体験」(無料)ですが、2月27日(土)・28日(日)10時00分から15時00分まで、「OTS犬吠埼温泉犬吠駅前広場」を「会場」に開催されます。
「内容」ですが、「なつかし」の「切符切り体験」ができます。
「銚子電鉄」、「仲ノ町倉庫」、「OTS犬吠埼温泉犬吠駅前広場」で開催される「デハ1001おつかれさま運転イベント」「おつかれさまデハ1001イベント〜昭和の名車ありがとう〜」。
この機会に「銚子市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「おつかれさまデハ1001イベント〜昭和の名車ありがとう〜」詳細
開催日時 2月27日(土)・28日(日) 10時〜16時半
開催会場 銚子電鉄 運行路線各所
仲ノ町倉庫 銚子市仲ノ町
OTS犬吠埼温泉犬吠駅前広場 銚子市
問合わせ 銚子電気鉄道 0479-22-0316
備考
今回引退する「デハ1001」と同様に、「元・営団地下鉄」より譲り受けた「車輛」「デハ1002」(2015年1月8日・2014年12月23日のブログ参照)ですが、1994年(平成6年)の「入線」以来、「銚子電鉄」の「路線」を、約20年間走り続けてきましたが、2015年(平成27年)1月10日(土)の「運行」を最後に、その「歴史」に「幕」を閉じています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2848 |
| 地域情報::銚子 | 09:32 PM |
|
PAGE TOP ↑
|
 |



