 |
■CALENDAR■
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
| | | | | |
<<前月
2025年11月
次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■POWERED BY■
■OTHER■
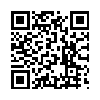
携帯からもご覧いただけます
|
2011,06,05, Sunday
本日ご紹介するのは、近隣市「成田市」「成田山書道美術館」です。
「成田山新勝寺」の「大本堂」から、後方にそびえる「平和の大塔」へと足を運ぶと、眼下に広がる緑豊かな「成田山公園」を望め、更に奥へ足を伸ばすと「竜智の池」に寄り添うようにたたずむ「成田山書道美術館」に辿り着きます。
四季折々の景観を楽しみながら、「美術館」の扉を開けるとそこに「書」の世界が待っています。
「書」の「総合専門美術館」として、優れた作品を常時観察でき、作品の保存、研究、普及活動、専門家から一般の方まで楽しめる「書」の世界が広がっています。
「成田山書道美術館」の館内は、吹き抜けに沿った「回廊式」の「ギャラリー」となっていて、特に目を引くのは、入口正面の「企画展示ホール壁面」に掲げられた高さ13.3m、幅5.3mもの「拓本」「原拓 紀泰山銘(げんたく きたいざんめい)」です。
この「拓本」は、中国の名山「泰山」にある中国の初代皇帝「玄宗皇帝」の施政方針を記した「碑」のもので、「美術館」のシンボルとなっています。
江戸時代後期以降の書道の名作の数々をご覧いただき、日本の「書」の幽玄な広がりと美しさに触れ、様々な角度からゆっくりと「書」の世界を楽しめるようです。
現在、「成田山書道美術館」では「松本芳翠墨華展」同時開催「第60回記念書海社展」が開かれています。
開催期間は4月30日(土)から6月12日(日)までで、9時〜16時(最終入館は15時半)に鑑賞できます。
ちなみに「松本芳翠」は「大正・昭和」の「現代書壇草創期」を代表する作家だそうです。
今回の展覧会では、日本芸術院賞の受賞作「談玄・観妙」をはじめとする代表作、約40点を出品。
また「松本芳翠」が主宰した「書海社」の「60回記念展」を同時開催します。
新緑色付く「成田市」の「成田山書道美術館」に「書」を鑑賞しにお出かけください。
「成田山書道美術館」詳細
所在地 成田市成田640
休館日 月曜日 (祝日または振替休日の場合は翌日)
展示替え等による館内整理期間 但し1月は無休
入館料 大人 500円 高・大学生 300円 中学生以下 無料
問合わせ 成田山書道美術館 0476-24-0774
備考
「成田山書道美術館」は、近現代の書蹟の収蔵では「質」「量」ともに群を抜いており、これらを生かした「展示」「普及」「研究活動」が行われています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=545 |
| 地域情報::成田 | 11:19 AM |
|
|
2011,05,19, Thursday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山新勝寺」(以下「成田山」と表記)で今週末(5月22日)に開催されます「開運厄除柴灯大護摩供護摩木祈願・火渡り行」です。
先(4月30日)のブログでアップしました「5月詣」の「成田山」。
正五九(しょうごく・1月、5月、9月のこと)といって、この期間に「成田山」にお参りすると平月にも増して御利益を授かることができると言われています。
今回ご案内の「開運厄除柴灯大護摩供護摩木祈願・火渡り行」は冠に「東日本大震災復興祈願」とつき、「被災地」「被災者」の皆さんの「復興祈願」を「成田」から送る意味もある催事のようです。
「成田山」では、お参り月となる5月と9月の第4日曜日(平成23年は、5月22日(日)及び9月25日(日)となります。)に、「開運厄除柴灯大護摩供護摩木祈願・火渡り行(かいうんやくよけさいとうおおごまくごまくきがん・ひわたりぎょう)」が公開されます。
「柴灯大護摩供」は、例年ですと、一年の最後のご縁日の12月28日に、古いお札を納め御利益に感謝する「納め札お焚き上げ・柴灯大護摩供」が行われていますが、平成21年からは年末だけでなく5月と9月にも執り行われています。
「柴灯大護摩供」とは、古来、山伏が山岳修行の際、「柴(しば)」を使い「護摩壇」を設け、「所願成就」を祈念する伝統行事です。
皆様のお願い事とお名前を書いた「護摩木」を道場中央に設けた「護摩壇」炉に投じます。
「護摩壇」は「お不動さま」の「智慧の炎」が立ち上り、「開運厄除」をはじめ「所願成就」を祈念します。
「お護摩」というのは、「ご本尊の不動明王の前に壇を設けて、供物を捧げ「護摩木」という特別な薪を焚いて祈る」という、「真言密教」の「秘法」のことです。
「成田山」では、この「特別護摩木」の申し込みを5月1日より受付、「護摩木」を申し込まれた方には、「護摩木祈願之証」が授けられます。
そして山伏に扮した僧侶たちやご信徒の皆様も参加できる「火渡り行」が執り行われます。
「成田山」では、「火渡り行」と併せて「お火加持」が行われるそうです。
「お火加持」とは、「護摩札」や「御守」のほか、自分の大切なものを「御護摩」の火にあてて「お不動様」の御利益をいただくことです。
揺らめく炎は、そのものを清浄にすると共に大切にする心を呼びさまし、更には本来備えている働きを存分に発揮させる御利益があるとされています。
投げ込まれた「護摩木」から立ち上る炎。
裸足で「火渡り」をする山伏の気迫溢れる表情。
「成田山」でお参り月に執り行われる「開運厄除柴灯大護摩供護摩木祈願・火渡り行」での迫力ある修行の様子を目の当たりにし、体験しにお出かけ下さい。
「東日本大震災復興祈願」「開運厄除柴灯大護摩供護摩木祈願・火渡り行」詳細
開催日時 5月22日(日) 11時45分〜 小雨決行
開催会場 成田山新勝寺 大本堂と釈迦堂あいだの広場
問合わせ 成田山新勝寺 0476-22-2111
備考
「成田山新勝寺」では、境内に「救援募金箱」を設置し、参詣のご信徒の皆様にご協力お願いしているそうです。
また「成田山新勝寺」発行誌「智光」巻末の「払込取扱票」でも救援募金を受け付けています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=518 |
| 地域情報::成田 | 09:37 AM |
|
|
2011,05,12, Thursday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山新勝寺」で明後日(5月14日)に開催されます「第34回 奉納梅若 成田山薪能」です。
先(4月30日)のブログ「成田山新勝寺」「5月詣」でアップしました「奉納梅若 成田山薪能」。
「薪能」は、奈良県「興福寺」の「修二会(しゅにえ)」の際の「薪献進」に始まる「神事能」がはじまりと言われ、その時期は13世紀半ばとされています。
仏法の守護神を迎えるための「聖火」の「薪」の採取に伴う芸能で、「薪猿楽(たききさるがく)」、「薪」の「神事」とも称されていたようです。
「明治維新」や「第二次世界大戦」で一時とだえてしまったこともあったようですが、「第二次世界大戦」後、1950年(昭和25年)「京都」「平安神宮」の「京都薪之能」以来、「薪能」は新しい傾向として全国各地の数多くの都市や寺社で開催されるようになり、今日(こんにち)ではビルの林立する「都市空間」や「遊園地」の「野外会場」が用いられるなど、新機軸の「薪能」、ショーとしての「薪能」も増えつつあるようです。
「成田山薪能」は、毎年5月の第3日曜日の前日に執り行われています。
若葉の芽吹く「不動の森」と「平和の大塔」を背景にして、「大本堂」の奥にある「光明堂」前に「特設舞台」が設けられ、かがり火の炎に照らされた幽玄な世界の中で「能」を上演。
幻想的な雰囲気に包まれて、一流の演者たちが織り成す日本古来の文化に触れることが出来、「成田山」ならではの「薪能」が披露されます。
この機会に「成田山」の「薪能」を堪能してみてはいかがでしょうか?
「第34回 奉納梅若 成田山薪能」詳細
開催日 5月14日(土)
開催時間 開場 16時半 開演 18時
開催会場 成田山新勝寺 光明堂前特設会場
出演 梅若宗家一門
演目
仕舞 邯鄲(かんたん)
狂言 文山立(ふみやまだち)
能 安達原(あだちがはら)
備考
「成田山表参道」の入り口近くには、「表参道」と刻まれた6m程のモニュメントがあり、頂上には「舞」を踊る堂々とした「歌舞伎役者」の像が建っています。
像は、「鏡獅子」の「舞」と「伎」を、本体の形状は「火、灯り、塔」をイメージし、「幽玄の世界」を表現しています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=509 |
| 地域情報::成田 | 09:43 AM |
|
|
2011,04,30, Saturday
本日二つ目にご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山新勝寺」で開催されます「東日本大災害物故者追悼復興祈願 第27回成田山平和の大塔まつり奉納総踊り」(以下、「第27回成田山平和の大塔まつり奉納総踊り」と表記)です。
「第27回成田山平和の大塔まつり奉納総踊り」は、昭和59年4月の「弘法大師」1150年の「御遠忌」にあたり、「世界平和」と「万民の幸福」を祈願して建立された「成田山平和の大塔 」の落慶を記念して始められました。
旧成田町7町の「女人講」をはじめ、約1000人に及ぶ女性たちが、JR成田駅前から成田山新勝寺門前までの表参道、及び大本堂前で踊りを奉納し、この度の大災害の物故者の追悼と、被災地の早期復興を祈願するそうです。
「成田山新勝寺」から発する「東日本大災害物故者追悼復興祈願」。
「成田山平和の大塔まつり奉納総踊り」を観覧しにお出かけください。
「東日本大災害物故者追悼復興祈願 成田山平和の大塔まつり奉納総踊り」詳細
開催日 5月7日(土)(7日が雨天時、8日に順延、8日も雨天の場合、中止)
区間・時間
JR成田駅前〜薬師堂
11時〜14時
薬師堂〜成田山門前(鍋店かど)
11時〜16時
コース
成田山表参道(JR成田駅前〜成田山門前)、成田山大本堂(平和の大塔の復旧作業をしているため、平和の大塔での総踊りはおこなわれません。)
12時 〜 出発セレモニー(成田市役所)
12時20分〜 表参道入口(JR成田駅前)
総踊りスタート
15時 〜 成田山大本堂前 総踊り
問合わせ (社)成田市観光協会 0476-22-2102
備考
「成田山平和の大塔まつり奉納総踊り」開催日は、成田山周辺で交通規制が実施されます。
JR成田駅前から成田山新勝寺門前までが会場となる関係でそちらを含む周辺が対象となるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=487 |
| 地域情報::成田 | 09:42 AM |
|
|
2011,04,30, Saturday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」の名刹「成田山新勝寺」「五月詣」です。
何度も当館ブログでアップしています「北総」を代表する鎮守「成田山新勝寺」。
5月は、「成田山新勝寺」のお参り月だそうです。
「正五九」といって「正月」、「5月」、「9月」に「成田山」にお参りすると普段の月よりも、一層ご利益があると言われています。
「五月詣」の期間に、5月7日(土)には、「東日本大災害物故者追悼復興祈願 成田山平和の大塔まつり奉納総踊り」、14日(土)には「奉納梅若 成田山薪能」が執り行われます。
青葉まぶしい「成田山」に、拝観してみてはいかがでしょうか?
「成田山新勝寺」詳細
所在地 成田市成田1
問合わせ 0476-22-2111
備考
「成田山新勝寺」総門向かい側にある「門前広場」において、「成田山開運不動市」と題して「骨董市」が開催されます。
5月の開催日は、15日(日)だそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=486 |
| 地域情報::成田 | 09:40 AM |
|
|
2011,04,29, Friday
本日二つ目にご紹介するのは、近隣市「成田市」「公津の杜近隣公園」で開催されます「公津みらいまつり」です。
開催会場となる「公津の杜近隣公園」は、「京成電鉄」「公津の杜駅」から徒歩10分の場所にあります。
「公津の杜近隣公園」では、広々とした芝生で寝転んだり、犬を散歩させたり、子供達に大人気のアスレチックで遊んだりできます。
また、「公園」には階段があり降りていくと、野鳥が羽を休める水辺や「パークゴルフ」を楽しめるスペースもあります。
成田市民の憩いの場として親しまれている「公津の杜近隣公園」に、最近ではなかなか見られなくなった「鯉のぼり」450匹がズラリとあげられ、「公津みらいまつり」と「こどもの日フェスティバル」が開催されます。
4月19日(火)〜5月9日(月)の期間中「公津みらいまつり」は「公津の杜近隣公園」内に450匹の「鯉のぼり」が渡されるほか、5月4日(祝・水)には、子供たちが未来に向かって健(すこ)やかに成長することを願って「こどもの日フェスティバル」が開催されます。
(荒天時順延)
両企画とも、「鯉のぼり」が泳ぐ大空を見上げながら、広々とした芝生の上でご家族揃って思い思いの休日を過ごせます。
また、5月4日(祝・木)「こどもの日フェスティバル」では、9時から15時半まで、家族が楽しめる様々なアトラクションが用意されるようです。
この機会に「成田市」「公津の杜近隣公園」にお出かけしてみませんか?
「公津みらいまつり」詳細
開催会場 公津の杜近隣公園
開催期間 4月19日(火)〜5月9日(月)
内容 450匹に及ぶ「鯉のぼり」が公園に飾られ大空を泳ぐ様子を楽しめる。
「こどもの日フェスティバル」詳細
開催日時 5月4日(祝・水) 9時〜15時半
荒天時は、5月5日(祝・木)
開催会場 公津の杜近隣公園 成田市公津の杜6-9
内容 ステージ発表 模擬店 遊びと体験コーナー他
問合わせ 成田市観光協会 0476-22-2102
備考
「公津の杜近隣公園」にて、5m〜8mの大きな「鯉のぼり」や、大人の手を広げた位の「鯉のぼり」が、子供たちの元気で健やかな成長を願い青空の下を泳ぎます。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=485 |
| 地域情報::成田 | 12:41 PM |
|
|
2011,04,25, Monday
本日二つ目にご案内するのは、「芝山町」「芝山仁王尊」の「ご利益」と「牡丹(ぼたん)」です。
先ほどブログでアップした通り「芝山仁王尊」「観音教寺」は、「天台宗」の古刹です。
「観音教寺」の「芝山尊天」は昔から庶民の間で「火事・泥棒除け」の「お仁王様」の通称で親しまれ、火消し衆や商家の篤い信仰を得て「江戸の商家で火事泥棒除けのお仁王様のお札を祀らないお店(たな)はない」とまで言われていたそうです。
「芝山尊天」には、こんな話があります。
昔「与六」という信心家の家に泥棒が入り、つづらを背負って立ち去ろうとしたところ、壁に祀った「お仁王様」のお姿が、忽然(こつぜん)と紙から抜け出し、盗賊を睨(にら)むと、目から金色の光を放ち、盗賊が腰を抜かし被害に遭わなかったそうです。
また「芝山仁王尊」には、「新門辰五郎」に所縁(ゆかり)があるそうです。
大正時代に、「客殿」と「庫裡」を再建するための資金の一部として「浄財」が「両山講」より寄進され、その記念に建立された「記念碑」があります。
「両山講」とは、「成田山」と「天應山」(芝山仁王尊)の両山を参詣する講中(グループ)のことで、その歴史は江戸時代の町火消し「を組」の「頭領」「新門辰五郎」に遡(さかのぼ)ります。
「新門辰五郎」の「新門」は浅草寺僧坊の「伝法院」の新門の門番を任されたことに由来すると云われ、「鳶職」や「香具師」等の取締りもする人物だったそうです。
その「新門辰五郎」の影響下にあった人達が講を組織し、近代まで熱心に「火事・泥棒除け」の「仁王尊詣り」をしてきていたそうです。
「芝山仁王尊」では、み仏をお祀りする処は浄土であるという理念の下に、「桜」を始め境内を四季折々の花木で埋め尽くしています。
「椿」、「桜」、「牡丹」、「つつじ」などが咲き誇り、今の時期だと「牡丹」が盛りをむかえています。
(5月には「つつじ」が咲き誇るようです。)
「芝山仁王尊」の「牡丹」は約300株が植えられていて、4月下旬〜5月上旬にかけ美しい花を咲かせます。
ゴールデンウィーク期間中は「ボタン祭」が行われるようです。
「芝山仁王尊」は「火盗難除け」の「お仁王様」であり、花木で満ち溢れた「天台宗」の古刹です。
季節の花「牡丹」を愛でに「芝山仁王尊」「観音教寺」までお出かけください。
「芝山仁王尊」詳細
所在地 山武郡芝山町芝山298
問合わせ 0479-77-0004
備考
「芝山仁王尊」の境内は一万坪に及ぶ広さを誇り、「県文化財」の「三重塔」など「七堂伽藍」が甍(いらか)を競い、御利益を求める多くの参詣者で賑わっているそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=476 |
| 地域情報::成田 | 09:54 AM |
|
|
2011,04,25, Monday
本日ご案内するのは、近隣市「芝山町」の「芝山仁王尊」「観音教寺(かんのんきょうじ)」です。
「芝山仁王尊」「観音教寺」は「比叡山延暦寺」を「御本山」とする「天台宗」の寺院で、正式名称を「天應山観音教寺福聚院」です。
奈良時代末期、人皇第四十九代「光仁天皇」の宝亀11年(780年)の正月、平城京が雷火に襲われ、皇室擁護の寺院が多く焼失したので、諸国に命じて新たに仏寺を建てせしめたそうです。
天応(天應)元年(781年)勅命により「征東大使」「中納言 藤原継縄」公がこの「布令」の下に当地に寺院を建立し、「御本尊」として奉持して来た「十一面観世音菩薩」を奉安し、創建されたそうです。
天長2年(825年)、後に「第3代天台座主」となった「慈覚大師」「円仁」により中興され、次第に甍(いらか)の数を増やし、近隣に八十余宇の子院を置くに至ったと伝えられています。
その後、中世「治承年間」に「千葉」の「豪族」である「千葉介平常胤」の崇敬を受け、許多の仏田が寄進され、永く祈願所として栄えますが、「豊臣秀吉」の「小田原攻め」の影響を受け、「観音教寺」も全山灰土と化したと伝えられています。
やがて江戸時代に入り「徳川幕府」の庇護の下、十万石の格式を持つ「伴頭拝領寺」として「関東天台」の中核となす寺院になったそうです。
特に「火事泥棒除け」「厄除け」の「仁王尊天」として大江戸の庶民の信仰を集め、いろは「四十八組」の「町火消」が纏(まとい)を先頭に競って参詣していたと伝えられています。
現在でも有名な「新門辰五郎」の旧「を組」の記念碑が境内に建っており、その信仰が今日まで連綿として伝えられていることが分かります。
(「観音教寺」「柴山仁王尊」HPの歴史より抜粋)
「観音教寺」の山号は「天応山」、関東有数の古刹。
江戸時代には「成田」の「不動尊」とともに民間の信仰を集めていたようです。
また「観音教寺」の「御本尊」は「十一面観世音菩薩」であり、「新上総国三十三観音霊場第33番(結願)」の寺です。
また「上総国薬師如来霊場28番(結願寺)」、「東国」「花の寺百ヶ寺」(千葉16番)となっています。
「山武郡芝山」に「天台宗」の古刹あり。
「芝山仁王尊」「観音教寺」に拝観してみませんか?
「芝山仁王尊」「観音教寺」詳細
所在地 山武郡芝山町芝山298
問合わせ 0479-77-0004
備考
「芝山仁王尊」「観音教寺」の本堂隣には「芝山はにわ博物館」があります。
「国指定史跡」「殿塚・姫塚」出土の「はにわ」、「県指定文化財」9点を含む「はにわ」等を一括展示しているそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=475 |
| 地域情報::成田 | 09:53 AM |
|
|
2011,04,14, Thursday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山新勝寺」で開催されます「東日本大災害物故者追悼復興祈願」「奉納 成田太鼓祭」(以下「成田太鼓祭」と表記)です。
「成田太鼓祭」とは、関東を中心とした各都県を代表する「和太鼓」や「日本の伝統音楽」、「伝統舞踏」のチームが「成田山」と「表参道」を賑やかに盛り上げる日本屈指の「太鼓祭」です。
ちなみに今年で23回を数えるお祭りで「第20回成田太鼓祭」(平成20年)では、「第13回ふるさとイベント大賞」で「優秀賞」を受賞しています。
「成田太鼓祭」会場は「成田山新勝寺」から「JR成田駅」までの間(「表参道」沿いから「大本堂」)にステージが設けられ、メイン会場は「成田山新勝寺」となります。
「成田太鼓祭」の みどころは大きく分けて2つあります。
みどころ1つ目は「成田山千年夜舞台」。
「成田山千年夜舞台」は、日本全国から有名な太鼓を招き「新勝寺大本堂」において「かがり火」の炎が燃える幽玄な太鼓演奏は毎回2000人を超える観客を集めて行われるイベントのメインステージです。
静寂に包まれた夜の境内の空気を震わせて、伝わる打ち手の気迫。
それを肌で感じる荘厳な舞台なのだそうです。
みどころ2つ目は「千願華太鼓」。
「千願華太鼓」は「成田太鼓祭」の幕開けを告げるオープニングイベント。
「千」という字には、「皆」という意味が込められているそうで、一人一人の力は微力でも、「千」、すなわち皆の力を結集すれば大きなエネルギーとなる。
「千」の願い。
出演者、スタッフ、観客、会場に集まったすべての人達がひとつとなって「成田山新勝寺」の大本堂前で被災地の復興を祈願し、命の鼓動が奏でられるそうです。
参加人数は今回600名(700名とも言われています)程度の打ち手が参加するそうです。
(「表参道太鼓パレード」もみどころのひとつでしたが、考慮の結果、確実な避難誘導が困難であると判断したため中止となりました)
「成田太鼓祭」の開催に寄せて、被災されている方々を支援しながら、我々自身が震災前の日常生活をいち早く取り戻すために積極的に活動することが、現在最も求められていることととし、参加者及び来場者を鼓舞し、連帯感と一体感を持たせ、「日本の復興」の先駆けとなるべく開催を決意されたそうです。
主催者は決定にあたり、相当な葛藤と覚悟も要しましたが、出した結論に対し、自信と誇りを持って臨んでいくそうです。
太鼓の音色には、人の心を震わせ、勇気を沸き立たせ、鼓舞する不思議な力があるそうです。
「日本復興」を祈り、自分達に出来ることから始め、先駆けとして開催される「東日本大災害物故者追悼復興祈願」「奉納 成田太鼓祭」。
復興の祈りを込めた「鼓動の祭典」を体感しに「成田」にお出かけください。
「奉納 成田太鼓祭」詳細
開催日時 4月16日(土)10時〜19時
4月17日(日)10時〜16時45分
開催会場 ステージ紹介
(ステージ会場位置の目安(参考)になる観光施設)
1「大本堂特設舞台」
(成田山新勝寺大本堂)
「千願華太鼓」「成田山千年夜舞台」
2「ANAみらいステージ」
(弘恵会田町駐車場)
3「仲町ステージ」
(成田観光館)
4「NAA総門ステージ」
(成田山新勝寺総門、若松本店)
5「薬師堂ステージ」
(薬師堂)
「全国太鼓情報発信基地」
6「上町公園ステージ」
(しのん(ガラス小物店))
7「上町ステージ」
(阿部商店(せんべい店))
8「JR東日本花崎町ステージ」
(ラーメンばやし、千葉興業銀行成田支店)
問合わせ 総合案内所「成田観光館」 0476-24-3232
備考
「響け とどけ 成田の祈り」というキャッチコピーの通り、「東日本大震災」の復興支援の一環として、主催者の思いを表しています。
各ステージにおける演奏に際し、出演者が十分な演奏が出来るような環境作りにご協力をお願いしますとの事です。
また「成田太鼓祭」開催に伴い、会場周辺で交通規制が行われます。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=457 |
| 地域情報::成田 | 09:59 AM |
|
|
2011,04,11, Monday
本日二つ目に紹介するのは、近隣市「芝山町」「芝山観光竹の子園」の「竹の子収穫体験」(以後「筍(たけのこ)狩り」と表記)(筍掘り?)です。
「芝山公園」の「桜」で紹介しました「芝山町」にて、今が「旬」の「筍狩り」を楽しむことができるスポット「芝山観光竹の子園」があります。
「芝山観光竹の子園」では、「筍狩り(竹の子狩り)」が楽しめます。
「芝山観光竹の子園」の入園料は500円、掘り道具は準備されています。
テントで受付をし、園内に入り、竹林の中で「筍(竹の子)」を探し、傷つけないように掘り進め「筍」を掘り出します。
普段出来ない体験でありますが、意外に体力がいる「筍狩り」(筍掘り?)。
「筍狩り」で春を収穫しに「芝山町」へお出かけしませんか?
「芝山観光竹の子園」「竹の子収穫体験」詳細
住所 山武郡芝山町朝倉157-1
開園期間 4月上旬から5月上旬 (雨天時休園)
入園時間 9時〜15時
問合わせ 芝山町産業経済課 0479-77-3918
(期間中問合先)
料金 (入園料)一律500円
(持ち帰り用) (〜4月25日)1kg350円
(4月26日〜)1kg300円
備考
「芝山観光竹の子園」では「掘り道具」は準備されています。
「運動靴」や「長靴」を用意下さいとのこと。
周辺には「朝倉安らぎの杜」という1500本余りの木々に囲まれた広場のある緑豊かな「憩いの場」があるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=453 |
| 地域情報::成田 | 09:27 AM |
|
PAGE TOP ↑
|
 |



