 |
■CALENDAR■
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
| | | | | |
<<前月
2025年11月
次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■POWERED BY■
■OTHER■
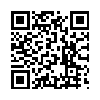
携帯からもご覧いただけます
|
2012,03,09, Friday
本日ご紹介するのは、近隣市「芝山町」「航空科学博物館」で明日(あした)の3月10日(土)・11日(日)に開催されます「航空ジャンク市」です。
「航空科学博物館」(2011年6月7日のブログ参照)は、「成田国際空港」に隣接する「山武郡芝山町」にあります「日本最初」の「航空専門」の「博物館」です。
平成元年(1989年)8月1日に開館して以来、「航空ファン」「航空マニア」「観光客」「地元客」の皆さんに愛され、賑わっている「観光スポット」です。
また近年人気の「社会科見学」できる「スポット」なので「子供たち」にも人気のある「施設」です。
「航空科学博物館」には、「アンリファルマン複葉機」の「原寸大模型」や「ピストンエンジンコーナー」などの「展示物」をはじめ、「飛行機のあゆみ」の展示、「飛行機の体験コーナー」等充実した「内容」となっています。
さらに「屋外展示場」には「新聞社」で活躍した「セスナ」、「ヘリコプター」など10機以上の「航空機」を展示し、有料搭乗も可能な「航空機」もあるそうです。
また「航空科学博物館」は「成田国際空港」に隣接するため(「空港」北側に立地)、「展望展示室」からは、「ガイド」の説明を参考に「成田国際空港」に離着陸する「航空機」を見ることができます。
「航空科学博物館」では、年間を通じ、様々な「イベント(行事)」「企画展」を行っていますが、今回ご紹介する「航空ジャンク市」(2011年9月6日のブログ参照)は特に人気のあるイベントなのだそうです。
大変好評の恒例イベント「航空ジャンク市」では、普段あまりお目にかかれない「航空部品」や「エアライングッズ」などを格安で販売しています。
前回は2011年9月10日(土)・11日(日)に行われ、大盛況のうちに終わったそうです。
レア物が多く、使用されていた「コックピットセット」や「エンジン」の「ファンブレード」、「ビジネスクラス」の「シート」、「飛行機」の先端にある「速度センサー」「ピトー管」、「機内食」を運ぶ「カート」など正に「航空関係の専門市」で「値段」もお買い得なものもあり、ファン垂涎のラインナップとなっています。
「航空ジャンク市」は人気のあるイベントのため、朝早くから並ばれている人も多く、10時からではありますが、欲しいものがある方はお早めのお出かけをおすすめします。
ちなみに当日は「整理券」も配られるようです。
「芝山町」の誇る人気施設「航空科学博物館」の人気企画「航空ジャンク市」にお出かけしてみてはいかがでしょうか?
「航空ジャンク市」詳細
開催日時 3月10日(土)・11日(日) 10時〜17時 (11日(日)は10時〜16時)
開催会場 航空科学博物館1階多目的ホール
問合わせ 航空科学博物館 0479-78-0557
備考
「航空科学博物館」では、「航空ジャンク市」の開催、及び準備のため3月6日(火)〜11日(日)の間、「DC8シミュレーター」、「ライブラリー」及び「多目的ホール」が利用できないそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=984 |
| 地域情報::成田 | 07:08 AM |
|
|
2012,03,07, Wednesday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山新勝寺」で3月11日(日)に開催されます「第22回全国氷彫刻展 成田山新勝寺大会」です。
「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照)は、「成田のお不動さま」の愛称で親しまれている「真言宗智山派」の「大本山」で、「関東三大不動」のひとつです。
天慶3年(940年)、「寛朝大僧正」によって開基され、以来一千年余りもの「歴史」を持つ「全国有数」の「霊地」です。
「成田山新勝寺」は、「成田山」という文字通り「境内一帯」が小高い「山」になっています。
そして「成田山新勝寺」のシンボル・「大本堂」の裏手には鬱蒼(うっそう)と「樹木」が茂る一帯があり、こちらが「成田山公園」(2010年11月12日・2011年11月8日のブログ参照)となります。
「成田山公園」の開園は昭和3年で、16万5千平方メートルという広大な「公園」です。
「公園」内は自然の起伏が巧みに取り入れられ、起伏を縫って「遊歩道」を散策することができます。
「成田山公園」の園内中央にある「一の池」、「二の池」、「三の池」の3つの「池」の周囲は、「春」は「梅」に「桜」、「初夏」の「新緑」、「秋」の「紅葉」と四季折々の表情を見せます。
またただいま開催中の「成田の梅まつり」(2月9日のブログ参照)は殊に有名で、「梅林」の「梅の香」ただよう中で味わう「野点」は格別なのだそうです。
また園内には「成田山書道美術館」(2011年6月5日のブログ参照)があり、「成田山公園」に隣接して「成田山霊光館」、「成田山仏教図書館」などがあります。
「成田山新勝寺」周辺には見処が多く、とても1日では見回れないほどあります。
特に「成田山新勝寺」周辺は、「門前町」として昔から栄えており、「JR成田駅前」から「成田山新勝寺」に至る「商店街」がメインの「表参道」には、創業100年以上という貫禄を見せる「老舗」も多くあり、「観光客」の人気スポットになっています。
今回「成田山新勝寺」で行われます「第22回全国氷彫刻展 成田山新勝寺大会」ですが、「祈願 東日本大災害復興」と冠をつけて開催されます。
「全国各地」より「職人」約20名の方々が参加され「成田山新勝寺」「大本堂」前を「会場」に「氷彫刻」を奉納し、「参詣者」のご健勝をご祈念、
併せて「氷彫刻技術」の向上を目的として開催されるそうです。
四角い「氷柱」が「職人たち」の「手」によって様々な形に作り上げられていく過程を目の前で見ることができるそうです。
「冬」ならではの「氷」の「芸術品」が並ぶ様子は圧巻だそうです。
毎年恒例となった「全国氷彫刻展 成田山新勝寺大会」の行われる「成田山新勝寺」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「全国氷彫刻展」「成田山新勝寺大会」詳細
開催日時 3月11日(日) 8時半〜15時
開催会場 成田山新勝寺 成田市成田1
当日スケジュール
9時30分 開会式 (大本堂1階表玄関前)
9時45分 競技開始
12時15分 競技終了・審査
13時00分 特別大護摩参詣「成功成就」
14時15分 表彰式
問合わせ 成田山新勝寺 0476-22-2111
備考
「成田山公園」で行われています「成田の梅まつり」ですが、「厳冬」で寒さが続き「梅」の「開花」が遅れているため、「開花」の遅れに合わせ、期間延長され、3月20日まで開催されるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=982 |
| 地域情報::成田 | 10:05 PM |
|
|
2012,03,06, Tuesday
本日ご紹介するのは、近隣市「成田市」「成田山書道美術館」で今週末の3月10日(土)〜4月22日(日)(3月27日〜31日を除く)の期間開催されます「収蔵優品展」「印人のしごと」です。
「成田山書道美術館」(2011年6月5日のブログ参照) は、「近代日本」の「書作品」を収蔵している「書」の「総合美術館」です。
「成田山書道美術館」は、収蔵の中心は江戸時代末期から現代まで、あまりにも現代に近いが故に見過ごされがちな「近代日本」の「書作品」を広い「視野」から収蔵しています。
「書道」をこころざす「人」は一度は訪れてみるべき「美術館」で、「成田山書道美術館」は「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照) の裏手に広がる「成田山公園」(2011年11月8日・2010年11月12日のブログ参照) の「三の池」のほとりに建てられています。
「書」の「総合美術館」として、優れた「作品」を鑑賞できることはもちろん、「作品」の保存、研究、普及など、「専門家」から「一般の人」が楽しめるそうです。
「成田山書道美術館」の「建物」内容ですが、「展示棟」1階 は、高さ13メートルの「壁面展示」ができる「中央プラザ」をもつ「企画展示室」、2階は「常設展示室」で「回廊式」の「ギャラリー」となっています。
「成田山書道美術館」では、1年間を通しいろいろな「展示会」を年間6〜7回行っています。
前回の企画展は「つどうみほとけ〜成田山新勝寺の仏教絵画」(1月1日のブログ参照)で、1月1日(祝・日)〜3月4日(日)の期間行われていました。
今回の「成田山書道美術館」では、「収蔵優品展 印人のしごと」が4月22日(日)まで行われています。
平成6年に一括して受け入れた「印譜コレクション」を中心に、「成田山書道美術館」で所蔵する「篆刻家」の「作品」が特集されるそうです。
50種を超える「印譜コレクション」には「日中」、「古今」の「印」が見られ、「印」の「歴史」の「概要」を垣間見ることができます。
また、「本」としての「美しさ」にも「魅力」があるようです。
「成田の梅まつり」(2月9日のブログ参照)で賑わう「成田山公園」に佇む「書」の「専門美術館」「成田山書道美術館」。
企画展「収蔵優品展 印人のしごと」の行われるこの機会に訪れてみてはいかがでしょうか?
「収蔵優品展 印人のしごと」「成田山書道美術館」詳細
開催期間 3月10日(土)〜4月22日(日)
開催会場 成田山書道美術館 成田市成田640
開館時間 9時〜16時 (入館は15時半まで)
休館日 月曜日 (3月27日〜3月31日は休館するそうです。)
問合わせ 成田山書道美術館 0476-24-0774
備考
「成田山書道美術館」では、「本館」2階「研修室」及び「会議室」を貸出しています。(有料)
「研修室」は、面積244平方メートル、「収容人数」200人、「会議室」は、面積64平方メートル、「収容人数」30人です。
料金等詳しくは「成田山書道美術館」HPをご参照下さい。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=981 |
| 地域情報::成田 | 11:59 AM |
|
|
2012,03,05, Monday
本日二つ目にご紹介するのは、近隣市「栄町」に伝わる「龍角寺の七不思議の民話」です。
「印旛郡栄町龍角寺」には「龍角寺」にまつわる「七不思議の民話」があります。
「龍角寺の七不思議の民話」は、「栄町」にある「龍角寺」という「寺」にまつわる「七不思議の民話」ではなく、「印旛郡栄町龍角寺」という「土地」にまつわる「七不思議の民話」なのだそうです。
(七つの中には「龍角寺」にまつわる「民話」もあります。)
「龍角寺」にまつわる「七不思議の民話」は、「三ケの岩屋」(「椀貸し」(岩屋古墳))、「八ツの井戸」、「親は古酒、子は清水」(「子者清水(こはしみず)」)、「坂田ヶ池の片歯の梅」(「片歯の梅」)、「竜灯の松」(「龍燈腰掛の松」)、「不増不滅の石」、「むらさめ返しの松」(「村雨返しの松」)と七つとなっています。
「三ケの岩屋」(「椀貸し」(岩屋古墳))の民話ですが、「岩屋」に住む「かくれ座頭」が「村人」に、「膳」・「椀」を貸す不思議な「民話」です。
「三ケの岩屋」とは「岩屋古墳」の二つの「石室」と「みそ岩屋古墳」の三つをいい、そこに「かくれ座頭」という「妖怪」が住んでいたといいます。
この近郷の人々はこの「岩屋」に「膳」・「椀」等を借りたいとお願いすると、翌日その前にそろえられており、その「食器」を借りたりしていました。
ある日、ある人が一組だけ返すのをわすれてからは、もうかしてくれなくなったといわれています。
その一組が今でも「龍角寺」に保存しているそうです。
「八ツの井戸」ですが、「八つの井戸」以外に新しい「井戸」を掘ると「たたり」が起こる不思議なはなしです。
この近郊の「山すそ」に、6m位の「清水」湧く「井戸」が8つあって、その「水」で生活を営んでいました。
不便さから「他所」に「井戸」を掘ると、ことごとくその「家」に不幸がおこったと言われ、8つの「井戸」以外は掘らなかったといわれています。
「親は古酒、子は清水」(「子者清水(こはしみず)」)ですが、「親」が飲むと「古酒」、「子ども」が飲むと「清水」の「味」がするという不思議な「井戸」のはなしです。
「岩屋古墳」のすぐ下にある「湧水」で、昔「親」が飲むと「古酒」で、「子ども」が飲むとただの「清水」であったことから、このように伝えられています。
「坂田ヶ池の片歯の梅」(1月28日のブログ参照)ですが、「人柱」を埋めた「堤」の「梅の木」から不思議な「実」がなる悲しいはなしです。
この「河」(池)は高い所へ、即(すなわ)ち逆(さか)さに流れていたと言われ、「サカサ」から「サカタ」に変化したといわれています。
そして昔、この堤(つつみ)がたびたびくずれることから、「女」の人柱を捧げ、その時に背負っていた「子」が「梅の実」をかじっており、その「実」から「芽」が出、「木」になり、「梅の実」がついたそうです。
しかしどの「実」もかじったような「歯」のあとがあったということから「片歯(形見)梅」といわれているそうです。
今も「池」(坂田ヶ池)のそばに「梅の木」が立っているそうです。
「竜灯の松」(「龍燈腰掛の松」)ですが、「日照り」を救うために「雨」を降らせた「龍」の不思議なはなしです。
1月2日のブログで案内しました「龍寺めぐり」の中の「龍神伝説」「雨講祈祷」の後、3つに割れた「頭部」が「松」の「老大木」にかかったといい、その名があるが、今は枯れてしまったそうです。
「不増不滅の石」ですが、「雨」が降っても「日照り」でも、溜まる「水」が増えも減りもしない不思議な「石」のはなしです。
「不増不滅の石」は「塔跡」のことで、中央の「くぼみ」にある「水」は、「雨」が降っても「日照り」になっても、増えることも減ることもなかったといわれています。
今も「龍角寺」境内に「不増不滅の石」が残っています。
「むらさめ返しの松」(「村雨返しの松」)ですが、その「木」(松)を境に、一方は「雨」が降り、一方は「雨」が降らないという不思議な「松」のはなしです。
「村」の北はずれに「松」の「老木」があって、その「松」を境にして、一方は「雨」が降ったり、他方は「雨」が降らなかったりしたといわれています。
「龍角寺の七不思議の民話」の伝わる「印旛郡栄町」では、「龍角寺七不思議の道」として「ウォーキングコース」にして巡る「散策」も行われています。
いにしえの「七不思議伝説」の伝わる「栄町」に訪れ、散策してみてはいかがでしょうか?
備考
「栄町」の「古刹」「龍角寺」は、「関東地方」で最も古い「寺院」のひとつです。
「龍角寺」周辺には「龍角寺古墳群」(2月25日のブログ参照)があり、「龍角寺岩屋(いわや)古墳」(2月27日のブログ参照)や「浅間山(せんげんやま)古墳」(2月29日のブログ参照)など「古墳時代」を代表する「史跡」が多く残っています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=980 |
| 地域情報::成田 | 01:05 PM |
|
|
2012,03,02, Friday
本日二つ目にご紹介するのは、近隣市「成田市」の「菜の花の名所」「甚兵衛公園」です。
「菜の花」は、「アブラナ」または「セイヨウアブラナ」の別名のほか、「アブラナ科アブラナ属」の「花」です。
「菜の花」は「食用」、「観賞用」、「修景用」に用いられます。
「春」に、一面に広がる「菜の花畑」は壮観で、代表的な「春」の「風物詩」でもあります。
「成田市」にある「甚兵衛公園」(2011年2月16日のブログ参照)は、義民「佐倉宗吾」のために掟(おきて)を破り「渡し舟」に出し、送り届けた後、「印旛沼」に身を投じたといわれる「渡し守」「甚兵衛」の名前が由来となっている「公園」で、「千葉県立印旛手賀沼自然公園」の一部です。
「宗吾霊堂」(2010年12月23日のブログ参照)に祀られています「佐倉宗吾」こと「佐倉惣五郎(木内惣五郎)」は、「藩主」「堀田氏」による苛政を直訴するべく「江戸」へと向かい、この渡しで「舟」を乗りました。
「渡し守」「甚兵衛」が、禁を破って「惣五郎」を「印旛沼」対岸の「吉高」まで送り届けたという伝承が「甚兵衛公園」に残っています。
現在「印旛沼」の畔(ほとり)には、「甚兵衛」の「供養塔」と「石碑」があります。
「甚兵衛公園」は、季節ごとに咲く「花」が見事なことで知られており、「春」には「菜の花」、「秋」には「秋桜」があたり一面に咲き乱れます。
特に「菜の花」は、「黄色一杯」の「花畑」が広がり、満開になると「黄金色の絨毯(じゅうたん)」を敷き詰めたように綺麗に咲いています。
また「甚兵衛公園」には、50本余りの「紅白梅」の「木」が植えられています。
今年は「寒波」の影響で2月中はまだ蕾(つぼみ)で、これから見頃を迎えると思われますが、「黄色」・「白色」・「紅色」といった色とりどりの「梅の花」を楽しむことができるようです。
四季折々の「花」が咲き誇る「公園」「甚兵衛公園」。
「菜の花」や「梅の花」を愛でに「成田市」に訪れてみませんか?
「甚兵衛公園」詳細
所在地 甚兵衛公園 成田市北須賀1626
問合わせ 成田市観光プロモーション課 0476-20-1540
備考
「甚兵衛公園」周辺には、「佐倉宗吾」の「旧宅」があり、「原生林」も広がっていて、「散策」に適しています。
また「甚兵衛公園」の「松の木」は「日本の名松100選」に昭和58年(1983年)5月に指定されています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=974 |
| 地域情報::成田 | 11:31 AM |
|
|
2012,02,29, Wednesday
本日ご紹介するのは、近隣市「栄町」の「浅間山古墳(せんげんやまこふん)」です。
「浅間山古墳」は「印旛郡栄町」にある「竜角寺古墳群」(2月25日のブログ参照)に属します。
「浅間山古墳」は、7世紀前半に築造されたと考えられる「前方後円墳」です。
「浅間山古墳」が属する「龍角寺古墳群」は、「古墳時代」後期の6世紀第二四半期に「古墳」の造営が始まりました。
「古墳群」は現在までに114基の「古墳」の存在が確認されていますが、「浅間山古墳」は「古墳群」内最大の「前方後円墳」で「墳丘長」は78mとされています。
「浅間山古墳」には「復室構造」の「横穴式石室」があり、「石室」は「筑波山」付近から運ばれた「片岩」の「板石」を用いて築造されており、「石室」内からは「金銅製冠飾」、「銀製冠」、「金銅製の馬具」や「挂甲」などが出土しています。
「墳丘」からは「埴輪」は検出されておらず、「前方後円墳」最末期の「古墳」であることは間違いないとされるが、「石室」の構造や「出土品」から「浅間山古墳」の「造営」を7世紀第二四半期という新しい時期を想定する「研究者」もあり、一般的には6世紀末から7世紀初頭と考えられている「前方後円墳」の「終焉時期」との関係で論議を呼んでいる「古墳」なのだそうです。
「龍角寺古墳群」を造営した「首長」は「印波国造」と考えられており、「浅間山古墳」の造営以前は、同じ「印旛沼」北東部にある「公津原古墳群」を造営した「首長」の勢力が「龍角寺古墳群」を造営した「首長」を上回っていたと考えられていますが、6世紀末以降、勢力を強めた「龍角寺古墳群」を造営した「首長」は、周辺地域で最も大きい「前方後円墳」の「浅間山古墳」を造営し、その後、日本最大級の「方墳」である「岩屋古墳」(2月27日のブログ参照)を造営し、更には7世紀後半には「龍角寺」を創建したと考えられています。
「浅間山古墳」を含む「龍角寺古墳群」は、「古墳時代」後期から「龍角寺」の創建に代表される「飛鳥時代」にかけての「地方首長」のあり方を知ることができる重要な「遺跡」と評価されています。
「古墳群」のうち、「岩屋古墳」は1941年に単独で「国の史跡」に指定されていましたが、2009年2月12日付けで、「浅間山古墳」を含む周辺の「古墳群」が追加指定され、「指定史跡名称」は、「龍角寺古墳群・岩屋古墳」と改められました。
また、「浅間山古墳」の「出土品」は2009年3月4日、「千葉県」の「有形文化財」に指定されています。
「龍角寺」が造営されたのとほぼ同時期に、「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)と「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)の「社殿」が造営されたとの見方もあり、これもやはり「香取海」を通して「常陸」、そして「東北方面」へ向かうルートを「ヤマト王権」が重要視していたことの表れと見られています。
「龍角寺古墳群」を作った「印波国造」と考えられる「首長」は、「ヤマト王権」が重要視する「交通路」を押さえることにより「王権」との結びつきを強め、「浅間山古墳」に示されるようにその力を強めたとされています。
また「龍角寺古墳群」の近くには「植生郡衙」跡とされる「大畑遺跡群」があります。
これは6世紀の「古墳時代」後期以降、「龍角寺古墳群」を造った「首長」は、7世紀後半の「龍角寺」建立、そして「律令制」が成立した後も「郡司」となってその勢力を保ったことを示唆(しさ)しており、「龍角寺古墳群」の画期である「浅間山古墳」の持つ意味は大きいといえます。
往時をしのぶ「古墳群」の中、異彩をはなつ「浅間山古墳」。
古代の歴史散策のできる「印旛郡栄町」にお出かけしませんか?
備考
「浅間山古墳」の「石室」と「石棺」に使用された「片岩」は、「筑波山」周辺からもたらされています。
これは「金鈴塚古墳」の「石棺」が「埼玉県」の「長瀞」付近から運ばれた「石材」を用い、一方、「埼玉古墳群」の「将軍山古墳」では、「石室」に「千葉県富津市」の「海岸」から運ばれた「石」を用いているのと同様の現象であり、「浅間山古墳」の「披葬者」も「関東地方」の「他地域」の「首長」との連携を深めていたことがわかります。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=969 |
| 地域情報::成田 | 10:04 AM |
|
|
2012,02,27, Monday
本日二つ目にご紹介するのは、近隣市「印西市」「木下(きおろし)南口商店街」で今週末の3月3日(土)に開催されます「木下駅南骨董市」です。
「印西市」「木下地区」は、江戸期以降栄えた歴史ある「宿場町」です。
「JR成田線」「木下駅」を中心に、徒歩10分圏内にありとあらゆる生活に必要なものが揃っています。
また隣の「茨城県」までも約2kmと、自転車で行ける距離になっています。
「木下」周辺は「利根川」をはじめ、「弁天川」、「六軒川」、「手賀川」など、「水」の豊富な環境にあります。
「木下の街」を歩いていると、たくさんの「橋」を見ることができます。
近年、川岸の「遊歩道」が整備され、ゆっくりと散歩もできるようになったそうです。
「JR成田線」「木下駅」は、107年以上の歴史をもつ「駅」で、東京近郊ではほとんど見られなくなった「木造風」のほのぼのした「田舎駅」だったそうです。
長く「木下地区」の歴史を見つめてきた古い「駅舎」は、2008年12月に新しい「橋上駅」として生まれ変わり、その際「木下駅」の南北を結ぶ「自由通路」が開通し、「利用者」は便利になったそうです。
「木下駅」の北口の細い道路を歩いていくと、昔ながらの「古い家屋」や「蔵」がいくつもあります。
「家屋」が密集していて、懐かしいもの、見るとほっとする空間が「木下地区」にはたくさんあるそうです。
「木下駅南骨董市」の会場ですが、「木下駅」「南口ロータリー」前のスーパー「ライフ」の南側に伸びる「木下南口商店街」が会場となります。
平成15年から「地域の活性化」を目指して「木下駅南骨董市」が始まりました。
「木下駅南骨董市」は「木下駅南骨董市実行委員会」が主催し、「木下南口商店街」が共催、「印西市」・「印西市商工会」・「印西市観光協会」の後援で開催されており、「木下南口商店街」の約200mの「通り」の両側には、「陶磁器」や「置物」、「古民具」から「おもちゃ」、「貴金属」に「着物」と出店が連なり、その数は60店以上で、県内だけでなく県外(茨城・埼玉・栃木・群馬・東京)の「業者」も参加する「骨董市」としては大きなものです。
毎月第1土曜日に行われていて、毎月5000人もの人達でにぎわうそうです。
また、「骨董市」に午前中に行くと、「抽選会」で「景品」がもらえることもあるようです。
「木下駅南骨董市」では、「開催日」当日は「商店街」が歩行者天国となり安心して買い物ができ、「産地直送」の「野菜」、「弁当」や「炊き込みご飯」なども出品、「季節」によって店頭に並ぶラインナップが変わっていき、四季折々の「産物」や「実用品」、「掘り出し物」探しと盛り沢山だそうです。
歴史ある「木下地区」「木下駅南口商店街」で行われる人気の「骨董市」。
昔懐かしい雰囲気の中、自分だけの「逸品」を探してみませんか?
「木下駅南骨董市」詳細
開催日時 3月3日(土) 7時〜15時頃
開催会場 木下南口商店街 印西市木下1521
問合わせ ホームショップマツシタ 0476-24-7883
備考
「木下駅南骨董市」は、荒天中止の「催し」です。
2月18日のブログで紹介しました「世界一大きなせんべい」は、「骨董市」が開かれる「印西市」「木下地区」の「せんべい」をブラッシュアップして作製、「ギネスブック」に「炭火で世界一大きな手焼きせんべいを焼く」で認定されています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=966 |
| 地域情報::成田 | 10:10 AM |
|
|
2012,02,27, Monday
本日ご紹介するのは、近隣市「栄町」の「龍角寺岩屋古墳(りゅうかくじいわやこふん)」(以降「岩屋古墳」と表記)です。
「岩屋古墳」は、「印旛郡栄町」にある「方墳」で、114基ある「龍角寺古墳群」(2月25日のブログ参照)の105号古墳であり、「龍角寺古墳群・岩屋古墳」として「国」の「史跡」に指定されています。
「岩屋古墳」は「印旛沼」北岸の標高約30mの台地上に位置しています。
「築造年代」は「古墳時代」終末期の7世紀前半頃の説と、7世紀中頃との説があります。
これはこれまで「岩屋古墳」から検出された「出土品」が全くなく、主に「横穴式石室」の構造で「築造時期」についての議論がなされており、「築造時代」を推定する材料にかける上に、「龍角寺古墳群」内で「岩屋古墳」の前に築造されたと考えられる「浅間山古墳(せんげんやまこふん)」の「造営時期」が7世紀初頭との説と7世紀第二四半期との説があることによります。
また「岩屋古墳」は、「東日本最大級」の「方墳(方形墳)」です。
同時期に築造された「大方墳」である「春日向山古墳」(「用明天皇」陵)、「山田高塚古墳」(「推古天皇」陵)をも凌(しの)ぐ規模であり、この時期の「方墳(方形墳)」としては「全国最大級」の規模であり、「古墳時代」を通しても5世紀前半に造営されたと考えられる「奈良県橿原(かしはら)市」の「舛山古墳」に次ぐ、「第二位」の規模の「方墳(方形墳)」となっています。
昭和初期に「上田三平」氏らの「調査」により、雄大な「方墳(方形墳)」であることが確認されています。
「岩屋古墳」は一辺約80m(78m)、高さ13.2mを誇り、周囲に「溝」がめぐらされ、「墳丘」は3段になっていて、1段目と2段目が低く3段目が高くなっているそうです。
「墳丘」周囲には南側を除く三方に約3mの「周溝」がめぐり、「周溝」の外側には「外堤」が見られます。
「岩屋古墳」はこれらを含めると全体規模は110m四方に達します。
また、2008年の「測量調査」により、「墳丘」南側の谷側から「墳丘」に向かって、「斜路」が作られていたことが判明しています。
「岩屋古墳」の「埋葬施設」として、下段の南面には東西2つの「横穴式石室」が10mの間隔で並んでいます。
西側「石室」は奥行4.23m、奥壁幅1.68m、高さ2.14mです。
東側の「石室」は西側よりやや規模が大きいですが、現在は崩落しているそうです。
「岩屋古墳」の沿革ですが、1970年(昭和45年)「明治大学」による、「石室」の実測、「墳丘」の「地形測量」を実施。
2007年(平成19年)「栄町教育委員会」による「104号古墳」を含む「清掃地形測量」を実施しています。
「岩屋古墳」は、1941年(昭和16年)1月27日、「国の史跡」に指定されました。
また2009年(平成21年)には「龍角寺古墳群」および周辺の「地形」を含む広範囲な「地域」が追加指定され、「龍角寺古墳群・岩屋古墳」として「史跡」の「名称変更」が行われました。
ちなみに「龍角寺古墳群・岩屋古墳」の「管理団体」は、「龍角寺」なのだそうです。
「国の史跡」に指定されている「龍角寺古墳群・岩屋古墳」。
古代の歴史を感じる「古墳群」を見に「印旛郡栄町」に訪れてみてはいかがでしょうか?
備考
「龍角寺古墳群」で「岩屋古墳」以降に築造された「みそ岩屋古墳」などの「方墳(方形墳)」では「方岩」は用いられることがなく、「貝の化石」を含んだ「砂岩」のみが用いられたことからも、「古墳」の「築造順」は「浅間山古墳」、「岩屋古墳」、「岩屋古墳」以外の「方墳(方形墳)」という順序であったことが推定できます。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=965 |
| 地域情報::成田 | 10:00 AM |
|
|
2012,02,25, Saturday
本日ご紹介するのは、近隣市「成田市」「栄町」にある「龍角寺古墳群(りゅうかくじこふんぐん)」です。
「龍角寺古墳群」は、「成田市」と「印旛郡栄町」の「印旛沼」北東部の「下総台地」上に、6世紀前半から7世紀にかけて造営された「古墳群」です。
「龍角寺古墳群」は、現在のところ114基の「古墳」が確認されています。
「古墳群」の中には、「龍角寺」(1月2日のブログ参照)参道沿いに中世から近世にかけて造られたと考えられている「塚」が数多くあり、見かけ上「古墳」との区別が難しいため、数については不確定な要素が残っています。
「龍角寺古墳群」は「前方後円墳」が37基、「方墳」が6基、「円墳」71基で構成されています。
しかし確認されている「前方後円墳」の多くが「円墳」に短小な「方形部」が付く「帆立貝形古墳」に類似したもので、現在「円墳」とされている「古墳」の中からも、今後「発掘調査」などが進めば「前方後円墳」が増える可能性があり、築造当時は「方墳」であった「古墳」の一部も、「墳丘」の改変などで今は「円墳」のようになっているものも考えられ、「方墳」の数も増える可能性があるようです。
「龍角寺古墳群」の立地ですが、「印旛沼」北西部の標高約30メートルの「下総台地」上に位置しています。
「龍角寺古墳群」がある付近の「下総台地」は幅が比較的狭く、「古墳群」は狭い台地上を北西側から南東側に約1.5キロメートルにわたって帯状に分布します。
「古墳群」の中で比較的早い時期に造られたと考えられる「前方後円墳」や「円墳」は、「古墳群」の西側である「印旛沼」に面する場所に位置しており、後半に造られた「龍角寺古墳群」を代表する「浅間山古墳」・「岩屋古墳」、そして「岩屋古墳」の後に造られた「みそ岩屋古墳」などの「方墳」は、「古墳群」の北方にかつて存在した「香取海」方面からの「谷」の「源頭部」にあたる丘陵上に築造されています。
これは「浅間山古墳」や「岩屋古墳」などの「方墳」は、「印旛沼」よりも北側の「香取海」方面を意識して「築造場所」に選んだものと解釈されています。
「龍角寺古墳群」のすぐ南東側には、「上福田古墳群」、「大竹古墳群」というやはり「古墳時代」後期から終末期にかけて造営された「古墳群」があります。
また「龍角寺古墳群」の南には4世紀から「古墳」の造営が見られる「公津原古墳群」、そして「印旛沼」東岸には「北須賀勝福寺古墳群」があり、「印旛沼」東岸には多くの「古墳群」が存在します。
「龍角寺古墳群」の「古墳群」を構成する「古墳」の多くは小型で、「前方後円墳」では全長20〜30メートル、「円墳」では直径10〜20メートルのものが多いようです。
「龍角寺古墳群」では当初、小型の「前方後円墳」や「円墳」が造られていたと考えられますが、7世紀前半以降「浅間山古墳」と、日本第二位の規模を誇る「方墳」である「岩屋古墳」という「印旛沼」周辺地域で最も大きい「古墳」が造営されています。
「龍角寺古墳群」は「古墳時代」前・中期の「古墳」は確認されておらず、「古墳時代」の後期にあたる6世紀から「古墳」の築造が開始されたと考えれています。
「印旛沼」付近を統合する「首長権」は、6世紀半ば頃までは「龍角寺古墳群」の南方にある「公津原古墳群」を造営した「首長」が握っていたと考えられますが、6世紀後半以降、「龍角寺古墳群」を造営した「首長」が強大化し、「首長権」の移動があったと見られています。
「龍角寺古墳群」を造営した「首長」が強大化した理由は、「古墳群」北方にある「香取海」の「水運」の「要衝」を掌握し、「常陸」、そして「東北方面」へ向かう「交通路」を押さえることに成功したからと考えれています。
これは「龍角寺古墳群」の「浅間山古墳」までの「古墳」は、「下総台地」の「印旛沼」に近い場所に造営されていたものが、「浅間山古墳」以後は「香取海」方面を意識した立地となったことにも現れています。
そして6世紀末から7世紀にかけての「ヤマト王権」の変革期にあたり、「関東北部」、そして「東北」へと向かう交通の「要衝」を押さえた「龍角寺古墳群」を造営した「首長」のことを「ヤマト王権」は重要視したと考えられており、「大王家」と直結した「壬生部」の「責任者」となったとの説も唱えられています。
「ヤマト王権」や「畿内」の「豪族」との関係を深めたことも、「終末期古墳」の時期としては最大の「方墳」である「岩屋古墳」の造営に繋がったものと見られています。
7世紀前半には、「古墳群」の北隣に「龍角寺」が創建されました。
そして「古墳群」西北には「植生郡」の跡とみられる「大畑遺跡群」もあり、「龍角寺古墳群」を造営したと考えられる「印旛国営」、最近の研究では「大生部直」氏は、「古墳群」の造営後も「龍角寺」の創建、そして「律令制」成立後も「郡司」としてその勢力を保ったと考えれています。
「龍角寺古墳群」は「古墳群」を構成する多くの「古墳」が、「房総のむら」内で比較的良好な状況で保存されており、また全国的に見ても最後の「前方後円墳」のひとつである「浅間山古墳」、そして「終末期古墳」の時代では最大の「方墳」である「岩屋古墳」など、学術的に見ても価値が高い「古墳」があります。
つまり「龍角寺古墳群」は「古墳時代」後期から「終末期古墳時代」の「古墳群」を知る上で貴重な資料であり、7世紀の「寺院」建立、そして「律令制」における「郡司」の時代に至るまで、「関東地方」の「一首長」について知ることのできる貴重な「遺跡」と評価され、以前より「史跡」とされていた「岩屋古墳」に追加される形で、「龍角寺古墳群・岩屋古墳」として2009年2月12日、「国の史跡」に指定されています。
また「浅間山古墳」の「出土品」は2009年3月4日、「千葉県」の「文化財」に指定されています。
太古の歴史に思いを馳せる「龍角寺古墳群」。
太古のロマンを感じに「龍角寺古墳群」散策に訪れてみてはいかがでしょうか?
備考
「龍角寺古墳群」の「古墳番号」ですが、現在「専門書」等で用いられている、「深澤」の論文(1988年)によって確定したものだそうです。
ちなみに「龍角寺古墳群」の主な「古墳」は「24号墳」、「101号墳」、「岩屋古墳」(105号墳)、「みそ岩屋古墳」(106号墳)、「108号墳」、「浅間山古墳」(111号墳)、「112号墳」となっています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=962 |
| 地域情報::成田 | 11:17 AM |
|
|
2012,02,23, Thursday
本日ご紹介するのは、近隣市「多古町」「多古町コミュニティプラザ」「文化ホール」で明明後日(しあさって)の2月26日(日)に開催されます「多古町ダンスフェスティバル2012」です。
「多古町コミュニティプラザ」で行われる「多古町ダンスフェスティバル2012」は、「フラダンス」や「ピアダンス」、「社交ダンス」を中心に「ヒップホップ」、「バレエ」、「タップダンス」、「ベリーダンス」、「よさこいソーラン」、「日本舞踏」の9種類の「ダンス」を1度に見ることができます。
「子どもから大人までダンスの楽しさを味わおう!」とうたっている通り、思わず踊り出したい、また見て楽しい9種類の「ダンス」を午前、午後の2回発表するそうです。
また、「多古町ダンスフェスティバル」は、入場無料の催しとなっています。
「多古町ダンスフェスティバル」終了後は、「多古町散策マップ」「たこるんぱ」(2月10日のブログ参照)を片手に「多古町」を散策してみてはいかがでしょうか?
「多古町」のダンス愛好家の集まる「ダンス」の美しさ、楽しさが伝わる「多古町ダンスフェスティバル2012」を見に「多古町コミュニティプラザ」「文化ホール」に訪れてみませんか?
「多古町ダンスフェスティバル2012」詳細
開催日時 2月26日(日) 10時〜15時半
開催会場 多古町コミュニティプラザ 文化ホール 香取郡多古町多古2855
問合わせ 勝又ダンススクール 0479-76-4560
備考
「多古町ダンスフェスティバル2012」当日は、「パン」や「おにぎり」、「飲み物」等を「多古町コミュニティプラザ」「文化ホール」ロビーにて販売するそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=959 |
| 地域情報::成田 | 09:09 AM |
|
PAGE TOP ↑
|
 |



