 |
■CALENDAR■
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
<<前月
2026年02月
次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■POWERED BY■
■OTHER■
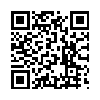
携帯からもご覧いただけます
|
2011,07,28, Thursday
本日ご紹介するのは、となりまち「香取市小見川」で来週月曜日(8月1日)に開催されます「第115回水郷おみがわ花火大会」です。
「水郷おみがわ花火大会」は毎年8月1日に「香取市小見川」で開催される歴史ある「花火大会」。
本年も開催は決定しています。
(6月15日のブログ参照)
昨年開催された「第114回水郷おみがわ花火大会」には、17万人訪れた人気のある「花火大会」です。
「水郷おみがわ花火大会」は1908年(明治41年)、当時の「香取郡小見川町」が水運の商都としてますます発展することを祈念して始められました。
関東でも有数の歴史を持つ「花火大会」で、2008年で100周年を迎えました。
ただし、公式回数としては「旧神里地区」での「花火大会」(1951年以前)の分を加えているため、2008年の大会は「第112回」としているそうです。
明治時代からの「小見川地区」の「夏」の「風物詩」であり、毎年10万人を超える人が見学に訪れ、会場付近では屋台等が多数出店し賑わいを見せています。
打ち上げ数は約8000発、その中でも「利根川」の川面を利用した「水中花火」が特徴であります。
なお、「旧佐原市」でも以前は「花火大会」(水郷佐原花火大会)が開かれ市民に親しまれていましたが、市町村合併の影響で2006年(第54回)を最後に、「水郷おみがわ花火大会」に統合されています。
ちなみに開催日8月1日は、かつての「利根川」「川開き」にあわせていましたが、例外として1992年(平成4年)は「アジア・オーストラリア地区水上スキー選手権大会」の日程に合わせるために8月22日に、また2001年(平成13年)は「町村合併50周年事業」のために8月5日に開催されました。
「水郷おみがわ花火大会」の開催会場は「利根川」「小見川大橋」下流で、河川敷や小見川区事務所などに駐車場が用意されていますが、来場者数が多いため例年会場付近は車や人で非常に混雑します。
また当日は、小見川区事務所付近から会場付近まで「シャトル船」(有料)が運航され、開催日は「黒部川」のイルミネーションも行われており、その様子も楽しむことができます。
「シャトル船」運航時間は15時から23時までで料金は中学生以上500円、小学生200円です。
「水郷おみがわ花火大会」では「桟敷席」(1坪)1万6000円にて販売中で、臨場感ある「打ち上げ花火」を間近で見ることができます。
(売り切れ次第終了)
「水郷おみがわ花火大会」の主な演目はなんといっても「全国尺玉コンクール」です。
1983年より開催されている「全国尺玉コンクール」では、全国の「花火師」が尺玉1発を打ち上げ、技を競います。
今年で29回目を迎え、「花火作り名人」24名が丹精込めて作った尺玉を目の前で見ることができます。
また「特大水中スターマイン」は「スターマイン」と「水中花火」を組み合わせたもので、「水郷おみがわ花火大会」の見処のひとつになっています。
「北総一」の「夏」の催し「水郷おみがわ花火大会」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「第115回水郷おみがわ花火大会」詳細
開催日時 8月1日(月) 19時〜
開催会場 小見川大橋下流 利根川河畔
問合わせ 水郷小見川観光協会事務局 (香取市小見川支所内) 0478-82-1117
備考
「第115回水郷おみがわ花火大会」会場周辺は、夜間で足元が悪いため、照明器具を持参の上お越し下さいと呼びかけています。
なお、雨天の場合は翌日(8月2日)に順延となります。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=619 |
| 地域情報::香取 | 10:47 AM |
|
|
2011,07,18, Monday
本日ご案内するのは、となりまち「香取市」「小見川」で今週7月22日(金)〜24日(日)に開催されます「小見川祇園祭」です。
毎年7月の第3週の金・土・日に行われている「小見川祇園祭」。(本年は7月22日〜24日)
(「屋台」(山車)の曳き廻しは土・日のみ)
寛永16年より始められたといわれていて、「利根川」水運の港町として栄えた「江戸文化」の粋が見られます。
「小見川」の「伝統的行事」「小見川祇園祭」では初日は「神輿」(3基)の渡御が行われ、残り2日で「屋台」(山車)(6基)が曳き廻されているそうです。
二層式の「屋台」(山車)は「彫物」や「色彩」があでやかであり、一階は「お囃子」、二階は「演芸場」となり、「各屋台(山車)」とも芸人さんの芸が披露されるそうです。
詳しく説明しますと「佐原」の「山車」と同様の二層構造の「屋台」(山車)でありますが、上部(大天上)には「屋根」がついており、屋台進行時は「芸座連」(げざれん)による演奏、停止時に上部の屋根を上げて「歌謡」が披露されます。
「芸座」(お囃子)は、小見川周辺の集落を単位とした「芸座連」が「屋台」に乗っています。
「小見川祇園祭」の「屋台」と「芸座連」ですが、以下の通りです。
「本町(ほんまち)」は額字は「本町」、主な彫物は「獅子」、「龍」で「芸座連」は「清水芸座連」。
「仲町(なかまち)」は額字は「仲町」、主な彫物は「龍」で「芸座連」は「内野芸座連」。
「川端町(かわばたちょう)」は額字はなし、主な彫物は「鷹」で「芸座連」は「木内芸座連」。
「小路(しょうじ)」は額字は「小路」、主な彫物は「忠臣蔵」で「芸座連」は「野田芸座連」。
「北下宿(きたしもじゅく)」は額字はなし、主な彫物は「龍」、「獅子」で「芸座連」は「下小川芸座連」。
「南下宿(みなみしもじゅく)」は額字はなし、主な彫物は明治25年制作、「芸座連」は「羽根川芸座連」。
「小見川祇園祭」当日は、「おまつり広場」が登場し、いろいろな催しを予定しているそうです。
また近年では、小見川市街地を流れる「黒部川」にぼんぼりをつるし「黒部川イルミネーション」として風情を醸し出したり、大橋の上で住民による踊りや音楽などの披露が行われ、「祇園祭」と共に「小見川」のまちを盛り上げています。
「黒部川イルミネーション」ですが、中日(7月24日(土))には、「黒部川」の「大橋」に「屋台」(山車)がそろい、合同で踊りが披露された後、「黒部川」上の「ぼんぼり」600個の「点灯式」(7月24日〜8月16日)が予定されています。
情緒豊かな「小見川ばやし」を奏でながら「屋台」(山車)6台が練り歩く「小見川祇園祭」。
往時「小見川藩一万石」の「城下町」であった「香取市小見川」の催しにお出かけしませんか?
「小見川祇園祭」詳細
開催会場 小見川駅前市街地 (須賀神社周辺) 香取市小見川
開催日時 7月22日(金)〜7月24日(日)
問合わせ 水郷小見川観光協会事務局 0478-82-1111
備考
「小見川祇園祭」に、お車でお越しの方は、「香取市役所小見川支所」の「駐車場」をご利用下さい。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=604 |
| 地域情報::香取 | 11:59 AM |
|
|
2011,07,13, Wednesday
本日2つ目にご紹介するのは、となりまち「香取市佐原」の「佐原の大祭」の「歴史」と「由来」です。
先(7月11日)のブログでご案内した「佐原の大祭」「夏祭り」。
いよいよ明後日(7月15日)より開催されます。
「小江戸」「佐原」の一大イベントである「佐原の大祭」は、約300年の歴史を誇ります。
今回は「佐原の大祭」の「歴史」「由来」をご紹介します。
「香取市」「佐原」の市街地の中心部を東西に分断するように流れる「小野川」を境にして、東側の地域を「本宿」と呼び、西側の地域を「新宿」と呼んでいます。
「本宿」は字のごとく、中世から続く元々の町場の地域です。
「祇園祭」は、京都で「貞観年間」(859年〜877年)に疫病の祟りを鎮めるためにはじめられた「祇園御霊会」に由来しています。
文献資料からは、14世紀にはすでに「八坂神社」の前身である「牛頭天王社」が「佐原八日市場」の地に祀られていたことが知られています。
「祇園祭」自体いつの頃から始められたのかは定かではありませんが、元禄15年(1702年)までには旧暦の6月10日に「浜下りの神事」が、6月12日には「祇園」の「神事」が行われていたそうです。
「浜下りの神事」とは、10日の暮れ前に「天王社」から「神輿」を出して「橋元」まで行き、川舟に乗せて「お神酒(みき)の奉献」と「神楽の奉納」を行い「天王社」へ帰る「神事」のことで、「祇園」の「神事」とは、12日の暮れ前に再び「神輿」を「天王社」から出して大工の治兵衛宅前に「御仮屋」を作り、そこへ「神輿」を運び、「お神酒の奉献」と「神楽の奉納」を行い「天王社」へ帰るというものだったそうです。
元禄16年(1703年)に「天王社」の別当寺であった「清浄院」より、多くの人が「神輿」に参詣できるようにとの申し出を受け、「浜下り」のあと「神輿」を帰さずに「御仮屋」へ留め置き、12日に戻すという「神幸」の形になったようです。
その後、各町内へも「神輿」を廻すようになり、正徳4年(1714年)に初めて「神輿神幸」に「練物」が登場するようになりました。
一方、「新宿」は天正年間(1573年〜1591年)に新しく開起された地域で、元々は「本宿」「新宿」の区別なく「佐原村」の「鎮守」として「天王社」を祀っていました。
その後、町場として発展を見た「新宿」は、新たに「諏訪社」を「鎮守」として祀るようになりました。
「諏訪祭」は、「信州諏訪社」の「御射山神事」に由来し、天保10年(1839年)に書かれた文書から、享保6年(1721年)に「名主」の「伊能権之丞」という人が中心となって、「本宿」の「祇園祭」とは別に、「練物」を中心とした「諏訪の祭礼」を新たに企画したことが知られています。
これ以降、「新宿」では「祇園祭」に係わらなくなり、今日に至っているそうです。
現在、「山車祭り」の起源を「諏訪祭」の享保6年(1721年)としているそうです。
これは「祇園祭」の「練物」は享保10年(1725年)を最後に出されなくなり、再び常態化するのは43年後の明和5年(1768年)のことだからだそうです。
ただし、明和5年においても依然、様々な出し物による「練物」の形態であり、現在のようないわゆる「佐原型」という「山車」の「祭り」が成立するのは、江戸時代の後期、文政年間(1819年〜1829年)以降と考えられているそうです。
明後日(7月15日)から始まる「佐原の大祭」「夏祭り」。
「江戸」から続く「佐原」の伝統・文化の「粋」を是非ご覧下さい。
備考
「佐原の大祭」の時に引き廻される「山車」の本物の2台展示されている「水郷佐原山車会館」には、祭りや山車に関わる資料、佐原囃子の道具等が展示されています。
「水郷佐原山車会館」では、3面スクリーンでお祭りの映像を見ることもでき、一年中お祭りの雰囲気を味わうことができるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=594 |
| 地域情報::香取 | 09:11 AM |
|
|
2011,07,13, Wednesday
本日ご紹介するのは、となりまち「東庄町」「東庄県民の森」で今週末(7月16日(土))に開催される「里山観察会」と「ほたる鑑賞会」です。
「東庄県民の森」では「里山観察会」と「ほたる鑑賞会」を行います。
「ほたる」が活動する夕方までは、「東庄県民の森」で「里山観察」(「木工クラフト体験」を含む)と「軽食」(各自で用意してくださいとのこと)をとり、「ほたる」が出るのを待つそうです。
夕食後(日が暮れた後)は、車で「香取市」の山間部「香取市岡飯田地区」(旧「小見川町岡飯田」)にある「里山」(田園地帯)まで移動します。
「里山」(田園地帯)は「環境保全」に取り組んでいて、今でも「ほたる」を見ることができるそうです。
青々とした「稲の上」を舞う「光」。
幻想的な、「ほたる」の飛び交う姿を鑑賞します。
暗闇の中、「ほたる」舞う「東庄町」の催しに参加してみませんか?
「里山観察会」「ほたる鑑賞会」詳細
開催日時 7月16日(土) 17時〜20時半
集合時間 16時 県民の森管理事務所
開催会場 東庄県民の森 香取郡東庄町小南639
定員 30名
参加費 200円 (保険代含む)
問合わせ 千葉県立東庄県民の森 管理事務所 0478-87-0393
備考
「東庄県民の森」では7月23日(土)9時半〜12時半に「親子森の学校」を開催。
「森」の観察をして、「森」、「木」の仕組みを学び、「木工クラフト製作体験」も行います。
また、「東庄県民の森」で栽培している「ジャガイモ収穫体験」を行うそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=593 |
| 地域情報::香取 | 07:59 AM |
|
|
2011,07,11, Monday
本日ご案内するのは、となりまち「香取市」の「夏」を彩る「佐原の大祭」「夏祭り」です。
「香取市」の「夏」を彩る「まつり」「佐原の大祭」「夏祭り」。
「佐原の大祭」は、「夏祭り」と「秋祭り」があり、共に「国指定重要無形民族文化財」にしていされていて、「関東三大山車祭り」のひとつとされ、約300年の伝統を有しています。
「日本三大囃子」「佐原囃子(さわらばやし)」の音を町中に響かせながら、「小江戸」と呼ばれる「町並み」(国選定重要伝統的建造物群保存地区)の中を家々の軒先をかすめながら進むさまは風情たっぷりで、「江戸時代」の情景を彷彿とさせます。
「佐原の大祭」自慢の「山車(だし)」は、「総欅造り(そうけやきづくり)」の「本体」に「関東彫り」の「重厚な彫刻」が飾り付けられ、上部には「江戸・明治期」の「名人人形師」によって制作された高さ4mにも及ぶ「大人形」などが乗ります。
「八坂神社祇園祭」である「7月の夏祭り」は、「小野川」をはさんで東側一帯(本宿地区)を10台の「山車」が引き廻されます。
一方、「諏訪神社秋祭り」である「10月の秋祭り」は、「小野川」の西側一帯(新宿地区)を14台の「山車」が引き廻されます。
「佐原」の「山車」は、「4輪2層」構造の「曳山」です。
いわゆる「江戸型山車」の形態とは異なり、独自に発展を遂げた形態だそうです。
使用される材料は主に「ケヤキ材」を用い、その他に「ヒノキ材」や「カシ材」などを用いて造られています。
「山車」の「人形」(飾り物)ですが、「眺高欄」を廻した「山車」の天上部にあり、「日本神話」など様々な「逸話」から取材した「歴史上の人物」の「大人形」や「作り物」が飾り付けられています。
「大人形」は、身の丈4〜5mにおよび日本最大級の大きさを誇っています。
この「大人形」は、江戸時代から明治・大正時代
にかけて「名人」と呼ばれた「人形師達」によって技術の粋を集め制作されたものです。
また「作り物」には、「麦藁細工(むぎわらざいく)」の「鯉」や「稲藁細工(いなわらざいく)」の「鷹」等、町内に住む人達の手によって制作される昔ながらの飾り物もあります。
「山車」本体は比較的簡素な造りとなっていますが、それを重厚にみせているのが周囲に装飾され彫刻です。
「彫刻」は、「関東彫り」と呼ばれ、「ケヤキ材」の木地を生かし、重厚かつ繊細に彫られており、「後藤茂右衛門」、「石川三之助」、「小松光重」、「金子光晴」など、名工と呼ばれた彫工の作品が数多く残されています。
「彫刻」の構図は、「龍」や「獅子」、「花鳥」のほか、「日本神話」などの「伝記物」、「太平記」、「太閤記」などの「軍記物」、「三国志」、「水滸伝」などの「中国の故事」から取材されており、昔話の名場面が、繊細に表情豊かに表現されています。
「佐原の大祭」の見処はなんといっても「山車の曳き廻し(ひきまわし)」です。
「山車の曳き廻し」は、長さ約4m、重さ20kgほどある「てこ」と呼ばれる2本の長い丸太が重要な役割をしめています。
この「てこ棒」を「山車」と「山車」の「車輪」の間に差し込み「梶」をとったり、停止させたりして速度をコントロールします。
「てこ棒」を操るには修練が必要で、「佐原の大祭」の「花」となっています。
一般的な「曳き廻し」に対して、「技」を競うとともに、最大の見せ場としての特別な「曳き廻し」を「曲曳き」といいます。
基本型の「曲曳き」として「のの字廻し」、「そろばん曳き」、「小判廻し」の3つがあり、いずれも「曳き綱」は使用されずに行われるそうです。
北総を代表する「国指定重要無形民族文化財」「佐原の大祭」を見に「香取市佐原」に訪れてみませんか?
「佐原の大祭」「夏祭り」 (本宿祇園祭) 詳細
開催日時 7月15日(金)〜17日(日) 10時〜22時
開催会場 香取市佐原 本宿地区
駐車場 利根川河川敷臨時駐車場 1000台・無料
問合わせ 香取市商工観光課 0478-54-1111(代)
水郷佐原観光協会 0478-52-6675
備考
「佐原の大祭」は雨天決行です。
平成22年から、「夏祭り」の日程が「7月10日以降の金・土・日」開催となっています。
「利根川河川敷臨時駐車場」から「お祭り区域」まで「シャトル舟」を運航(往復券 大人1000円)しています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=591 |
| 地域情報::香取 | 09:33 AM |
|
|
2011,07,06, Wednesday
本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「水郷佐原水生植物園」今週末(7月9日(土)〜)で開催される「はす祭り」です。
先のブログで何度かご紹介しています「水郷佐原水生植物園」。
「水郷佐原水生植物園」は、6月中に開催されていた「水郷佐原あやめまつり」が記憶に新しい施設です。
今回の「はす祭り」も「あやめまつり」に次ぐ人気の「水郷佐原水生植物園」の催しです。
「水郷佐原水生植物園」内の「日中友好ハス園」では、非常に珍しい「千弁蓮(せんべんれん)」「多頭蓮(たとうれん)」をはじめ、日本ではほとんど見られない小型の「碗蓮(わんれん)」など、「中国」の「南京市」から贈られた「ハス」を中心に「300種以上のハス」を栽培し、品種数では「日本一」の規模を誇ります。
最盛期の7月・8月には、鮮やかな緑色の葉の上に「白」や「ピンク」「黄色」の花々が次々に顔をのぞかせ、優美に咲き誇ります。
「はす祭り」期間中の日曜日・祝日には「早期観蓮会」や、「地酒」を用いた「象鼻杯(ぞうびはい)」・「はす」の「花茶」(冷)や「葉茶」(温)のもてなし、「はす博士」による「解説会」といった催しも行われているそうです。
「優美」な「蓮(はす)」の「花々」の「祭典」を観覧に「香取」にお出かけしませんか?
「はす祭り」詳細
開催日 7月9日(土)〜8月14日(日)
開園時間 8時〜16時 (土・日・祝日は6時開園)
所在地 水郷佐原水生植物園 香取市扇島1837-2
入園料 大人 500円 小中学生 250円
「はす祭り」イベント情報
早朝観蓮会
「はす」の花は、夜明けとともにほころび始め、昼前には閉じてきます。
涼しい朝のうちに「はす」をご覧いただけるよう、週末に「早朝観蓮会」を行います。
7月9日(土)〜8月7日(日)までの土・日・祝日 午前6時開園
「はす博士」の「解説会」
身近に「はす」を親しんでいただけるよう、園内を散策しながら、「はす博士」による「はす」にまつわる色々なお話が聞ける企画です。
栽培から文化的なお話まで、興味ある方は是非お越しくださいとのこと
7月10日(日)・17日(日)・24日(日) 7時〜9時
「象鼻杯」
今年も「早朝観蓮会」では「象鼻杯」を味わっていただけます。
「象鼻杯」は、「はす」の「葉」に「地酒」を注ぎ、「茎」から「酒」を吸うもので、「象の鼻」に見立ててこのように言います。
古くから「観蓮会」で行われている催しで、暑さしのぎの「清涼剤」なのだそうです。
「はす茶」
「早朝観蓮会」をお楽しみの後は、冷たい「はす」の「香り茶」や、「はす」の「葉茶」でのどをうるおし、くつろぐ催し
7月9日(土)〜8月7日(日)までの土・日・祝日 7時〜10時
「熱帯睡蓮展」
7月9日(土)〜8月31日(水)
「睡蓮栽培教室」
7月18日(祝) 8時〜
(各イベントは中止になる場合があります)
問合わせ 0478-56-0411
備考
「水郷佐原水生植物園」には「花」の中にもうひとつの「花」を咲かせたように見える「重台蓮」・「八重絞り」の「大酒錦」といった日本では数少ない貴重な品種が栽培されています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=584 |
| 地域情報::香取 | 11:08 AM |
|
|
2011,06,30, Thursday
本日ご案内するのは、「文月(7月)」の「北総の祭」情報です。
まず最初にご案内するのは、「香取市」の「佐原の大祭」です。
今年の「佐原の大祭」は7月15日(金)〜7月17日(日)の10時〜22時(各日)に開催されます。
「佐原っ子」が待ちに待った「一大行事」で、「北総の小江戸」「香取市」の「夏」の「風物詩」となっています。
「勇壮な山車(だし)の曳き廻し」が見られる「佐原の大祭」、今年は「山車」が「8台」出る予定だそうです。
「山車の曳き廻し」は「佐原の大祭」の「花」。
一般的な「曳き廻し」に対し、技を競う「最大の見せ場」「曲曳き」は「のの字廻し」、「そろばん曳き」、「小判廻し」の3つがあり、いずれも「曳き縄」は使用されずに行われるそうです。
「関東三大山車祭り」のひとつと称され、約300年の伝統を有する「壮大な祭り」です。
次にご案内するのは、「成田市」の「成田祇園祭」です。
今年の「成田祇園祭」は7月8日(金)〜10日(日)の3日間開催され、8日(金)は12時半〜、9日(土)は9時〜、10日(日)は13時〜実施されます。
「300年」の「歴史」を誇る「初夏」の「風物詩」として、「成田市」の「夏」の「最大のイベント」となっています。
「成田山新勝寺」ご本尊「不動明王」の「本地仏」「奥の院」「大日如来」の「祭礼」で、「大日如来」を「ご尊体」とした「御輿」が渡御し、併せて「成田山」と「9町内」「10台」の「山車」や「屋台」が市内を巡行します。
毎年約40万人の見物客が訪れる「お祭り」です。
次にご案内するのは、地元「銚子市」で開催される「浅間様(せんげんさま)」です。
本年は7月16日(土)の午前0時〜午後10時に行われます。
生まれて初めて迎える「旧暦6月1日」(7月第3土曜日)の早朝に裸足でわが子を抱いて「浅間神社」の階段を駆け登りお参りするとご利益があるとされ、今でも「初山(はつやま)」と呼ばれて信仰されています。
「浅間様」では、「社(やしろ)」に向かう坂道に夜店が並び昔ながらの懐かしい「お祭り」を体感することが出来ます。
「初夏」を彩る「夏祭り」「浅間様」は、当館のお泊まりの「お客様」も「銚子電鉄」で「浅間様」最寄り駅「本銚子駅(もとちょうしえき)」までお出かけされる「お客様」もいらっしゃいます。
季節も「夏」に移り変わり「北総」もいよいよ「お祭り」のシーズンがいよいよ始まります。
「初夏」の「北総の祭」にお出かけしてみませんか?
備考
「佐原の大祭」で演奏される「佐原囃子」は「日本三大囃子」に数えられています。
「成田祇園祭」では夜間に「山車」がライトアップされ、幽玄な「山車」・「屋台」の姿を楽しむことが出来ます。
「浅間様」の神社は高台(丘陵地)にあるので境内からは、「利根川」の向こう岸にあるとなりまち「茨城県神栖市波崎町」が良く見渡せます。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=575 |
| 地域情報::香取 | 11:12 AM |
|
|
2011,06,26, Sunday
本日ご紹介するのは、近隣市「神崎町」の「オハツキイチョウ」です。
「神崎町」は「香取市」「成田市」と「利根川」をはさんだ「茨城県稲敷市」と隣接した「千葉県」「北部」のまちです。
1889年(明治22年)4月1日「町村制」施行に伴い、「神崎村」と「米沢村」が発足。
翌年1890年(明治23年)3月12日「神崎村」が「町制施行」し「神崎町」(初代)となりました。
その後、1955年(昭和30年)1月5日「神崎町」と「米沢村」が合併し、「神崎米沢町」が発足。
同日、改称し「神崎町」(2代目)になり、現在に至っています。
「神崎」の「オハツキイチョウ」は、「神崎ふれあいプラザ」の隅にある「雌樹」で樹高26.6m、根回り4mの巨木です。
この「オハツキイチョウ」はかつてこの地にあった「神崎小学校」の開校を記念して「明治33年」に植樹されたもので、現在「神崎小学校」は移転しており、地元有志が植樹したそうものだそうです。
「オハツキイチョウ」とは、通常の「イチョウ」と異なり「種子」が「葉の上」につくことから付けられた名前で珍重されています。
「オハツキイチョウ」は「生きている化石」ともいわれ、地球上にたった「一族一種」の貴重な植物でもあります。
「オハツキイチョウ」は「イチョウ」の「変種」で、「葉の上」に「実」を結ぶ、また「葉上」に「葯(よろいぐさ)」を付ける「イチョウ」のことをいい、全国に約20本ほどの存在が知られているそうです。
「オハツキイチョウ」は名前の由来は、「葉の上」に「種子」がつくことからつけられているようです。
「神崎」の「オハツキイチョウ」は樹勢がとても旺盛で毎年多くの「銀杏(イチョウ)」が実るそうです。
「神崎町」にある貴重な「オハツキイチョウ」を見に立ち寄ってみてはいかがでしょうか?
「神崎」の「オハツキイチョウ」詳細
所在地 香取郡神崎町本宿96
問合わせ 神崎町教育委員会 0478-72-1601
備考
「神崎」の「オハツキイチョウ」は昭和40年(1965年)4月27日に「千葉県」の「天然記念物」に指定されています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=571 |
| 地域情報::香取 | 01:35 PM |
|
|
2011,06,24, Friday
本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「千葉県立中央博物館大利根分館」(以下「大利根分館」と表記)です。
「大利根分館」は、「与田浦」に位置し「利根川」の自然と歴史、農業に関する資料をはじめ「利根川下流域」の「東下総地域」の歴史、民族、自然などに資料が展示、保存されています。
「大利根分館」の「常設展示」は、テーマ「利根川の自然と歴史」をバックボーンにしています。
エントランスホールの地形模型による「流路・流域」等を説明した「利根川のすがた」に始まり、「第1展示室」では、「利根川は生きている」というマルチスライドによる自然のコーナーを組み入れながら、「利根川」がまだ「東京湾」に注いでいた中世までの「東下総」の歴史を編年的に概説しています。
「第2展示室」では、「利根川」が「銚子口」への流路を変えた近世以降の「東下総地域」を「農業」・「漁業」・「水運」・「商業」・「文化」等の分野にわけ、「利根川」とのかかわりのなかで各論的に説明しています。
2つの「展示室」とも小コーナー毎に資料を精選して展示していますが、資料の一部展示替えを行っています。
また「展示回廊」では、「利根川」に生息するいきものを展示しているほか、中庭や屋外にも各種の資料を展示しています。
上記のように、館内はエントランスホールと3つの「展示室」、中庭、屋外の展示構成からなり「第3展示室」を除きすべて常設展示なのだそうです。
「大利根分館」では「企画展示」や「イベント」も開催されます。
「大利根分館」では、現在「企画展」「水郷を旅する人々」(〜6月26日)を開催中。
「松尾芭蕉」・「小林一茶」や江戸庶民など「水郷を旅した人々」の足跡と作品、描かれた水郷の風景や近代の「水郷観光」を紹介しています。
「利根川の自然と歴史」「千葉県の農業」をテーマとする「千葉県立中央博物館大利根分館」。
「利根川」とともに歩んだ人々の模様をご覧いただける「大利根分館」にお立ち寄り下さい。
「千葉県立中央博物館大利根分館」詳細
所在地 香取市佐原ハ4500
定休日 月曜日 (祝日の場合は翌日)、10月1日〜3月31日
営業時間 9時〜16時半
料金 入館200円 (企画展開催中は300円)
問合わせ 0478-56-0101
備考
「千葉県立中央博物館大利根分館」では「ナウマンゾウ」の「頭部化石」(模造)等も展示しています。
また「大利根分館」にある「板碑」(供養塔)は、「千葉県」の「指定文化財」になっています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=569 |
| 地域情報::香取 | 12:25 PM |
|
|
2011,06,15, Wednesday
本日二つ目にお伝えするのは、となりまち「香取市」「小見川」で開催されている「水郷おみがわ花火大会」の開催決定です。
「香取市」は昨日、「水郷おみがわ花火大会」を予定通り8月1日に開催すると発表しました。
「水郷おみがわ花火大会」会場の「小見川大橋」周辺が「東日本大震災」で液状化被害を受けたことにより、中止も検討されましたが、開催を求める声が寄せられ、仮復旧の目処がたったことから開催を決めたそうです。
「水郷おみがわ花火大会」は毎年8月1日に行われていて「北総」の「夏」の風物詩として皆に親しまれたお祭り。
大会は今年で115回目を数える歴史ある「花火大会」で例年10万人以上集める「大人気」の催しです。
開催決定には「香取市」の関係各所の尽力によるもので、大変嬉しい決定のお知らせでした。
備考
今回の「水郷おみがわ花火大会」では、「香取市」は会場の安全対策や警備体制を強化し、来場する皆様に「懐中電灯」の持参を呼び掛けているようです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=560 |
| 地域情報::香取 | 11:54 AM |
|
PAGE TOP ↑
|
 |



