 |
■CALENDAR■
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
<<前月
2026年02月
次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■POWERED BY■
■OTHER■
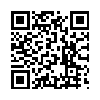
携帯からもご覧いただけます
|
2016,09,27, Tuesday
本日ご紹介するのは、近隣市「成田市」「成田市さくらの山」で10月1日(土)に開催されます「ジンギスカン発祥の地成田」「さくらの山ジンギスカンまつり」です。
「成田市」は、「面積」約214平方km、「人口」は132061人(平成28年8月末日現在)で、「千葉県」の「北部中央」に位置する「中核都市」です。
「成田市」の「北」は、とうとうと流れる「坂東太郎」・「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)をへだてて「茨城県」と接し、「西」は「県立自然公園」に指定されている「印旛沼」(2011年2月3日のブログ参照)、「東」は「香取市」と接しています。
「成田市」の「西側」には「根木名川」、「東側」には「大須賀川」がながれ、それらを取り囲むように広大な「水田地帯」や肥沃(ヒヨク)な「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の「畑地帯」が広がっています。
「成田市」「北部」から「東部」にかけての「丘陵地」には「工業団地」や「ゴルフ場」が点在し、「成田市」の「南」には「日本の空の玄関口」(WORLD SKY GATE)・「成田国際空港」(2015年4月7日・2012年12月10日のブログ参照)があります。
また「成田市」の「中心部」である「成田地区」は1000年以上の「歴史」がある「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照)の「門前町」として栄え、毎年多くの「参拝者」で賑わいます。
「成田市内」にはほかにも数多くの「寺社」が点在しており、「成田市」は、豊かな「水」と「緑」に囲まれ、「伝統的」な「姿」と「国際的」な「姿」が融和した「都市」として知られています。
「成田市」は、平成18年(2006年)3月27日、「香取郡」「下総町」、「香取郡」「大栄町」の2町が合併し、新生「成田市」が誕生、「北総台地」(下総台地)の「中核都市」としてさらなる飛躍を果たしました。
かつての「田園観光都市」「成田」は、「信仰のまち」としての「顔」と、「経済」、「文化」の様々な「分野」での「国際交流」の「拠点」として、「国際交流都市」の「顔」をもつ「まち」へと大きく変貌しています。
「宮内庁下総御料牧場」は、1969年(昭和44年)8月18日まで、「成田市」「三里塚地区」に存在していた「御料牧場」の「名称」です。
江戸時代、「下総台地」の「北部」に「江戸幕府」によって「佐倉牧」が設置されて「軍馬」や、「農耕馬」の「放牧地」があり、「佐倉牧」は7つの「牧」から構成されていたことから「佐倉七牧」とも称され、「三里塚一帯」には「七牧」の1つであった「取香牧(トッコウマキ)」が置かれていたそうです。
明治時代に入り「文明開化」の「煽り」を受け「国内」での「羊毛」の「生産」を高める「必要性」が起こり、
1 青草に富むこと
2 樹林地に恵まれていること
3 物資の輸送に便利な所
を条件に「内務省」は「用地選定」に「アメリカ」の「牧羊家」「アップ・ジョーンズ」を起用して「各地」の「実地調査」を行いました。
その結果、「七牧」の一つ「取香牧」(現・成田市取香、三里塚周辺)の「隣接地」が「牧羊場」に定められ1875年(明治8年)9月、「下総牧羊場」が開場し、この時、「取香牧」も閉場し「牛馬」の「改良」に当たる「取香種蓄場」として発足しました。
この頃、「内務卿」・「大久保利通」は「現地の視察」を行い、また「牧羊場」・「種蓄場」「両場」の「初代場長」に「内務省」の「岩山敬義」が就任しました。
1878年(明治11年)5月、「大久保」が暗殺され「非業の死」を遂げ、その「影響」もあってか1880年(明治13年)1月、「両者」が合併して「下総種蓄場」となったそうです。
この「合併」は「事業」を整理する「意味合い」が含まれていたとされています。
「下総種蓄場」は「場内」を「三里塚区」、「両国区」(現・富里市両国)など「七区」に分かれており、「本庁」は「両国区」「高堀」に置かれたそうです。
「下総種蓄場」の「管理」は1881年(明治14年)にそれまでの「内務省」から新設された「農商務省」に移され1885年(明治18年)6月には「宮内省」「御料局」の「直管」となり1888年(明治21年)10月に「宮内省下総御料牧場」と改められ、それまで「高堀」にあった「本庁」が「三里塚」に移され、その後、「牧羊事業」は次第に縮小され「綿羊」の「数」も減少したそうです。
1966年(昭和41年)3月、「政府」は「臨時新東京国際空港閣僚協議会」を改組し「千葉県」と協議・検討を続けた結果、「富里」の「東方」約10kmに位置する「三里塚」付近が「航空管制」、「気象条件」などの「諸条件面」で「富里」と差異がなく、また「国有地」である「下総御料牧場」および「県有地」を「最大限」に利用しかつ「敷地面積」を「航空審議会」「答申」「規模」の約半分にする事により「民有地」の「買収」が極力少なくして「地元住民」に対する「影響」を「最小限」に留めることができるなど「利点」があるこてが判明しました。
同年7月4日の「閣議」で「新東京国際空港(現・成田国際空港)の位置及び規模について」を決定、「牧場」は、「空港敷地」となることが決まったそうです。
明治から大正にかけて「牧場経営」は「改善」が図られ、「事業」は更に縮小へと向かい、1922年(大正11年)には「牧場」の「経営」が悪化し、「馬」の「繁殖」を一時中止したそうです。
1923年(大正12年)、「牧場」の「総面積」の6割にあたる2044町歩を「帝室林野局」へ移管し、かつての「7区」から「三里塚」、「両国」の「2区」だけとなりました。
1969年(昭和44年)8月、「御料牧場」は「栃木県」「高根沢町」に移転することが決定され同月18日に「牧場」の「閉場式」が行われましたが「成田空港反対闘争」「激化」の折であり「空港反対派」が「場内」に乱入するという場面もあったそうです。
かくして「宮内庁下総御料牧場」は明治以来の「歴史」に幕を閉じ、「新牧場」へは80家族約300人、「家畜」約400頭が移転しました。
「下総御料牧場」の一部は「三里塚記念公園」として保存され今日に至っており、「御料牧場」移転後「社台牧場」など、「民間」の「サラブレット生産牧場」も「北海道」「日高地方」にその拠点を移しました。
しかし今なお「三里塚」周辺には「出羽牧場」、「新田牧場」、「新堀牧場」、「千代田牧場」、「鈴木牧場」などが点在し、かつての「馬の産地」の「面影」を垣間見ることができるそうです。
「三里塚」の「春」は「桜樹」10万株ともいわれ、「花」で満ちあふれ多くの「人」を集め近くの「成田山新勝寺」、「宗吾霊堂」とともに「名勝地」として「人々」に親しまれていました。
「三里塚」の「桜」は「牧場」開創の際「防風林」として「スギ」、「マツ」、「ケヤキ」と共に「ヨシノザクラ」、「ヤマザクラ」、「ボタンザクラ」などが植えられた事に始まります。
広い「牧場」を散策しながら「花の観賞」が出来る事も特徴で、
「一里、二里、花は桜の三里塚」
ともてはやされていたそうです。
また1969年(昭和44年)の4月1日から15日まで行われた「最後」の「桜まつり」には、名残を惜しむ延べ20万人の「花見客」で賑わったそうです。
「ジンギスカン」(成吉思汗)は、「マトン」(成羊肉)や、「ラム」(仔羊肉)などの「羊肉」を用いた「日本」の「焼肉料理」です。
「一般的」には「北海道」を代表する「郷土料理」とされる他、「岩手県」「遠野市」、「長野県」「長野市」など「一部地域」でも盛んに食されています。
「ジンギスカン」は、「中央部」が「凸型」になっている「ジンギスカン鍋」を熱して「羊肉」の「薄切り」と、「野菜」を焼き、「羊肉」から出る「肉汁」を用いて「野菜」を調理しながら食します。
使用する「肉」には、「調味液漬け込み肉」の「味付け肉」、「冷蔵(チルド)肉」の「生肉」、「冷凍肉」の「ロール肉」があります。
「ジンギスカン」の「起源」については、「俗説」で「かつてモンゴル帝国を率いたジンギスカン(チンギス・カン)が遠征の陣中で兵士のために作らせた」と説明される場合もありますが、実際には「モンゴル」の「料理」とはかけ離れています。
また「羊肉」を用いる「中国料理」としては「清真料理」の「カオヤンロウ」という「羊肉料理」がありますが、これも「日本」で食べられている「ジンギスカン」とは程遠いですが、ただし「ジンギスカン料理」の「起源自体」は「中国大陸」にあるといわれ、「日本軍」の「旧満州」(現・中国東北部)への「進出」などを機に、「前述」の「カオヤンロウ」から「着想」を得たものが「日本人向け」に「アレンジ」され、現在のような「形式」になったものとみられます。
「最初」の「ジンギスカン専門店」は、1936年(昭和11年)に「東京都」「杉並区」に開かれた「成吉思(ジンギス)荘」とされています。
他にも、「山形県」「蔵王温泉」や、「岩手県」「遠野市」等がそれぞれ、上記の「東京」や、「北海道」のものとは「発祥」を異にする、独自のものとしての「ジンギスカン鍋」の「起源」を主張しています。
上記のように明治8年(1975年)、「成田」に「日本初」の「牧羊場」が誕生、後に「宮内庁下総御料牧場」となり、「皇室」「ご滞在」に際し、「賓客」には「ジンギスカン」が振る舞われたそうです。
やがて周辺の「農家」で「牧羊」が始まると、「ジンギスカン」もすぐに「地域」に広まったそうです。
「成田空港」の「建設」により「御料牧場」は「栃木県」「塩谷郡」に移転しましたが、「成田」では今も変わらず「ジンギスカン」が親しまれています。
「成田市」では、「ジンギスカン」とゆかりのある「地」「成田」として、「成田市さくらの山」「展望デッキ」付近を「会場」に「さくらの山ジンギスカンまつり」を開催するそうです。
「さくらの山ジンギスカンまつり」ですが、10月1日(土)10時00分から15時00分まで行われる「野外」の「イベント」で、「2部入替制」となっています。
「さくらの山ジンギスカンまつり」は、「第1部」は11時00分から12時30分まで、「第2部」は13時30分から15時00分までの「2部入替制」で行われ、「受付」は「各回」30分前から、「各回」90分制限となっているそうです。
「さくらの山ジンギスカンまつり」の「チケット価格」ですが、1組6000円(各回30枚限定)、「内容」ですが、「大人」4人分の「肉」・「野菜」、「紙皿」、「割箸」、「エプロン」、「七輪」1台、「炭」、「駐車スペース」1台分確保となっています。
※1組につき大人6人程度のスペースです。
※七輪ブース内は、ペットの連れ込みをお断りいたします。
※お持ち込みの食材の調理はご遠慮ください。
※追加の生肉・生野菜を会場で別途販売いたします。
「さくらの山ジンギスカンまつり」では、「ジンギスカン」を盛り上げる様々な「ショー」、「アトラクション」、「体験教室」(参加無料)などが行われ、「内容」は下記の通りです。
成田市観光キャラクター「うなりくん」(2011年1月15日のブログ参照)の「うなりくんふわふわドーム」(1回300円)
oriさん(ペルウ゛ィス/キッズヨガ)
ラキ・フラスタジオ(フラダンス)
沖縄島唄ナイチャーズ兼ゴスペルチームシュイラ
アクラム(ベリーダンス)
シンタロウダンス教室(キッズダンス)
Baha!(キッズダンス)
「成田市民」の「憩いの場」「成田市さくらの山」で開催される「ジンギスカン発祥の地成田」ゆかりの「イベント」「さくらの山ジンギスカンまつり」。
この機会に「成田市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「ジンギスカン発祥の地成田」「さくらの山ジンギスカンまつり」詳細
開催日時 10月1日(土) 10時〜15時
開催会場 成田市さくらの山展望デッキ付近 成田市駒井野1338-1
問合わせ 空の駅さくら館 0476-33-3309
備考
「ジンギスカン発祥の地成田」「さくらの山ジンギスカンまつり」ですが、「雨天」の場合、「翌日」10月2日(日)に「順延」となっており、10月2日(日)が「荒天」の場合は「中止」となるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3170 |
| 地域情報::成田 | 10:07 AM |
|
|
2016,09,26, Monday
本日ご案内するのは、近隣市「印西市」「結縁寺(ケチエンジ)」で9月28日(水)に開催されます「銅造不動明王立像の御開帳」です。
「印西市」は、「千葉県」の「北部」、「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の緩やかな「起伏」の上に位置している「自治体」です。
「印西市」は、三方を「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)、「手賀沼」、「印旛沼」(2011年2月23日のブログ参照)に囲まれ、「四季折々」に「表情」を変える「自然環境」に恵まれ、「市民」や、この地を訪れる「人」に、「やすらぎ」と、「うるおい」を与えています。
「印西市」は、江戸時代から「商業の町」として栄え、「江戸」と、「佐倉」、「銚子」を結ぶ上で「重要なまち」でした。
そのため、「印西市」には「歴史的建造物」や、「遺跡」も数多く残っており、当時の「面影(オモカゲ)」を偲(シノ)ばせています。
現在も「印西市」は「地理的条件」にも恵まれ、「東京都心」、「千葉県」の「県庁所在地」「千葉市」、「成田国際空港」(2015年4月7日・2012年12月10日のブログ参照)という「日本」を代表する「高機能拠点」の中心に位置している「まち」として発展を続けています。
「印西市」は、昭和29年(1954年)12月に「旧・木下町(キオロシマチ)」、「旧・大森町」、「旧・船穂村」、「旧・永治村」の一部が合併して「町制」を施行し、平成8年(1996年)4月に「市制」を施行しました。
「印西市」が含まれる「千葉ニュータウン」は、昭和42年(1967年)に「計画」が決定され、昭和59年(1984年)に「入居」が開始されています。
そして、現在「印西市」では、「町の歴史」を今に伝える「神社」や、「仏閣」、「由緒」ある「まつり」も、「人々」によって大切にされています。
「銅造不動明王立像」の「御開帳」が行われる「結縁寺」(2011年9月27日のブログ参照)は、周りを「銀杏(イチョウ)」の「木」に囲まれた「印西市」にある「小寺」で、「寺伝」によりますと、神亀年間(724年〜729年)に奈良時代の「僧」・「行基」の開山によって創建されたと言われています。
また「源頼政」の「家臣」が「頼政」の戦死後、その「首」をこの地に葬って一寺を建立したとも伝えられています。
「結縁寺」ですが、「真言宗豊山派」の寺院で、「山号」は「晴天山」、御本尊」は「不動明王」を祀っています。
(「結縁寺」は、「天晴山」・「西光院結縁寺」とも呼ばれています。)
また「結縁寺」では、「御本尊」「不動明王」とともに「阿弥陀三尊」も祀られ、「結縁寺」「境内」に咲く「彼岸花(ヒガンバナ)」ですが、「印西八景」(2012年2月12日のブログ参照)のひとつに指定されているそうです。
「結縁寺」「銅造不動明王立像」ですが、嘉元元年(1303年)に造られた「銅造」の「御本尊」で、「高さ」47cmの「大きさ」、「左」の「上牙」で「下唇」を、「右」の「下牙」で「上唇」を噛(カ)みしめた「面相」、逞(タクマ)しい「体つき」など、鎌倉時代の「特色」を表している「御尊像」だそうで、上記のように「結縁寺」では、「阿弥陀三尊」とともに祀られているそうです。
「不動明王」こと「梵名」「アチャラ・ナータ」ですが、「仏教」の「信仰対象」であり、「密教特有」の「尊格」である「明王」の「一尊」であり、また「五大明王」の中心となる「明王」です。
「不動明王」は、「密教」の「根本尊」である「大日如来」の「化身」、あるいは「その内証」(内心の決意)を表現したものと見なされています。
「不動明王」は、「お不動さま」の「名」で親しまれ、「大日大聖不動明王」、「無道明王」、「無動尊」、「不動尊」などとも呼ばれています。
「不動明王」は、「アジア」の「仏教圏」の中でも、特に「日本」において根強い「信仰」を得ており、「造像例」も多く見られています。
また「日蓮宗系」「各派」の「御本尊」(いわゆる「十界曼陀羅」)にも「不動明王」が書かれていますが、「愛染明王」と同様、「空海」によって伝えられた「密教」の「尊格」であることから、「日蓮」以来、代々「種子」で書かれています。
なお「日蓮」の「曼陀羅」における「不動明王」は、「生死即涅槃(セイシソクネハン)」を表しているとされています。
上記のように「結縁寺」の「寺宝」「銅造不動明王立像」は「造高」47cm、「裳」(下半身をまとう衣)「前面」の「刻銘」により嘉元元年(1303年)の「造像」とわかるそうです。
「牙」は「片方」を上、「片方」を下に向けて出すが、「眼」はいわゆる「天地眼」とせず、「両眼」を見開いています。
上記のように鎌倉時代後期に造像され、貴重な「銅造不動明王立像」が今回御開帳され、「銅造不動明王立像の御開帳」ですが、9月28日(水)に、「結縁寺」にて執り行われます。
「不動明王」ですが、「真言行者」の「守護神」であり、「忿怒形」(「怒り」の「表情」)を以て、「人々」を導くといわれています。
上記のように「銅造不動明王立像」は、「像高」47cm、「右手」に「宝剣」、「左手」に「羂索」を持っており、「全体的」に力強く「写実的」だそうです。
また「銅造不動明王立像」の「正面」の「裳」(「腰」から下の「衣」)には、
「嘉元元年癸卯九月十五日 願主権律師瀧尊」
の「銘」が刻まれており、1303年鎌倉時代後期に造像されていたことがわかるそうです。
なお、「結縁寺」の「寺宝」「銅造不動明王立像」ですが、1914年(大正3年)4月17日に「国」の「重要文化財」に指定されています。
「印西」の古刹「結縁寺」の「寺宝」が公開される「行事」「銅造不動明王立像の御開帳」。
この機会に「印西市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「結縁寺」「銅造不動明王立像の御開帳」詳細
開催日時 9月28日(水) 13時〜14時
所在地 結縁寺 印西市結縁寺516
問合わせ 0476-42-5111 印西市生涯学習課
備考
「結縁寺」のある地区は、「朝日新聞」の選ぶ「にほんの里100選」に選ばれた、どこか懐かしい農村地区だそうです。
「結縁寺」周辺は「自然」豊かなところで、更に「結縁寺」「境内」付近には「蓮の花」、「彼岸花」、「コスモス」など「季節ごと」の「彩り」が、「風情」を漂わせています。
「結縁寺」の「寺宝」「銅造不動明王立像」の「光背」と、「岩座」ですが、後に補ったものなのだそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3139 |
| 地域情報::成田 | 08:50 PM |
|
|
2016,09,24, Saturday
本日ご案内するのは、となりまち「旭市」「千葉県東総文化会館」「大ホール」で9月25日(日)に開催されます「第11回あさひのまつり」です。
「千葉県東総文化会館」ですが、、「旭市」「ハ」に所在する「公共文化施設」です。
「千葉県東総文化会館」ですが、「自然」との「共生」、「魅力」ある「屋内外空間」の「創生」、「遠目」に映える「シンボル」などを「基本構想」にして設計され、「千葉県東総文化会館」は、「千葉県民」及び「旭市民」に「芸術文化」の「創作発表」、「鑑賞」の「場」を提供することを通じて「県民文化」の「発展」に寄与することを「目的」に建設された「公共文化施設」となっています。
「千葉県東総文化会館」の「施設」は、平成3年(1991年)6月1日に開館した「公共文化施設」で、「千葉県東総文化会館」の「建設面積」4724.88平方m、「延床面積」5941.07平方mとなっており、「千葉県東総文化会館」の「構造」ですが、「鉄骨鉄筋コンクリート造り」、「地下1階地上3階建て」、「駐車場面積」28台(主催者用)となっています。
「千葉県東総文化会館」の「大ホール」の「収容」ですが、900席(固定席)(1階・座席数768席、2階・座席数132席)となっており、その他「千葉県東総文化会館」「小ホール」の「収容」ですが、302席となっています。
「千葉県東総文化会館」「大ホール」の「間口」ですが、16.0m(8間5尺)、「奥行」は15.5m(8間4尺)、「高さ」は9.5m(5間2尺)となっています。
「千葉県東総文化会館」「小ホール」の「間口」ですが、10.0m(5間3尺)、「奥行」は8.2m(4間3尺)、「高さ」6.0m(3間2尺)となっています。
「千葉県東総文化会館」では、数多くの「催し」、「イベント」、「コンサート」等が開かれています。
「あさひのまつり」とは地域に伝わる「お囃子」や「神楽」などが披露される「旭市」の「郷土芸能」の「祭典」です。
今年(2016年)で11回目を数える「あさひのまつり」ですが、本年も「千葉県東総文化会館」「大ホール」にて開催されます。
「第11回あさひのまつり」ですが、「入場無料」の「催し」となっており、「座席」ですが、「全席自由」となっています。
「第11回あさひのまつり」ですが、「地域」に伝わる「お囃子」や、「踊り」・「神楽」など「郷土芸能」の「祭典」で、「旭市内」9団体が出演するそうです。
今回開催される「第11回あさひのまつり」の出演団体は、下記の通りです。
「飯岡子供囃子連」(お囃子)
「泉川宮本お囃子保存会 いずみ連」(お囃子)
「あさひ八万高」(お囃子)
「飯岡ばやし日の出会」(お囃子)
「大塚原響友会」(お囃子・神楽)
「新田町お囃子連」(お囃子)
「双陽会」(海上広原暁会お囃子連)
「泉神曾」(お囃子)
「袋お囃子保存会」(お囃子・獅子舞)
「千葉県東総文化会館」で開催される「旭市」の「伝統文化」を今に伝える「まつり」の「祭典」「第11回あさひのまつり」。
この機会に「旭市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「第11回あさひのまつり」詳細
開催日時 9月25日(日) 13時〜開演 (開場12時半)
開催会場 千葉県東総文化会館 大ホール 旭市ハ666
入場料 無料・全席自由
問合わせ 旭市生涯学習課文化振興班 0479-55-5728
備考
「第11回あさひのまつり」に参加する「袋お囃子保存会」ですが、百八十年前の江戸・文政年間から「お囃子」を受け継いでいるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3144 |
| 地域情報::旭 | 10:08 AM |
|
|
2016,09,23, Friday
本日ご紹介するのは、となりまち「東庄町」「千葉県立東庄県民の森」で9月25日(日)に開催されます「秋の祭」(フリーマーケット)です。
「千葉県立東庄県民の森」(2011年4月22日のブログ参照)は、「緑」豊かな「下総台地」(北総台地)(2012年7月10日のブログ参照)にあり、「自然環境」の豊かなところにあります。
「千葉県立東庄県民の森」内には、「硬式用テニスコート」が3面、「5人立て専用」の「弓道場」があり、「緑」豊かな「自然」の中で、「テニス」が楽しめたり、厳(オゴソ)かに「弓道」を楽しむことができます。
「千葉県立東庄県民の森」の「区域面積」は、100ha(ヘクタール)で、「千葉県」の「北部」を流れる「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)に近く、上記のように「緑」豊かな「下総台地」(北総台地)にあって、「眼下」に「干潟八万石」の「大水田地帯」や遠く「九十九里浜」(九十九里海岸)(2012年5月11日のブログ参照)を望むことができます。
「千葉県立東庄県民の森」には、「芝生広場」、「湿地植物園」、「水鳥観察舎」などもあり、その他にも「森林館」(管理事務所)、「ふるさと館」、「展望台」、「フィールドアスレチック」、「水鳥広場」、「お花見広場」、「森の教室」、「花しょうぶ園」、「樹木園」、「見晴し台」などがあります。
「千葉県立東庄県民の森」「周辺」の「夏目堰」は、「カモ」や「白鳥」などの「水鳥」が多数飛来しており、「千葉県立東庄県民の森」「水鳥観察舎」からも「観察」ができるので、「四季折々」の「バードウォッチング」が楽しめる「スポット」として知られています。
「夏目堰」は、もとは「椿海」(2011年4月17日のブログ参照)「潟湖」の「一部」でしたが、「椿海」「周辺」は江戸時代に干拓され、現在は「干潟八万石」といわれる「大水田地帯」になっています。
「千葉県立東庄県民の森」は、「県土」の「自然」を守り、多くの「県民」が「森林」と親しみ、「森林」を知り、その「恵み」を受けながら、「自然」と共に生きる「心」の「創造」を目指して造られたものです。
このため「千葉県立東庄県民の森」は、「森林」での「学習」、「レクリエーション」、「スポーツ」、「文化活動」、「林業体験」など、「森林」の「総合利用」を図る「施設」として整備されています。
「山野草(サンヤソウ)」または「山草(サンソウ)」とは、「国内外」の「平地」から「高山」に至る「野外」に自生する「観賞価値」のある「草本(ソウホン)」、「低木」及び「小低木」の一部を含む幅広い「意味」を持つ「言葉」であるが、「日本国内」における「近代的」な「山野草栽培」の「歴史」は100年程度と浅いこともあり、未だに「明確」な「定義」が確立されていません。
一般的には「野生植物」のみを指すと思われることが多いですが、近年では「国内外」で「品種改良」されたものが「山野草」として流通している「例」も多く、「取扱業者」が「便宜的」につけた「不適当」な「名称」で取り引きされている場合もあります。
また、「ラン科」の「エビネ属」や、「キンポウゲ科」の「オオミスミソウ」などのように、「優秀」な「技術」を有する「専門業者」等により「積極的」な「育種」が試みられ、「観賞価値」の高いものが広く普及しつつあるものもあります。
さらに、「日本春蘭(シュンラン)」、「富貴蘭(フウラン)」、「長生蘭(セッコク)」、「日本桜草(サクラソウ)」などの「高度」に「園芸化」された「古典園芸植物」を広く含む場合があります。
「山野草」という「名」の下で栽培されているのは、「日本」の「野生植物」だけではなく、「海外」の「植物」であっても、そのような「名」で呼ばれ、栽培されているものはあります。
全体として、「小柄」で、「花」は美しくても「派手」ではないものが、それに「既成」の「園芸植物」や、「観葉植物」とはあまり似ていないものが好んで「この名」で呼ばれるようです。
一般に「園芸植物」といえば、代々にわたって栽培され、「品種改良」によってより美しく、派手になったものを栽培することであり、これは、特に「西洋」の場合にその「傾向」が強いそうです。
それに対して、「日本」では、そのような「傾向」とともに、むしろ「虚飾」を好まず、「自然」な「姿」を好む「傾向」がひとつの「流れ」としてあります。
たとえば「日本庭園」や、「盆栽」にその「傾向」が見て取れ、「山野草」はその「延長上」のものと考えられます。
「山野草」の「歴史」ですが、「趣味」として「野生」の「植物」を取り込んで栽培することが古くからあったのは間違いないところです。
多くの「栽培植物」が確立していた江戸期においても「山」の小さな「花」を取り込もうとする「努力」があったことは、たとえば「イナモリソウ」の「名」の「由来」からも推察できます。
「栽培植物」として「野草」や、「山草」を扱った「書籍」も、たとえば大正7年に「採集栽培 趣味の野草」が、昭和7年に「山草と高山植物」が出版されたとの「記録」があります。
「山野草ブーム」ですが、1970年代頃からの「エコロジーブーム」など、「自然」へ向けられる「目」が増えたことによってか、「高山植物」や、「野生植物」を「観賞」の「対象」として栽培することが「話題」に上るようになったそうです。
その後、「エビネブーム」・「野生ランブーム」などいくつかの「波」を越えつつ、ひとつの「ジャンル」として定着しました。
「初期」の「頃」は、「呼称」として「山草(サンソウ)」が使われることが多かったそうで、これに、より「一般的名詞」として使われてきた「野草」が結びついた「形」で、2000年代現在ではほぼ「山野草」が定着しているように見えるようです。
「蚤の市(ノミノイチ)」(flea market)は、「ヨーロッパ」の「大都市」の「各地」で「春」から「夏」にかけて、「教会」や、「市庁舎」前の「広場」などで開かれる「古物市」で、「パリ」の「蚤の市」が有名です。
「北米」では「大規模」な「倉庫」や、「体育館」など「屋内」で開催されるものもあり、「出店者」は「一般家庭」や、「仲間」で集まった「グループ」から、「古物商」や、「雑貨商」の様な「事業者」まで幅広いそうです。
「蚤の市」(flea market)は、「フランス語」(marche aux puces)の「訳」であり、もともと「ノミ」のわいたような「古着」が主な「商品」として扱われていたことに由来するとか、「ノミ」のようにどこからともなく「人」や、「物」がわき出てくる様子を表現したなどいわれていますが、「語源」は定かではありません。
もっとも現在の「イギリス」や、「フランス」では「身体」の「血」を吸う「ノミ」とは関係なく、「汚らしい」、「みすぼらしい」といった「意味」に捉えられています。
「日本」に「蚤の市」という「言葉」および「概念」を紹介したのは「柔道家」の「石黒敬七」氏とされています。
「同種」の「市」は、「日本」でも最近はあちこちで催されていますが、「蚤の市」の持っている「不潔」な「イメージ」から、「歴史」のある「古物市」では「ガラクタ市」、「ボロ市」(世田谷区など)といった「名称」が使われ、最近の「若者」・「ファミリー」向けの「大規模イベント」として開催されるものは、「フリーマーケット」という「ケース」が多いようです。
特に「掘り出し物」の中には、「古美術」などが含まれることが多く、「出品者」がそれと知らずに所有していた「有名画家」の「絵画」が発見されることもあります。
「アメリカ西海岸」では「スワップ・ミート(Swap Meet)」と呼ばれることも多いそうです。
「日本各地」で行われる「蚤の市」や、「ガラクタ市」は、1990年代以降「若者」・「ファミリー」向けの「フリーマーケット」と呼ばれるものが多くなりました。
従来の「蚤の市」は、「神社」などの「境内」で「縁日」に併せて行われることが多いですが、「フリーマーケット」と称する「催し」は、主に、「競馬場」や、「サッカー場」などの「駐車場」、「大規模公園」などの「一角」で行われることが多いようです。
「東京都内」の場合は「明治公園」、「代々木公園」、「大井競馬場」、「秋葉原UDX」などで行われるものが「規模」が大きいといわれます。
「日本」の場合、「a flea market」ではなく、自由参加できることから「free market」という「意味」の「単語」として使用される場合が多いようです。
「free market」とは、本来「蚤の市」と全く「別」の「意味」の「経済学用語」(自由市場のこと)なので「注意」が必要です。
尚、「日本」で「同種」の「市」を開催する場合、「形態」によっては「主催者」に「古物商取引」の「許可」(鑑札取得)が必要な場合があります。
近年、「インターネット」上でも「フリーマーケット」が開催される場合が多くなってきています。
主に、古くなった「生活用品」を出す「ケース」が多く、「幼児服」など「短期間」しか「身」につけられなかったものを出品する「ケース」が多いそうです。
これらの「衣類」、「生活用品」の中には「キャラクター商品」なども含まれ、特に「人気」のあった「キャラクター商品」の場合、「製造元」がすでに「生産」を終了している場合が多く、「販売価格」も高騰し、「新品購入時」とほぼ変わらないかそれ以上の「値段」で取り引きされるものも多いそうです。
「秋の祭」(フリーマーケット)ですが、「千葉県立東庄県民の森」の「恒例イベント」で、9月25日(日)に開催されます。
「秋の祭」(フリーマーケット)の「開催時間」ですが、10時00分から15時00分までとなっており、「秋の祭」(フリーマーケット)の「開催会場」ですが、「千葉県立東庄県民の森」「ふる里館」、「芝生広場」となっています。
「秋の祭」(フリーマーケット)の「開催内容」ですが、「山野草展示会」、「模擬店」などの「イベント」に、「フリーマーケット」の「出店」といった「内容」になっています。
「秋の祭」(フリーマーケット)の「フリーマーケット」の「募集」ですが、「フリーマーケット」12区画程度(要予約)となっており、「秋の祭」(フリーマーケット)の「フリーマーケット」「参加費」ですが、「フリーマーケット」1区画(4m×4m)・500円となっています。
「自然」あふれる「千葉県立東庄県民の森」で開催される「恒例イベント」「秋の祭」(フリーマーケット)。
この機会に「東庄町」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「秋の祭」(フリーマーケット)詳細
開催日時 9月25日(日) 10時〜15時
開催会場 千葉県立東庄県民の森 香取郡東庄町小南639
問合わせ 千葉県立東庄県民の森 0478-87-0393
備考
「秋の祭」(フリーマーケット)ですが、「雨天決行」で行われる「イベント」です。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3133 |
| 地域情報::香取 | 10:36 PM |
|
|
2016,09,22, Thursday
本日ご案内するのは、となりまち「香取市」「香取神宮」「香取護国神社」で9月25日(日)に開催されます「香取護国神社秋季大祭」です。
「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)は、「香取市」「香取」に鎮座する「日本屈指」の「神宮」で、「式内社」(名神大社)、「下総国一宮」、「旧社格」は「官幣大社」で、現在は「神社本庁」の「別表神社」です。
「香取神宮」は、「関東地方」を中心として「全国」に約400社ある「香取神社」の「総本社」であり、「鹿嶋市」の「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)、「神栖市」の「息栖神社(イキスジンジャ)」(2010年11月7日のブログ参照)とともに「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)の「一社」であり、「宮中」の「四方拝」で遥拝される「一社」です。
「香取神宮」の「創建」ですが、「神武天皇」の「御代18年」と伝えられ、「香取神宮」の「御祭神」は「日本書紀」の「国譲り神話」に登場し、「鹿島神宮」の「御祭神」「武甕槌大神(タケミカヅチノオオカミ)」とともに活躍した「神様」「経津主大神(フツヌシノオオカミ)」です。
上記のように「香取神宮」は、「下総国一宮」で、明治以前に「神宮」の「称号」を与えられていたのは、「伊勢神宮」、「香取神宮」、「鹿島神宮」のみという「わが国」「屈指」の「名社」です。
「香取神宮」の約37000坪ある「境内」には、「本殿」、「幣殿」、「拝殿」、「祈祷殿」、「楼門」、「宝物館」、「神徳館」、「弓道場」、「社務所」などがあります。
中でも「香取神宮」「本殿」・「中殿」・「拝殿」が連なる「権現造」の「社殿」は、「鹿皮」のような「色」をした「桧皮葺」の「屋根」に「黒塗り」の「姿」が実に美しい「建造物」となっています。
「香取神宮」「境内」には、「摂社」、「末社」が多く祀られており、「摂社鹿島新宮」、「摂社奥宮」、「摂社匝瑳神社」、「末社六所神社」、「末社桜大刀自神社」、「末社裂々神社」、「末社市神社」、「天降神社」、「末社馬場殿神社」、「末社日神社」、「末社月神社」、「末社押手神社」、「末社璽神社」、「末社大山祇神社」、「末社諏訪神社」などを祀っており、「香取神宮」「参道」「左手」に「香取護国神社」(2013年9月25日のブログ参照)が祀ってあります。
「香取神宮」の「御祭神」ですが、上記のように「出雲」の「国譲り神話」の中で、「鹿島神宮」の「御祭神」である「武甕槌大神」とともに「出雲」に赴いた「経津主大神」であり、その「武威」に「大国主大神」が従うことになったとされ、古代から「武神」として「信仰」を集めてきました。
古代においては、「鎮護国家」の「神」として「大和朝廷」の「東国経営」の「一翼」を担い、中世には「下総国」の「一宮」となり、江戸時代には「徳川幕府」の「庇護」を得ています。
「香取神宮」「本殿」ですが、平安時代には「伊勢神宮」などと同様の20年ごとの「建て替え」の「制度」がありましたが、戦国時代に廃れ、現在の「香取神宮」「本殿」は、元禄13年(1700年)に「江戸幕府」によって造営されたものなのだそうです。
「香取神宮」「本殿」ですが、正面「柱間」が三間で、「前庇」と短い「後庇」を加えた「両流造(リョウナガレヅクリ)」の「全国」でも「最大級」のもので、「黒漆塗」、「檜皮葺(ヒワダブキ)」の「重厚」な「社殿」となっています。
また「香取神宮」「本殿」には、「蟇股(カエルマタ)」や、「虹梁(コウリョウ)」・「組み物」には「極彩色」の「装飾」が施され、前代の慶長期の「桃山様式」の「手法」を受け継いでいます。
「香取神宮」は、「香取の森」と呼ばれる12万3千平方mに及ぶ「広大」な「山林」の中にあり、「香取の森」は「荘厳」で「霊気」に満ちた「神秘さ」を深めた「空間」が広がっており、正に「神域」であることを感じることができる「パワースポット」となっています。
「香取神宮」の「社叢林」は3.5ha(ヘクタール)、古くから「神宮の森」として古くから「信仰の場」として「大切」に保護されてきたため、「目通り幹囲鉾(幹周)」3mを越える「スギ」をはじめ、「イヌマキ」・「モミ」などの「巨木」が林立しており、「落葉」に埋もれた「古道」や「古井戸」は往時の「景観」を偲ばせ、「香取の森」は昭和49年(1974年)に「千葉県」の「県指定天然記念物」に指定されています。
「香取の森」、「香取神宮」の「位置」する「山」(森)は、その「形状」(森の全景)が「亀」に似ていることから、「亀甲山(キッコウサン)・(カメガセヤマ)」とも呼ばれて(称されて)います。
この「地域」は、「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の「北縁」に当たり、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)によって「徐々」に浸食された「地域」であり、「台地」「上面」は「標高」約40mであり、「浸食」が進み「谷津田」が入り組み、「島状」となった「台地」も多く、「香取神宮」を含んだ「台地」もそのひとつなのだそうです。
「香取の森」は、「スダジイ」を「優占種」とする「自然林」と「スギ」の「人工林」とから構成されており、「香取神宮」「本殿」の「周辺」には「巨木」が多く、特に「御神木」とされる「スギ」はこの「地域最大」のもので、上記のように「目通り幹囲鉾(幹周)」は約7.4m、「高さ」35mで、「樹齢」は千年といわれています。
「香取の森」の「高木層」は「スギ」で占めていますが、「亜高木層」には「スダジイ」・「シラカシ」・「シロタモ」などの「常緑広葉樹」が多くみられ、「草木層」には「アスカイノデ」・「フモトシダ」・「イワガネソウ」・「ベニシダ」などの「シダ類」をはじめとして「リュウノヒゲ」・「ヤブラン」・「フウラン」などの「草木類」が数多く自生しています。
「香取の森」付近には、「スギ」・「スダジイ」・「アカガシ」・「イチョウ」・「ケヤキ」・「イヌマキ」・「ナギ」などの「巨木」・「古木」があり、いずれも「樹齢」数百年といえるもので、「林床」には、「県内」では「北限」といわれる「アリドオシ」があるそうです。
また「香取の森」には、「スギ」の「老齢木」としては「県下」でも「有数」な「スポット」であり、「学術的」にも貴重なものなのだそうです。
「護国神社」ですが、明治時代に「日本各地」に設立された「招魂社」が、1939年(昭和14年)3月15日「交付」、同年4月1日に「施行」された「招魂社ヲ護國神社ト改称スルノ件」(昭和14年内務省令第12號)によって「一斉」に「改称」して成立した「神社」です。
「招魂社」の「名称」ですが、「招魂」が「臨時」・「一時的」な「祭祀」を指し、「社」が「恒久施設」を指すため、「招魂社」の「名称」に、「矛盾」があるとして「護国神社」に改称されたそうです。
「護国」の「名称」ですが、1872年12月28日(明治5年11月28日)の「徴兵令詔書」の「一節」「國家保護ノ基ヲ立ント欲ス」、1882年(明治15年)1月4日の「軍人直諭(グンジンチョクユ)」の「一節」「國家の保護に尽さば」など、「祭神」の「勲功」を称えるに、最も相応(フサワ)しく、既に「護国」の「英雄」等の「用語」が用いられて「親しみ」も深い、との「理由」で採用されたそうで、「護国神社」の「総数」ですが、1939年(昭和14年)4月時点で131社とされています。
「香取護国神社」は、上記のように「香取神宮」「参道」「左手」に鎮座し、1946年(昭和21年)9月に創建されました。
「香取護国神社」「御祭神」ですが、明治以降の「国難」に殉じた「香取郡」「出身」の「御霊」を「御祭神」としています。
「香取護国神社」では、「春」・「秋」、二度の「例祭」(大祭)が行われており、この度(タビ)「香取護国神社」では、「香取護国神社秋季大祭」が9月25日(日)に斎行われます。
「香取護国神社秋季大祭」では、「日清」・「日露」の「戦役」から、先の「大戦」で散華された「香取郡市」「出身」の「戦没者」の「英霊」をお祀りする「香取護国神社」の「秋季大祭」が斎行されます。
「香取護国神社秋季大祭」「当日」は、「香取神宮」の「巫女」による「浦安の舞」が奉奏されるそうです。
「香取護国神社」で奉奏される「浦安の舞」ですが、「御霊」を「お慰め」するため、行われるそうです。
「浦安の舞」は、「昭和天皇」の「御製」を「元」にした「神楽舞」で、「世界」の「恒久平和」を祈る「舞」だそうです。
なお「香取護国神社秋季大祭」ですが、どなたでも「御参列」することが出来るそうですので、希望される「方」は、「香取神宮」「社務所」までお問い合わせ下さいとのことです。
「日本屈指」の「名社」「香取神宮」「境内」に鎮座する「香取護国神社」で斎行される「行事」「香取護国神社秋季大祭」。
この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「香取護国神社秋季大祭」詳細
開催日時 9月25日(日) 11時〜12時
開催会場 香取神宮 香取護国神社 香取市香取1697
問合わせ 香取神宮 0478-57-3211
備考
「香取神宮」「楼門」ですが、「香取神宮」「本殿」と同じく元禄13年(1700年)の「造営」で、3間1戸で、「香取神宮」「楼門」の「屋根」は「入母屋造銅板葺」ですが、もとは「挧葺(トチブキ)」であったそうです。
また、周囲の「緑」の中で、「香取神宮」「楼門」の鮮やかな「朱塗り」と、「奥」に見える「香取神宮」「社殿」の「黒」が「鮮烈」な「コントラスト」をみせています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3131 |
| 地域情報::香取 | 08:22 PM |
|
|
2016,09,21, Wednesday
本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「道の駅・川の駅水の郷さわら」で9月24日(土)・25日(日)で開催されます「大収穫祭」です。
「香取市」は、2006年(平成18年)3月27日に「佐原市」・「山田町」・「香取郡」「小見川町」・「栗源町(クリモトマチ)」の1市3町が合併(新設合併)し、誕生した「市」です。
「香取市」は、「千葉県」の「北東部」に位置し、「北部」は「茨城県」に接し、「首都」「東京」から70km圏、「世界の空の玄関口」(WORLD SKY GATE)「成田国際空港」(2015年4月7日・2012年12月10日のブログ参照)から15km圏に位置しています。
「香取市」「北部」には、「水郷」の「風情」が漂う「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)が「東西」に流れ、その「流域」には「水田地帯」が広がり、「香取市」「南部」は「山林」と「畑」を中心とした「平坦地」で、「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の「一角」を占めています。
「香取市」の「産業」ですが、「温暖」な「気候」と肥沃(ヒヨク)な「農地」に恵まれた「地域」の「特性」を活かした「農業」が盛んに営まれており、「香取市」は「首都圏」の「食料生産地」の「役割」を担っています。
「香取市」の「農業」ですが、古くから「水郷」の「早場米産地」として知られる「米どころ」で、「千葉県内」1位を誇る「米」の「生産地」であり、また「食用甘しょ」の「生産」・「販売額」「全国一」を誇る「甘しょ生産地」として知られています。
ちなみに「早場米」とは、8月「お盆過ぎ」には「稲刈り」が始まり、「出荷」される「米」のことで、「香取市」は「良質」な「早場米」の「産地」として知られています。
「香取市」の「特産品」ですが、上記のように「米」、「サツマイモ」(「ベニコマチ」・「ベニアズマ」)(2012年9月10日・2010年10月30日のブログ参照)、「ニラ」、「ネギ」、「ゴボウ」、「梨」(水郷なし)(2010年9月10日のブログ参照)、「いちじく」(2012年9月2日のブログ参照)、「千葉県一」の「生産」を誇る「ブドウ」(2010年8月17日のブログ参照)、「カサブランカ」(ユリ)、「日本酒」(「東薫」(東薫酒造)(2011年2月2日のブログ参照)・「雪山」(馬場本店)・「大姫」(飯田本家))、「醤油」(イリダイ醤油・ちば醤油)(2011年5月25日のブログ参照)となっています。
「特産品」の多い「香取市」には、「道の駅くりもと紅小町の郷」(2013年4月30日・2012年4月28日・2012年3月28日のブログ参照)、「風土村」(2013年3月1日・2012年2月26日のブログ参照)、「道の駅・川の駅水の郷さわら」(2013年3月19日・2012年3月29日のブログ参照)といった「人気」の「道の駅」や、「直売所」があり、多くの「観光客」、「地元客」の「皆さん」が、「香取市産」の「特産品」を求めに訪れています。
「道の駅・川の駅水の郷さわら」は、「千葉県」の「北東部」、「水郷筑波国定公園」(2012年8月3日のブログ参照)に指定された「雄大」な「景観」を楽しむことができる「香取市」「佐原」の「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)の「川辺」にある「道の駅」「川の駅」です。
「香取市」「佐原」ですが、「利根川水運」の「物資集散」の「地」として栄えた「水郷の商都」であり、「利根川」の「支流」「小野川」(2012年9月7日のブログ参照)沿いに発達した「小江戸」と呼ばれる「古い町並み」が残り、現在「佐原の町並み」は往時をしのばせる風情ある「人気観光スポット」となっており、「道の駅・川の駅水の郷さわら」から、「香取市」「佐原地区」内の「まちなか」に向かうと「佐原の町並み」があります。
豊かな「水」と「緑」に囲まれた「水郷佐原」の「風土」は、「佐原小唄」でも
「佐原よいとこ水の郷(サト)」
と唄われており、「道の駅・川の駅水の郷さわら」の「名称」の「由来」となっています。
「道の駅・川の駅水の郷さわら」には、隣接した「観光船乗り場」や「プレジャーボート」等の「係留桟橋」、「大型駐車場」、「レンタサイクル」、「レンタルボート」もあり、「利根川」周辺の「観光拠点」として利用されています。
「道の駅・川の駅水の郷さわら」は、「道の駅」と「川の駅」の「機能」を有する「施設」で、多くの「利用客」で賑わう「人気観光スポット」です。
「道の駅・川の駅水の郷さわら」では、「地場産」の「素材」を、ふんだんに使った「加工品」や「名産品」を多数取り揃えている「特産品直売所」を有し、「道の駅・川の駅水の郷さわら」「特産品直売所」では、「香取市」の「生産者」が心をこめて生産した「安心」・「安全」・「新鮮」な「野菜」を「畑」から直送しており、「安心」・「安全」・「新鮮」な「野菜」を求めに、連日多くの「買い物客」で賑わっています。
また「道の駅・川の駅水の郷さわら」では、「地場産品」を用いた美味しい「お料理」を提供している「フードコード」があり、「フードコード店舗」ですが、「和食」を提供している「あやめ」、「イタリアン・洋食」を「提供」している「温々(ヌクヌク)」、「うどん・そば処」の「さわら麺処」、「ラーメンショップ」の「麺屋桃太郎」の4店舗が入っています。
「道の駅・川の駅水の郷さわら」の「事業区域面積」ですが、約16.9ha(ヘクタール)となっており、「川の駅水の郷さわら」と「道の駅水の郷さわら」「概要」は、下記の通りです。
「川の駅水の郷さわら」
所在地 〒287-0003 香取市佐原イ4051番地-3
問合わせ TEL 0478-52-1138 FAX 0478-52-1122
営業時間 (防災教育展示)
9時30分〜16時30分
営業時間 (佐原河岸、水辺交流センター)
9時00分〜17時00分
休館日 月曜日(祝日のときは翌日)、年末年始、施設点検日 (防災教育展示、佐原河岸、水辺交流センター)
延床面積
車両倉庫 約360平方m
河川利用情報発信施設(防災教育展示等) 約1490平方m
水辺交流センター 約830平方m
「道の駅水の郷さわら」詳細
所在地 〒287-0003 道の駅水の郷さわら 香取市佐原イ3981番地-2
問合わせ TEL 0478-50-1183 FAX 0478-50-1185
営業時間
特産品直売所・フードコード
9時00分〜19時00分 (4月〜9月)
9時00分〜18時00分 (10月〜3月)
(年中無休、施設点検日等を除く)
駐車場
普通車146台、大型車22台、身障者用4台、大型自動二輪車21台 (24時間・年中無休)
トイレ
男13、女12、多機能1 (24時間・年中無休)
休憩・情報コーナー (24時間・年中無休)
延床面積 約1110平方m
「道の駅・川の駅水の郷さわら」の「施設整備」の「目的」は、下記の通りです。
本施設は、佐原広域交流拠点PFI事業として、国土交通省と香取市が協働で行っている事業であり、平成18年度からPFI事業を進めるための検討委員会や有識者等委員会を開催し、平成20年(2008年)7月10日に特定目的会社(SPC)PFI佐原リバー(株)が事業者となりました。
当該事業は、直轄河川事業でのPFI手法を採用した全国初の試みであり、国土交通省が施工する高規格堤防(スーパー堤防)上に設置される、地域交流施設(道の駅)と平常時は河川利用者等への情報発信として防災教育等に利用すると共に、災害時には水防活動の拠点となる施設(川の駅)が一体となって整備されるものです。
利根川下流部における防災拠点としての利用の他、利根川の自然環境を活かしたカヌー等の水辺の利用拠点や利根川における舟運による交通と道路による交通との利便性を活かした交通の交流拠点ともなるものです。
香取市は、江戸時代より利根川水運の物流拠点として栄え、古い町並みが残されており、重要伝統的建造物群保存地区に選定されているなど、これら地域文化を活かした、川からのまちづくりを推進し、都市再生を目指す拠点施設整備を行っています。
ちなみにPFI事業とは、下記の通りとなっています。
PFIとは、国や地方公共団体が各々単独で行っていた公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる新しい事業手法であり、PFI法にもとづき実施します。
我が国のPFIに対する方針としては、公的債務の深刻化に鑑み、1999年7月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(通称PFI法)」を策定しています。
PFI事業に携わる事業者は、本事業の遂行のみを目的とする特別目的会社(SPC)を設立し、事業を実施します。
「道の駅・川の駅水の郷さわら」は、「災害時」の「災害対策施設」の「機能」を有していますが、平常時は「防災教育」や「水辺」の「利用拠点」として有効活用されています。
「道の駅・川の駅水の郷さわら」の「防災施設」(主要諸室)は、下記の通りです。
災害対策支援室 (平常時) 施設事務所、多目的研修室
待機室、河川情報室 (平常時)防災教育展示室
災害対策資材倉庫
自家発電気室 (平常時)防災教育展示室
水防従事者案内所 (平常時)総合案内所
情報収集室 (平常時)多目的研究室
屋外水防従事者便所 (平常時)施設利用者用便所
水防倉庫
水防従事者控え室 (平常時)飲食施設
「人気」の「道の駅」「道の駅・川の駅水の郷さわら」では、「実りの秋」を祝い、「大収穫祭」(秋の大収穫祭)(2015年9月24日・2013年9月26日・2012年9月22日・2010年9月28日のブログ参照)を9月24日(土)・25日(日)の2日間、9時00分から17時00分まで開催するそうです。
「大収穫祭」ですが、「地元出荷者」が「自分」の「畑」でとれた「野菜」を「メイン」におもてなしする「お祭り」で、「新米のすくい取り」や、「ビンゴ大会」など、「子ども」が楽しめる「イベント」も数多く予定しているそうです。
「大収穫祭」の「内容」は、下記の通りです。
「大収穫祭」詳細
「採れたて農産物」
新米販売
ビカピカの新米が各種勢揃い!
フルーツ販売
ぶどう・梨・ブルーベリー・いちじく等旬のフルーツが並びます!
野菜詰め放題!
旬の野菜を多数ご用意!
切り花・鉢植え
切り花や鉢植えをお手頃価格で!
「グルメ大集合」
さつまいもスティック
農家のお母さんが手作り出来立てをどうぞ!
新米もち
お雑煮ときなこ餅が100円!
チョコバナナ
お祭りと言ったらこれ!
鰻のかば焼き
ふっくら香ばしいできたてかば焼き!
椎茸焼きと販売(24日(土)のみ)
新鮮な椎茸はシンプルにいただきます
ポップコーン
色々な味をご用意しています。
「試食品コーナー」
新米試食
コシヒカリ・ふさおとめ・ミルキークイーン・ふさこがねの4種類を食べ比べできます!
フルーツ試食
もきたてのみずみずしいぶどう・梨など
製造加工食品試食
果肉たっぷりのイチジクアイスや、ブルーベリージャムなどもあります。
「イベント各種」
お米すくい取り大会
一斗升に入れた米のすくい取りにチャレンジ!
ビンゴ大会(午前・午後各1回)
野菜お買い上げのお客様はビンゴゲームのチャンス!
三角くじ・ひもくじ
製造加工品お買い上げでチャンス2倍!
輪投げ大会(25日(日)のみ)
たまご・キノコ・はちみつ・ソース等、景品いろいろ!
さらに「大収穫祭」では、「日頃」の「感謝」を込めて「ガラポン大抽選会」を開催するそうです。
「ガラポン大抽選会」ですが、「レシート」1000円につき1回「大当たり」の「チャンス」があり、「ハズレ無し」、「当日」「お買い上げ」の「レシート」のみ「有効」の「大抽選会」となっています。
「ガラポン大抽選会」の「景品」は、下記の通りです。
1等 新米こしひかり(3kg)
2等 かきもち
3等 サツマイモクッキー
4等 梨
5等 たまご
6等 ペットボトル飲料
参加賞 ポケットティッシュ
「香取市」の「人気スポット」「道の駅・川の駅水の郷さわら」で開催される「秋の味覚」が「満載」の2日間「大収穫祭」。
この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「大収穫祭」詳細
開催日時 9月24日(土)・25日(日) 9時〜17時
開催会場 道の駅・水の郷さわら 香取市佐原イ3981番地-2
問合わせ 道の駅・川の駅水の郷さわら 0478-50-1183
備考
「大収穫祭」ですが、「雨天決行」で行われる「イベント」です。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3143 |
| 地域情報::香取 | 10:08 AM |
|
|
2016,09,20, Tuesday
本日ご案内するのは、近隣市「印西市」「和泉鳥見神社」で9月22日(祝・木)に開催されます「いなざき獅子舞」です。
「印西市」は、「東京」の「都心」から約40km、「県庁所在地」「千葉市」から約20km、「世界の空の玄関口」(WORLD SKY GATE)「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)から約15kmに位置し、三方を「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)、「印旛沼」(2011年2月23日のブログ参照)、「手賀沼」に囲まれた「水」と「緑」豊かな「市」です。
「印西市」は、「周辺」の「佐倉市」、「四街道市」、「白井市」、「八街市」、「成田市」、「富里市」、「印旛郡」「酒々井町」、「印旛郡」「栄町」と合わせて「印旛地域」と称されています。
「印西市」に隣接する「自治体」ですが、「柏市」、「我孫子市」、「白井市」、「八千代市」、「佐倉市」、「成田市」、「印旛郡」「酒々井町」、「印旛郡」「栄町」、「茨城県」「北相馬郡」「利根町」となっています。
ちなみに、隣接する「茨城県」「北相馬郡」「利根町」とは、「印西市」からは「直接的」な「往来」は出来なくなっており、「我孫子市」または、「印旛郡」「栄町」を「経由」する必要があるそうです。
「千葉県」では、「他県」と接していながら、「直接的」な「往来」ができない「自治体」は、「印西市」のみとなっています。
「印西市」ですが、2008年(平成20年)に「印西市」・「印旛郡」「印旛村」・「印旛郡」「本埜村」の「1市2村」の「枠組み」で、「市町村合併」の「特例」等に関する「法律」(新合併特例法)の「期限」である2010年(平成22年)3月末までの「合併」に関する「話し合い」を行うために、2008年10月24日に「合併問題懇談会」が、それぞれの「市村の長」および「議会議員の代表」により構成、設置され、翌2009年(平成21年)1月9日に「合併協議会」が設置されました。
「合併協議会」では、「合併」の「期日」を2010年(平成22年)3月23日とし、「合併方式」は「印西市」に「印旛郡」「印旛村」・「印旛郡」「本埜村」を編入する「編入合併」、「新市」の「名称」は「印西市」とすることで「合意」、「合併申請」が行われ、2010年3月5日「総務省告示第73号」で「合併」が決定。
これにより、予定通り、2010年3月23日に、「新・印西市」が誕生しました。
「印西市」の「人口」ですが、「人口」96443人、「世帯」37413世帯、「男性」47926人、「女性」48517人となっています。
(2016年(平成28年)8月1日現在)
「印西市」ですが、「千葉ニュータウン中央・印西牧の原地区」、「木下地区」、「印旛地区」、「本埜地区」から構成されています。
「千葉ニュータウン中央・印西牧の原地区」ですが、「印西市」「西部」の「下総台地」(北総台地)(2012年7月10日のブログ参照)上、「千葉ニュータウン」が広がり、「千葉ニュータウン中央駅」・「印西牧の原駅」「周辺」および「国道464号線」沿線は、「印西市」における「経済」・「商業」の「中心地」(新「市街地」)となっています。
「千葉ニュータウン中央・印西牧の原地区」ですが、最も「印西市」で「人口」が多く、「北総線」および「国道464号線」に沿って発展しており、「北総エリア」における「一大ショッピングゾーン」を形成しています。
「印西市」「北西部」の「利根川」沿いの「低地」に所在する「木下(キオロシ)地区」(「旧・木下町」)ですが、、「利根川水運」の「宿場町」であった「旧・市街地」があり、「印西市」の「市役所」や「警察署」などの「行政機関」が位置し、「印西市」「行政」の「中心地」となっています。
「木下(キオロシ)地区」ですが、古くからの「町並み」が残る「旧・市街地」であり、「利根川」および「木下(キオロシ)街道」に沿って発展しています。
「印旛地区」(旧・「印旛村」)は、「印西市」の「東南部」に位置し、「北総エリア」の「基幹病院」である「日本医科大学千葉北総病院」があり、「印旛日本医大駅」を中心として「宅地化」が進行している「エリア」です。
一方「印旛地区」は、「谷津田」をはじめ、「自然」も多く残されており、「樹齢」300年を越える「吉高の大桜」(2011年4月5日のブログ参照)や、「ナウマン象発掘の地」などの「観光名所」もあります。
「本埜地区」(旧・「本埜村」)ですが、「印西市」の「北東部」に位置し、「北印旛沼」に面し「水田」が広がり、「冬」には「越冬」のために、800匹を越す「白鳥」が、飛来することで知られています。
一方「本埜地区」は、「印西牧の原駅」「北側」に位置する「千葉ニュータウン」「滝野地区」で「宅地化」が進行、また「成田国際空港」に近いこともあって、近年「国道464号線」の「沿道」「みどり台」などに、「研究所」や「物流センター」などの「進出」が目立っているそうです。
「印西市」は、江戸時代より「利根川」の「水運」が盛んで、「物資輸送」の「拠点」のひとつであった「木下(キオロシ)河岸」や、「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)、「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)、「息栖神社(イキスジンジャ)」(2010年11月7日のブログ参照)の「東国三社詣」(2010年10月23日のブログ参照)などに向かう「道中」の「宿場町」として栄えた「木下(キオロシ)街道」付近を、中心に栄えてきました。
上記のように、「印西市」は江戸時代から「商業のまち」として栄え、「江戸」と「佐倉」・「銚子」を結ぶ上で「重要なまち」として、また「香取神宮」、「鹿島神宮」、「息栖神社」を詣でる「旅人」の「宿場町」として繁栄し、そのため、「印西市」には「歴史的建造物」、「遺跡」も数多く残り、当時の「面影(オモカゲ)」を偲(シノ)ばせている「まち」です。
現在も「印西市」は「地理的条件」にも恵まれ、上記のように「東京都心」、「千葉市」、「成田国際空港」という「日本」を代表する「高機能拠点」の「中心」に近く位置している「まち」として「利点」を活かし「発展」を続けています。
「鳥見神社(トミジンジャ・トリミジンジャ)」ですが、「印旛沼」「北岸」内に集中して分布(鎮座)している「神社」で、その「範囲」は「古代」の「言美郷」にも比定されています。
一説に、「大和国城上郡鳥見白庭山」の「鳥見大明神」を勧請したともいわれ、「御祭神」ですが、「物部氏」の「祖神」を祀っているそうです。
8世紀初めに成立した「常陸国風土紀(ヒタチノクニフドキ)」(2012年6月3日のブログ参照)に「景行天皇」が「下総国印旛沼」の「鳥見の丘」より「霞の郷」を望んだとの「古伝」があるそうです。
「鳥見神社」ですが、「印西市」「小林」にも鎮座する「神社」で、「鳥見神社」「旧社格」ですが、「郷社」となっています。
なお、「印西市」には、「小林」の他、「大森」(村社)、「平岡」(村社)、「小倉」(村社)、「中根」(村社)、「浦部」(無格社)にも「鳥見神社」があります。
「和泉鳥見神社」の「御祭神」ですが、「饒速日命(ニギハヤヒノミコト)」、「宇麻志間知命(ウマシマジノミコト)」、「御炊屋姫命(ミカシキヤヒメノミコト)」を祀っています。
「和泉鳥見神社」ですが、「由緒」は不明で、「社務所」の「張り紙」には、慶安3年(1650年)9月14日再興、文化13年(1816年)5月15日建て替え、弘化4年(1847年)修理とあります。
現存する「最古」の「記録」は、「鳥居」の安政6年(1859年)「八月吉日」との「銘」だそうです。
「和泉鳥見神社」には、「神楽殿」はありませんが、「秋祭り」として「いなざき獅子舞」が執り行われています。
「いなざき獅子舞」ですが、「秋分の日」(元々は「彼岸の入り」)に行われる「御祭」だそうです。
「いなざき獅子舞」は、上記のように「和泉鳥見神社」の「秋祭り」として、江戸時代より奉納されています。
「いなざき」とは、「稲」の「収穫」を前にしてという「意味」があり、「獅子舞」は「秋」の「豊作」を感謝する「気持ち」と、「子孫繁栄」を表現したものなのだそうです。
「いなざき獅子舞」では、「大獅子」、「中獅子」、「女獅子」の「三匹獅子」に「道化」が加わり、「道化の舞」、「四方固めの舞」、「花笠めぐりの舞」、「けんかの舞」、「綱(鋼)くぐりの舞」が演じられます。
「いなざき獅子舞」は、かつての「円光院」「跡地」から「行列」が出発し、「舞」(獅子舞)は2時間に渡り、「和泉鳥見神社」「境内」で奉納されます。
「いなざき獅子舞」は、「風流系統」に分類される「三匹獅子舞」に「道化」を加えたもので、「全体」としては「勇みの姿」だそうです。
かつての「円光院」「地内」に勢揃いした「獅子」は、「道笛」の「音」にのって「道化の露払い」で「社前」に至ります。
「いなざき獅子舞」の「流れ」ですが、上記のように「道化の舞」に始まり、「女獅子」、「中獅子」、「大獅子」の「順」で「四方固めの舞」次いで「道化」と、「獅子」が「四方」の「花笠」の「周囲」をまわる「花笠めぐりの舞」を行い、そして「舞人」の交替した「大獅子」が「綱(鋼)くぐりの舞」を演じて「納め」となります。
「いなざき獅子舞」ですが、昭和41年(1966年)4月29日に「印西市」の「市指定無形民俗文化財」に指定されています。
「秋」の「豊作」への「感謝」と、「子孫繁栄」の「願い」が込められた「和泉鳥見神社」で奉納される「舞」「いなざき獅子舞」。
この機会に「印西市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「いなざき獅子舞」詳細
開催日時 9月22日(祝・木) 14時〜16時半
開催会場 和泉鳥見神社 印西市和泉622
問合わせ 印西市生涯学習課 0476-42-5111
備考
「いなざき獅子舞」が催行される「和泉鳥見神社」では、「正月」七日に「おびしゃ」が行われるそうです。
「おびしゃ」とは、「関東」、特に「利根川流域」に多く伝わるもので、「矢」を射て「吉凶」を占うものや、「お供え」として、その「年」の「幸運」を願うものなどがあります。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3129 |
| 地域情報::成田 | 02:04 PM |
|
|
2016,09,19, Monday
本日ご紹介するのは、地元「銚子市」「銚子ポートタワー」で9月17日(土)〜25日(日)の期間開催されます「第14回オリンパスズイコークラブ千葉支部写真展」です。
「銚子市」(2010年9月20日のブログ参照)は、1933年(昭和8年)2月11日、「銚子町」、「本銚子町」、「西銚子町」、「豊浦村」の3町1村が合併し、「全国」で116番目、「千葉県」では「県庁所在地」「千葉市」に次いで2番目の「市」として誕生しました。
その後、「銚子市」は、1937年(昭和12年)に「高神村」、「海上村」、1954年(昭和29年)に「船木村」、「椎柴村」、1955年(昭和30年)に「豊里村」、1956年(昭和31年)に「豊岡村」と順次合併、発展してきました。
現在の「銚子市」の「人口」ですが、64804人となっており、「世帯数」は27595世帯となっています。
(2016年(平成28年)4月1日現在)
「銚子市」は、「関東地方」の「東部」、「千葉県」の「北東部」にある「市」で、「全国屈指」の「漁港のまち」で、「市」の「北部」には「坂東太郎」「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)が流れ、「銚子市」で「太平洋」に注いでいます。
「銚子市」は、「東京」から100km圏内、「関東平野」の「最東端」に位置し、「北」は「利根川」、「東」と「南」は「太平洋」に面しています。
「銚子市」は、江戸時代に「利根川水運」が開発され、「醤油醸造業」と「漁業」で発展、「農業」は「露地野菜」を中心に発展した「観光都市」です。
「銚子市」は、「利根川」沿いの「低地」と「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)からなり、「表層」は「関東ローム層」に覆われています。
「銚子市」には、「北総台地」(下総台地)「最高峰」の「愛宕山」(「標高」73.6m)があり、「水田」は「台地山間」の「谷津田」と「利根川」沿いに広がっており、「畑地帯」は「台地」の「平坦部」に位置し、比較的「農業」(2011年6月15日・2月19日のブログ参照)に適しています。
「銚子ポートタワー」(2011年11月30日・2010年9月30日のブログ参照)は、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)「河口」近くにあり、「銚子漁港」(2012年1月24日のブログ参照)を見下ろす「高台」にある「ビュースポット」、「観光スポット」です。
「銚子ポートタワー」ですが、「高さ」57.7m、「ハーフミラー」で覆われた「建造物」で、「総反射ガラス張り」の「おしゃれ」な「タワー」となっています。
「銚子ポートタワー」「展望室」からは、「太平洋」の「大海原」をはじめ、遠く「鹿島灘(カシマナダ)」(2012年6月16日のブログ参照)や、「日本一」の「銚子漁港」、「利根川」「河口」も一望でき、「眺望」は素晴らしく「利根川」に沈む「夕景」も楽しめる「観賞スポット」となっています。
「銚子ポートタワー」は、「千葉県」により、「水産物卸売センター」「ウオッセ21」(2011年4月26日・2010年8月25日のブログ参照)と並ぶ「観光部門施設」として建設され、1991年(平成3年)に竣工しました。
なお「銚子ポートタワー」は、「千葉県」の「ふるさと千葉5ヶ年計画」の「一環」として建てられたものなのだそうです。
「銚子ポートタワー」の「設計者」ですが、「(株)横川建築設計事務所」で、「構造様式」は「鉄骨造りハーフミラーガラス」「ツインタワー」となっており、「(一社)銚子市観光協会」が「指定管理」・「運営」しています。
「銚子ポートタワー」の「概要」ですが、1Fに「インフォメーション」、「昇降ロビー」・「イベントコーナー」・「売店」があります。
また「銚子ポートタワー」1Fには、「銚子」の「観光」を「ガイド」してくれる「検索システム」も用意されています。
「銚子ポートタワー」2Fには、「展望ロビー」が設けられており、「展示会」・「イベント」・「催事」・「会議室」などに使われています。
「銚子ポートタワー」3Fは、「展望ロビー」(高さ・43.05m)、「銚子ポートタワー」4Fが「展望ホール」(高さ・46.95m)となっており、三方を「海」と「川」で囲まれた「銚子の風景」を見渡すことができます。
「銚子ポートタワー」「隣地」には、「新鮮」な「魚介類」や「国内外」から取り寄せられた「豊富」な「海の幸」を販売している「水産物卸売センター」「ウオッセ21」や「シーフードレストランうおっせ」があります。
「水産物卸売センター」「ウオッセ21」では、「週末」や「年末」など、「新鮮」な「魚」を買いに来る「買い物客」や「観光客」、「ツアー客」の「皆さん」で賑わいをみせます。
なお「銚子ポートタワー」から「水産物卸売センター」「ウオッセ21」には、1Fで「連絡用歩道橋」で結ばれて(繋(ツナ)がって)います。
「銚子市」や、となりまち「茨城県」「神栖市」を「中心」に活動している「写真クラブ」「オリンパスズイコークラブ千葉支部」(坂尾正純支部長)。
「第11回オリンパスズイコークラブ千葉支部写真展」ですが、「年」4回、「オリンパス」から派遣される「プロカメラマン」「指導」のもとで撮影された、「地元」「銚子」の「風景」や「風俗」、「祭り」の「写真」の中より、「自ら」厳選した「作品」約50点を「銚子ポートタワー」「2階展示ホール」にて展示しています。
「第11回オリンパスズイコークラブ千葉支部写真展」では、「テーマ性」を持った「組み写真」や「光」を「巧み」に利用した「写真」など「バラエティ」に富んだ「作品」を楽しめるそうです。
「地域」の「写真愛好家」の「皆さん」が集い、「プロカメラマン」の「直接指導」を受けてグングン腕を上げている「オリンパス・ズイコークラブ千葉支部」の「皆さん」は、9月17日(土)から「川口町」の「銚子ポートタワー」で「第14回オリンパス・ズイコークラブ千葉支部写真展」を開催するそうです。
「第14回オリンパス・ズイコークラブ千葉支部写真展」ですが、9月17日(土)から9月25日(日)までの「期間」開催され、「入場料」「無料」で行われます。
「第14回オリンパス・ズイコークラブ千葉支部写真展」では、「オリンパス・ズイコークラブ千葉支部」の「皆さん」は、「写真家」の「三澤史明」「先生」の「指導」を受けながら「クラブ員」「個々」の「個性」を生かした「作品作り」を行っているのが「特徴」で、「各自」が「テーマ」を定めて1年間撮り溜めた「写真」の中から「三澤」「講師」とともに「出展作」3点ずつを選び展示しているそうです。
「第14回オリンパス・ズイコークラブ千葉支部写真展」「講師プロフィール」は、下記の通りです。
「講師プロフィール」
三澤史明(ミツザワシメイ)氏
ズイコークラブ千葉支部専任講師。
1980年(昭和55年)12月6日、新潟県新潟市生まれ。
大学を卒業し飲食店に就職するも、写真の魅力に引き込まれ写真界へ。
日本写真芸術専門学校夜間部卒業後、2007年(平成19年)、「竹内敏信事務所」へ入社。
2009年(平成21年)、「第5回名取洋之助写真奨励賞」受賞。
2010年(平成22年)、独立。
「三澤史明」氏の「写真展」と「ライフワーク」は、下記の通りです。
「写真展」
2006年(平成18年) 「鳥っこちゃん」(ギャラリーLE DECO)
2010年(平成22年) 「第5回名取洋之助写真奨励賞受賞作品展」(富士フィルムフォトサロン東京)
2011年(平成23年) 「幸福論」(快晴堂フォトサロンギャラリー)
「ライフワーク」
日本国内の「失いたくない光景」をテーマに置き、都市風景、スナップ、ドキュメンタリーと幅広く撮影。
出身地新潟の小さな離島、栗島の生活と風景や本州の東端、千葉県銚子市のノスタルジーなスナップ写真にも力を入れている。
「第14回オリンパス・ズイコークラブ千葉支部写真展」開催に際し、「オリンパス・ズイコークラブ千葉支部」の「皆さん」より、下記の「ごあいさつ」を残されています。
ごあいさつ
当クラブはオリンパスカメラのユーザークラブとして1982年(昭和57年)に結成され、オリンパス(株)ズイコークラブからプロ写真家・三澤史明先生を招き、個別指導で写真を学んでいます。
その発表の場として年2回クラブ展を開催し、今回は会員23名、68点の作品を展示いたします。
ごゆっくり鑑賞いただき、ぜひご意見・ご指導たまわりたくご案内申し上げます。
会員一同
文中まま表記
上述のように「第14回オリンパス・ズイコークラブ千葉支部写真展」ですが、「会員」23名、68点の作品を展示するそうです。
「第14回オリンパス・ズイコークラブ千葉支部写真展」「出展者」・「作品」は、下記の通りです。
「第14回オリンパス・ズイコークラブ千葉支部写真展」「出展者」・「作品」詳細
宮内進 氏 「水揚げの港」(3枚組)
山中亘 氏 「路地」(3枚組)
富山憲夫 氏 「絆」「乱舞」「夢」
佐久間徹雄 氏 「泥んこ祭り」(3枚組)
奥田君雄 氏 「菖蒲咲くころ」(3枚組)
坂尾正純 氏 「青春時代」(3枚組)
山中草平 氏 「モロッカン」(3枚組)
石井欣子 氏 「舞姿」
久永勝三 氏 「藍色に誘われて」(3枚組)
武部静枝 氏 「浴衣で京都」「昼さがり」「お昼ですよ」
宮内勝廣 氏 「祇園茶屋にて」(3枚組)
田村俊雄 氏 「流鏑馬」(3枚)
小倉浩子 氏 「勇壮華麗」(3枚)
信田宗一 氏 「祈り」(3枚組)
高木啓仁 氏 「火渡り修行」(3枚組)
宮内謙一 氏 「青鷺」(3枚組)
雨田秀樹 氏 「離陸」「水鏡」「綱渡り」
宮内弘文 氏 「あさつゆ」「神懸り」「妬ける!」
宮内勝利 氏 「山の外灯」「古い橋脚」「煙った山里」
網中登代子 氏 「五月晴れ」(3枚組)
山根良太 氏 「静寂」「帰港」「黄金の渚」
久永邦枝 氏 「待ち合わせ」(3枚組)
青柳和仁 氏 「皐月」(3枚組)
「人気展望スポット」「銚子ポートタワー」で開催される「写真展」「第11回オリンパスズイコークラブ千葉支部写真展」。
この機会に「銚子市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「第11回オリンパスズイコークラブ千葉支部写真展」詳細
開催期間 9月17日(土)〜9月25日(日)
開催時間 10時〜17時
開館時間 8時半〜17時半
開催会場 銚子ポートタワー2階展示ホール 銚子市川口町2-6385-267
入館料 大人350円 小・中学生200円 65歳以上300円
問合わせ 銚子ポートタワー 0479-24-9500
備考
「第11回オリンパスズイコークラブ千葉支部写真展」ですが、「最終日」は15時00分までとなっています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3128 |
| 地域情報::銚子 | 12:42 PM |
|
|
2016,09,18, Sunday
本日ご紹介するのは、近隣市「匝瑳市」「ふれあいパーク八日市場」で9月19日(祝・月)に開催されます「敬老の日プレゼント」です。
「ふれあいパーク八日市場」(2012年6月16日・5月1日・2010年9月11日のブログ参照)は、「東関東自動車道」「成田IC(成田インターチェンジ)」から「国道295号線」・「国道296号線」を「匝瑳市」「方面」に向かい、「東総広域農道」「入口」を「左折」し、「東総広域農道」を約7km(「成田IC」より約30分)、「県道八日市場・山田線」「交差点」にあります。
また「地域高規格道路」「千葉東金道路」(「東金有料」・「東金道」)「銚子連絡道」「横芝光IC(よこしばひかりインターチェンジ)」からは、「国道126号線」を「匝瑳市」「方面」に向かい、「県道八日市場・山田線」へ入り、約4km(「横芝光IC」から約30分)、「東総広域農道」との「交差点」に「ふれあいパーク八日市場」があります。
「ふれあいパーク八日市場」には、1.5ha(ヘクタール)の「敷地」に「普通車」83台、「大型車」3台を収容できる「駐車場」を完備しています。
のどかな「田園風景」が広がる「匝瑳市」にある「ふれあいパーク八日市場」は、「安心・安全・新鮮な農産物、こだわりの匝瑳市産」を「皆様」にお届けするために、平成14年(2002年)3月17日に「産声」をあげた「都市と農村交流ターミナル」です。
「ふれあいパーク八日市場」では、「匝瑳」の「大地」をこよなく愛する「生産者」が、「手塩」をかけた「恵み」の「農産物」等の「数々」を、「見て・触って・食して」お楽しみいただける「施設」となっています。
「ふれあいパーク八日市場」ですが、2002年(平成14年)3月の「開館」以来、「施設」の「運用面」(交流・イベント、直売、レストラン運営事業等)については、「八日市場市ふるさと交流協会」(「合併後」は「八日市場ふるさと交流協会」に名称変更)が行っていましたが、「事業」を「継続」・「拡大」していく中で、「協会」が保有する「資産」や「雇用者数」が増加し、「財務運営」や「雇用計画」等について、「協会」は「法人格」を持たない「任意的団体」であったため、その「代表者」が「無限責任」を追わなければならないという「問題」が顕著となり、そこで「行政」としても何らかな「法人格」を有する「組織形態」への「移行」を検討する「必要」があると考え、「匝瑳市」と「協会」との「双方」で「法人化」を目指すことで「意見」が一致したそうです。
「ふれあいパーク八日市場」の「法人形態」に関しては、「協会」と「匝瑳市」の「間」で「数回」の「協議」を重ね、主に下記の「理由」から「第3セクター方式」による「有限会社」の「設立」を進めることで「結論」に達したそうです。
1 協会単独で有限会社になることは、ふれあいパーク八日市場が公共施設であるため難しいこと
2 NPO法人、株式会社についても検討したが、両法人形態の有する性質上、協会単独での法人化は困難であること。
3 第3セクター方式による有限会社形態をとることにより、公共施設の利用、交流協会の財務運営等について、官民一体となってすすめることが可能であること。
「第3セクター」による「有限会社」の「設立」に関して「協議」をする「機関」として「ふるさと交流協会第3セクター設立検討委員会」を設立したそうです。
「委員会」の「委員」には、「市」3名、「協会」3名、「農協」2名、「市観光協会」1名の「計」9名で構成し、「法人設立」を目指して「検討」を重ね、また「専門的」な「アドバイザー」として「千葉県農業会議」及び「会計事務所会計士」に「必要」な応じて「出席」を依頼したそうです。
なお、「委員会」においての「検討事項」ですが、「商号」、「資本金」、「社員」その「出資割合」、「役員」と、その「報酬」及び「営業年度」などであったそうです。
以上の「経緯」から、2005年(平成17年)12月1日に、「都市交流事業」・「各種イベント」の「企画運営」、「直売事業」、「レストラン運営」等を「目的」とする「ふれあいパーク八日市場有限会社」が設立されました。
「ふれあいパーク八日市場」の「会社概要」は、下記の通りです。
商号 ふれあいパーク八日市場有限会社
事業内容 都市と農村交流ターミナル
設立 平成13年11月1日
所在地 千葉県匝瑳市飯塚299-2
TEL 0479-70-5080 FAX 0479-70-5081
納入会員 ふるさと交流協会 会員数 128名
「ふれあいパーク八日市場」の「施設概要」ですが、「店舗」「入口」を入りますと、向かって「右側」に「農特産物コーナー」、「左側」に「文化コーナー」があります。
「ふれあいパーク八日市場」「農特産品コーナー」の「メイン」で販売しているのが、「匝瑳市産野菜」で「キャベツ」、「ほうれん草」、「小松菜」、「トマト」などが「定番商品」で、どれをとっても「質」が良いと言われています。
また「ふれあいパーク八日市場」の「人気」の「秘密」ですが、「野菜」だけではなく、「農特産物」の「加工品」がとても「豊富」で、中でも「棒もち」、「卵焼き」、「卵焼きで巻いた太巻き寿司」等「人気」の「加工品」を求めに「近隣」から来店される「方」が多いそうです。
「ふれあいパーク八日市場」「店舗」「左奥」に「匝瑳産」の「食材」をふんだんに使った「料理」を提供している「レストラン」「里の香」があります。
また「匝瑳市」は、「日本有数の植木のまち」として知られており、「ふれあいパーク八日市場」「店舗」(本館)の「外」「西側」には「花・植木見本園」が設置されており、また「ふれあいパーク八日市場」「店舗」(本館)を抜けると、隣接する「飯塚沼農村公園」に行くこともできます。
「ふれあいパーク八日市場」では、上記のように「匝瑳産」の「新鮮な農産物」や、懐かしい「ふるさとの味」に出会える「憩いの場」として、「匝瑳市民」はもとより「近隣市町村」からも「大勢」の「来客」のある「人気スポット」となっています。
また「ふれあいパーク八日市場」では、「なにかがあるふれあいパーク」を「キャッチフレーズ」に、「毎週末」や「祝祭日」に、いろいろな「イベント」を行っています。
「敬老の日(ケイロウノヒ)」ですが、「日本」の「国民の祝日」のひとつであり、「日付」は9月の「第3月曜日」です。
「敬老の日」は、「国民の祝日に関する法律」(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)「第2条」によりますと、
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」
ことを「趣旨」としています。
2002年(平成14年)までは「毎年」9月15日を「敬老の日」としていましたが、2001年(平成13年)の「祝日法改正」いわゆる「ハッピーマンデー制度」の「実施」によって、2003年(平成15年)からは現在のように9月「第3月曜日」となりました。
しかし、「適用」「初年度」の2003年(平成15年)の9月「第3月曜日」が偶然9月15日であったため、「敬老の日」が9月15日以外の「日付」になったのは、2004年(平成16年)の9月20日が「最初」なのだそうです。
なお、「敬老の日」を「第3月曜日」に移すにあたって、当時、「提唱者」が「存命」であったため、「日付」の「変更」について「遺憾の意」を表明されたほか、「高齢者団体」から「反発」が相次いだため、2001年(平成13年)に「老人福祉法」「第5条」を改正して、9月15日を「老人の日」、「同日」より1週間を「老人週間」としました。
「敬老の日」の「始まり」ですが、「兵庫県」「多可郡」「野間谷村」(後の「八千代町」を経て現在の「多可町」「八千代区」)で、1947年(昭和22年)9月15日に「村主催」の「敬老会」を開催したのが「敬老の日」の「始まり」であるとされています。
これは、「野間谷村」の「村長」であった「門脇政夫」(1911年〜2010年)氏が、
「老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村作りをしよう」
という「趣旨」から開いたもので、9月15日という「日取り」は、「農閑期」にあたり「気候」も良い9月中旬ということで決められました。
1948年(昭和23年)7月に制定された「国民の祝日に関する法律」において、「こどもの日」、「成人の日」は定められたものの、「老人」のための「祝日」は定められませんでした。
「門脇」氏は1948年(昭和23年)9月15日に開催された「第2回敬老会」において、9月15日を「としよりの日」として「村独自」の「祝日」とすることを提唱しました。
「門脇」氏は「県内市町村」にも「祝日制定」を働き掛け、その「趣旨」への「賛同」が広がったそうです。
1950年(昭和25年)からは「兵庫県」が「としよりの日」を制定。
1951年(昭和26年)には「中央社会福祉協議会」(現「全国社会福祉協議会」)が9月15日を「としよりの日」と定め、9月15日から21日までの1週間を「運動週間」としました。
1963年(昭和38年)に制定された「老人福祉法」では、9月15日が「老人の日」、9月15日から21日までが「老人週間」として定められ、翌1964年(昭和39年)から実施されました。
さらに1966年(昭和41年)に「国民の祝日に関する法律」が改正されて「国民の祝日」「敬老の日」に制定されるとともに、「老人福祉法」でも「老人の日」が「敬老の日」に改められました。
このため、「母の日」のように輸入された「記念日」と違い、「日本」以外の「国」にはないそうで、ただし、「五節句」のひとつである9月9日の「重陽」と「主旨」が類似しています。
「敬老の日」の「起源」を「野間谷村」の「敬老会」に求めるならば、9月15日という「日取り」は上述の通り「野間谷村」の「農事暦」と、「気候」に由来するものになります。
「門脇政夫」氏の「事績」を伝える「多可町広報」の「記事」によりますと、9月という「開催時期」には、「農閑期」であることや、「気候」に加え、「養老の滝伝説」も参考にしたといわれています。
(元正天皇が霊亀3年(717年)9月に滝を訪れて養老の滝と命名、同年に養老と改元し、全国の高齢者に賜品を下した。)
このほか、「聖徳太子」が「四天王寺」に「悲田院」を建立した「日」が593年9月15日であるとして、「敬老の日」をこれに由緒づける「説」もあります。
「四天王寺縁起」によりますと、「聖徳太子」が「四天王寺」建立(593年)と、「悲田院」を含む「四箇院」(現代でいう社会福祉施設)を設立したとありますが、9月15日という「日付」には根拠がないそうです。
「四天王寺」「悲田院」の「伝統」を継ぐとする「四天王寺福祉事業団」も、「敬老の日」「由来」の「諸説」のひとつとして挙げるにとどまるそうです。
なお、「四箇院」の「創設者」を「聖徳太子」とする「伝承」も、後年の「太子信仰」の中で仮託されたものと考えられています。
「敬老の日プレゼント」ですが、「ふれあいパーク八日市場」で開催されている「敬老の日」の「企画」で、9月19日(祝・月)に行われます。
「敬老の日プレゼント」ですが、70歳以上の「方」を「対象」、「先着」200名様に、「ふれあいパーク八日市場」にて「敬老の日」「当日」2000円以上の「レシート」「ご持参」で「粗品」を差し上げる(プレゼントする)そうです。
「匝瑳」の「魅力」満載の「人気スポット」「ふれあいパーク八日市場」で開催される「敬老の日」「企画」「敬老の日プレゼント」。
この機会に「匝瑳市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「敬老の日プレゼント」詳細
開催日 9月19日(祝・月)
開催時間 10時〜15時
開催会場 ふれあいパーク八日市場 匝瑳市飯塚299-2
営業時間 9時〜18時
問合わせ ふれあいパーク八日市場 0479-70-5080
備考
「ふれあいパーク八日市場」では、「野菜を自分でつくりたい!」そんな方を、募集しているそうです。
「育成農場」で「農業」を学び、後々はふれあいパークの会員として売場に列べられるような「野菜」を作れるそうです。
詳しくは「ふれあいパーク八日市場」「HP」「野菜を自分でつくりたい!」を参照下さい。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3130 |
| 地域情報::匝瑳 | 10:21 AM |
|
|
2016,09,16, Friday
本日ご紹介するのは、となりまち「神栖市」「神栖中央公園」(土研跡防災公園)で9月17日(土)・18日(日)に開催されます「第7回かみす舞(ブ)っちゃげ祭り2016」です。
「神栖市」は、「茨城県」の「東南端」に位置し、「東側」は「太平洋」に面し、「南側」・「西側」は「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)を経て「千葉県」に接し、「北西側」は「鹿嶋市」及び「潮来市」に接した「南北」に長い「形状」をしており、「神栖市」の「面積」ですが、147.26平方kmとなっています。
「神栖市」の「北部」から「東部」一帯は「鹿島港」及び「鹿島臨海工業地帯」が整備され、「製造品出荷額」は「茨城県」第1位、「温暖な気候」を活かした「ピーマン」は、「ブランド品」として高い「評価」を受け、「全国」第1位の「生産量」を誇っています。
また、「神栖市」「南部」は「波崎漁港」を中心に「漁業」が盛んに営まれ、「水産加工品」などが「特産品」となっており、「商業」を含めた「各産業」がバランス良く形成されています。
「神栖市」は、平成17年(2005年)8月1日に「神栖町」と、「波崎町」との「市町村合併」により、「人口」9万人余りの「市」として誕生しました。
(2016年8月末日現在・神栖市の人口は、94893人)
「神栖市」ですが、昨年(2015年)「市制施行10周年」を迎えています。
「神栖市」は、「東」は「太平洋」「鹿島灘(カシマナダ)」(2012年6月16日のブログ参照)に面し、「南」は「利根川」、「常陸利根川」が流れています。
「神栖市」は、かつて「広大な面積」の「池」「神之池(ゴウノイケ)」(2012年3月27日のブログ参照)がありましたが、現在は「鹿島開発」のため、一部を残して大部分が埋め立てられています。
「神栖市」は以前、「農業」と、「漁業」が中心の「地域」でしたが、1960年(昭和35年)に始まった「鹿島開発」により、「世界的」にも珍しい「堀込式人工港」である「鹿島港」を「核」に、「鉄鋼」・「石油」を中心とした「重化学コンビナートのまち」として発展、「工業立地企業」からの「税収」により「財政」は豊かになり、「福祉」が充実、現在「神栖市」は「県外」からの「転入者」も多く、このため隣接する「自治体」「鹿嶋市」との「広域市町村合併構想」は、「自主財源確保」の「観点」から「合併」には至っていません。
「神栖中央公園」(土研跡防災公園)ですが、「茨城県」「神栖市」「木崎」に新しく開園した「防災公園」です。
「神栖中央公園」(土研跡防災公園)は、「防災機能」を備えた「総合公園」として平成22年度より「整備」を進めてきた「公園」で、2014年(平成26年)6月1日に開園されました。
「神栖中央公園」(土研跡防災公園)は、約19ha(ヘクタール)もの「広大な敷地」の中に、「神栖市」の「備蓄」の中心となる「防災倉庫」、「飲料水」を確保する「耐久性貯蓄槽」、「防災トイレ」、「カマドベンチ」などの「防災機能」を備えた「地域」の「防災拠点」となる「公園」で、「平常時」には、たくさんの「樹木」が「四季」を彩り、「広大」な「芝生広場」には「大型遊具」や、「噴水広場」、「ふれあいの丘」(つき山)など、「ふれあい」や、「憩いの場」として、「子供」から「お年寄り」まで楽しめるように整備されています。
「神栖中央公園」(土研跡防災公園)の「概要」は、下記の通りです。
「神栖中央公園」(土研跡防災公園)詳細
・施設
駐車場
ふれあいの丘(標高15m・直径80m)
多目的広場
大型遊具
噴水広場(4月中旬から9月末まで)
散歩道
ヘリポート
防災アリーナ(建設予定)
・主な防災機能
備蓄倉庫(RC2階建て、備蓄スペース975平方m、食糧、飲料水、毛布、資機材などを備蓄)
飲料水 耐震性貯水槽100平方m
生活用水 井水耐震性貯水槽80平方m、手押し式防災井戸2か所
防災トイレ56基(スツール型、マンホール型)
ヘリポート
カマドベンチ
自家用発電機
太陽光備蓄型LED照明
防災パーゴラ(防災時にテント等に取り付けることで、災害対策本部や、救護所等に)
などとなっています。
「かみす舞っちゃげ祭り」(2015年9月17日・2014年9月15日・2013年9月20日・2012年9月19日・2011年9月22日のブログ参照)は、「神栖市内」を含め、「茨城県内外」からの「参加演舞チーム」による「よさこい鳴子踊り」を通じて、「神栖市民」に「感動」と、「元気」、そして「地域交流」のきっかけを与え、また「全国各地」からの「参加者」・「観覧者」の来市により、「全国レベル」での「神栖市」の「知名度向上」と、「市内観光」・「商工業の活性化」を図る「目的」とし、開催されています。
また「かみす舞っちゃげ祭り」は、「コンテスト形式」の「よさこいイベント」ではなく、「演舞審査」等を行わない、純粋に「よさこい演舞」を楽しみたい「踊り子のための祭り」となっています。
なお、これまで「かみす舞っちゃげ祭り」「会場」は、「神之池緑地公園」「陸上競技場」「特設ステージ」(メインステージ会場)、「神栖市文化センター」「大ホール」(ステージ会場)、「神之池緑地内遊歩道」(パレード会場)で行われていましたが、現在は「神栖中央公園」(土研跡防災公園)にて開催されています。
「かみす舞っちゃげ祭り」ですが、今年(2016年)で7回目を迎える「よさこいイベント」です。
「第7回かみす舞っちゃげ祭り2016」ですが、9月17日(土)に行われる「前夜祭」と、9月18日(日)の「本祭」の2日間開催され、2014年(平成26年)から「会場」が変更され、2014年6月に完成(オープン)した「神栖中央公園」(土研跡防災公園)にて開催されています。
上述のように「第7回かみす舞っちゃげ祭り2016」の「会場」は、「神栖中央公園」(土研跡防災公園)内「特設会場」で開催され、「メインステージ会場」として「神栖中央公園」(土研跡防災公園)内「特設ステージ」(ステージ寸法23.4m×14.4m)、「パレード会場」として「神栖中央公園」(土研跡防災公園)内「遊歩道」(ステージ寸法8.0m×8.0m)の2会場で開催されます。
(ステージ寸法は変更になる場合があります。)
(「屋内」の「演舞会場」はありません。)
「第7回かみす舞っちゃげ祭り2016」では、今年(2016年)も「茨城県」「神栖市」の「チーム」はもちろん、「北海道」をはじめ、「県外」からもたくさんの「チーム」が参加する予定になっており、また、「前夜祭」に「大洗高校マーチングバンド」「演奏」や、「よさこい演舞コンテスト」、「神栖市イメージキャラクター」「カミスココくん」(2015年1月12日のブログ参照)「JAしおさいイベント」(ピーマン早食い競争など)、「総乱舞」、「旗の競演」等が行われ、「本祭」では、「終了時間」を延長して「舞っちゃげナイト」が行われるそうです。
「第7回かみす舞っちゃげ祭り2016」の「参加チーム」は「よさこいチーム」51チーム、「ダンスチーム」21チームで、「参加チーム」ですが、下記の通りです。
・北海道
夢想漣(ユメソーラン)えさし(招待チーム)
旭川北の大地(招待チーム)
コカ・コーラ札幌国際大学(招待チーム)
江別まっことえぇ&北海道情報大学(招待チーム)
Excla!matioN(エクスクラメーション)
・栃木県
新芸組遊駆人(シンゲイグミアクト)
・埼玉県
所沢風炎祇神伝〜雅〜(トコロザワフエンギシンデンミヤビ)
・東京都
開第三中ソーランクラブ「粋」
東京カペラ
東京ばあばスコレー
・千葉県
REDA舞神楽(レダマイカグラ)(招待チーム)
櫻゛(ザクラ)
がむしゃら桜連
よさこい柏紅塾
YOSAKOI舞ちはら
千葉工業大学よさこいソーラン風神
おみが和よさこい会和気藹藹(ワキアイアイ)
元気舞心(ゲンキマイシン)
チーム☆利エ蔵(チームリエゾウ)
ACT(アクト)
華舞然蓮(カムサレン)
木更津かずさ連
遊奏舞陣(ユウソウブジン)
・茨城県
真壁桜乃舞
華の乱
かしまスポーツクラブ一丸天舞
うしく河童鳴子会
雅華組(ミヤビグミ)
水戸城東YOSAKOI漣
よさこい飛翔
水戸藩YOSAKOI連
総踊りだよ!全員集合!
筑波大学斬桐舞(キリキリマイ)
颯流(ソウル)
常陸國大子連
将門YOSAKOI響
龍ヶ崎天荘中村組
さかど花吹雪
ハッチよっちょれ会
筑波よさこい連
秋山舞の会
茨城YOSAKOI小柳組&桜舞姫
青塚つばさ会
錦照会北蓮華潮娘よさこい連合合同チーム
・よさこい連合会
日川郷よさこい連
浜っ娘連
Kamirenn花舞
遊元
飛翔舞陣
黒潮美遊潮っ子組
桜嵐坊
・一般ダンスチーム
バイラオーラの会
3☆CRAT(スリーカラット)
STEELO ふなっちナンバー
STEELO Sinobu ナンバー
STEELO KAZU ナンバー
STEELO TOMOMI ニュージャックスウィングクラス
STEELO あべ Waack クラス
STEELO ケンセイ LOCK クラス
STEELO ショウゴ&イズ ナンバー
HOOP TOMO&IZU ナンバー
HOOP Shinobu ナンバー
なっち&DOS DIOSAS
YALA DANCE SCHOOL (NEX)
YALA DANCE SCHOOL (S.D.S)
Petit(ハピネスダンススクール)
POME(ハピネスダンススクール)
EXTRA(ハピネスダンススクール)
T☆girls
KITTY
KITTY Jr
ZUMBA Kids+Kids Jr
フラハラウロコマイマイ(フラダンス)
YUYA KIDS
なお「前夜祭」、「本祭」の「タイムスケジュール」ですが、「神栖市観光協会HP」「かみす舞っちゃげ祭りOFFICIAL SITE」をご参照下さい。
「土研跡防災公園」「神栖中央公園」で開催される「よさこい演舞」の「祭典」「第7回かみす舞っちゃげ祭り2016」。
この機会に「神栖市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「第7回かみす舞っちゃげ祭り2016」詳細
開催日時 9月17日(土) 11時〜21時(予定) 前夜祭
9月18日(日) 10時〜20時(予定) 本祭
開催会場 神栖中央公園(土研跡防災公園) 茨城県神栖市木崎1203-9
問合わせ かみす舞っちゃげ祭り実行委員会事務局 0479-26-3021
備考
「第7回かみす舞っちゃげ祭り2016」ですが、「雨天決行」、「荒天中止」となっており、「時間」ですが、変更になる場合がありますので、ご注意下さい。
「第7回かみす舞っちゃげ祭り2016」の「前夜祭」の行われる9月17日(土)には、19時00分より、色鮮やかな「花火」が、「秋」の「神栖の夜空」を彩る「第44回神栖花火大会」が「神之池緑地公園」「陸上競技場」周辺を「会場」に開催されます。
今年(2016年)は約6000発の「打ち上げ花火」が打ち上げられるそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3127 |
| 地域情報::神栖 | 10:58 AM |
|
PAGE TOP ↑
|
 |



