 |
■CALENDAR■
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
<<前月
2026年02月
次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■POWERED BY■
■OTHER■
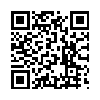
携帯からもご覧いただけます
|
2017,02,17, Friday
本日ご案内するのは、近隣市「四街道市」「和良比皇産霊神社(ワラビムスビジンジャ)」で2月25日(土)に開催されます「和良比はだか祭り(ワラビハダカマツリ)」です。
「千葉県」「北部」に位置し、「県庁所在地」「千葉市」に隣接する「四街道市」は、「東京都心」へも40km圏内にあり、「首都圏」の「ベットタウン」として発達してきました。
「東西南北」、四つの「街道」が交わっていることから「四街道」の「市」の「名前」のとおり、「人」と「情報」と「産物」の「交流地」でもある「四街道市」ですが、江戸時代には「佐倉藩」の「領内」で、「幕末」の「藩主」は「老中」・「堀田正睦」だったそうです。
「堀田正睦」ですが、江戸時代末期の「大名」・「老中首座」で、「下総佐倉藩」の「第5代藩主」であり、「正俊系」「堀田家」「9代」です。
「堀田正睦」の「経歴」は、下記の通りです。
文政8年(1825年)3月 家督相続。従五位下・相模守に叙任。
文政12年(1829年)4月12日 幕府の奏者番となる。
天保5年(1834年)8月8日 寺社奉行を兼帯し、備中守に遷任。
(先任同役に土屋相模守彦直がおり、同役同士が同じ官職に任官しない内規により、遷任)
天保8年(1837年)5月16日 大阪城代に異動し、従四位下に昇叙。備中守如元。
天保8年(1837年)7月9日 大納言(徳川家祥=後の家定)付老中に異動。侍従を兼任。
天保12年(1841年)3月23日 本丸老中に異動。
天保14年(1843年)閏9月8日 老中御役御免。溜間詰格となる。
安政2年(1855年)10月9日 老中再任。老中首座となる。勝手入用掛を兼帯。
安政3年(1856年)10月17日 外国御用取扱兼帯。
安政3年(1856年)月日不詳 名を正睦と改める。
安政5年(1858年)1月8日 幕府使者となり上洛。
安政5年(1858年)4月20日 帰府。
安政5年(1858年)6月1日 養君(世継ぎ徳川慶福=後の家茂)御用。
安政5年(1858年)6月23日 老中御役御免。帝鑑間席となる。
大正4年(1915年)11月10日 贈従三位。
「堀田正睦」の「学問」に関する「特徴」は、「知識」の「コレクション」ではなく「体系的」な「学問」を志向した「結果」として、幕末と明治に「有為」の「人材」を育成した点にあります。
「手塚律蔵」を招いて「日本」で初めて「英語」の「体系的」な「研究」を始めさせたこともそのひとつであり、「堀田」〜「手塚」「人脈」からは「西周」、「神田孝平」、「津田仙」、「内田正雄」、「大築尚忠」、「三宅秀」といった「人物」が輩出され、また「佐倉藩」「人脈」は安政年間の「蝦夷地調査」、明治の「沼津兵学校」「教授陣」等「多方面」に関わっていったそうで、「木戸孝充」も一時期は「手塚門下」であったそうです。
上述のように「堀田正睦」は、「蘭学」、「学問」を推奨したため、「四街道市」の「旧跡」にも「名残」があるそうです。
「四街道市」は、上記のように「都心」から40km圏内、「県庁所在地」「千葉市」「中心部」からも8kmと「利便性」の高い「立地条件」である事から、「JR四街道駅」周辺や「マンション」や「住宅地」が立ち並び、「首都圏」の「ベットタウン」として発展しており、また、「再開発」の進む「四街道駅」「南口」からは、228基もの「ガス灯」が立ち並び、「長さ」も約2300mと「日本一」の「長さ」を誇るそうです。
一方、「四街道市」では、「梨」、「落花生」などの「生産」が盛んな「近郊農業地帯」でもあります。
「四街道市」ですが、上記のように「千葉県」「中北部」の「内陸」に位置し、「下総台地」(北総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の「南」に位置する「自治体」で、「南」と「西」に「千葉県」の「県庁所在地」「千葉市」(花見川区、稲毛区、若葉区)、「北」と「東」に「佐倉市」が隣接しており、「四街道市」の「市」の「東縁」を「利根川水系」の「鹿島川」が「印旛沼」(2011年2月3日のブログ参照)へと「北流」しています。
「四街道市」の「市」の「中央部南方」を「JR総武本線」が「南東」から「北西」に、「四街道市」の「中央部北方」を「東関東自動車道」が「東西」に走っており、「四街道市」の「中央部南方」に「四街道駅」が、「四街道市」の「北東部」に「物井駅」と「東関東自動車道」の「四街道IC(よつかいどうインターチェンジ)」があり、「四街道市」の「南部」を「国道51号線」が「南東」から「北西」に走っており、「吉岡交差点」は、「交通情報」の「渋滞情報」でよく登場するそうです。
「四街道市」の「市域」「大半」は「印旛沼」「南側流域」の低い「台地」となっており、「樹枝状」の「谷津田」が多数切れ込んでいるそうです。
「四街道市」の「主要」な「谷津田」は、「東部」から「南部」の「鹿島川」とその「支川」、「中央部」の「手繰川」「源流」、「西北部」の「勝田川」「支川」となっており、「西部」のごく一部が、「津川水系」「葭川(ヨシカワ)」の「流域」となっています。
「四街道市」「全体」として「印旛沼」へ流れ込む「河川」に沿った、「南」が高く「北」が低い「微傾斜」となっており、「四街道市」の「最低標高点」は、「最北端」の「鹿島川」へ「小河川」が流れ込む「合流点」で、約5m、「四街道市」の「最高標高点」は、「最南部」の「吉岡新開」の「御成街道」付近で、40m強となっています。
「四街道市」の「市名」の「由来」ですが、「四街道駅」から「西」に500mほどの「場所」(現在の「四街道十字路」)に、「北 成田山道」、「南 千葉町道」、「東 東宇がね(東金)道、馬渡道」、「西 東京、船橋道」という「名」がついたそうです。
(「和良比地区」に「字・四海道」も存在します。)
ちなみに近くには「御成街道」や「千葉街道」、「成田街道」や「佐倉街道」(年貢道)がありますが、「成田街道」と「佐倉街道」が交わるのは「佐倉城下」であり、これらの「街道」は、「四街道」の「地名」とは直接関係がないそうです。
「和良比皇産霊神社(ワラビムスビジンジャ)」ですが、「四街道市」「和良比地区」に鎮座する「神社」で、「和良比皇産霊神社」の「御祭神」ですが、「高皇産霊大神(タカミムスビノオオカミ)」が祀られています。
「和良比皇産霊神社」は、「JR四街道駅」の「南」1km程の辺り、「千葉郊外」の「住宅地」の「外れ」に鎮座しています。
「和良比皇産霊神社」は、「和良比どろんこ祭り」が行われていることでも知られている「神社」ですが、もともとは「大六天」が祀られていた「和良比大六天社」であったそうです。
古くに勧請されたといわれている「和良比大六天社」の他に「建速須佐之男命(タケハヤスサノオノミコト)」と、「高皇産霊大神」が祀られていたそうです。
江戸時代、「和良比皇産霊神社」は、もとは「西」に数百m離れた「字御屋敷」という「場所」に鎮座していたそうで、そこは「神仏習合」の「地」で、同じ「建物」の「半分」が「真言宗豊山派」の「吉祥院」(創建年不明)という「寺院」、残りの「半分」が「皇産霊神社(ミムスビジンジャ)」となっていたそうです。
明治時代の「神仏分離令」により、「真言宗豊山派」「吉祥院」と、「皇産霊神社」を分離、「皇産霊神社」を「大六天社」に合祀し、現在に至るかたちとなっていったそうです。
その結果、「字御屋敷」には「真言宗豊山派」「吉祥院」、「字中山」には「皇産霊神社」が、鎮座するかたちになり、現在でも、その名残として、「和良比皇産霊神社」「社殿」に掲げられている「額」には、「大六天」とあります。
「和良比はだか祭り」ですが、「和良比皇産霊神社」と、「神社」「隣」の「和良比ヶ丘公園」内「神田(シンデン)」で行われる「神事」・「伝統行事」です。
「和良比はだか祭り」の「原型」ですが、明治初年に「真言宗豊山派」「吉祥院」から「和良比皇産霊神社」が遷宮する際に執り行われた「まつり」とされており、古くは「和良比皇産霊神社」に合祀されている「厄除神」として「信仰」の篤い「大六天」の「まつり」であったそうで、「御遷宮」の際に「御手洗池(ミタラシイケ)」(神田)で水ごりした「習慣」が「はじまり」といわれています。
現在「和良比はだか祭り」は、「子供」の「無病息災」、「五穀豊穣」を祈る「まつり」として行われています。
「和良比はだか祭り」ですが、「和良比皇産霊神社」で執り行われる「神事」には、「一般」の「参加」はできないそうですが、「和良比皇産霊神社」「隣」「和良比ヶ丘公園」内「神田」で行われる「幼児祭礼」、「泥投げ」、「騎馬戦」は、「一般」の「参加」もできるそうです。
「和良比はだか祭り」は、上記のように「五穀豊穣」と、「厄除け」を祈る「和良比皇産霊神社」の「伝統行事」で、「通称」「どろんこ祭り」として広く知られています。
「和良比はだか祭り」「当日」ですが、「豊作」を祈願する「神事」で始まり、「裸衆祭礼」、「神田」(または「御手洗池」)で、「しめ縄」の「わら」を「稲」に見立て「田植え」をするそうです。
「和良比はだか祭り」の「神事」では、30〜40人の「締め込み」の「裸衆」が身を清めた後、上記のように「和良比皇産霊神社」「社殿」の「注連縄(シメナワ)」の「わら」を「稲」に見立てて、「神社」の下にある「神田」で、「田植え」を行い「豊作」を祈ります。
続いて「和良比はだか祭り」では、「幼児祭礼」、「騎馬戦」、「泥投げ」と続き、「通称」「どろんこ祭り」の「名称」の通り、「泥だらけ」の「お祭り」となるそうです。
「幼児祭礼」ですが、「子ども参り」となっており、この日に備えて着飾った「満1歳未満」の「赤ん坊」(幼児)を抱え、「神田」にて「額(ヒタイ)」に「泥」を塗るそうで、「赤ん坊」(幼児)の「額」に塗ってもらうことで「厄除け」になると伝えられています。
「幼児祭礼」で「赤ん坊」(幼児)への「祝福」が終わると、「裸衆」に「御神酒(オミキ)」が振る舞われ、「和良比はだか祭り」は、いよいよ「メインイベント」ヘ、「騎馬戦」に続いて「壮絶」な「泥合戦」を3回繰り広げるそうです。
「和良比はだか祭り」の「泥合戦」(泥投げ)の「合間」には、「和良比皇産霊神社」「境内」で「焚き火」を囲み「裸衆」が「暖(ダン)」をとり、さらに「酒」(御神酒)が入るそうです。
「暖」をとり、「酒」の「勢い」もあることから、「和良比皇産霊神社」に「裸衆」の「熱気」があふれ、3回行われる「壮絶」な「最終戦」(最終合戦)ですが、「酔い」も手伝い、激しい「泥」の「投げ合い」が行われるそうです。
「和良比はだか祭り」では、参加している「ふんどし姿」の「裸衆」が「泥まみれ」になるばかりでなく、「裸衆」にも「泥」が飛んでくる「迫力」がある「まつり」で、最後は、「神社総代」(神職)の「胴上げ」を行い、「和良比はだか祭り」はお開きとなるそうです。
「和良比はだか祭り」「日程」は、下記の通りです。
開催日 毎年2月25日
開催時間 13時00分頃〜15時00分頃
当日次第
時間 内容
11時00分〜 祭礼(神事・氏子のみ)
(見学不可)
13時00分〜 裸衆祭礼(お祓い)、幼児祭礼(子ども参り)、泥投げ・騎馬戦、総代胴上げ
(一般見学可)
15時00分頃 終了
「和良比地区」の「産土神」「和良比皇産霊神社」で開催される「神事」・「伝統行事」「和良比はだか祭り」。
この機会に「四街道市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「和良比はだか祭り」詳細
開催日時 2月25日(土) 13時〜
開催会場 和良比皇産霊神社 四街道市和良比692
問合わせ 四街道市産業振興課 043-421-6134
備考
「四街道市」ですが、その名の通り、四つの「街道」、「東」・「東金道」・「馬渡道」、「西」・「船橋道」、「南」・「千葉町道」、「北」・「成田山道」が交わる「場所」であり、「人」、「物」、「情報」の「交流地」でもあり、「JR四街道駅」から「南西」へ500m程行(イ)った「四街道十字路」の「傍ら」には、「駒形方面」の「道標石塔」が立っているそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3333 |
| 地域情報::成田 | 10:13 AM |
|
|
2017,02,16, Thursday
銚子の気候は比較的温暖なため、一足早く春の訪れを感じる事ができます♪
春の房総は魅力がいっぱい
特典満載の春爛漫プランをご用意しました!
貸切温泉や卓球体験を無料サ-ビスしちゃう太っ腹企画です♪
プラン詳細は予約フォームのプラン内容からどうぞ

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3326 |
| お知らせ | 08:35 PM |
|
|
2017,02,16, Thursday
本日ご案内するのは、近隣市「匝瑳市」「稲生神社」、「子安神社」(子安社)で2月19日(日)に開催されます「亀崎の如意輪参り(カメザキノニョイリンマイリ)」です。
「稲生神社」は、「匝瑳市」「亀崎」に鎮座する「神社」で、毎年2月中旬の「日曜日」に「稲生神社」「境内」に祀られている「子安神社」(子安社)で、「女性だけ」の「仏教行事」「如意輪参り」(2016年2月11日・2014年2月11日・2013年2月15日・2012年2月16日・2011年2月12日のブログ参照)が行われていることで知られています。
「稲生神社」は、「国道296号線」が、「県道109号線」が交差する「交差点」から、「国道296号線」を「南東」へ1.4km進み「右折」し、「道なり」に300m進んだ「右側」に鎮座しています。
「如意輪参り」は、「稲生神社」「隣」の「亀崎コミュニティーセンター」「横」の「養淨(寿)寺」から、「稲生神社」までを「万燈」を「先頭」に踊りながら練り歩き、更に「稲生神社」「境内」の中で踊るそうです。
「如意輪参り」ですが、「如意輪観音」の「子安信仰」に基づく「安産祈願」の「行事」で、「地元」の「人々」によりますと、400年の「歴史」があるそうです。
「亀崎の如意輪参り」は、上記のように江戸時代から続く「安産祈願」の「行事」で、「女人講」の「子安信仰」から始まったと伝えられ、「稲生神社」「境内」に祀られている「子安さま」を踊りながら詣でるそうです。
「亀崎の如意輪参り(カメザキノニョイリンマイリ)」「当日」の「流れ」ですが、「如意輪参り」「出発」前「養淨(寿)寺」(亀崎コミュニティーセンター)に、昼過ぎに、艶(アデ)やかに着飾った「着物」にお揃いの「襷(タスキ)」をかけた「踊り手」の「女衆」と、「囃子方」をつとめる「男衆」が集まります。
そして「養淨(寿)寺」を出た「女人講」は、400m程離れた「稲生神社」まで、短い「道中」を「大杉囃子」等を踊りながら歩き、その際「大榊」を「先頭」に、「花万燈」、「踊り」の「行列」が続くそうです。
「女人講」ですが、現在「亀崎の如意輪参り保存会」の「皆さん」により継承されており、「亀崎の如意輪参り(カメザキノニョイリンマイリ)」ですが、「匝瑳市」の「市指定無形民俗文化財」に指定されています。
「稲生神社」「境内」の小さな「子安社」(子安神社)には、「三種」の「軸物」「木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)」、「子安観音」、「如意輪観音」を吊るして飾り、「御神酒(オミキ)」と、「おにぎり」が供えられて、「稲生神社」に到着後「女人講」は、「習わし」により「稲生神社」「境内」の「子安社」(子安神社)を「時計回り」に3周しながら、「大杉囃子」に合わせて踊るそうです。
「大杉囃子」が踊り終わると、次に「奉納踊り」として「いそべ」、「松かざり」、「大漁節」の3曲を「稲生神社」「社殿」前で「男衆」が演奏し、「女人講」「全員」が「お囃子」に合わせて「子安社」(子安神社)の前に並んで「踊り」を奉納します。
「亀崎の如意輪参り(カメザキノニョイリンマイリ)」では、「踊り」「奉納」後、「女性たち」が「安産祈願」の「御神酒」をいただき、「供え物」の「おにぎり」を「参詣者」に配って終了となります。
「豊栄地区」「亀崎」に鎮座する「稲生神社」、「子安社」(子安神社)で行われる江戸時代から伝わる「伝統行事」「亀崎の如意輪参り(カメザキノニョイリンマイリ)」。
この機会に「匝瑳市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「亀崎の如意輪参り(カメザキノニョイリンマイリ)」詳細
開催日時 2月19日(日) 12時〜
開催会場 稲生神社、子安社(子安神社) 匝瑳市亀崎130
問合わせ 匝瑳市産業振興課 0479-73-0089
備考
「如意輪観音」の「姿」は、「観音菩薩」が「如意宝珠」の「三昧(サンマイ)」(「精神」を集中して「心」を乱さない状態)に入った「姿」ともいわれ、その「柔和(ニュウワ)」な「姿」から「女性」の「徳」を表現し、「如意輪観音」を祀る「女人信仰」の「十九夜講」(「女性」は「お産」や、「月経」で穢(ケガ)れた「身」であるので「死後」は「血の池地獄」に落ちるとされ、救済されるには「女人講」に集まって「如意輪観音菩薩」に祈るようにと「各宗派」が説いていたとされる。)が江戸時代後期に「安産」や、「子育て」の「子安信仰」に変化していったそうです。
ちなみに「三昧」(サマーディの音写)とは、「仏教」における「禅定(ゼンジョウ)」、「ヒンドゥー教」における「瞑想(メイソウ)」において、「精神集中」が深まりきった「状態」のことで、「サマーディ」の他の「漢字」で「音写」に、「三摩堤」、「三摩地」等もあり、一般に9段階の「到達点」があるとされています。
「千葉県」「北部」には、「子安塔」が多く見られることから、「女人講」も盛んであったといわれています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3325 |
| 地域情報::匝瑳 | 03:55 PM |
|
|
2017,02,16, Thursday
本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山公園」で2月17日(土)〜3月5日(日)の期間開催されます「平成29年成田の梅まつり」です。
「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照)は、「成田市」に鎮座する「真言宗智山派」の「寺院」であり、「真言宗智山派」の「大本山」のひとつで、「弘法大師」「空海」が敬刻開眼した「不動明王」の「御尊像」を「御本尊」として開山された「不動尊信仰」の「総府」です。
「成田山新勝寺」は、1000年以上の「歴史」をもつ「全国有数」の「霊場」で、「成田」を代表する「観光地」でもあり、正月3が日には約300万人、「年間」約1000万人以上の「参拝客」が訪れています。
「成田山新勝寺」の「御本尊」は「不動明王」で、古来より、「お不動さま」の「御霊験」・「御利益」は数限りなく、数多の「信仰」を集め、「成田山新勝寺」は、今日(コンニチ)では毎年1000万人を超える「参詣者」を迎える「関東地方」「有数」の「著名寺院」です。
「全国有数」の「広大」な「敷地」を誇る「成田山新勝寺」「境内」には、「車」の「祈祷」をする「交通安全祈願殿」、「自然」豊かな「公園」、「成田山書道美術館」(2011年6月5日のブログ参照)や、「成田山仏教図書館」等多くの「施設」を有しています。
「成田山新勝寺」ですが、「家内安全」、「交通安全」等を祈る「護摩祈祷」のために訪れる方が多い「不動明王信仰」の「寺院」のひとつであり、「成田のお不動さま」の「愛称」で親しまれています。
「成田山新勝寺」の「御本尊」である「不動明王」ですが、「真言宗」の「開祖」「弘法大師」「空海」が自ら「一刀三礼」(ひと彫りごとに三度礼拝する)の「祈り」をこめて「敬刻開眼」された「御尊像」なのだそうです。
「成田山新勝寺」では、この霊験あらたかな「御本尊」「不動明王」の「御加護」で、千年以上もの間、「御護摩」の「火」を絶やすことなく、皆様の「祈り」が一体となり「清浄な願い」となって現れるそうです。
「成田山新勝寺」は、平安時代中期に起きた「平将門の乱」の際、939年(天慶2年)「朱雀天皇」の「密勅」により「寛朝大僧正」を「東国」に遣わしたことに「起源」を持ちます。
「寛朝大僧正」は、「京」の「高雄山」(神護寺)「護摩堂」の「空海」作の「不動明王像」を奉じて「東国」へ下り、翌940年(天慶3年)、「海路」にて「上総国」「尾垂浜」に上陸、「平将門」を調伏するため、「下総国」「公津ヶ原」で「不動護摩」の「儀式」を行ったそうです。
「成田山新勝寺」では、この天慶3年を「開山の年」としています。
「平将門の乱」「平定後」の永禄年間(1566年)(永禄9年)に「成田村一七軒党代表」の「名主」が「不動明王像」を背負って「遷座」され「伽藍」を建立された「場所」が、現在の「成田市」「並木町」にある「不動塚」周辺と伝えられており、「成田山発祥の地」といわれています。
「成田山新勝寺」の「寺名」ですが、「また新たに勝つ」という「語句」に因み「新勝寺」と名づけられ、「東国鎮護」の「寺院」となったそうです。
「成田山新勝寺」では、平成20年(2008年)に「開基1070年祭記念大開帳」が行われ、これにあわせて、平成19年(2007年)には「総欅造り」の「総門」が落慶され、「新勝寺」の「表玄関」として荘厳な「たたずまい」を見せています。
この「総門」は、開かれた「庶民のお寺」「成田山」と「門前町」とをつなぐ「担い手」として、「大開帳」を記念し創建されたもので、「総門」前にある「門前広場」は「参拝客」の「憩いの場」となっています。
「成田山新勝寺」ですが、「総門」をくぐって、「境内」に入ると大きな赤い「提灯」のある「仁王門」があり、「境内」には、数多くの「建造物」が立ち並んでいます。
「仁王門」から「東海道五十三次」にならった53段の「石段」を上がると、「成田山」の「シンボル」である「大本堂」が現れ、「成田山新勝寺」「大本堂」では、「世界平和」と「人々の幸せ」を願って「開山」以来毎日欠かさずに「御護摩祈祷」が厳修されています。
「成田山新勝寺」の「伽藍」ですが、「JR」および「京成電鉄」の「成田駅」から「成田山新勝寺」への「参道」が伸び、「参道」を10分ほど歩き、急な「石段」を上った先の「台地上」に「境内」が広がっています。
「石段」の途中に「仁王門」、「石段」を上った先に正面に「大本堂」、その手前「右手」に「三重塔」、「鐘楼」、「一切経堂」等が建っています。
この他、「大本堂」の「左手」に「釈迦堂」、「大本堂」の背後の一段高くなった地には「額堂」、「光明堂」、「開山堂」、「成田山平和大塔」(2012年5月7日のブログ参照)等が建っており、「境内」の「東側」は広大な「成田山公園」(2011年11月8日・2010年11月12日のブログ参照)があります。
「成田山新勝寺」にある「釈迦堂」、「光明堂」、「成田山表参道」にある「薬師堂」(2013年5月22日のブログ参照)ですが、「歴代」の「成田山」の「大本堂」です。
これほどの数の「御堂」が現存している「寺院」は大変珍しく、それぞれの「建物」には「建立時」の「建築様式」を今に伝えており、江戸中期から末期の「建物」である「仁王門」、「三重塔」、「釈迦堂」、「額堂」、「光明堂」の5棟が「国」の「重要文化財」に指定されています。
「成田山新勝寺」「大本堂」の「奥」にある165000平方mもの「広大」な「広さ」を誇る「成田山公園」は、「春の訪れ」を告げる「梅」、「桜」、そして「新緑」と、「秋」の「紅葉」、「雪景色」など、「四季折々」の「表情」を楽しむことができる「憩いの場」として、「成田山」の「ご参詣」の「皆様」や、「市民」から大変親しまれています。
「成田山公園」は、「旧・齋藤家」「夏の別荘」や、「澁澤榮一邸」等を手がけた「庭師」、「2代目」「松本幾次郎」により昭和3年(1928年)に完成しました。
以来、「自然」が織り成す「四季」を通じて変化に富んだ、「日本庭園」ならではの情緒豊かな「風景」を作り出し、「野鳥」や、「虫たち」の「オアシス」となるほど「自然」に近い「状態」の「公園」として、幾年ものあいだ大切に守られてきました。
「成田山公園」「園内」「各所」には、「松尾芭蕉」や、「高浜虚子」等、「著名」な「文人達」の「句碑」が建っており、当時の「成田」でも「俳句」や、「歌」をたしなんでいたという事を物語っており、「公園」の「自然」の中にも様々な「先人の知識」や、「足跡」が残されています。
「成田山新勝寺」「大本堂」の「奥」に広がる「風光明媚」な「成田山公園」では、「四季折々」の「草花」や、「風景」を楽しむことができ、「平均樹齢」50年を越える約500本の「紅梅」や、「白梅」が植えられています。
「成田山公園」の「梅」は、例年2月中旬から3月中旬にかけて咲き、「成田山公園」は「梅の香り」でいっぱいになります。
「成田の梅まつり」(2016年2月18日・2015年2月17日・2014年2月16日・2013年2月11日・2012年2月9日・2011年2月10日のブログ参照)は、「成田山公園」を「会場」に行われている「催し」で、「成田」の「新春・恒例行事」として、「園内」の「梅」が色づく2月から3月にかけて行われています。
「成田の梅まつり」は、毎年約1ヶ月間にわたり開催され、「期間中」の「週末」を中心に様々な「イベント」を開催、訪れる方に「おもてなし」を行っています。
「平成29年成田の梅まつり」ですが、2月18日(土)から3月5日(日)までの「期間」、「成田山公園」を「会場」に行われ、「期間中」の各「土・日曜」に「イベント」を開催するそうです。
「平成29年成田の梅まつり」「期間中」の「イベント」ですが、「観梅の演奏会」、「甘酒進上」、「表千家観梅の野点」、「観梅の投句コンテスト」、「氷の彫刻展」、「草木染」「華の集い展」となっています。
「観梅の演奏会」は、「成田山公園」の「梅」を愛(メ)でながら「伝統音楽」を楽しむ「催し」で、毎回大勢の「お客様」が「春」を奏でる「音色」に耳を傾け、「好評」を得ている「催し」です。
「観梅の演奏会」「演奏会場」は、「成田山公園」内の「西洋庭園」で、「伝統音楽」の「演奏会」を行います。
「観梅の演奏会」は、11時00分からと、13時30分からの1日2回行われ、「開催日」、「演奏会出演者」は、下記の通りです。
2月18日(土) 筝 (清翔会)・尺八 (竹樹会)
2月19日(日) 筝 (清翔会)・尺八 (竹樹会)
2月25日(土) 津軽三味線 (通若会社中)
2月26日(日) 津軽三味線 (佐藤通弘・通芳)、民謡
3月4日(土) 二胡 (ワン・シャオフォン)
3月5日(日) 二胡 (ワン・シャオフォン)
「甘酒進上」ですが、「米麹」を使って、その場で、手作りした「甘酒」を「無料」で配る「おもてなし」で、ほんのりとした「甘さ」は、「公園散策」で冷えた「指先」や、「体」を芯から温めてくれます。
「甘酒進上」は、「期間中」の各「土・日曜」の10時00分から15時00分まで「成田山公園」「園内」「西洋庭園」にてふるまわれます。
「表千家観梅の野点」は、「表千家成田市茶道会」の「協力」により、「無料」で行われる「催し」で、「期間中」の各「土・日曜」に開催され、「会場」は、「文殊の池」上「梅林」、10時00分から15時00分(受付終了は14時30分)まで行われます。
「表千家観梅の野点」「先生」の「スケジュール」は、下記の通りです。
2月18日(土) 八尾 宗保 先生
2月19日(日) 矢澤 宗文 先生
2月25日(土) 行方 宗岑 先生
2月26日(日) 阿地 宗玲 先生
3月4日(土) 熊谷 宗光 先生
3月5日(日) 諸岡 宗清 先生
となっており、「表千家観梅の野点」では、初めて「お茶」を召し上がる方でも気軽に参加できるそうです。
「観梅の投句コンテスト」は、「成田の梅まつり」「恒例」の「投句コンテスト」で、「兼題」は「梅」となっており、1人2句以内「未発表」の「作品」に限り応募・受付しています。
「観梅の投句コンテスト」の「投函箱設置場所」は、「成田山公園」「西洋庭園」及び「宗吾霊堂」(2010年12月23日のブログ参照)「大本堂」前に設置されるそうです。
「観梅の投句コンテスト」の「賞」は、「秀句」9句、「入選」20句となっており、「秀句」9句は、下記の「賞」となっています。
成田山新勝寺貫主賞
成田市長賞
成田市議会議長賞
京成電鉄株式会社賞
JR成田駅賞
宗吾霊堂賞
三橋鷹女賞
成田商工会議所賞
一般社団法人成田市観光協会賞
「氷の彫刻展」は、「期間中」の「最終日」3月5日(日)に「成田山新勝寺」「大本堂」前「広場」周辺で開催される「イベント」で、「氷の彫刻展」では、四角い「氷柱」を「職人たち」の手により、様々な形に作り上げていく様子を目の前で見ることができ、「冬」ならではの「氷の彫刻展」が並ぶ様は圧巻だそうです。
「氷の彫刻展」「スケジュール」は、下記の通りです。
10時15分 開会式
(大本堂正面階段踊り場/雨天時・第一講堂)
10時30分 競技開始
12時30分 競技終了・審査
13時00分 特別大護摩参詣「成功成就」
14時15分 表彰式
「草木染」「華の集い展」は、2月26日(日)から3月5日(日)までの「期間」、「成田観光館」で行われる「展示会」で、「自然」の「草花」を「染料」として、「スカーフ」や、「タペストリー」等の「大小」様々な「布地」に染み込んだ「作品」が展示され、「自然」の持つ「色彩」を堪能できるそうです。
「草木染」「華の集い展」ですが、9時00分から17時00分まで(入館は16時30分まで)となっており、「月曜日」は「休館」となっています。
「四季折々」の「表情」を見せる「風光明媚」な「庭園」が美しい「成田山公園」で開催される「新春・恒例」の「催し」「平成29年成田の梅まつり」。
この機会に「成田市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「平成29年成田の梅まつり」詳細
開催期間 2月18日(土)〜3月5日(日)
開催時間 10時〜15時
開催会場 成田山公園 成田市成田1
備考
「平成29年成田の梅まつり」でふるまわれる「甘酒」ですが、弘化4年(1847年)頃「創業」の「糀店」の「麹」を使用しており、「天然」の「甘味」が利いた「糀」の「甘酒」となっています。
なお「甘酒進上」ですが、「雨天」の場合、「中止」だそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3327 |
| 地域情報::成田 | 10:54 AM |
|
|
2017,02,15, Wednesday
本日ご案内するのは、地元「銚子市」「浄国寺」で2月16日(木)に開催されます「浄国寺お宝めぐり」です。
「浄国寺」(2010年11月23日のブログ参照)ですが、「銚子市」「春日町」に鎮座する「一立山 無衰院 浄国寺」という「浄土宗」の「寺院」で、「浄国寺」の「御本尊」ですが、「阿弥陀如来」、「浄国寺」の「創建」ですが、建長7年(1255年)「記主禅師」「浄土宗第三祖良忠上人」(然阿良忠(ネンナリョウチュウ)上人)が開山したと伝えられています。
「浄土宗」「所蔵」「海上郡浄国寺事実」(1728年)によると、「浄国寺」の「開基事実」を尋ねても定かではなく、「開創時」の「資料」の無いことを嘆いており、「中興」・「啅助上人」は、この地が、「良忠上人」「縁故の地」であるとして「庵」を結んだとあり、その後、寛文元年(1661年)「顕誉智典上人」が「庵」を訪ね、現在の地に「一寺」を建立することを願い、「深川霊厳寺」の「末寺」となり、「立山無衰院浄国寺」と号したとあるそうです。
この「寺号」に関して、「浄国寺」「所蔵」の「称賛寺規式条々」(「海上氏」「菩提寺」の「寺内法度」)「裏書」には、「海上氏」が滅び、「称賛寺」も衰退してしまい、現在の地に再建しましたが、「東照山称賛寺」の「寺号」が「徳川家」に憚(ハバ)られるので、「熊野権現」の「夢告」に従い、今の「山号」・「寺号」を決めたと記されており、「寺内法度」である「規式条々」正和元年(1312年)の他、「海上氏」「当主」の「烏帽子(エボシ)」、「海上胤秀」・「内室妙考」・「蔵人親子の像」が伝わっているそうです。
(「三像」は「戦災」で「焼失」)
「浄国寺」「境内」の「概観」等ですが、その後、延宝から正徳年間に出来上がったもので、「深川霊厳寺志」には
「開山記主禅師東関開創四八字随一云々」
とあり、江戸期には「銚子」の「興隆」と共に発展しましたが、享保8年(1723年)と、「太平洋戦争」で、「諸堂」「字」を焼失してしまったそうで、現在の「浄国寺」「本堂」ですが、昭和37年(1962年)に再建、「浄国寺」「山門」ですが、平成15年(2003年)に再建されています。
現在の「浄国寺」ですが、「千葉県下」「浄土宗」「寺院」「筆頭」の「別格寺院」となっています。
「浄国寺」の「西北」には、「望西台」と呼ばれる「高台」があり、明和年間(1764年〜1771年)に、この台にあった「日観亭」という「庵」で、「望西八景」の「歌会」が行われ、文化・文政年間(1804年〜1818年・1818年〜1830年)には、多くの「文人」・「墨客」が訪れており、「夏目成美」の「序」で始まる「墨画帖」には、「小林一茶」・「渡辺華山」等、多くの「文人」・「墨客」の「筆」が、「浄国寺」に残されているそうです。
尚、「望西台」ですが、「浄国寺」「墓地」の一番「西側」にあり、かつては「眼下」に「銚子」の「市街地」や、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)、「茨城県」「波崎方面」(茨城県神栖市方面)が望めたようで、ここで詠まれた「句」が、「浄国寺」に残っているそうです。
しかし現在は、「浄国寺」「崖下」近くに「住宅」や、「アパート」が建ち、「往時」の「面影」が薄らいでいるそうですが、平成17年(2005年)7月、「浄国寺」・「檀徒総代」・「鴎俳句会(カモメハイクカイ)」等の手によって、「浄国寺」「所蔵」の「墨画帖(ボクガチョウ)」に書かれている
この台の清風ただちに心涼しく 西方仏土(サイホウブッド)もかくやあらんと
ほととぎす 爰(ココ)をさること 遠からず 一茶坊
と刻んだ「句碑」が建立されています。
また「浄国寺」「境内」には、これら「文人」・「墨客」に尽くした「行方屋」・「桂丸」(大里家)の建立した「芭蕉句碑」(松尾芭蕉)、近年、上述の「浄国寺」に建てられた「一茶句碑」等があります。
また「浄国寺」には、
古池や 蛙(カワズ)飛び込む 水の音
等の「俳句」を残した江戸時代の「俳人」「松尾芭蕉」の「碑文」
枯枝に からすのとまりけり 秋の暮 はせお
という「句碑」が、「浄国寺」「本堂」「左側」の「熊野大権現」の「側(ソバ)」にあります。
この「句」は、
つるべ落としの秋の陽が西山に傾く頃、ふと見上げた大木の枝に葉が一枚もなく、1羽のカラスがとまっているのがなんともいえず淋しい
という「意味」なのだそうで、この「碑」は「高さ」1m25cmの「自然石」で、「桂丸(カツラマル)」(「銚子」の「俳人」、「大里庄治郎家」「六代目」で、「名」を「富文」という)と、「野崎小平次(ノザキコヘイジ)」によって、弘化2年(1845年)に建立されたそうです。
「松尾芭蕉」の「句碑」の「説明板」には、下記の「文言」が記されています。
広大な浄国寺境内の夕暮れには、今でもこうした情景に出会いそうです。
芭蕉がこの寺を訪ねた記録はありませんが、檀家の行方屋庄次郎(俳号桂丸)が、句碑の片隅に「あきの夕(ユウ) 誰(タ)が身のうへぞ 鐘がなる」の句が添えてあります。
地元の豪商大里庄次郎と野崎小平次が、俳聖(ハイセイ)芭蕉を追慕して弘化2年に建てました。
〜原文まま表記〜
ちなみに「大里庄治郎家」(行方屋(ナメガタヤ))ですが、「茨城県」「行方市」の「出身」で、「行方屋」は「銚子」で「御殻宿」(東北諸藩廻米問屋)として「銚子湊」の「繁栄」を支えたそうです。
また「大里庄治郎家」は、「銚子」を代表する「旧家」で、「銚子市長」や、「銚子市議会議長」、「銚子商工会議所会頭」等を代々務めた「家柄」なのだそうです。
「浄国寺」には、その他「墓地内」に「詩人」・「宮崎丈二の墓」があり、「江戸相撲」の「長老」であった「初代 千賀ノ浦 関」の「墓」、「酒仏」とも呼ばれ、「酒」に関する「祈願」・「願掛け」をする「酒徳利」・「猪口」・「御膳」の形をした「お墓」(「鈴木玄庵」という「医師」の「墓」、「師」の「人徳」を慕う「人々」が没後、建立し、礼拝、祈願をするようになった)等があります。
「浄国寺」「年中行事」は、下記の通りです。
1月1日 修正会(シュショウエ)
3月8日(旧暦) 徳本上人奉賛大施餓会(トクホンショウニンホウサンオオセガキエ)
併修、外川・阿姫(おさつ)供養 (外川漁港・高神)
3月 春季彼岸会(シュンキヒガンエ)
4月8日 釈尊降誕会(シャクソンコウタンエ)
7月 お盆・棚行(タナギョウ) (東京近郊)
8月1日〜7日 新盆七日法要
8月13日〜15日 お盆・棚行
8月16日 施餓鬼会
8月24日 地蔵盆
8月24日 川口千人塚施餓鬼会
9月 秋季彼岸会
10月第3土曜日 十夜法要・書道展
12月31日 除夜の鐘
「浄国寺」では、平成23年(2011年)11月に、「東日本大震災」と、「福島第一原発事故」で、「避難生活」を余儀なくされていた「福島県」「相馬市」の「小学生」を「銚子」に招いた「子ども寺子屋イン銚子」(2011年11月24日のブログ参照)を開催しました。
「子ども寺子屋イン銚子」では、「福島県」「相馬市」の「小学生」が、「銚子」の「小学生」と交流し、「地球の丸く見える丘展望館」(2010年8月30日のブログ参照)や、「犬吠埼」(2012年4月16日のブログ参照)、「犬吠埼灯台」(2011年1月1日のブログ参照)を観光した他、「銚子駅前イルミネーション事業」「LIGHTING CEREMONY(点灯式)」(2011年11月23日のブログ参照)に参加、「浄国寺」にて「チャリティ・コンサート」に参加されています。
「浄国寺」「境内」には、「樹齢」100年にも及ぶ「雌雄一対」の「大銀杏」や、「松」、「梅」等の「古木」が立ち並び、「梅」の「開花時期」には、多くの「観梅客」や、「参拝客」の「人々」が訪れます。
「浄国寺」「境内」の「庭」は、「銚子」の「おすすめ観光スポット」のひとつで、中でも「樹齢」300年以上になる「紅梅」・「白梅」が美しい「梅の木」が有名です。
「浄国寺」の「梅」(2011年2月4日のブログ参照)ですが、「銚子地方」の「梅」の「標本木」(標準木)であり、「銚子」の「春の訪れ」を知らせる「木」として知られています。
「由緒」ある「寺院」「浄国寺」では、2月16日(木)10時00分から15時00分まで「浄国寺お宝めぐり」を開催するそうです。
「浄国寺お宝めぐり」ですが、通常「一般公開」されていない「小林一茶」、「渡辺華山」の「直筆」の「書」や、「徳本上人諸侍記」、「釈迦涅槃御掛軸」、「地獄図御掛軸」等、「浄国寺」「所蔵」の「宝物」が「年」に一度、「開催当日」に限り「特別公開」されるそうです。
なお「浄国寺お宝めぐり」ですが、「無料」で参加できるそうです。
「銚子」の「名刹」「浄国寺」で開催される「浄国寺」「寺宝」を公開する「年」に一度の「特別公開」「浄国寺お宝めぐり」。
この機会に「銚子市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「浄国寺お宝めぐり」詳細
開催日時 2月16日(木) 10時〜15時
開催会場 浄国寺 銚子市春日町23
問合わせ 銚子市観光商工課 0479-24-8707
備考
「銚子地方気象台」(2011年1月5日のブログ参照)によりますと、1月17日(火)に「職員」が、「浄国寺」「境内」にある「樹齢」300年以上の「銚子地方」の「梅」の「標本木」(標準木)の「開花」を確認されたそうです。
「浄国寺」の「梅」の「開花」ですが、昨年(2016年)より1日遅い「開花」であったそうで、平年(1月20日)と比べ3日早い「開花」だったそうです。
ちなみに「銚子地方」の「標本木」(標準木)「浄国寺」の「梅」の「花」の「最早」の「開花日」ですが、1998年(平成10年)1月3日だったそうで、「最晩」の「開花日」ですが、1967年(昭和42年)2月26日だったそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3324 |
| 地域情報::銚子 | 09:48 AM |
|
|
2017,02,13, Monday
本日ご案内するのは、地元「銚子市」「飯沼山圓(円)福寺」「大師堂」で2月14日(火)・15日(水)に開催されます「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」、「釈迦涅槃図公開」です。
「円福寺」(圓福寺)こと「飯沼山圓(円)福寺」(2012年2月19日のブログ参照)は、「真言宗」の「寺院」で、「山号」は「飯沼山」、「御本尊」は「十一面観世音菩薩」です。
「飯沼の観音さま」「銚子の観音さま」として知られる「飯沼山圓(円)福寺」は、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)の「河口」、「日本一の水揚げ量」を誇る「銚子漁港」(2012年1月24日のブログ参照)(第1卸売市場)(2010年12月18日のブログ参照)の近くにあり、「銚子市」の中心に位置していたことから、「市街」は、その「門前町」として発展してきました。
「飯沼観音」(2010年11月24日のブログ参照)の「門前」「西側」は、「銚子銀座通り」(ココロード銚子)(2011年10月1日のブログ参照)となっており、「門前」「東側」には「島田総合病院」や「今川焼」の「さのや」(2010年12月16日のブログ参照)があります。
「飯沼山圓(円)福寺」ですが、「寺伝」によりますと、724年(神亀元年)「漁師」が「海」で、「十一面観世音菩薩」を「網」ですくい上げ、その後弘仁年間(810年〜824年)、この地を訪れた「弘法大師」「空海」が開眼(カイガン)したとされています。
「飯沼山圓(円)福寺」ですが、鎌倉時代以降、この地を治めた「海上氏」の「帰依」を受け、「寺運」は興隆したそうです。
天正19年、「徳川家康」に「朱印」を賜り、「諸堂」を整備、安政2年(1855年)刊の「利根川図志」では
「境内に見せ物 軽わざしばい、其外茶見世多く至って賑はし」
と、その「盛況」を写しており、「円福寺」(圓福寺)は「隆盛」を極めていたそうです。
しかし、1945年(昭和20年)「銚子大空襲」があり、「多宝塔」以下「観音堂」、「仁王門」、「鐘楼」、「太子堂」、「馬頭観音堂」、「二十三夜堂」、「茶枳尼天堂」、「龍蔵大権現堂」など「諸堂」を焼失したそうです。
その後、「銚子のシンボル」である「観音堂」の「再建」は、昭和46年(1971年)に「衆庶」の「信助」により「見事」に完了。
「飯沼観音」の「境内」の「大仏」は「銚子」「近在」の「人たち」の「喜捨」で、正徳4年(1714年)に鋳造され、平成20年(2008年)「五重塔」(形式「三間五重塔婆」「総高」33.5m)の「完成」に伴い、現在の「場所」に移っています。
「飯沼観音」ですが、「一般」に「観音さま」の「呼び名」で親しまれており、「飯沼観音」「境内」には、「江戸」の「豪商」・「古帳庵」の「句碑」などがあり、「日本」における「河川測量」の「原点」である「飯沼水準原標石(イイヌマスイジュンゲンショウセキ)」が存在し、「文化財」としても、「歴史的」、「学術的」にも「価値」があるそうです。
1872年(明治5年)12月「オランダ人」「リンド」により「水準原標石(スイジュンゲンショウセキ)」(2011年2月21日のブログ参照)が設置され、これを「起点」として「日本水位尺」が定められたそうです。
「水準原標」とは、「水準測量」(「高さ」を測る「測量」)を行う「時」の「原点」となる「点」のことだそうです。
また「飯沼観音」は、「坂東三十三観音霊場(バンドウサンジュウサンカンノンレイジョウ)」(2010年10月13日のブログ参照)の「二十七番札所」として「信仰」を集めています。
なお、「飯沼山圓(円)福寺」、「飯沼観音」ですが、「日本百観音」、「西国三十三所」、「坂東三十三所」、「秩父三十四所」となっています。
この度(タビ)「飯沼山圓(円)福寺」、「飯沼観音」では、2月14日(火)・15日(水)9時00分から16時00分までの2日間、「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「釈迦涅槃図公開」を開催するそうです。
「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「釈迦涅槃図公開」ですが、「由緒」ある「飯沼山圓(円)福寺」、「飯沼観音」に所蔵されている「寺宝」の「一部」を「拝観無料」で公開している「人気」の「催し」で、毎回「大勢」の「観光客」、「歴史ファン」、「マニア」の「方々」で賑わっています。
「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「釈迦涅槃図公開」開催に伴い、「飯沼山圓(円)福寺」では、下記のような「挨拶」で「御来場」を呼びかけています。
寺宝展も今回で6回目となります。
これまでの展示会で毎回
「これが読めたらもっと楽しいだろうねえ。」
という感想を頂戴いたしました。
そこで今回は、13世紀から18世紀の21点を選んで、展示部分の文字を現代の文字に改めたものを添えてみました。
古い書物を見るだけではなく、読む楽しみも味わっていただければと思います。
文字には書かれた時代や書いた人の個性が表れます。
どんな時代だったのだろう、どんな人が書いたのだろうと、想像をめぐらせながら御覧になるのも面白いのではないでしょうか。
〜文中まま表記〜
「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「釈迦涅槃図公開」の「内容」ですが、13世紀から18世紀の21点を選んで、「展示部分」の「文字」を、現代の「文字」に改めたものが添えてある「寺宝展」で、「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」では、「読む楽しみ」が味わえると共に、「文字」から時代や「人物」を想像しながら御覧いただけるそうです。
また「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」では、「佐々木孝浩」「教授」による「解説」が行われ、「午前の部」11時00分から、「午後の部」14時00分からとなっており、「両日」とも1日2回開催、「参加」無料、「各回」「定員」150人となっています。
「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「釈迦涅槃図公開」に出展される「展示品」は、下記の通りです。
「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「出典作品」
源氏物語(ゲンジモノガタリ) 幻(マボロシ) (鎌倉初期)
源氏物語(ゲンジモノガタリ) 夕霧(ユウギリ) (鎌倉中期)
古今和歌集(コキンワカシュウ) 20巻存巻4 (鎌倉後期)
伊勢物語(イセモノガタリ) (南北朝期)
古今和歌集(コキンワカシュウ) 20巻 (室町前中期)
着到和歌(チャクトウワカ) (文明12年(1480)10月22日〜11月1日)
本阿弥光悦筆古歌巻(ホンアミコウエツヒツコカカン) (江戸初期)
伊勢物語(イセモノガタリ) 伝小堀宗甫畢 (江戸前期)
東岸居士(トウガンコジ) (寛永元年(1624))
鉢かつき(ハチカツキ) 3巻 (江戸前期)
竹取物語(タケトリモノガタリ) 3巻 (江戸前期)
伊勢物語(イセモノガタリ) 2巻 (慶長13年(1608))
徒然草 2巻 (慶長17年(1612))
光悦謡本(コウエツタイボン) 実盛(サネモリ) (慶長)
三十六人歌合(サンジュウロクニンウタアワセ) 1冊 (慶長)
八島(ヤシマ) (寛永)
平家物語(ヘイケモノガタリ) 12巻 (延宝5年(1677))
好色一代女(コウショクイチダイオンナ) 6巻 井原西鶴著 (貞享3年(1686))
恋女房染分茶番(コイニョウボウソメワケチャバン) 3巻 櫻川慈悲成著/歌川豊国画 (寛政4年(1792))
風流錦絵 伊勢物語(フウリュウニシキエ イセモノガタリ) (明和7年(1770))
援山三十六歌仙(エンザンサンジュウロッカセン) (天明9年(1789))
また「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「釈迦涅槃図公開」では、「釈迦涅槃図公開」も開催され、2月14日(火)・15日(水)9時00分から16時00分まで行われます。
「釈迦涅槃図公開」の「イベント内容」ですが、「釈迦涅槃図」(千葉県指定有形文化財)の「ご開帳」や、「飯沼山圓(円)福寺」に伝わる「寺宝」等の「一般公開」を行うそうです。
また「釈迦涅槃図公開」では、「銚子観光ボランティアガイド」「観光船頭会」「有志」による「お宝」の「案内」もあるそうです。
「釈迦涅槃図公開」では、「法会」「釈迦涅槃会」も開催され、「詳細」は、下記の通りです。
「法会」「釈迦涅槃会」詳細
開催日時 2月15日(水) 10時〜
開催場所 飯沼山圓(円)福寺 涅槃堂 銚子市馬場町292
なお「飯沼山圓(円)福寺」、「飯沼観音」の「寺内」の「お宝案内」は、下記の通りです。
梵鐘「県指定有形文化財」(本坊)
北斎二世の絵馬(本坊)
大銅壺(本坊)
龍伝 水戸光圀公筆(本坊)
古帳庵句碑(境内)
龍神 船首像(境内)
飯沼水準原標石(飯沼観音境内)
また「飯沼観音」「本堂」では、「特別展示物」「直筆」の「原稿」が展示され、「飯沼観音」「本堂」「特別展示物」は、下記の通りです。
芥川龍之介 俊寛-硫黄が島
芥川龍之介 鸚鵡
芥川龍之介 保吉の手帳
泉鏡花 夜釣
泉鏡花 婦系図 第九十五
歌川龍平 泥棒の弟子入
賀川豊彦 欧米の宗教的断層
金子薫園 宇治の夜のこと
岸本水府 三味線
北原白秋 香炎華序
齋藤茂吉 冬探し
佐藤春夫 海棠日記抄
田中貢太郎 雑木林の中
田中貢太郎 真珠飾の帽子
谷崎精二 盗み
永田幹生 青春の夢 二の三
成瀬無極 四十歳
林芙美子 春の夜店で
日夏耿之介 詩集 黒衣聖母
前田曙山 緋金襴 三
三木露風 南面の窓
三木露風 清明な世界
宮崎安右衛門 受難より復活へ
室生犀星 吉田三郎と僕
与謝野晶子 江楼夢
与謝野晶子 家・町
吉井勇 地異記
吉井勇 紅声窩小吟
吉田紘二郎 木槿咲く
若山牧水 曇り日の座談
若山牧水 秋風の歌
「由緒」ある「寺院」「飯沼山圓(円)福寺」「大師堂」で開催される「貴重」な「嵯峨本」を拝観できる「催し」「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」、「千葉県指定有形文化財」の「特別公開」「釈迦涅槃図公開」。
この機会に「銚子市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「釈迦涅槃図公開」詳細
開催日時 2月14日(火)・15日(水) 9時〜16時
開催会場 飯沼山圓(円)福寺大師堂 銚子市馬場町292
問合わせ 飯沼山圓(円)福寺 0479-22-1741
備考
「第6回寺宝展〜くずし字を読んでみよう〜」「釈迦涅槃図公開」ですが、「主催」「飯沼山圓(円)福寺」、「後援」「銚子市」、「銚子市教育委員会」、「協力」「慶應義塾大学附属研究所斯道文庫」、「銚子市観光協会」、「島長水産」、「一山いけす」、「銚子電気鉄道」(2012年2月11日のブログ参照)により、開催されます。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3323 |
| 地域情報::銚子 | 09:48 AM |
|
|
2017,02,11, Saturday
本日ご紹介するのは、近隣市「匝瑳市」「ふれあいパーク八日市場」で2月12日(日)に開催されます「ベーコン・燻製卵づくり体験」です。
「ふれあいパーク八日市場」(2012年6月16日・5月1日・2010年9月11日のブログ参照)は、「東関東自動車道」「成田IC(成田インターチェンジ)」から「国道295号線」・「国道296号線」を「匝瑳市」「方面」に向かい、「東総広域農道」「入口」を「左折」し、「東総広域農道」を約7km(「成田IC」より約30分)、「県道八日市場・山田線」「交差点」にあります。
また「地域高規格道路」「千葉東金道路」(「東金有料」・「東金道」)「銚子連絡道」「横芝光IC(よこしばひかりインターチェンジ)」からは、「国道126号線」を「匝瑳市」「方面」に向かい、「県道八日市場・山田線」へ入り、約4km(「横芝光IC」から約30分)、「東総広域農道」との「交差点」に「ふれあいパーク八日市場」があります。
「ふれあいパーク八日市場」には、1.5ha(ヘクタール)の「敷地」に「普通車」83台、「大型車」3台を収容できる「駐車場」を完備しています。
のどかな「田園風景」が広がる「匝瑳市」にある「ふれあいパーク八日市場」は、「安心・安全・新鮮な農産物、こだわりの匝瑳市産」を「皆様」にお届けするために、平成14年(2002年)3月17日に「産声」をあげた「都市と農村交流ターミナル」です。
「ふれあいパーク八日市場」では、「匝瑳」の「大地」をこよなく愛する「生産者」が、「手塩」をかけた「恵み」の「農産物」等の「数々」を、「見て・触って・食して」お楽しみいただける「施設」となっています。
「ふれあいパーク八日市場」ですが、2002年(平成14年)3月の「開館」以来、「施設」の「運用面」(交流・イベント、直売、レストラン運営事業等)については、「八日市場市ふるさと交流協会」(「合併後」は「八日市場ふるさと交流協会」に名称変更)が行っていましたが、「事業」を「継続」・「拡大」していく中で、「協会」が保有する「資産」や「雇用者数」が増加し、「財務運営」や「雇用計画」等について、「協会」は「法人格」を持たない「任意的団体」であったため、その「代表者」が「無限責任」を追わなければならないという「問題」が顕著となり、そこで「行政」としても何らかな「法人格」を有する「組織形態」への「移行」を検討する「必要」があると考え、「匝瑳市」と「協会」との「双方」で「法人化」を目指すことで「意見」が一致したそうです。
「ふれあいパーク八日市場」の「法人形態」に関しては、「協会」と「匝瑳市」の「間」で「数回」の「協議」を重ね、主に下記の「理由」から「第3セクター方式」による「有限会社」の「設立」を進めることで「結論」に達したそうです。
1 協会単独で有限会社になることは、ふれあいパーク八日市場が公共施設であるため難しいこと
2 NPO法人、株式会社についても検討したが、両法人形態の有する性質上、協会単独での法人化は困難であること。
3 第3セクター方式による有限会社形態をとることにより、公共施設の利用、交流協会の財務運営等について、官民一体となってすすめることが可能であること。
「第3セクター」による「有限会社」の「設立」に関して「協議」をする「機関」として「ふるさと交流協会第3セクター設立検討委員会」を設立したそうです。
「委員会」の「委員」には、「市」3名、「協会」3名、「農協」2名、「市観光協会」1名の「計」9名で構成し、「法人設立」を目指して「検討」を重ね、また「専門的」な「アドバイザー」として「千葉県農業会議」及び「会計事務所会計士」に「必要」な応じて「出席」を依頼したそうです。
なお、「委員会」においての「検討事項」ですが、「商号」、「資本金」、「社員」その「出資割合」、「役員」と、その「報酬」及び「営業年度」などであったそうです。
以上の「経緯」から、2005年(平成17年)12月1日に、「都市交流事業」・「各種イベント」の「企画運営」、「直売事業」、「レストラン運営」等を「目的」とする「ふれあいパーク八日市場有限会社」が設立されました。
「ふれあいパーク八日市場」の「会社概要」は、下記の通りです。
商号 ふれあいパーク八日市場有限会社
事業内容 都市と農村交流ターミナル
設立 平成13年11月1日
所在地 千葉県匝瑳市飯塚299-2
TEL 0479-70-5080 FAX 0479-70-5081
納入会員 ふるさと交流協会 会員数 128名
「ふれあいパーク八日市場」の「施設概要」ですが、「店舗」「入口」を入りますと、向かって「右側」に「農特産物コーナー」、「左側」に「文化コーナー」があります。
「ふれあいパーク八日市場」「農特産品コーナー」の「メイン」で販売しているのが、「匝瑳市産野菜」で「キャベツ」、「ほうれん草」、「小松菜」、「トマト」などが「定番商品」で、どれをとっても「質」が良いと言われています。
また「ふれあいパーク八日市場」の「人気」の「秘密」ですが、「野菜」だけではなく、「農特産物」の「加工品」がとても「豊富」で、中でも「棒もち」、「卵焼き」、「卵焼きで巻いた太巻き寿司」等「人気」の「加工品」を求めに「近隣」から来店される「方」が多いそうです。
「ふれあいパーク八日市場」「店舗」「左奥」に「匝瑳産」の「食材」をふんだんに使った「料理」を提供している「レストラン」「里の香」があります。
また「匝瑳市」は、「日本有数の植木のまち」として知られており、「ふれあいパーク八日市場」「店舗」(本館)の「外」「西側」には「花・植木見本園」が設置されており、また「ふれあいパーク八日市場」「店舗」(本館)を抜けると、隣接する「飯塚沼農村公園」に行くこともできます。
「ふれあいパーク八日市場」では、「匝瑳産」の「新鮮な農産物」や、懐かしい「ふるさとの味」に出会える「憩いの場」として、「匝瑳市民」はもとより「近隣市町村」からも「大勢」の「来客」のある「人気スポット」となっています。
また「ふれあいパーク八日市場」では、「なにかがあるふれあいパーク」を「キャッチフレーズ」に、「毎週末」や「祝祭日」に、いろいろな「イベント」を行っています。
「ベーコン」(Bacon)とは、「豚肉」を「塩漬け」して「燻製」にしたものです。
「ベーコン」ですが、本来は「豚」は「半丸枝肉」を「塩漬け」し「燻煙」した「サイドベーコン」ですが、「日本」では「バラ肉」の「部位」を用いたものを特に「ベーコン」といい、他の「部位」は「ロースベーコン」、「ショルダーベーコン」等というそうで、なお「モモ肉」の「部位」は「ハム」にし、「ベーコン」には加工しないそうです。
「英語」の「Bacon」ですが、「ゲルマン語」から「古フランス語」「経由」で借用した「語」で、本来は「背中」の「肉」(ロース)を意味しており、おそらく「back」と「語源的」に関係があるようです。
本来の「ベーコン」は「背中」や、「脇腹」の「肉」を使用するもので、「ヨーロッパ」では実際にそうしていますが、「北アメリカ」で「バラ肉」から作られるようになり、その「習慣」が「日本」にも伝わったそうです。
「ベーコン」の「製法」は、下記の通りです。
1 豚のバラ肉を血絞りする。
2 肉重量の3〜6%の食塩と、砂糖・香辛料等の調味料を加え漬け置きする(塩せき)。
※工業的に作る場合、さらに発色剤・防腐剤等の食品添加物類も添加されることが多い。
3 塩抜きをする。
4 燻煙する。
※工業的に安価に作る場合、燻煙に合わせて、燻液を使うこともあります。
「ベーコン」の「利用方法」ですが、「具材」兼「調味料」として用いられ、「ほうれん草」等の「野菜」と炒めたり、「スープ」に入れたり、「サラダ」に散らして「香り」と、「旨味」を付与する等、「多方面」に利用できる「食材」でもあります。
なお、「日本」では「鯨肉」の「畝須」の「部位」を、「鯨のベーコン」と呼び、昭和30〜50年代初頭までは、「豚肉」の「ベーコン」同様に一般的に食されていました。
また「アメリカ合衆国」では、「脂肪分」の多い「バラ肉」を用いる「ベーコン」は1980年代以降の「健康ブーム」で一時期敬遠され「売り上げ」を落としましたが、その後「風味づけ」のための利用が見直され、また「油脂」による「汚れ」を出さない「調理法」等の「研究」が進んだことから、「ファーストフード店」や、「レストラン」等を起点に2000年代頃から「ブーム」が起きました。
「燻製」とは、「煙」を使って「食べ物」を加工する事、または加工して作られた物で、特定の「素材」を使い「煙」を起こし作ります。
「燻製」は、「人類」が「火」を利用しはじめた太古の時代からの「調理法」のひとつとされ、「食材」を燻すことで、「保存性」を高め、独特の「風味」をつけることができ、「日本」においては、「ベーコン」、「スモークサーモン」、「燻製卵」(クンタマ)等が代表的なものとして知られています。
「燻製」の「分類」ですが、「作成時」の「温度」を「基準」に大別して3つに分けられ、「温度」の高いものから、「熱燻」、「温燻」、「冷燻」となるそうです。
「熱燻」
ほぼロースト状態(大体80度以上・食材中のタンパク質が凝固)
「温燻」
じんわり温め状態(大体40度ぐらいから80度ぐらい・食材中のタンパク質が凝固しない。脂が溶けている)
「冷燻」
燻製をかけるだけ(大体40度未満・食材中の脂が溶けていない)
なお、上記の「温度」は、「目安」であり、厳密に規定されているものではありません。
「燻製」ですが、下記のような「道具」・「部材」が必要となるそうです。
燻煙材
いわゆるスモークチップ。
サクラ・ヒッコリー・リンゴ等の樹木を乾燥させチップ状にしたものや、チップを圧縮固形化したスモークウッド、また茶葉等の植物の葉や皮等も用いられる。
熱源
燻煙を出し続けるためには、熱源が必要である。
炭・薪・ガスといった直火や電熱器等が用いられる。
なお前述のスモークウッドはいわゆる線香のように点火すれば燃え尽きるまで煙を出し続けるため、熱源は不要である。
燻製器
燻煙を食材に効率よくかけることができれば、基本的には何でもよい。
そのため、市販の燻製器の他、中華なべやフライパンを用いることが出来る。
また木材やダンボール、スチールロッカー等を用いて自作することも可能。
また上質の燻製を作るためには、温度管理が必要となるため温度計、サーモスタットを用いることもある。
「燻製」に適した「食品」ですが、「燻煙」は「脂」にのりやすい(風味がつきやすい)ため、一般的には「脂質」の多い「食材」が「燻製」に適しているとされています。
逆に「食材表面」に「水分」が多いと「燻煙」が「水分」と反応し、「タール化」され、苦くなったり、酸っぱくなったりするため、不向きとされています。
「ベーコン・燻製卵づくり体験」ですが、「ふれあいパーク八日市場」で開催される「新春」の「恒例イベント」で、2月12日(日)10時00分から14時00分まで行うそうです。
「ベーコン・燻製卵づくり体験」の「定員」は20人(申し込み順)、「参加費」ですが、1000円で、「申し込み」は事前に「ふれあいパーク八日市場」までとなっています。
「ベーコン・燻製卵づくり体験」の「内容」ですが、「簡単」な「手作りベーコン」と、「燻製卵」の「作成体験」となっています。
「ベーコン・燻製卵づくり体験」が行われる「ふれあいパーク八日市場」では、「参加者」の「皆さん」に「持参品」として、「軍手」、「エプロン」、「三角巾」、「ベーコン持ち帰り用」の「容器」、「昼食」(ふれあいパーク八日市場内でも購入できます)の「持参」を呼びかけています。
「匝瑳」の「都市と農村総合交流ターミナル」「ふれあいパーク八日市場」で開催される「ふれあいパーク」「新春恒例イベント」「ベーコン・燻製卵づくり体験」。
この機会に「匝瑳市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「ベーコン・燻製卵づくり体験」詳細
開催日時 2月12日(日) 10時〜
開催会場 ふれあいパーク八日市場 匝瑳市飯塚299-2
営業時間 9時〜18時
問合わせ ふれあいパーク八日市場 0479-70-5080
備考
「日本」では普通「ベーコン」は「バラ肉」を用いますが、「ロース肉」を使ったものを「ロースベーコン」(カナディアンベーコン)、「肩肉」で作ったものを「ショルダーベーコン」というそうです。
「ベーコン」は、「弱火」でじっくりと焼くことで「油」が溶け出し、「カリカリ」に揚がった状態になり、これは「フライド・ベーコン」と呼ばれ、「ベーコンエッグ」や、「シチュー」等にも使われています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3322 |
| 地域情報::匝瑳 | 09:48 AM |
|
|
2017,02,10, Friday
本日ご紹介するのは、近隣市「芝山町」「航空科学博物館」1F「多目的ホール」で2月11日(祝・土)・12日(日)に開催されます「飛行機工作教室」です。
「航空科学博物館」(Museum of Aeronautical Sciences)(2011年6月7日のブログ参照)は、「航空」に関する「科学知識」について、その「啓発」を図り、もって「航空思想の普及」及び「航空科学技術の振興」に寄与し、あわせて「日本の航空」の「発展」に資することを「目的」に、「総合的」な「航空思想普及施設」として「成田国際空港」(2015年4月7日・2012年12月10日のブログ参照)側に平成元年(1990年)に、「山武郡」「芝山町」「岩山」に開館しました。
「航空科学博物館」ですが、「中央棟」、「西棟」、「東棟」、「展望塔」、「屋外」からなり、「地上2階一部5階」の「建物」が構成されています。
「航空科学博物館」1F「中央棟」には、「アンリ・ファルマン複葉機」の「実物大復元模型」(イラスト有り)と、「ピストン・エンジンコーナー」、「ミュージアムショップ」「バイプレーン」があり、「航空科学博物館」1F「西棟」には、「ボーイング747大型模型」(操縦体験可能・要「整理券」)と「ボーイング747」の「客室」・「コックピット」・「タイヤ」、「DC-8前脚」、「旅客機の胴体比較」(DC-8とYS-11)、「DC8シミュレーター」(パイロット訓練用シミュレーターを改修したもの)があります。
「航空科学博物館」「ミュージアムショップ」「バイプレーン」には、「航空機」の「スケールモデル」など「航空関係」の「品物」をたくさん取り揃えています。
「航空科学博物館」2F「中央棟」には、「下田画伯」の「イラスト」による「飛行機のあゆみ」と、「日本の名機」と「歴史的」な「ソリッドモデル」、「西棟」には、「小型機」・「ヘリコプター」の「コックピット」(操縦席に座れます)と「戦前」・「現在」の「パイロット」の「制服比較」、「東棟」には、「NAAコーナー」と、「エコエアポートコーナー」、「成田国際空港」を「インターネット」や「ビデオ」、「模型」等で紹介する「コーナー」があります。
「航空科学博物館」2F「東棟」にある「成田国際空港」を紹介する「NAAコーナー」は、2014年(平成26年)3月25日に「リニューアルオープン」しています。
「航空科学博物館」「NAAコーナー」は、「成田空港ジオラマ」、「音の体験ルーム」、「情報コーナー」、「エコエアポートコーナー」からなり、様々な「方向」から「成田国際空港」について学べる「施設」となっており、白く「スタイリッシュ」な「デザイン」に一新された「成田空港ジオラマ」と、「楽しく、分かりやすく」を「コンセプト」に「内容」を一新した「音の体験ルーム」がリニューアルされています。
「航空科学博物館」3Fは、「展望台」(屋上)となっており、「成田国際空港」を離着陸する「ジャンボ」を間近に眺め、迫力ある「航空機」の「エンジン音」を体験できるようになっています。
「航空科学博物館」4Fは、「展望レストラン」「バルーン」となっており、「展望レストラン」「バルーン」では、「成田国際空港」の素晴らしい「眺め」を見ながら「食事」ができます。
「航空科学博物館」5Fでは、「ガイドの説明」(土・日・祝日中心)を参考に離着陸する「ジャンボ」を見ることができるそうです。
「航空科学博物館」屋外には、「航空機」と「多目的広場」があり、「小型機」や「ヘリコプター」の「実物」を展示、「YS11試作1号機」(イラスト有り)や「セスナ195」「朝風」(イラスト有り)等があり、「有料搭乗航空機」として「プロペラ」が回る「飛行機」や「ヘリコプター」に搭乗できる「有料体験装置」があるそうです。
「航空科学博物館」の「沿革」は、下記の通りです。
1977年(昭和52年) 地元自治体の芝山町より成田空港の開港に関連した博物館建設の要望が運輸大臣に提出される。
1984年(昭和59年) 博物館の建設・運営の事業主体となる財団法人航空科学振興財団が設立。
1988年(昭和63年) 博物館工事に着工。
1989年(平成元年) 8月1日 開館。
1994年(平成6年) 入館者100万人を達成。
1999年(平成11年) 成田空港第1ターミナルビル内にミュージアムショップ「バイプレーン」を開店。
2004年(平成16年) 1月18日 入館者300万人を達成。
2011年(平成23年) 6月23日 成田国際空港株式会社が航空科学博物館敷地(駐車場)内に成田空港闘争の史実や反対派のヘルメットなどを展示した資料館「成田空港空と大地の歴史館」を建設し、開館。
2012年(平成24年) 4月1日 公益財団法人航空科学博物館に移行。
2015年(平成27年) 6月20日 博物館敷地内に「航空科学博物館バスターミナル」を開設。
「航空科学博物館」では、「航空」に関する「科学知識」に関する「講習会」、「講演会」、「見学会」、「航空教室」、「セミナー」等を開催しており、「四季折々」様々な「催し」、「イベント」を行って、「展示即売会」(航空スケッチ大会、紙飛行機工作教室、航空機の部品・航空グッズの販売を行う航空ジャンク市等)などを催行しています。
「飛行機工作教室」ですが、「航空科学博物館」「館内」1F「多目的ホール」を「会場」にして開催される「体験教室」で、「建国記念日」の2月11日(祝・土)、「翌日」の2月12日(日)の「各日」13時00分から14時30分まで行われます。
「飛行機工作教室」の「費用」は、「材料費」300円となっており、「飛行機工作教室」の「申込方法」ですが、「飛行機工作教室」「開催日」「当日」(各日)に、「航空科学博物館」「開館」(10時00分から)と同時に「受付」にて、「原則」「小学生」以上、「先着」40名に「整理券」を配布するそうです。
「飛行機工作教室」の「内容」ですが、「お子様」向けの「ゴム動力飛行機」を作って飛ばす「体験教室」となっており、また「飛行機工作教室」では、「ゴム動力飛行機」のよく飛ぶ「コツ」等も説明してくれるそうです。
「航空専門」の「博物館」「航空科学博物館」で開催される「体験教室」「飛行機工作教室」。
この機会に「芝山町」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「飛行機工作教室」詳細
開催期間 2月11日(祝・土)・12日(日)
開催時間 各日13時〜14時半
費用 材料費300円(先着40名様・原則小学生以上)
開催会場 航空科学博物館 山武郡芝山町岩山111-3
開館時間 10時〜17時(入館〜16時半)
入館料 大人 500円 中高生 300円 4才以上 200円
休館日 月曜日(月曜が祝日の場合は翌日)
問合わせ 航空科学博物館 0479-78-0557
備考
「飛行機工作教室」が開催される「航空科学博物館」周辺には、「人気」の「観光スポット」、「道の駅」「道の駅風和里しばやま」(2011年8月27日・2010年9月8日のブログ参照)、「空の駅風和里しばやま」(2012年9月5日・4月23日のブログ参照)があります。
この度(タビ)「道の駅風和里しばやま」、「空の駅風和里しばやま」では、下記「日程」で「設備点検」のため、「休館」となるそうですので、ご来訪の予定の方は、ご注意下さいとのことです。
道の駅風和里しばやま 2月22日(水)
空の駅風和里しばやま 2月23日(木)
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3320 |
| 地域情報::成田 | 10:04 AM |
|
|
2017,02,09, Thursday
本日ご案内するのは、近隣市「九十九里町」「皇産霊神社」で2月11日(祝・土)に開催されます「関万歳(セキマンザイ)」です。
「九十九里町」は、「山武郡」に属する「まち」であり、「旧・山辺郡」に属していた「まち」で、「名前」の通り「九十九里浜」(2012年5月11日のブログ参照)に面しており、「いわし」(2012年5月17日のブログ参照)の「名産地」として知られており、「千葉県」の「南東部」の「太平洋岸」に位置し、「九十九里浜」で有名です。
「九十九里町」の隣接する「自治体」は、「東金市」、「山武市」、「大網白里市」となっています。
「九十九里町」の「産業」ですが、「漁業」、「水産加工業」、「観光業」、「ガス事業」となっています。
「九十九里町」の「漁業」は、主(オモ)に「イワシまき網漁業」、「小型船」による「ハマグリ漁」、「観光遊漁船」(釣り船)の3種となっており、「九十九里町」の「漁業」は「片貝漁港」を中心に営まれています。
「片貝漁港」は、「山武郡」にある「第4種漁港」で、「九十九里平野」(2012年7月6日のブログ参照)の「中央部」を流れる「作田川」「河口」に位置し、「海岸」近くを走る「千葉県道30号線」「飯岡一宮線」沿いに「市街地」が形成されている「九十九里町」にあります。
「片貝漁港」は、「避難港」でもあるため、「利用漁船」が「安全円滑」に「出入港」できる「航路」の「確保」が「課題」となっており、また円滑な「輸送機能」を確保するため「幹線道路」との「スムーズ」な「アクセス」を図る「道路」も「課題」となっているそうです。
「九十九里町」の「水産加工業」は、主(オモ)に「カタクチイワシ」を「原料」とした「水産加工業」が行われています。
「九十九里町」「水産加工業」の「生産品目」ですが、「みりん干し」、「目刺し」、「丸干し」、「煮干」、「ごま漬け」、「野菜漬け」となっています。
なお、「九十九里町」の「地元」で採れる「岩ガキ」(2012年5月28日のブログ参照)は、「大ぶり」で「味」が「クリーミー」だそうです。
「九十九里町」の「観光業」は、「海水浴」、「サーフィン」、「海釣り」等があります。
1970年代頃まで「九十九里」における「観光」といえば、「夏季」の「海水浴」が中心で、「浜沿い」には「季節民宿」が営まれていました。
しかし、「自動車」の「普及」と「交通網」の「整備」により、「九十九里」は「首都圏」からの「日帰り圏」となってしまい、現在ではほとんど見られなくなったそうです。
「九十九里町」の「サーフィン」ですが、「四季」を通じて「質」の良い「波」を求めて、たくさんの「サーフィン」がやってくる「人気サーフスポット」となっています。
「九十九里町」の「ガス事業」ですが、「九十九里平野」の中にあるため、「天然ガス」が噴出しており、「九十九里町」の「町内」の「ガス供給」は「まち」が行っています。
「九十九里町」の「交通」ですが、1961年(昭和36年)までは「東金駅」と、「片貝」を結ぶ「九十九里鉄道」がありましたが、現在は廃止されています。
「九十九里町」の「バス」ですが、「ちばフラワーバス」・「小湊鐵道」・「九十九里鉄道」によって「路線」が運行されており、「東京駅」や、「千葉駅」と、「片貝」や、「サンライズ九十九里」を結ぶ「高速バス」、「急行バス」も運行されています。
「九十九里町」の「名所」・「旧跡」・「観光スポット」は、下記の通りです。
「片貝海水浴場」
「豊海海水浴場」
「ビーチタワー」
「伊能忠敬記念公園」
「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)の「生家跡」や、「銅像」などがあり、「伊能忠敬出生地」として「千葉県」の「史跡」に指定されています。
ちなみに「伊能忠敬」ですが、「上総国」「山辺郡」「小関村」(現在の九十九里町小関)で生まれたそうです。
「関東地方甘藷栽培発祥の地碑」
「九十九里町」では、享保20年(1735年)、「不動堂村」ほか2箇所で「青木昆陽」による「サツマイモ」の「試作」が行われ、「関東」で初めて成功したそうです。
「関東地方甘藷栽培発祥の地碑」ですが、「豊海小学校」の近くにあり、「青木昆陽不動堂甘藷試作地」として、「千葉県」の「史跡」に指定されています。
「武家屋敷門」(2015年7月26日のブログ参照)
「片貝中央海岸」は、「九十九里町」の4つの「海水浴場」(片貝、不動堂、真亀、作田)のひとつで、「子ども」から「お年寄り」まで安心して遊べるよう、「自然環境」が整備されています。
「片貝中央海岸」では、4月下旬には、「本州一」早い「海開き」が開かれています。
「片貝中央海岸」は、「九十九里町」で「元日」に行われる「元旦祈願祭」(2013年12月27日のブログ参照)の「会場」としても知られている「海水浴場」です。
「皇産霊神社」ですが、「山武郡」「九十九里町」「片貝」(上総国山辺郡)に鎮座する「神社」で、「旧社格」は「郷社」です。
「皇産霊神社」は、「俗称」・「産土さま(ウブスナサマ)」と呼ばれ、「地域」の「人々」に親しまれている「神社」で、「皇産霊神社」「本殿」は、「九十九里町」の「町指定文化財」に指定されています。
「皇産霊神社」の「御祭神」ですが、「天御中主神(アメノミナカヌシノカミ)」、「高皇産霊神(タカミムスビノカミ)」、「神皇産霊神(カミムスビノカミ)」を「主祭神」として祀っています。
「皇産霊神社」ですが、天慶年間(938年〜946年)の「創建」と伝えられ、往時は「本隆寺」を「別当寺」として「第六天神宮」と称していましたが、明治の「神仏分離令」で、「天御中主神」・「高皇産霊神」・「神皇産霊神」を「御祭神」とし、「社号」を「皇産霊神社」と改め、大正2年(1913年)「郷社」に列しました。
「皇産霊神社」では、毎年「正月13日」は「祭礼日」で、昔の3村の「各部落」から「氏子」が「太鼓」等を載せた「山車」を「先頭」に「囃子」で囃しながら「皇産霊神社」へ向かい、「幟(ノボリ)」を「皇産霊神社」「鳥居」前に並列し、「神官万歳」を唱え、「福」の「種」を撒いたそうです。
寛政6年(1794年)「小関村」と、「片貝村」の「水争い」から「堰」を作り、「水」を分け合うようになったことを祝い、「漫才」が行われていたという「伝承」があり、「関万歳(セキバンザイ)」になったと伝えられており、また「獅子舞」・「かっこ舞」の「奉納」もあるそうです。
「関万歳(セキバンザイ)」の「祭り」では、昔の3村の「鎮守」である「須原区」・「正一稲荷神社」、「屋形区」・「恵比寿神社」、「西の下区」・「八坂神社」から、「氏子」が「太鼓」等を載せた「山車」を「先頭」に「囃子」を囃しながら、「皇産霊神社」へ向かうそうです。
「関万歳(セキバンザイ)」では、多くの「出店」や、「獅子舞」・「鞨鼓舞」の「奉納」がある他、「福の種まき」と呼ばれる「神事」が行われるそうです。
「関万歳(セキバンザイ)」で奉納される「鞨鼓舞」、「獅子舞」ですが、「須原鞨鼓舞」、「屋形獅子舞」、「西の下獅子舞」です。
「屋形獅子舞」は、江戸中期の正徳元年(1711年)、「夷大明神」の「遷宮祭」で「獅子舞」を奉納し、「五穀豊穣」・「浜大漁」を祈願したのが「はじまり」と伝えられています。
「恵比寿神社」と、「八坂神社」の「祭礼」(屋形のまつり)では、「宮獅子」として「平獅子」を舞いましたが、時代とともに「芸獅子」の「演目」が増えました。
現在は「三番叟・序の舞・平獅子(布舞・語弊の舞・鈴の舞)・下手・相生」、「芸獅子」として「四つ足・玉取り・蛇・花かがり・蜘蛛」、「狂言」として「伊勢参り・鳥刺し・和唐内」、「囃子」として「屋形囃子・中山囃子・馬鹿囃子」等多数の「演目」が演じられます。
「狂言もの」は「地区」の「子供たち」が「主役」で、長い「台詞」をこなし「大人顔負け」の「演技」を披露します。
「九十九里町」では、「芸能」の「伝承」のため十年単位で「発表会」を開催しており、直近では、平成23年(2011年)に12年ぶりに「獅子舞大会」が開かれています。
「西の下の獅子舞」は、「八坂神社」の「祭礼」(毎年旧暦2月7日)で、「神社」と、「御仮屋」で奉納された後、「神輿」とともに「ムラ廻り」をしながら演じられます。
「西の下の獅子舞」は、江戸後期の文政2年(1819年)、「東金」・「松ノ郷」の「八坂神社」を「西の下」に勧請した際、「江戸」の「魚河岸」から寄贈された「神輿」の「露払い」として、「区内」の「長男」に「獅子舞」を伝習されたのが「はじまり」と伝えられています。
「西の下の獅子舞」の「演目」は、「神社」や、「村廻り」では、「悪魔払い」の「平獅子」(序の舞・語弊の舞・鈴の舞)が演じられます。
「舞台」等では、「芸獅子」(相生・四つ足・玉取り・蛇がかり・蜘蛛がかり・花がかり・お染獅子・鳥刺し・和唐内・伊勢まいり岡崎)等が演じられます。
「関万歳(セキバンザイ)」では、「鞨鼓舞」や、「獅子舞」の「舞手」や、「関係者」が「皇産霊神社」へ向かい、「神社」の「隣近所」の「民家」で休息するそうです。
その頃「皇産霊神社」には、多くの「参拝者」が集まり、「皇産霊神社」「境内」に設けられた「特別舞台」で行われる「手品」を見学するそうです。
そして、まず「須原区」の「鞨鼓舞」の「メンバー」が「近所の民家」から入り、「神前」で「お払い」を受けたあと、「特別舞台」で「鞨鼓舞」が行われ、「鞨鼓舞」ですが、「一人立三匹」で「鞨鼓」(鼓)は持たないそうです。
「獅子舞」は「龍顔」で、「舞台」「正面」に「語弊」を3本立て、「比較的」ゆったりと約20分間舞い、「舞手」は「小学生」で、この「鞨鼓舞」は、この後行われる「獅子舞の厄払い」(場所を清める)のために「舞い」だといわれています。
「関万歳(セキバンザイ)」では、「獅子舞の厄払い」に続き、「餅まき」が行われます。
「餅まき」の「餅」ですが、「紅白」の7〜8cmの「丸餅」で、1個づつ「ビニール」で包まれ、「餅」には10個〜20個に1個の「割合」で「赤」、「黒」等の「紙」が入っており、それぞれ「ラーメン」、「タッパー」等が当たるそうです。
「餅まき」は、昔は「福の種まき」といい、「餅」の「籾種」と、「赤大豆(ササゲ)」といったものをまき、これを「家」の「神前」に供え、「丘万作」・「浜大漁」・「家内安全」を祈ったといわれていますが、現在は「餅」のみが、まかれるそうです。
「餅まき」ですが、「関万歳(セキバンザイ)」中、3回行われる「鞨鼓舞」、「獅子舞」、「獅子舞」の後に3回行われ、「餅」は「豪勢」に、「計」4俵(約240kg)も撒くそうです。
「鞨鼓舞」は、「小学生」のみの「舞手」が舞いますが、「鞨鼓舞」に続いて行われる「屋形区」・「西の下区」の「獅子舞」は、それぞれ「小学生」と、「青年」の2組づつが舞うそうです。
「獅子舞」ですが、「2人立1匹」で、「小学生」は「獅子」には「道化」が「面」を付けて現れ、「獅子」を「餌」で釣ったり、からかったりし、「舞」は「手振り」、「足運び」等熟達した「白熱」の「演技」だそうです。
「関万歳(セキバンザイ)」にも参加する「西の下」の「獅子舞」ですが、「八坂神社」に伝承されており、この「獅子舞」は、文政2年(1819年)に「八坂神社」が創建されたときに、「江戸」の「魚河岸」から「神輿」が寄贈され、その「神輿」の「露払い」として「獅子舞」が伝習されたのが「はじまり」とされており、「西の下区」の「獅子舞」ですが、「千葉県」の「県指定無形民俗文化財」に指定されています。
なお、「関万歳(セキバンザイ)」ですが、昔、旧1月13日〜14日に催行されていましたが、数十年前から現在の2月11日に行われるように変わったそうです。
「九十九里」の「丘万作」、「浜大漁」の「守護神」である「古社」「皇産霊神社」で催行される「祭礼」「関万歳(セキバンザイ)」。
この機会に「九十九里町」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「関万歳(セキバンザイ)」詳細
開催日 2月11日(祝・土)
開催会場 皇産霊神社 山武郡九十九里町片貝前里地区
問合わせ 九十九里町教育委員会 0475-70-3192
備考
「関万歳(セキバンザイ)」の「様子」ですが、「九十九里ポータルサイト」にて「動画」で公開されています。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3318 |
| 地域情報::九十九里 | 10:54 PM |
|
|
2017,02,08, Wednesday
本日ご案内するのは、近隣市「鹿嶋市」「鹿島神宮」「本殿」で2月11日(祝・土)に開催されます「紀元祭」です。
「常陸国一宮」「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)は、「茨城県」「鹿嶋市」に鎮座する「神社」で、「全国」に約600社ある「鹿島神社」の「総本社」です。
「鹿島神宮」は、「千葉県」「香取市」に鎮座する「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)、「茨城県」「神栖市」に鎮座する「息栖神社(イキスジンジャ)」(2010年11月7日のブログ参照)と合わせて「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)と呼ばれ、江戸時代から「東国三社めぐり」として「人気」があったそうで、「初詣」には、「全国」から60万人以上が参拝し、「初詣」の「参拝者数」では「茨城県」2位を誇ります。
「鹿島神宮」は、「茨城県」「南東部」、「北浦」(2011年12月6日のブログ参照)と「鹿島灘(カシマナダ)」(2012年6月16日のブログ参照)に挟まれた「鹿島台地」上に鎮座し、「鹿島神宮」は、「伊勢神宮」・「香取神宮」とともに、明治維新前に「神宮」の「名称」を使用していた「三社」のうちの「一社」です。
「鹿島神宮」の「御祭神」「武甕槌大神(タケミカヅチノオオカミ)」(建御雷神)で、「鹿島神」という「一般名称」でも知られており、「古事記」では、「伊弉諾尊(イザナギノミコト)」が「軻遇突智(カグツチ)」の「首」を切り落とした際、「剣」についた「血」が「岩」に飛び散って生まれた「三神」のうちの「一柱」とされています。
「武甕槌大神」は、「香取神宮」の「御祭神」「経津主大神(フツヌシノオオカミ)」とともに、「天孫降臨」に先立ち「国譲り」の「交渉」をしたといわれている「神様」で、「武甕槌大神」は、「武の神」として古くから「皇室」や「藤原氏」の「崇敬」を受け、さらに鎌倉時代以降は「武家政権」の「信仰」も得て、「社殿」・「楼門」・「宝物類」の「奉納」や「所領寄進」が繰り返されてきました。
「鹿島神宮」「楼門」は、寛永11年(1634年)、「水戸徳川初代藩主」「徳川頼房」公が奉納した「楼門」で「日本三大楼門」のひとつとして知られています。
「鹿嶋社楼門再興次第記」によれば、「三代将軍」「徳川家光」公の「病気平癒」を「徳川頼房」公が「大宮司」(神宮の最高責任者)「則広」氏に依頼し、「徳川家光」公が快方に向かった為に奉納されたとあり、「浅草」の「水戸藩下屋敷」で130余人の「大工」が切組み、「船筏」で運んで組み立てたそうです。
「鹿島神宮」「楼門」ですが、昭和15年(1940年)の「大修理」の際、「丹塗り」とし、昭和40年代に「檜皮葺」の「屋根」を「銅板葺」としたそうです。
また「鹿島神宮」「楼門」は、「鹿島神宮」「境内」「鹿島神宮の森」の「縁」の中にひときわ「朱色」が鮮やかな「楼門」で、「鹿島神宮」「楼門」の「扁額」は「東郷平八郎」「元帥」の「直筆」によるものだそうです。
「鹿島神宮」「本殿」は、「三間社流造」、「向拝一間」で「檜皮葺」、「漆塗り」で「柱頭」・「組物」等に「極彩色」が施されています。
風格ある「鹿島神宮」「本殿」は、「江戸幕府」「2代将軍」「徳川秀忠」公より奉納されたもので、「国」の「重要文化財」に指定されています。
「鹿島神宮」「本殿」ですが、元和5年(1619年)の「造営」までは、現在の「奥宮」の「社殿」を使用されていました。
「鹿島神宮」「本殿」の背後には「杉の巨木」の「御神木」が立っており、「御神木」ですが、「樹高」43m・「根回り」12mで、「樹齢」約1000年といわれ、さらに後方、「玉垣」を介した位置には「鏡石(カガミイシ)」と呼ばれる「直径」80cmほどの「石」があり、「神宮創祀の地」とも伝えられています。
「鹿島神宮」「奥宮」ですが、1605年(慶長10年)に「鹿島神宮」「本殿」として奉納された「建物」で、「鹿島神宮」では場所を移して「奥宮」としたそうです。
「鹿島神宮」「奥宮」周辺ですが、神秘的な「雰囲気」を醸し出しており、「鹿島神宮」「奥宮」には、「鹿島神宮」「御祭神」「武甕槌大神」の「荒魂」が祀られています。
「鹿島神宮」「奥宮」「社殿」は、元々「江戸幕府」を開いた「徳川家康」公が、上述の「鹿島神宮」「本殿」として奉納したものを、元和5年に「徳川秀忠」公の「社殿」奉納に際し、「現在地」へ引移して「奥宮」「社殿」になったそうで、「鹿島神宮」「本殿」と比べると、「重厚さ」が感じられる「建物」となっています。
「鹿島神宮」の「境内地」ですが、「東京ドーム」15個分(約70ha(ヘクタール))に及ぶ「大きさ」で、「鹿島神宮」の鎮座する「地」は「三笠山(ミカサヤマ)」と称され、この「境内」は「日本」の「歴史上」、重要な「遺跡」であるとして、「国の史跡」に指定されています。
(摂社坂戸神社境内、摂社沼尾神社境内、鹿島郡家跡も包括)
「鹿島神宮」「境内」(70ha)のうち約40haは、鬱蒼(ウッソウ)とした「樹叢」で、「鹿島神宮樹叢」の「大きさ」は、「東京ドーム」約15個分の「広さ」を持ち、「鹿島神宮樹叢」として「茨城県指定天然記念物」に指定されています。
「鹿島神宮樹叢」には約800種の「植物」が生育し、「鹿島神宮」の長い「歴史」を象徴するように「巨木」が多く、「茨城県内」では随一の「常緑照葉樹林」になっており、木漏れ日の中を散策するなど、「森林浴」にも最適な「スポット」となっています。
その他「鹿島神宮」「境内」には、透き通る「湧水」で「禊(ミソギ)」も行われる「御手洗池」や、「鹿園」など、多くの「見どころ」があります。
「鹿島神宮」の「創建」ですが、2674年前の「初代」・「神武天皇」「御即位」の「年」にあたり、「神武天皇」は、「東征」の「途上」における「大神」の「布津御霊劔(フツノミタマノツルギ)」による「守護」に感謝され、「鹿島の地」に「大神」を勅祭されたそうです。
これに先立つ神代の昔、「武甕槌大神」は「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」の「名」を受け、「葦原中国」といわれた「我が国」の「国譲り」から「国造り」まで、その「建国」に大いにその「御神威」を発揮されました。
「鹿島神宮」は、その「御威徳」から「武の神」として崇められ、日出づる「東方」に坐します「鹿島立ち」の「御神徳」によって、「事始め」、「起業」、「開運」、「旅行交通安全の神」、「常陸帯」(2012年1月13日・2011年10月16日のブログ参照)の「故事」によって「安産」、「縁結び」の「神」を仰がれています。
「鹿島神宮」「文化財」ですが、「布津御霊劔(フツノミタマノツルギ)」と称される「長大」な「直刀」が「国宝」に指定されているほか、「鹿島神宮」「境内」は「国」の「史跡」に指定され、「本殿」・「本殿」・「楼門」など「社殿」7棟が、「国」の「重要文化財」に指定されており、そのほか「鹿島神宮」は、「鹿」を「神使」とすることでも知られています。
「鹿島神宮」は、古くから「朝廷」から「蝦夷(エゾ)」に対する「平定神」として、また「藤原氏」から「氏神」として崇敬され、その「神威」は中世の「武家の世」に移って以後も続き、「歴代」の「武家政権」からは「武神」として崇敬され、現代も「鹿島神宮」は「武道」で篤く信仰されています。
「鹿島神宮」では80以上もの「年中行事」の中では「祭頭祭」(2016年3月8日・2015年3月8日・2014年3月5日・2013年3月6日・2012年3月2日・2011年3月6日のブログ参照)、「神幸祭」(2012年8月26日のブログ参照)、また12年に一度「午年」ごとに行われる「式年大祭御船祭」(2014年8月31日のブログ参照)が特に「有名」で、2014年9月1日(月)には、「3日間」に渡って「御船祭」が催行されています。
(「式年大祭御船祭」「前日」8月31日(日)午後には、「御座船清祓式」(2014年8月29日のブログ参照)が執り行われました。)
「紀元節祭」ですが、「紀元節」が「祭日」とされていたとき、その「当日」、「宮中」の「賢所」、「皇霊殿」、「神殿」で行われた「祭事」で、「紀元節」の「祝宴」も行われ、また、「全国」の「神社」においても行われていたそうです。
「紀元節祭」は、初めて「紀元節」とされた1873年(明治6年)1月29日に、「宮中」の「皇霊殿」において行われたのが「最初」なのだそうです。
このときには「皇霊殿」においてのみ「祭祀」が行われ、「賢所」には「便り」の「御拝」が行われただけであったそうで、1914年(大正3年)から、「全国」の「神社」でも「紀元節祭」を行うように定められ、1927年(昭和2年)の「皇室祭祀令」の「一部改正」によって、「賢所」、「皇霊殿」、「神殿」の「宮中三殿」において行われるようになったそうです。
「紀元節祭」は、「皇室祭祀令」が定める「大祭」のひとつで、「天皇」が「皇族」および「官僚」を率いて親ら「祭典」を行います。
「天皇」の「出御」は午前9時30分で、「御拝礼御告文」を奏して「入御」。
ついで「皇后」、「皇太后」の「御拝」、「皇族」の「御拝」があります。
「参列員」は「文武高官」「有爵者」「優遇者」、「勅任待遇」までの「官僚」で、「正午」から午後3時30分(15時30分)まで、「有資格者」の「参拝」が許されたそうです。
「当夜」は「賢所御神楽」の「儀」に準じて「皇霊殿」に「御神楽」の「奏楽」があり、このとき「天皇」が「御拝」して、「入御」ののち「神楽」に移り、「天皇」は、「神楽」が終わるまで就寝しなかったそうです。
「紀元節祭」は、「伊勢神宮」、「官国幣社」以下の「神社」においては、1914年(大正3年)から、「中祭式」で「祭典」が行われました。
1947年(昭和22年)5月2日の「皇室祭祀令」「廃止」、1948年(昭和23年)7月20日の「休日ニ関スル件」「廃止」を受けて、1949年(昭和24年)以降、「紀元節祭」という「名称」の「宮中祭祀」は行われなくなったそうです。
ただし、「昭和天皇」は同年より2月11日に「宮中三殿」で「臨時御拝(リンジギョハイ)」という「名目」で「紀元節祭」と同様の「祭祀」を行い、「今上天皇」もこれを継承しており、「橿原神宮」へも「勅使」が派遣され、「御神楽奉納」は「神武天皇祭」(4月3日)に併せて行われています。
「民間」では、「一部」の「有志」によって「建国祭」等と「名称」を変えて「式典」が行われているそうで、また、1967年(昭和42年)の「建国記念の日」「制定」以降、「全国」の「神社」でも再び「紀元節祭」が行われるようになったそうです。
「神社本庁」等から「宮中」での「紀元節祭」「復活」の「要求」があるそうですが、「宮内庁」はこれを拒否しているそうです。
「紀元祭」は、「神武天皇」「建国」の「大業」を仰ぎ、「日本民族」の「自覚」を深め、「皇室」の「隆昌」と「国家」の「安泰」を祈念する「祭祀」です。
「紀元祭」ですが、「鹿島神宮」で執り行われる「行事」のひとつで、上記のように「日本」の「建国」を祝賀する「祭祀」です。
「鹿島神宮」では、2月11日(祝・土)に「紀元祭」を執り行っています。
「鹿島神宮」「紀元祭」は、上記のように「初代」「神武天皇」が「橿原」の「宮」に即位され、「我が国」を始められたことをお称えすると同時に、今後長きにわたって栄えることを祈る「祭典」なのだそうです。
「常陸国一宮」「鹿島神宮」で開催される「新春」に行われる「国」の「始まり」を祝い、「益々」の「発展」を祈願する「祭祀」「紀元祭」。
この機会に「鹿嶋市」に訪れてみてはいかがでしょうか?
「紀元祭」詳細
開催日時 2月11日(祝・土) 10時〜
開催会場 鹿島神宮 本殿 茨城県鹿嶋市宮中2306-1
問合わせ 鹿島神宮 0299-82-1209
備考
「紀元節」は、「古事記」や、「日本書紀」で「日本」の「初代天皇」とされる「神武天皇」の「即位日」をもって定めた「祝日」で、かつての「祝祭日」の中の「四大節」のひとつなのだそうです。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=3317 |
| 地域情報::鹿島 | 10:55 AM |
|
PAGE TOP ↑
|
 |



